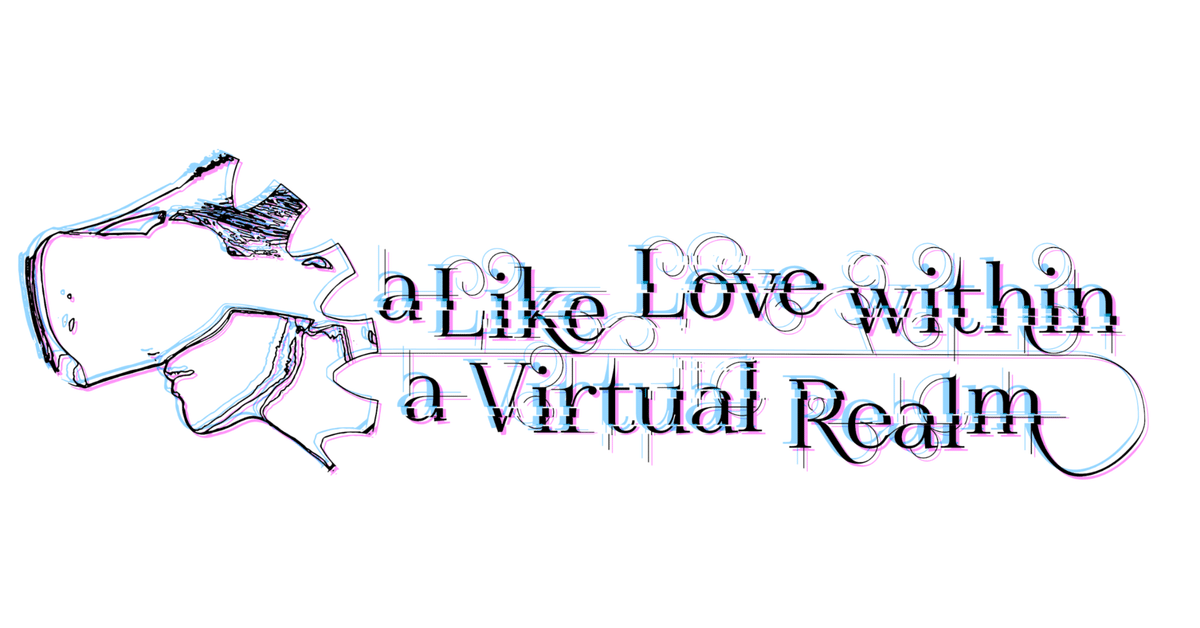
#11 #LLVR [a Like Love within a Virtual Realm]
目を覚ます。まず感じたのは頭の重さ。あと妙に視界が暗い。ぼんやりとした頭は明らかに酔っているからだった。そこから考えて昨日(今朝?)寝落ちしたのだと推測され、ごそごそと起き上がりコントローラーを探した。その間に動きを検知しヘッドセットの視界が明るくなる。いつものワールドが映り、そして意外な人物が隣で寝ていた。
「……あれ」
リュウくんだ。VR睡眠など、たとえ酔っていようともしなさそうなリュウくんが、隣で寝ている。トラッカーの充電が切れたのだろう手足があらぬ方向に向いていて、普段ピシッとしている姿からはおおよそこういう姿を人に見せるように思えなかったので、シンプルに驚いてしまった。
「おはようございます、カトルさん」
「わっびっくりした」
起きていたらしい。久しぶりに肩が揺れるほど驚いてしまった。
「えーと、大丈夫?」
「……飲み過ぎました」
「いやー、その、ごめんね……」
「いえ」
飲んだのは自分ですから、とリュウくんは体を起こした。まだ頭がフラフラしているようだ。
「カトルさんは、大丈夫ですか」
「うん。大丈夫大丈夫。二日酔いなったことないから」
「羨ましいです」
「……落ちないで、いてくれたの?」
「はい」
「意外だなぁ、なんか。別に放っておいて落ちてちゃんと寝てくれてよかったのに」
リュウくんはふーと大きく息を吐いた。本当にしんどそうだ。私の胸の罪悪感の渦が大きくなりそうになったのだが――
「寂しいじゃないですか、誰も、いないの」
「……へ?」
間抜けな声が出て罪悪感の渦がどっかいってしまった。予想外の回答に私の思考は固まっている。
「朝起きたとき、ひとりなのは、寂しいかなと」
「それ、で、いてくれたの」
うーん、とリュウくんは軽く首を回した。
「まあ、あれです。酔った人を駅まで送る、みたいなやつです」
「そう、なの?」
「そうです」
ふわぁ、とリュウくんが欠伸をする。人前で欠伸をするとか隙を見せないタイプだと思っていたので、これまた意外だった。
「じゃあ、落ちます」
「え、あ、うん」
「さすがに、ちゃんと寝直さないと、マズそうなので」
「さすがに、そうだよね。おつかれさま。おやすみ」
「はい。じゃあ、おやすみなさい」
「――リュウくん!」
そういえばお礼を言わなければ、と声をかける。メニューを開いてボタンを押そうとしたリュウくんが、私の声で動作を止めこちらを向いた。
「あの、ありがとう、いてくれて」
「――どういたしまして」
「おやすみ。お大事にね」
「はい」
そこに最初から誰もいなかったかのように、リュウくんは消えた。さすがに私も落ちて寝直した方がいいだろう。私もすぐにヘッドセットの電源を、切った。
「カトルって、リュウくんと付き合ってるの?」
同じキャバクライベントの友達であるパルにふいに聞かれて、ぶっと空気を吹き出してしまった。
「えっなんで⁉」
「いやほら、仲良いじゃん? こないだそっちいったら一緒にV睡してたし」
「あ――ああ、来てたの? あれはたまたま、二人とも酒飲んで寝落ちしただけだよ」
「そうなの? 結構みんな噂してるよ」
「え、そうなの?」
お酒を飲む手が止まる。パルはにやにやと笑っている。
「そうだよ? なんかカトルとリュウくんの間ってちょっと独特の雰囲気あるよね、って」
「そんなことないと思うけどなぁ」
「でもなんか特別そうな空気を醸し出してるよ」
「いやいやないないない。そもそも私男に興味ないし!」
「そう言ってバリスで男の彼女を作った人が何人いるやら」
ふふふと彼女――というか彼はカシュ、といい音をさせて次の酒缶を開けた。
「パルだって相手いるじゃん」
「いるけど男だよ?」
「……マジ?」
「マジ」
私の酒の手は止まったままだ。いろんな情報が錯綜している。私の中で。
「男とか女とか関係ないね。自分が落ち着ける場所が一番。そう思ったわけ」
「……マジ?」
「マジ」
思わずさっきと全く同じ返しをしてしまった。
「さすがにリアルの付き合いはないけどね。オフで会ったことないからわかんないけど、もしかしたらこの子なら平気かもなーとかってたまに思うよ」
「マ――そうなのかぁ……」
さすがに三度目は止めた。しかし私がノルちゃんとアインの関係と同じような目で見られていたとは。
「カトルはどうかわかんないけど、リュウくんの方は多分カトルのこと好きなんじゃないかな」
「そうかなぁ」
私はやっと缶に口を付けた。くび、とひとくちだけ飲む。リュウくんが? 私を? まさかそんなこと。
「だってリュウくん、カトルとよく話してるしね。人見知りみたいだけど、カトルのとこによく行ってるみたいだし?」
「うーん」
その程度で付き合っている疑惑を持たれてしまうのか。バリス怖い。そう思いながらまた酒をひとくち飲む。そりゃあ惚れた腫れたの話がどこまでも終わらないわけだ。
「あ、リュウくん」
「へっ⁉」
パルの声が向けられた方を見ると、リュウくんがいてこんばんは、と片手を上げた。やっほーと一応手を振り返したが、驚いて心臓がバクバクいっている。このワールド入室音がなかったのか。
「お疲れ様です」
「おつかれさまー」
パルが手招きをし、リュウくんは私の隣に座った。
「お二人とも、飲んでるんですか」
「飲んでますよ。リュウくんは?」
「俺は、今は特に」
「そうなんだ? じゃあ今から開けない?」
「……考えておきます」
リュウくんとパルの様子を観察する。自分ではこんなものだと思っていたのだが。
「カトルさんは、今日はあまり酔ってないんですか」
「え? いや? 飲んでるよ?」
「今日は尻尾触りに来ないから、飲んでないのかと」
フ、とリュウくんが笑った。あ、そうかこういうとこか、と腑に落ちる。確か初めてイベント外で会ったとき酔っぱらっていて、それで勢いで尻尾をもふもふしてから、会うと尻尾のところへ移動するのが普通になっていた。なるほど。そりゃあ誤解されるわけだ。
「別に、いっつも触りたいわけじゃないし」
「どしたのカトル。急にツンデレみたいになって」
「違うって!」
なんで照れなきゃいけないんだ。私は酒缶を煽る。
「何かあったんですか」
「いやね、最近カトルとリュウくん仲良いじゃん?付き合ってないのー? って聞いてたの」
パルが楽しそうにリュウくんに話す。
「それで! 違うって! 話してたの!」
一応、俺、男なんだけど。なんでこんな、女の子みたいになってんだ。確かにバリスの中では女の子でいるけど!
「違うんですか」
「リュウくん⁉」
私の反応を見てリュウくんが笑っている。意外と笑ってくれるところ、好きなんだよな。恋愛的な意味じゃなく。
「俺はわりと好きですけどね」
「……へっ」
「あら」
私が呆けた声を出してパルが驚いて口に手をあてた。その様子を見て、リュウくんはまた笑った。
「ちょ、リュウくん!」
「すいません」
謝りながら、はははと珍しく声を上げて笑っている。そりゃあこういうところかわいいなと思うし、好きだなと思うし、尻尾もふりにいくくらいには居心地良いなと思ってるし――あれ。
「あら、ちょっと呼ばれちゃった。行ってくるね。お二人ともごゆっくり~」
「ちょっとパル!」
じゃあねー、とパルはさっさと消えてしまった。呼ばれたとかこのタイミングで嘘じゃないだろうか。その可能性は高い。
私は何を話していいかわからなくなって、目線を泳がせた。
「……」
「すみません、お邪魔でしたか」
「ううん! 大丈夫。そゆことじゃ、なくて……」
どういう心持ちでいればいいかわからなくなって酒をまた煽る。早く酔いよ回ってくれ。
「――さっきの話、ですけど」
「え? さっき?」
「さっき」
リュウくんは床に座って私と視線を合わせた。こちらからリュウくんに近づくことは多々あれど、リュウくんの方から近づいてくれることなどない、なんなら初めてではないだろうか。思わずどきりとしてしまって、リュウくんの黒い瞳から目が離せない。
「好きですよ、カトルさんのこと」
「……へ」
また呆けた声が出てしまった。なに? 好きだって? 俺を?
「いや、いやいやいや、リュウくん、俺男だけど⁉」
慌ててボイチェンを切る。
「ほら、こんな声だし! あ、もしかして好きって友達的な意味で――」
「男なのもわかってます。でも――言っておこうかなって」
「なん、で……」
「俺、恋愛に不慣れなので。早めにフラれておこうかなって」
リュウくんの声はいつも通りの平坦さで、けれど言葉は重くて、なんだかちぐはぐだった。
「付き合ってくださいとは言わないですから、安心してください」
「え、ええ……」
俺は困惑した。告白とは関係を発展させるためにするものではないのか。
「伝えたかっただけです。それで勝手に、俺が楽になりたかっただけです。すいません」
「――な、なんで、今……」
「たまたまそういう話をしてらしたから、ですかね」
酔いなど覚めてしまっていた。リュウくんの気持ちが、わからない。どんな気持ちで、どんな想いで、リュウくんは好意を伝えてくれたのだろう。フラれることを前提として、何故伝えてくれたのだろう。
「すいません。混乱させてしまったようで」
リュウくんは俺に手を伸ばして、優しく頭を撫でてくれた。それになんだか安心感を覚えてしまって。

「――リュウ、くん」
「はい」
「わかんないんだけど、その、……リュウくんが思ってるほど、嫌じゃ、ないから」
リュウくんの手が止まった。
「うん。そうだな。嫌じゃないよ。さすがにオフでも会ってリアルでも付き合って、とかってなると、ちょっと難しい気がするけど……その、リュウくんの傍にいるの、なんていうか、落ち着くし、安心するし――だから、えっと、今まで通りみたいな感じにはなるけど……」
アイトラッキング機能のあるVRヘッドセットじゃなくてよかった。彷徨う目線がバレないから。
「――これからも、仲良く、してほしい、から」
「…………」
言葉は尻すぼみになった。当たり前だ。こんな告白されたことないし、こんな返しもしたことがない。リュウくんはフリーズでもしたのかというくらい固まって動かない。アバターが瞬きしているのでフリーズではないようだ。
「――ふ、はは」
リュウくんがやっと動いた。微かな笑いをこぼして上を向き、はははと笑い声を上げている。
「そ、そんなにおかしかった……?」
「いや、違うんです、すいません」
リュウくんはずれたヘッドセットを直しながら言う。
「カトルさんが、思ったよりかわいい人だったから、驚いたんです」
「な、なに、」
顔が熱くなるのがわかる。そんな俺の顔はVRヘッドセットで隠されているおかげで、リュウくんのあやすような手つきで撫でられても、アバターでは平気な顔をしていられた。
No.11
大人になって
いろんなことを知って
いろんなことを経験して
それでもまだ知らないことが
たくさん周りにはころがっていて
君もそんな中のひとつだった
好き という気持ちは
どうにも自分が思っているようり自由なようで
それは自分に向けられることも
もちろん当然可能性はあって
ただ
君から
向けられるなんて
思ってもみなくて
驚いたけど 嬉しかった
そう 嬉しかった
その好意を嬉しいと思えたことが
嬉しかった
この仮初の世界でどうか
これからも隣にいて欲しい
