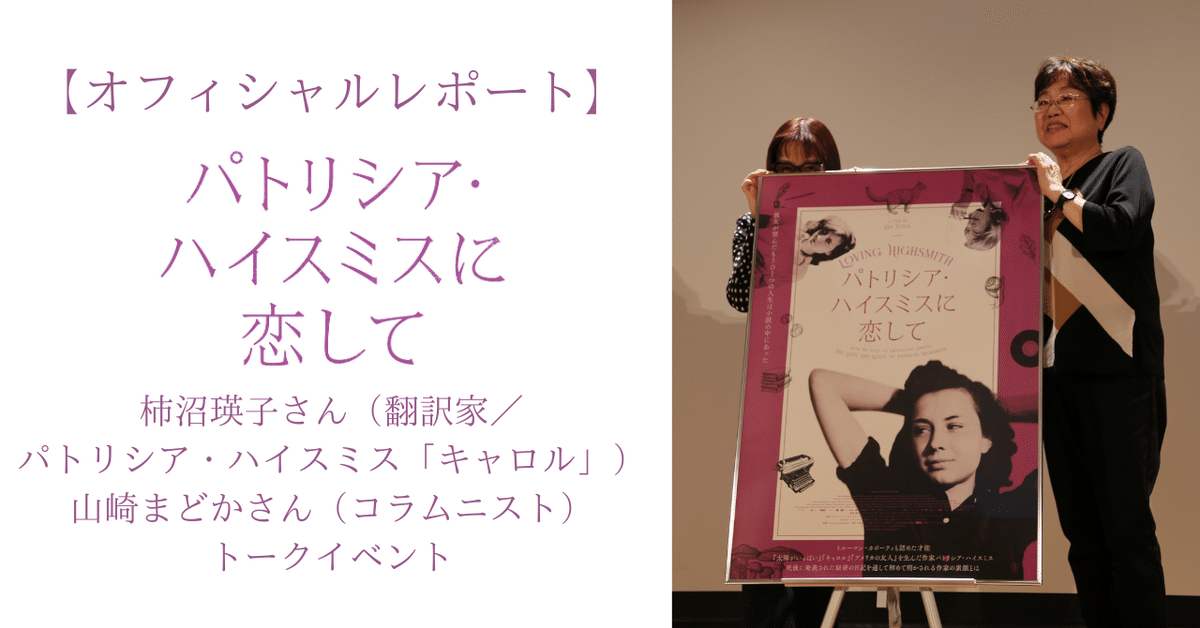
【オフィシャルレポート】『パトリシア・ハイスミスに恋して』柿沼瑛子さん&山崎まどかさんトークイベント!
『太陽がいっぱい』『キャロル』『アメリカの友人』を生んだアメリカの作家パトリシア・ハイスミスの知られざる素顔に迫るドキュメンタリー『パトリシア・ハイスミスに恋して』が、2023年11月3日(金・祝)より新宿シネマカリテ、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、アップリンク吉祥寺ほか全国順次公開。
『パトリシア・ハイスミスに恋して』の日本公開を記念して、日比谷図書文化館 日比谷コンベンションホールにて、10月25日(水)特別試写会上映後に、『キャロル』『水の墓碑銘』はじめハイスミスの著作を翻訳されてきた柿沼瑛子さんと、映画や文学を中心に女性の文化を見つめ続けてきた山崎まどかさんの二人の視点から、愛を渇望し孤独に生きた知られざるハイスミスの素顔を紐解く本作の魅力をたっぷりと掘り下げた。(以下、敬称略)

柿沼:本日はよろしくお願い致します。ハイスミスの作品は「キャロル」をはじめいくつか訳させて頂いていますが、今ハイスミスの伝記をやっております。まもなくそれが終了しますので、それを読んでいただくと今日の映画の裏事情というのも一層分かるのではないかと。(ついでに)伝記の宣伝もしてこいと出版社に言われています。
山崎:すごい楽しみです。今回の映画はパトリシア・ハイスミスの日記をもとに、どちらかというと私生活とか恋愛生活といったものを軸に語っていた感じなんですけれとも、柿沼さんはどうご覧になられました?
柿沼:彼女の場合、恋愛がないと、おそらく小説が書けない人だったので、そのあたりが裏付け調査じゃないですけど、その辺の事情がよく分かりました。逆に、ちょっときれいすぎると言ったら語弊がありますけど、(映画だと)ハイスミスが1人で何か苦しんで悩んで、だけど良い作品を書いたんですよ、みたいな感じになっているようにも見えるんですが、本当はもうちょっと色々と醜い部分とかあったりするかなと思いました。ただ、一応、そのあたりも、やっぱりちょこちょこっと映画の方には出ては来ますからね。でも、ハイスミスはやっぱり稀有な人だったと思います。多分人一倍感じやすいから、人一倍憎むし、愛するし、全てのものが、倍になって受け止めているからだから、それってものすごく大変だったんじゃないと思いますね。
山崎:私達も何となく今は、パトリシア・ハイスミスはレズビアンで、レズビアン文学の金字塔になっている「キャロル」 ーー映画にもなって、柿沼さんが翻訳されて日本でも出版されてーー映画も小説も定番になっていると思うんですけど、実は柿沼さんが翻訳されたハイスミスの後期の作品、「イーディスの日記」を取り寄せて、そのあとがきを読んだら、91年の時点ではあまり彼女のセクシャリティってことは大っぴらに議論がされてなかったっていう認識なんだと思ったのですが。
柿沼:そうですね、まあ公然の秘密ですからね。例えば、LGBTQ+系の本屋さんに行くと、「ああハイスミスね。こっちよ」と言って、レズビアンの本がある棚へ案内してくれたりとか。ただ、当時は、なんか作品のせいで「人間嫌い」という印象が強かったから、(この映画で描かれているみたいに)こんなふうに激しく愛したり憎んだりする人なんだっていうのと、まだイメージが一致していなかったっていうのはありますね。
山崎:本でもよく知られて、「キャロル」以降、大きくそういうことが知られるようになって。どこか彼女の作品の中には、レズビアンを直接的に描いた、クイア的なところがあるという“読み”が普通になったのは、ここ最近と考えていて宜しいでしょうか?
柿沼:とりわけ「トム・リプリーもの」はホモ・エロティシズムが強いと昔から言われていましたね。ハイスミスは自分のセクシャリティを「私は私だから」と、レズビアンとかそういう呼び名で呼ばれたくないみたいなところがありましたから。記者がトム・リプリーのホモセクシャリティについて質問しても、いつもはぐらかしていましたし、「彼はちょっと女性に興味がないだけなのよ」みたいな言い方をしていましたけど、おそらくトム・リプリーの中にハイスミスがかなり入っているというのはありますね。
山崎:リプリーはすごく彼女が好きで繰り返し書いて、長い長いシリーズものになっている、かつ映画化もリプリーのシリーズは多くて。(会場に向かって)『太陽がいっぱい』ってご覧になった方この中でいらっしゃいますか?
(大勢の方が手を挙げる)
柿沼:結構いらっしゃいますね。
山崎:『キャロル』は当然(観ていらっしゃる)。ちなみにリメイクの『リプリー』を観たって方はいますか?
柿沼:こちらも結構いらっしゃいますね
山崎:映画を見ると、彼女の証言よりもむしろ映画作家たちは(ハイスミスのことを)理解して描いているところがあって、そこがハイスミスの作品と映画の面白いところだなって。
柿沼:そうなんですよ。知らず知らずのうちに作品のなかに反映されてしまうんですよ。トム・リプリーという人は、相手を好きになるとその人になりたくて必死に近づこうとするけれど、相手が拒絶するとすぐに嫌いになって殺してしまうところがあって。…少し話が飛ぶんですが、『キャロル』の話していいですか?
山崎:はい。
柿沼:『キャロル』のモデルになった女性が実際いるのですが、『キャロル』に出ているブルームベール(デパート)でアルバイトしている時にお人形買いに来た人なんですよね。その人にハイスミスは一目惚れしてしまって、伝票をもとに何度かこっそり訪ねていくんです。訪ねていって、チラリともしかしたら彼女かもしれない姿を見た時に、「わたしは一瞬彼女を殺したい」と思ったと。「そうしたら自分の中に永遠に彼女を閉じ込めておけるのに」って。それは『キャロル』の時だから、まだ2作目で30歳になる前かそこいらの若さですよね。その時に、自分のものにならないならいっそ殺してしまえ、といった意識が芽生えていたと。彼女の特別な愛の形がそのころからあったんだと思います。
山崎:今回は3人の元恋人の証言が柱になって、日記とともに彼女の実像に迫るというものなんですけれど、やっぱり面白いなと思ったのが、それぞれニューヨークとパリとベルリンの、言ってみればレズビアンシーンやクラブシーンみたいなものの真ん中にいる恋人たちなんですよ。
柿沼:そうですね。
山崎:特に最初に出てきたニューヨークに住んでいた彼女に関していうと、グリニッジビレッジのレズビアンシーンの話とかも出てきて、『Chained Girls』という60年代に撮られたドキュメンタリーというよりエクスプロイテーション的な作品で、ちょこっとだけ観たレズビアンバーのシーンがあるってことを知ったんですね。だからそこにハイスミスも通っていたんだって驚きましたし。あとパリでも、ベルリンでもそういうシーンに彼女が顔を出していたっていうことも分かって、すごく興味深かったんですね。
柿沼:それは彼女独自のネットワークの作り方で、あの人は超保守的な南部の小さな町で育って、ニューヨークに出た途端、セクシャリティを解放したわけで、その時にニューヨークのレズビアンシーンに入り込んでいって。ハイスミスは美人でもないけれど、はつらつとしてすごい綺麗だったんですよね。
山崎:雰囲気ありますよね。一言でいうと超モテそうですよね。
柿沼:年上の知的な、例えば書店の女主人とかにモテて。ものすごい可愛がられて、その人がレズビアンの社交界の上流階級の人たちへ紹介して。あと作家さんたちにネットワークを持っていて、そういった人たちに次々とハイスミスを紹介していく。そういった人たちがイギリスの社交界に紹介していく、どんどんネットワークをひろげていったんです。
山崎:レズビアンのアンダーグラウンドネットワークの中にハイスミスもいた。面白いなと思うのは、そういうシーンで目立つ人でありながら、彼女はすごく孤独なんですよね。 LGBTQのシーンとかコミュニティの中にいるっていう感じがドキュメンタリーを観てもあんまりしないんですよ。
柿沼:彼女自身はただレズビアンのアイコンではあるんだけど、レズビアンが嫌いだと一度言ったことがあって。みすぼらしくてヤルことばっか考えていてとかディスってたりするんです。多分、それは彼女がクラブシーンにデビューした時がそんな感じだったんだろうなと。あの人はわりと天邪鬼で逆のことを言うので、どこまで信用していいのかわからないんですけど。「キャロル」にしてもあれは最初「The Price of Salt」というタイトルで出ましたが、「これパトリシア・ハイスミスだよね」って評判はどんどん広がっていて。パトリシア・ハイスミスの名前で出したら、前渡金というかアドバンスを4倍にしますよっていう話も断って。最終的に1990年でしたか、「キャロル」と改題した時にはじめてパトリシア・ハイスミスという名前を出したから。彼女はカテゴライズされるのを一番嫌うようです。自分の書いている小説についても、ミステリーではありませんとか言って、とにかくカテゴライズされるのが嫌だったみたいで。
山崎:なるほど。なんかそこが人間嫌いというイメージを醸し出してしまっている。

柿沼:カタツムリが大好きで。
山崎:カタツムリの話、逸話がいろいろありますよね。
柿沼:ハンドバッグのなかにカタツムリを入れて、レタスを食べさせていたとか。あと税関をこっそり突破するとか。
山崎:そう、ブラの中にカタツムリを入れて突破したとか。「11の物語」という短編集にカタツムリという怖い短編もあるので。
柿沼:カタツムリのつがいは愛する相手を殺すことによって成立するので、まさにハイスミスですよね。
山崎:ちょっとアイデンティファイしていたんでしょうかね。
柿沼:そう思います。
山崎:映画には猫もいっぱい出てきたんですけども。
柿沼:猫も大好きでした。
山崎:猫が好きなのはなんかわかるな。カタツムリはそうかそういうことかと今思いました。
柿沼:彼女は最後に要塞みたいなお家にひとりで住んでいたようなわけではなくて、友達もたくさんいたから、彼女の難しい性格を分かった上で、友達になってくれた人たちも結構いたりするので。ハイスミスはすごい手紙魔だったので、1週間に3通とか5通とか送りつけてたらしいんですけど。そういったいろんなことを打ち明けられるストレートの女性の友人が二人いたんですけど、意外かもしれませんが、「キャロル」にリチャードという人が出てくるんですがーーーテレーズと無理やり結婚しようとするーーーそのリチャードのモデルというのがマークという人なんですけど、実は晩年に大親友になりまして、創作の悩みなどをストレートに打ち明けたりとかして、彼の奥様含めて3人ですごく仲良かったようです。だから本当に心を許せる人はいたんですよ。
山崎:人嫌いだけど、人恋しい感じを、この監督も強調しているところかなって。
柿沼:人から触れられるのが嫌いだったみたいで。恋人は別なんですが、人に触られるのが本当に嫌で、手が触れただけでピクっとして相手から「嫌われているのかな」と思われたり。でもそれは自然の反射で。最後に彼女は白血病で亡くなるんですけれど、本当に苦しい時に初めてマッサージを許したと聞いてなんか悲しい気持ちになりました。
山崎:そうですね、なんか慣れない猫みたいですね。
柿沼:最期の最期にやっと他人の手によるマッサージを許したというのは、悲しい。
山崎:他人の手では安らげない。恋人は別?
柿沼:そうです。
山崎:恋の期間は長いわけではないんですか?
柿沼:ハイスミスの場合は、この人が好きってなると一方的に一人で盛り上がってしまう。上手くいけば上手くいくで、例えばキャロライン、マダムエックスとはなんだかんだいって4年くらい続くんです。だけど、最後はお互いトゲトゲしてきちゃって愛が冷めて、最終的にはハイスミスが家を追い出すというショッキングな終わり方をするんです。あと、最後の恋人のタベア・ブルーメンシャイン。あの人はハイスミスが好きになるの分かるくらい、年取ってからもあんなに生き生きしていて生命力に溢れている人ですよね。
山崎:彼女は亡くなってしまってあれは晩年の姿なんですけれど、『アル中女の肖像』を観た方ってどのくらいいますか?あ、一人いっらっしゃいますね。
柿沼:ベルリン三部作ですよね。
山崎:はい、ベルリン三部作が日本でも公開になっていて、今劇場でやっているかはわからないのですが、是非とも若い時のタベアを観てほしい。すごい美女です。ものすごい美女がすごいお酒を飲んでベルリンの街を放浪しているみたいな映画なんですけど、あれをみてパトリシア・ハイスミスがどうしてもって好きになってしまった気持ちは分かりました。
柿沼:あれは本当に最後の激しい恋で、タベアさんというのは長い関係をもてる人ではなくて、いろんな女の人と同時に関係を持つような生活の仕方をしていたけれど、ハイスミスもそういうところはあるんだけど、自分が好きになった人には自分だけを見ていてほしいという気持ちがすごいあって。
山崎:独占欲が強い?
柿沼:そう、独占欲強いですね。だから結果的にわたしと一緒になるか別れるかどっちかよと勢いに任せて言ってしまったんですよね。そうしたらタベアに「私は一人の人と長く関係は持てないんです」って言われて、そこで終わってしまい、なんか墓穴をもってしまったという。
山崎:でも、元恋人も全員年齢がいっているので、生の声を聞けるのぎりぎりだったみたいでよかったですよね。
柿沼:もう二人死んでしまっているんですものね。
山崎:だって本当に50年代、60年代、70年代のレズビアンシーンなんて本人の口から聞けない。パトリシア・ハイスミスのドキュメンタリー映画が今まで作られなかったのが不思議なくらい。
柿沼:実は亡くなった直後に話はあったんですけれど、それは立ち消えになってしまったみたいですね。
山崎:でもこれだけのドキュメンタリーができたってことは、彼女の日記とノートが発見されたってことが大きいですか?
柿沼:そうですね。それとハイスミスに興味を持っている人、この監督さんみたく多かったけど、なかなか踏み出せなかったと。でも日記やノートが見つかって取材がしやすくなったというのもあるかもしれませんね。最後に出てきたモニーク・ビュフェさん、あの人はタベアとの恋愛に傷つきボロボロになったハイスミスを優しく包んで、「あなたは私にまた夢を見させてくれた」とハイスミスに言わせしめた天使のような女性なんです。
山崎:その日記には私たちが知らなかったようなハイスミスの姿が出ていたのでしょうか?
柿沼:すごいですよ。歴代恋人の名前とか書いて、その比較表みたいなのがあって(笑)
山崎:ジェームス三木かって感じですね。
柿沼:この映画の中に「ガールズブック」の話とか出てきましたよね。マリジェーン・ミーカー。あれは「キャロル」の続編を作ろうとしてたんでるけど、テレーザがどうしても上手く動いてくれないから、だったら自分のことを書こうと思って、自分の過去と自分が関わってきた恋人たちのことをいれて書こうとした、それが「ガールズブック」なんです。ただこれは59ページで中退してしまったんですけど。その時の取材のために書いた表がそれなんですけれど。
山崎:でも、付き合った人ショックですよね。
柿沼:あんまりよくは思わないでしょうね。

山崎:日記の中には最期、彼女が孤独になってしまった時、人種差別のことが書かれていたとチラっと触れられていたんですけれど、そのことに関してはどうでしょうか?
柿沼:本質的な話は、彼女の実家のコーツ家の人たちがでてきましたよね。ド南部の超保守的なところで生まれ育って、おばあさんに育てられているから、心の根っこでは南部白人の価値観があるんですね。黒人の公民権運動が盛んになった時も、「黒人の福祉厚生のために私たちの税金を使うな」みたいなことを言って批判を浴びたりとか。
山崎:反シオニスト的なところがあった?
柿沼:アメリカの出版界というのはユダヤ人が作りましたから。経済にしても出版界にしても。ハイスミスの露骨な反シオニスト的な体質は嫌われたし、やっぱりアメリカは黒か白かで決めたがるでしょ?だからハイスミスのようなグレイゾーンのもやもやしたものが残るというのは好まれないんですよ。だから、ハイスミスはアメリカでは人気が出なかったんですよね。
山崎:ほんとうにヨーロッパの作家みたいな感じはします。たしかに。
柿沼:彼女は「見知らぬ乗客」でヒッチコックが(映画化権を)買って印税が入ったので、ヨーロッパでデラシネのような生活を始めるんですが、そこで自由を味わってしまうと、逆にアメリカのマッカーシズム政権下のものすごい赤狩りと同性愛者たちが抑圧されていた時代ですからそこにもう戻れなくなってしまう。
山崎:そういう体制側の介入が嫌いっていうのは、フランスにいた時に税務署に攻め込まれてやんなっちゃった彼女ですから、すごくよくわかります。でもそういうところが、アメリカは黒白で決めたがるってありましたが、実際に今回のガザの騒動でパレスチナ支持の発言をした作家がイベントを取りやめになったりということが既に行われているんです。ただこういう時代だからこそ、パトリシア・ハイスミスのもっているグレイな感じってすごい必要なんじゃないかと、あと、もうひとつ思うのは、ハイスミスはすごい影響力がありますよね。作家のなかでハイスミスから影響を受けている若い作家はたくさんいると思います。
柿沼:ミステリー界でいうとピーター・スワンソンとか、大っぴらにハイスミスのファンを公言していて。日本でもピーター・スワンソンは人気があって、イヤミスって分かります?湊かなえさんみたいな。
山崎:バッドエンドな。
柿沼:(日本人は)そういうのが好きなのでハイスミスは受けやすいのかと思うんですよね。
山崎:今回の映画を観てからハイスミスの作品を読むとまたいろいろと見えてくることがありますよね。人間の孤独みたいなものとか感じる。疎外感とか。
柿沼:いくら愛しても孤独なんですね、あの人。映画を観てすごく感じました。
山崎:映画化もたくさんされているんですけれど、彼女的には好きな映画はあったんでしょうか?
柿沼:一時期、「『太陽がいっぱい』が綺麗すぎる」と嫌っていた噂があったんですけど、彼女はあの映画を気に入っていたのですけれど、ラストに正義が勝つ映画にしてしまったことが気に食わなかったと言っています。あと、『アメリカの友人』ですかね、あれは「テンガロンハットを被ったリプリーはちょっと…」とあまり評判が良くなかったようです。
山崎:私は映画としてはあれが一番好きでした。
柿沼:あれ、映画はいいんですよね。テンガロンハットさえ被っていなければ。晩年に彼女は体が弱ってしまっていて、修道院あがりの男の介護士を雇うんだけど、その人とよく自分の映像化された作品のビデオを見ていたそうですよ。実は気になっていたんじゃないですか。
山崎:『キャロル』を観てほしかったですね。
柿沼:『キャロル』の脚本を書いたフィリス・ナジーはハイスミスの晩年に関わりのあった人なんです。ハイスミスは火葬されたんですよね。生前から火葬に興味があって、イギリスの新聞に火葬の記事を書いてみませんかって引き受けて、そのアテンドをしたのがフィリス・ナジーだったんです。最初、全然口をきいてくれず嫌われているんじゃないかって思っていたそうなんですけれど、終わってからすごい親切な手紙がきて、彼女がライターを目指していると話したらものすごく励ましてくれたそうです。いつの日かわたしの作品を脚本化していいのよとはなしたそうです。
山崎:素晴らしい話ですね。
柿沼:やっぱりハイスミスに『キャロル』観せたかったですね。



【パトリシア・ハイスミス プロフィール】
1921年1月19日、アメリカ、テキサス州フォートワース生まれ、ニューヨーク育ち。バーナード・カレッジ在学中より短篇小説の執筆を始める。1950年に発表した長編デビュー作『見知らぬ乗客』でエドガー賞処女長編賞を受賞、本作は翌年ヒッチコック監督により映画化。1952年、クレア・モーガン名義で自らの体験を基にしたロマンス小説『キャロル』を刊行。その他の主な著書に「トム・リプリー」シリーズ、『水の墓碑銘』、『殺意の迷宮』など。1962年よりヨーロッパに移住。1995年、スイスのロカルノで死去。74歳没。
【STORY】
トルーマン・カポーティに才能を認められ、『太陽がいっぱい』『キャロル』『アメリカの友人』を生んだアメリカの人気作家、パトリシア・ハイスミス。生誕100周年を経て発表された秘密の日記やノート、貴重な本人映像やインタビュー音声、タベア・ブルーメンシャインをはじめとする元恋人たちや家族によるインタビュー映像を通して明かされる、多くの女性たちから愛された作家の素顔とは―。ヒッチコックやトッド・ヘインズ、ヴィム・ヴェンダースらによる映画化作品の抜粋映像を織り交ぜながら、彼女の謎に包まれた人生と著作に新たな光を当てるドキュメンタリー。
監督・脚本:エヴァ・ヴィティヤ
ナレーション:グウェンドリン・クリスティー
出演:マリジェーン・ミーカー、モニーク・ビュフェ、タベア・ブルーメンシャイン、ジュディ・コーツ、コートニー・コーツ、ダン・コーツ
音楽:ノエル・アクショテ
演奏:ビル・フリゼール、メアリー・ハルヴォーソン
2022年/スイス、ドイツ/英語、ドイツ語、フランス語/88分/カラー・モノクロ/1.78:1/5.1ch 原題:Loving Highsmith 字幕:大西公子
後援:在日スイス大使館、ドイツ連邦共和国大使館
配給:ミモザフィルムズ
© 2022 Ensemble Film / Lichtblick Film
『パトリシア・ハイスミスに恋して』
2023年11月3日(金・祝)より新宿シネマカリテ、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、アップリンク吉祥寺ほか全国順次ロードショー
■オフィシャルサイト
https://mimosafilms.com/highsmith/
■X(Twitter)
https://twitter.com/highsmithfilm
■Instagram
https://www.instagram.com/mimosafilms/
■Facebook
https://www.facebook.com/mimosafilmsinc
