
コンビニの魔女-プロローグ-
少し前のことだけど、ミリーは、自分が本当は、魔女だったことを思い出した。
「なんでそんな当然のこと、忘れていたんだろう?」
駅へと向かう急な坂道を駆け下りながら、ミリーの胸はすっきりと澄んで、高らかに鳴っていた。じんわりとした温かいものがどんどんと溢れていたく。朝の騒がしい風景は、びゅんびゅんと過ぎ去っていった。脚にプロペラがついているいみたいだ。嬉しくて、喜びが溢れて、おかしくて、胸の内側から、笑い声が聞こえてきそうだった。
( 私は、自分らしく生きていいんだ!)
ハイヒールで地面を蹴り上げる。
そのまま、空に向かって飛び立ってしまいそうだった。
いつも通りの時間に起き、いつも通り会社に行く。
その日までミリーは、きっちり整然と整った、まっすぐな道を歩いていた。
だけど、まっすぐに舗装された道を歩きながら、心の中ではいつも疑問を抱いていた。
「どこか遠くの、別の場所に行きたいような気がする。だけど実際、私はどこに行きたいんだろう?」
「一人前」に見えるように。
誰からも咎められないように。
仲間外れにされないように。
自分のことが分からないまま、振る舞ってきた。
自分のことが分かっていない、ということにも、気づいていなかった。そこそこうまくやれているつもりだった。
本当は違う。今なら分かる。
遅れを取らず、かといって早く進みすぎることもせず、体の内側を張り詰めさせて歩いてきた。
そんなきっちり整った、退屈なその道に、突如曲がり道が出現したのだ。
「会社、辞めよう」
駅に到着する頃には、ミリーの心はすっかり決まっていた。
別に、魔法の家計に生まれたとか、幼い頃から魔力を発揮していたとか、そういう訳ではない。
人よりも特別秀でたものがある訳でもない。
だけど、ミリーが魔女であることは明らかなことだった。
それは2年生が終われば3年生に進級することと同じくらい、当然のことだった。
会社に着くと、朝一番で部長を会議室に呼び出し、退職の意向を告げた。

「そうか、残念だね」
電気をつけていない薄暗い会議室に、朝の日が差し込んで、部長の顔を見ることができない。光の向こうから、なんとなく“しゅん”、とした様子がうかがえる。だけど、特段驚いた様子はなかった。長年のサラリーマン生活の中では、部下の退職なんてよくある出来事の一つでしかないのだろう。
一方、ミリーにとって、これは一大事だ。ただの「転職」じゃない。これまでの人生を全て捨てて、まったく違う別の人物の人生を生き直すようなものなのだ。
小さな印刷会社の営業部。ミリーはそこに、所属している。部長は、優しさが取り柄の、善良な男だった。部長には、“サプライズ”の匂いがしない。きっとこのまま、特別なサプライズがやってくることもなく、もちろん自分でサプライズを引き起こすこともなく、人生が進んでいくのだろう。
「突然のことで、すみません。残り1ヶ月間、どうぞよろしくお願いします」
ミリーは静かに言った。頭を下げながら、なんとなく窓の外をチラッと見る。
窓の外では、いつものように、ビルの管理人が植木に水をまく姿が見える。平穏な風景。
ミリーひとりが、「大きな転換」の真っ只中にいる。
「次の職場はもう決めているの?」
朝日の向こうから、部長の声が投げ込まれてきた。
次の瞬間、外の方で「ブイーン」と音がなった。ビルの中庭で、芝刈り機のスイッチが入ったみたいだ。
「はい!」
ミリーはきっぱりと言った。こんなに溌溂としたミリーは、部長にとってもちょっと気味が悪かったかもしれない。職場の人々にとってミリーは、“おとなしい樺山さん”なのだ。
本当のことは、言わないことにした。
(これからは、魔女として生きるんです)
そんな風に言ったところで、信じてもらえる訳がないのだ。
心の中で、ウィンクをしてみせながら、ミリーは言った。
「でも、まだ秘密にさせてください」
もちろん、ずっと秘密にしているつもりだった。
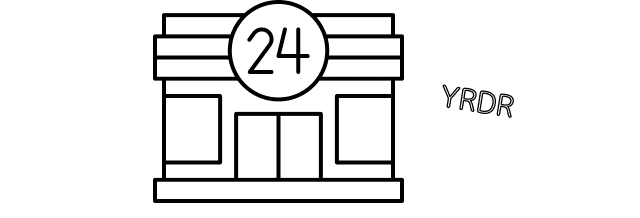
それから、2ヶ月が経った。
ミリーは今、騒がしい大きな通りのコンビニエンスストアでアルバイトをしている。
「いらっしゃいませー」
朝の通勤時間帯レジにはお客が途切れることなくやってくる。
火曜日は朝6時から午後2時まで、ずっとレジに立ち続けるのだ。
「ありがとうございましたー。お次の方、どうぞー」
元気よく接客できるし、仕事もテキパキとこなす。
ミリーはすっかり“頼りになる新米店員”になった。
「ミリーちゃん、すっかりレジに慣れたわね。頼もしいわぁ」
朝のピークに一区切りがついた時、石森さんが上機嫌に話しかけてきた。
石森さんは、火曜日の朝のシフトに一緒に入る主婦で、ミリーにとっては「パートさん」たちの中で一番話しやすい相手だった。
「ありがとうございます」
にこりと微笑みを浮かべながら、ミリーは愛想よく言った。
ミリーは昔から、何でも卒なくこなすタイプだった。
(まあね。そりゃ私、何でもできちゃう方だから)
そんなことを思いながらも、胸の中でじわっと嫌な汗が滴るのを感じた。
(でも私、コンビニの仕事なんか順調に覚えてるヒマ、ないのよ)
ミリーは焦っていた。
なぜかって?
それは、魔法を見失ってしまったからだ。
自分が本当は魔女だったことを思い出したあの日、会社を辞める決断をしたあの日、確かにミリーは自分の魔法を掴んでいた。目や口や鼻があるのと同じように、魔法だって、当然あるものなのだと、心の底から思えた。
具体的にどんな魔法なのかまでは分からなかったけれど、そんなことは問題じゃない。自分の肺がどんな色や形をしているのか見ることができなくたって、呼吸をすれば自分には肺があることが分かるのだから。
あの日、ミリーには、自分の魔法で人生を切り開いていけるのだ、ということが明らかなくらいはっきりと分かっていた。
だけど、その魔法は、いつの間にやら、どこかへ行ってしまったのだ。
仕事の引き継ぎで忙しくなってしまったからだろうか?
会社を辞めた後の生活の不安に、胸が押しつぶされそうになっていたからだろうか?
最後の出勤日を向かえる頃には、魔法の予感はかけらも残っていなかった。
「よし、私はこれから、魔女として生きていくのよ!」
そう声に出してみても、なんだか虚しい気持ちになるのだった。
勢いよく会社は辞めたものの、毎日の行く宛てといえば、コンビニしかない。魔法の手がかりが見るかることもなく、魔女らしいことなど何もできずに、日々が過ぎていくのだった。
いいなと思ったら応援しよう!

