
わたしが“遺贈寄付”を社会に広めたい理由
はじめまして。日本承継寄付協会の代表をしている三浦美樹といいます。
わたしは、寄付を通じて社会のお金の流れを変えることを目指し、そのために「遺贈寄付」を社会に広める活動をしています。
寄付と聞くと、ものすごく社会課題に関心の高い人やお金持ちの人がするものだと感じませんか?
わたしは寄付をすることが特別なことでも一部の人がするものでもなく、だれでも気軽に負担なくできる社会になるべきだと思っています。
例えば、お気に入りの洋服やおいしいコーヒーを買って幸せな気持ちになるように。応援したい取り組みに寄付をして、幸せな気持ちになる。
そんな日常が当たり前になるように、暮らしの中にさまざまな寄付の入り口をつくろうとしています。
今回、だれでも負担なくできる寄付の方法について、たくさんの人に知ってもらいたくてnoteをはじめることにしました。
遺贈寄付をするとどんないいことがあるのか?やり方は?寄付先の選び方は?わたしたちの団体のこれまでの活動についてなど…これからいろいろと書いていきたいと思っています。
1本目のこの記事では、わたしとわたしが運営する団体 日本承継寄付協会の取り組みについて自己紹介させてください。
先日開催されたIndustry Co-Creation(ICC)サミット FUKUOKA 2024のソーシャルグッド・カタパルトではプレゼンの機会をいただき、優勝することができました!プレゼンの動画がYouTubeで公開されているので、よかったらこちらもみてください。
亡くなった後に、自分の思いを社会に繋げ・残す
わたしが目指しているのは、だれでも気軽に負担なく寄付できる社会です。
そのためにまず取り組んでいるのが、日本で毎年50兆円ものお金が循環する財産の一部を、NPOの活動費など社会的な取り組みに寄付をする「遺贈寄付」。この取り組みを利用しやすく、そしてみなさんに知ってもらうこと。
遺贈寄付という言葉を、みなさん聞いたことはありますか?
当たり前ですが、人間は誰もが死を迎えます。その時に保有している財産を、自分の子どもや親族だけでなく、社会にも還元できる。そんな取り組みです。
「地元のために使ってほしい」「子どもたちを支えるNPOに使ってほしい」といった思いを、遺言書に残すことで寄付ができます。
亡くなったあとの財産から寄付をするので、生前の生活に負担がかかりません。1万円ほどの少額からもできるので、だれにとっても負担のない寄付の方法です。
もし50兆円と概算される年間の相続財産のうち、5%でも遺贈寄付されるようになると、毎年2.5兆円が若い世代や地域の高齢者、社会のために使えるお金が生まれることになります。
この遺贈寄付の取り組みは、高齢者が保有している資産を無理ない形で社会に還元することができる。そんな方法でもあると考えています。
日本の平均寿命は80代後半です。相続は基本的に亡くなった方の子どもにされていきます。
亡くなった方の相続人になるお子さんは、60〜70代。60〜70代といえば、自分が何歳まで生きるのか分からず老後の資金が不安なタイミングです。
相続したお金は使わず、80〜90代になるまで銀行に預けたまま亡くなって、またその子どもである60〜70代に相続されていくーー。

このように、高齢者間で資金が循環していくのは、老後に不安があるからです。物価が上がるのではないか。なにか怪我をするのではないか。不安は尽きません。
遺贈寄付であれば、自分が亡くなった後の遺産の相続先として、NPO法人を選ぶことができるので、財産が動くのは自分が人生を全うした後のこと。そして少額からでもできるので、残されたご家族に多大な負担をかけるものではありません。
お子さんがおらず財産を残す必要がないので、ふるさとや未来の子どもたちの教育に遺贈寄付をする。多くの財産を残せないからこそ、孫たちの思い出に残る使い方をしようと、近所の子ども食堂に30万円を遺贈寄付する。そんな選択ができるようになっています。
この遺贈寄付の取り組みは、海外ではメジャーではあるものの国内ではまだまだ認知がなく、活用が進んでいません。
情報を届けたり利用しやすい仕組みを構築して、一人ひとりに行動してもらうことができれば、いまの社会や未来をよりよくできる。
わたしが2019年に設立した日本承継寄付協会は、そのために活動しています。
だれでも負担なくできる寄付を社会に広げる取り組み
遺贈寄付をさまざまな方に知っていただき、利用していただくために、日本承継寄付協会はいろいろな活動を行っています。
認知をさらに広めるために、「えんギフト」という情報誌をつくって配布しています。遺贈寄付のやり方や、寄付先候補となるNPOなどの情報をまとめた日本で唯一の遺贈寄付の専門誌です。
相続について相談するときにほとんどの人が訪れる、全国の公証役場や士業事務所に設置していただいています。今年は1万部を配布予定です。

遺贈寄付の相談にのることができる人も足りていないので、専門家育成の認定講座を行っています。
金融機関や司法書士・弁護士・税理士などの士業の方やファイナンシャルプランナーさんのように、お金の相談にのる人たちが寄付の相談窓口にもなれれば、より確実に情報を届けることができます。
遺贈寄付の遺言書には作成費がかかるので、その費用を助成するキャンペーン「フリーウィルズキャンペーン」も行っています。昨年は50件の申し込みがありました。申し込みベースで「11億7800万円の遺贈寄付」がうまれる見込みになりました。
遺贈寄付に関する全国調査も毎年行って、実態を明らかにしながら活動にも反映しています。
これらの取り組みを、わたしたちはマッチング手数料はいただかず、主に会費と協賛金、研修費用で運営しています。
マッチング手数料を受け取り運営しているところもありますが、現段階では遺贈寄付をしようとする方の心理的ハードルになってしまう可能性を考えました。
マッチング手数料がないからいいという話ではありません。寄付の金額の大小や寄付先に関わらず、それぞれが協力できる範囲でお金や労力や気持ちを出し合って支えあう。そうやって、みんなでスピード感を持って広めていきたいと考えました。
協賛してくださる皆様をはじめとした、みんなの力を持ち寄ることで、利害関係を極力なくして遺贈寄付の存在や仕組みを広めることができる。そんな非営利のわたしたちらしい強みをいかして、挑戦していきたいと思っています。

寄付が身近になれば社会がもっとよくなる
この活動をはじめたのは、社会に恩返しをしたいと強く感じたからでした。
わたしは1️9歳のときに大きな交通事故にあっています。10回の手術を受けて、4年のあいだ入退院を繰り返しました。足を切断する可能性もあったし、一生歩けなくなる可能性もありました。
やりたいことが何もできないどん底な4年間を過ごしたわたしは、なにか夢中になれる目標がないと生きていけない気がして、司法書士の資格試験を目指しました。合格率3%と言われる試験。受かることは不可能に思える挑戦でした。
27歳で合格し、31歳のときには相続専門の司法書士事務所を構えて独立。
相続専門の司法書士として電話相談も含めると2,000件以上の相続の相談にのってきました。その間に、離婚を経験してシングルマザーとして子育てをしながら、毎日とても忙しくさせてもらっていました。
そんな忙しさにも慣れてきたころ、このままいわゆる社会的な成功を追い求めていいのだろうか。むしろ自分が受け取ってきたものを未来に返したい、社会に恩返しがしたい。そういう気持ちがあふれてきたタイミングがありました。
今までは、自分が頑張ることで道を切り開いてきたと思っていました。でもいろいろな人に支えられていたんだという、当たり前のことに気がついたんです。
一方で社会には支援を必要としている人たちがいて、そういった方々を支援する団体は資金調達に悩んでいます。
もっとたくさんの人にとって遺贈寄付が身近なものになれば、社会がよりよくなる方向にお金の流れを変えていけるんじゃないかと考えました。
39歳のときに、遺贈寄付を日本中に広めるために生きていこうと決めて、団体「日本承継寄付協会」を設立。一人で活動をはじめました。
それから5年、今では志を共にするメンバーも増えましたが、まだまだ道は半ばです。
遺贈寄付を通じて思いやりが循環する社会をめざして、さらに頑張っていきたいと思っています。応援をいただけたらうれしいです。
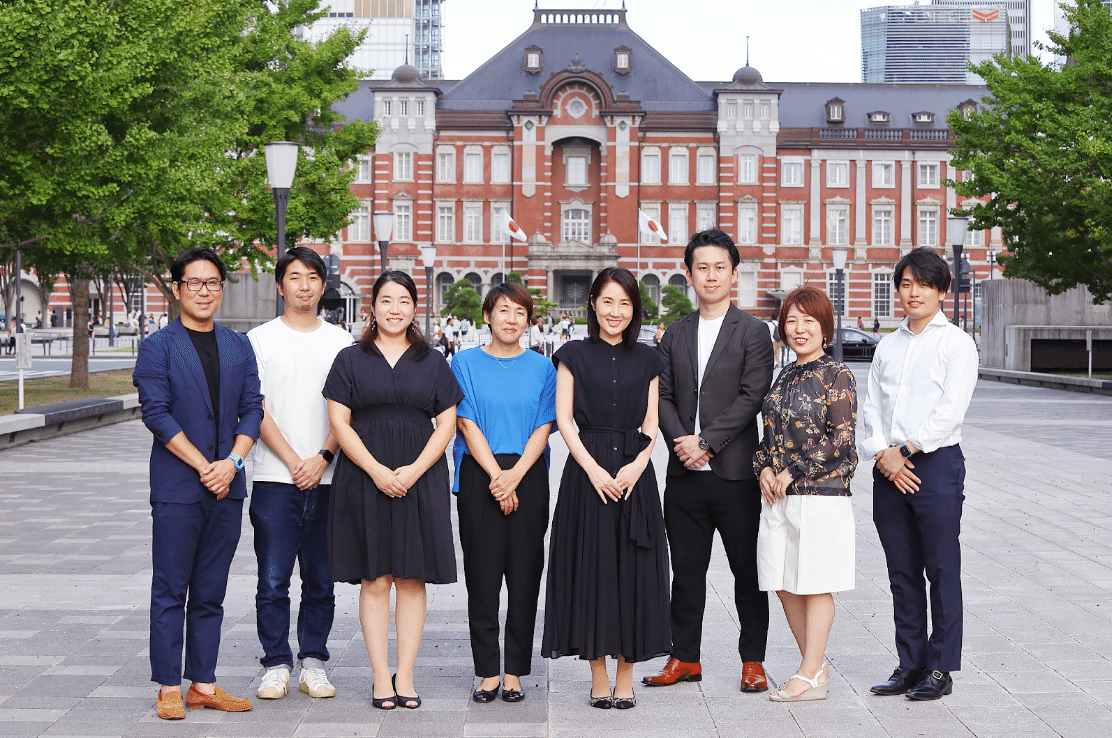
“遺贈寄付が分かる”を届ける情報誌「えんギフト」は無料で配布しています。
もし興味をもっていただけた方がいれば、ぜひこちらのリンクから無料配布のお申し込みをお願いします。
