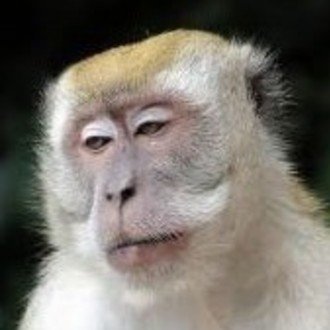星と風と海流の民#60~おわり/沖縄に縄文人の痕跡を訪ねて#05

帰京後、大山の貝塚遺跡について改めて調べてみた。
ほんの少し資料を読むだけでも、この遺跡が持つ歴史的な意義が次々と浮かび上がってくる。驚いたのは、僕が訪れた数年前には既にこの貝塚が1972年に国の史跡に指定されていたことだ。この大山貝塚は、沖縄で初めて層位的な発掘が成功した場所であり、それが沖縄考古学における土器編年の確立に大きく貢献したという。
僕とティムが歩いた雑木林は、市の中央部に広がる琉球石灰岩台地の最上段に位置していた。そこは西海岸に面した三段の段丘の一角で、石灰岩の小洞窟の前庭部に堆積した小規模な混土貝層から成り立っている。その地からは、貝殻や石器、骨器といった実用品に加えて、大量の土器が発掘された。それらの土器は層位ごとに形式が異なり、それぞれが当時の文化層を物語っている。下層からは伊波式や荻堂式土器が発見され、貝塚時代初期の特徴をよく表している。
中でも、中層から発見された「大山式土器」のことは特筆すべきことだと書かれていた。この土器は沖縄貝塚時代前期後半を代表する形式として知られ、その時期区分の基準ともなったという。深鉢形で平底を持ち、箆で器体上半分に押捺された方形の連続文様は、当時の工芸技術の高度さを如実に示している。また、上層からはカヤウチバンタ式土器が発見され、貝塚時代中期の文化的進展を明らかにしている。このように、大山の貝塚は沖縄の文化史を語る上で欠かせない存在らしい。
雑木林の林道を歩いているだけでは、このような遺跡の意義も意味も分からなかったが、その場に漂う時代の気配を肌で感じた。
「ミスク森が、沖縄の古代人の村だったのかぁ。考えたこともなかったなぁ」クルマ走らせながらティムが呟くように言った。
「ミスク森?」
「沖縄の土着信仰だよ。美底山は、ずっと昔から豊作祈願や悪霊退散、健康を祈るための儀式が行われる場所だったんだ。沖縄のカミは、自然そのものだからな。山や森、岩や泉がカミなんだ。ウチのオフクロも、あの人が見てる神はキリスト教徒たちが見ているカミとはちがう。
ミスク森は、そんなカミの宿るところだ。今はそれを今風に"心霊スポット"と云ってる」
「カミは昔からお座しますものだ。2000年前や3000年前どころじゃない、聖域そのものは人知を超えた遥か昔からあるものさ」
「マイクの話を聞いてると、しまいにめまいがしてくるな。・・そうか。カイヅカか。たしかにそうだよな。人が集まって暮らせば、ゴミ捨て場は出来る。そのゴミ捨て場は、その時代の象徴だろうな。今ならそれはプラスチック缶だろうな」
「貝塚は、当時の生活や文化を物語る貴重な遺跡だ。沖縄に貝塚が生まれるほど人が住みついたのは、4000年ほど前からだ。彼らは台湾やフィリピン、それに東南アジアの島々からやってきた。それが沖縄に生きた縄文人たちだ。彼らの特徴は黒潮に乗って渡ってきた南の海洋民族だということだ。隼人の人々だ」
「隼人?Sea Peoplesかあ」
「ん。太平洋を渡りきるほどの航海技術を持っていた。彼らは沖縄だけじゃなく奄美とか先島にも定着して、それぞれ独自の文化を作り上げている。何れも漁労中心の採集生活で、洞窟や岩陰に住んだり、弓矢とか銛を使った狩りや漁をしてた」
「さっき森の中で見た洞窟がそれか?」
「かもしれない。それが形を変えて今の形になってるのかもしれない」
「祠だったもんな」
「海を渡った人々は、舟にヤムイモやタロイモを乗せていた。沖縄では定着しなかったようだがパンノキとかココヤシも、彼らは移動と共に運んだんだ」
「豚は?」
「豚は縄文後期になってからだそうだ。鶏はもっと遅くなってからだ」
「肉食は?しなかったのか?」
「2000年ほど前に、中国に魏という国が有った。ここの書に日本列島の人々を描いたものがある。『魏志倭人伝』というんだ」
「ふうん」
「そのなかに"其地無牛馬虎豹羊鵲"とある。この地に牛、馬、虎、豹、羊、カササギは無いと書かれている。獣肉は食べなかったのかもしれないな。
・・ただ。これは想像だけど、亀は食べたと思う」
「亀?」
「ポナペのナンマドールを訪ねた時、亀を養殖した池が有った。甲羅を積んだ亀塚があるという話を聞いたからな。海の動物は魚類以外も食べたと思うな」
「なるほど」

隼人たちは、狩猟や漁労を主とする採集生活を送りながら、洞窟や岩陰を住処にしていた。その中で培われた航海技術は、やがて沖縄だけでなく奄美や先島にも広がり、それぞれ独自の文化を生み出していった。彼らは舟にヤムイモやタロイモを積み込み、移動先で食料や作物を持ち込んだ。豚や鶏が沖縄に定着したのはもっと後の時代だが、彼らの移動と交易は、周辺地域に文化的な影響を及ぼした。
そして紀元前1000年頃になると、沖縄では焼畑農業が広がり始める。ただし、本土で広まった水稲耕作は沖縄に及ばなかった。その理由は明らかではないが、稲作文化を持ち込んだ人々が沖縄を経由しなかったことや、地理的条件が大きく影響したと考えられる。本土との交易はあったものの、民族単位の移動はほとんどなかった。沖縄の独自性や純血性は、ある意味でその地理的隔絶と資源の乏しさがもたらしたものかもしれない。
それでも、隼人たちは周辺地域との交易を通じて文化や技術を交換し、それが後のグスク時代や琉球王国の成立につながっていく。
帰京したのち、近くの図書館で手にした資料を見つめながら・・僕はティムと歩いたの美底山の聖域である「ミスク森」拝所のことを思い浮かべた。
「ミスク」は御嶽(うたき)を指す。僕らが歩いたあの森は、数千年も地域の人々が代々守り続けてきた場所だった。南太平洋の星と風と海流の民を追いながら、僕は沖縄の神々に出会ったのだ。
いいなと思ったら応援しよう!