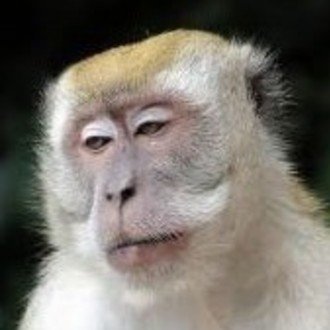星と風と海流の民を訪ねて: スンダランドとラピタ人 Kindle版
きっかけはラピタ人だった。
海幸彦山幸彦の原点である隼人/縄文人にラピタ人の血流を感じたことからだった。
遥か昔、ラピタ人と呼ばれる人々が広大な太平洋にその存在を刻んだ。 彼らは人類史上初めて遠洋航海を始めた民族として知られ、現在のポリネシア人の先祖先とされている。
彼らが日本へ流れてきたのではないか?
そんな疑問から「星と風と海流の民」を意識するようになった。
ラピタ人の起源については、いくつかの説がある。 台湾や中国南部のオーストロネシア人が新石器時代に人口増加の影響で移住を始めるたのではないかという説がある。これらの地域では約3 0,000年から35,000年前に人類が生活していた痕跡があり、これをラピタルーツとする意見もある。僕は30年余りかけて、これを訪ねた
そのラピタの軌跡を追っているとき、僕はスンダランドに出会ったのである。
最終氷期の頃、東南アジアにはスンダランドと呼ばれる広大な陸地が存在していた時代があった。この、海水面は現在よりも低く、マレー半島、スマトラ島、ジャワ島、ボルネオ島といった地域続きの大地豊かな自然環境が広がり、多様な生物や人々の生活が営まれていたと考えられている。
しかし、氷期が終わり、地球の温暖化が進むにつれて状況は一変する。 氷河が溶け始め、海水面が徐々に上昇。 広大だったスンダランドの陸地は水没し、人々は島々に分断される。
今ではスンダランドの痕跡は、大半が海の底に眠っている。
スンダランドは、地球が刻んできた長い歴史の一部を物語る存在だ。 自然の力による変化は時々厳しいが、そこには新たな環境への適応や生命の逞しが垣間見える。陸地がどのような姿だったのかを想像することで、自然の偉大さや私たちが生きる地球の変化を全面的に感じることができるのだ。
この稿では、こうした太平洋西側で起きたヒトの大きな潮流を、実際に現場を訪ねて追った記録をまとめたものである。
目次/星と風と海流の民を訪ねて
●はじめに/グアム・南洋の民との出会いから
1.1/ポナペのナンマドールを訪ねて
1.2/ポナペの友人トシさんに会う
1.3/ポナペのトシさんとルシアとの夕餉
1.4/ポナペの早い朝で中島敦を思う
1.5/ポナペを描いた敦の風物抄
1.6/ポナペ・ナンマドールへ向かう
1.7/ポナペ・ナンマドールで幻視したもの
1.8/ポナペ・ナンマドールからの帰路
1.9/ポナペが西欧文明に出会ったこと
2.1/シンガポール・フォートカミングの丘を歩く
2.2/早朝のフォートカミングの丘へ
3.1/バヌアツで見つめるラピタの裔
3.2/バヌアツ・バウアフィールド国際空港
3.3/バヌアツ・白砂のビーチとサンゴ礁
3.4/バヌアツ・産業としての金融
3.5/バヌアツで歩いた朝のマーケット
3.6/バヌアツ・黒いピキニニマルウア
3.7/バヌアツ・テウエア遺跡
3.8/バヌアツの国立博物館
3.9/バヌアツにラピタ人の影を追う
幕間#01/ラピタの彷徨を幻視する
4.1/グアムとチャモロ人
4.2/グアムにチャモロ人の遺跡を訪ねた
4.3/グアムの朝のマーケット
4.4/グアムでプンタンとフーナの岩を訪ねた
4.5/グアム・マゼラン記念碑
4.6/グアムに残されたチャモロ遺跡
幕間#02/夏華人に追われた隼人たち
5.1/カンボジアに扶南王国を訪ねた
5.2/カンボジア・アンコール・ボレイ博物館
5.3/カンボジアの消えた古都ヴィヤダブラ
5.4/カンボジア・アンコール・ボレイの村を歩
5.5/カンボジア・若き友たちとの話
5.6/カンボジアで見つめるミトコンドリア・イヴ
幕間#03/ミランコビッチ・サイクル
6.1/トンガ・隼人たちの鳥居を訪ねた
6.2/トンガで話す南太平洋の今
6.3/トンガで考えたラピタ人の軌跡
6.4/トンガ・隼人たちの聖域に立つ鳥居を訪ねた
6.5/トンガで日本語と古代ポリネシア語について考えた
7.1/ハワイという隼人たちの最終帰着点を訪ねた
7.2/ハワイのビショップ博物館を訪ねた
7.3/ハワイ・カーネの聖地コオラウ山地を訪ねた
7.4/ハワイというカアアア渓谷クアロア牧場を歩く
7.5/ハワイを買い漁った欧米人たち
7.6/ハワイではカーネと呼ばれるタンガロアのこと
幕間#04/スンダランドとイヴの子供たち
8-1/竹芝桟橋から見つめた隼人の道
9.1/オキナワで出会う縄文人の影
9.2/オキナワ・丸山遺跡#01
9.3/オキナワ・丸山遺跡#02
●おわりに/海上の道
いいなと思ったら応援しよう!