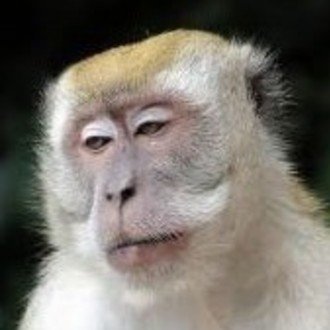オデッサ考古学博物館03

オデッサの博物館を彷徨しながら考えたのは、ポントス・カスピ海草原に生きたヤムナ/アンドロノヴォ/シンタシュタの人々のことだ。彼らは、小氷河期が終わったために、余儀なく新たな牧草地や資源を求めて、さらに南へ移動するしかなかった。そしてインドやイランへ拡散していったのではないか・・それを考えていた。
見つめていたのは、黒海北岸へのギリシャ人が進出したころの豊富な遺品だった。しかし僕が幻視したのは、南東へ広がっていったヤムナ/アンドロノヴォ/シンタシュタ人のことだった。彼らこそがアーリア人の始祖なのだ。
間氷期の温暖化のとき、ユーラシアのステップ地帯は、深刻な乾燥化に陥った。草原は縮小し、ヤムナ/アンドロノヴォ/シンタシュタの人々は生活基盤を失った。・・ヒトの大移動はいつでもこうした気候変動が引き金となる。
元来、遊牧民だった彼らは、居住地を移すことにさほどの抵抗感はなかったと思う。そして彼らは馬と戦車を中心にした軍事力を備えていたので、他地域への侵入や支配も左程難しくはなかったに違いない。・・その移動はBC2000年頃から始まっている。ひとつはカスピ海東岸を抜けてインド亜大陸へ。そしてもう一つの流れは、カスピ海南側イランへと向かった。

インド亜大陸へ拡散した人々は、トルクメニスタンからアフガニスタン(アンドロノヴォ文化Andronovo Culture)を抜けてインド北部に入った。そしてパンジャブ地方やガンジス川流域へ定住した。
しかし、そこには既にドラヴィダ人がいた。インダス文明を生み出した人々だ。
現存するヒンドゥーの聖典『リグヴェーダ』を読むと、その中にダサDasaやダシュDasyuと言う敵対的な存在が登場する。これはまさに先住民ドラヴィダ人を指している。その抗争と支配から、アーリア人はヴェーダ文明を築き上げていった。
今でもインド文化に残るカースト制だが、上位と下位の差は、はっきりと肌の色の差で現れる。今でもアーリア人が上位支配階級なのだ。
例えば・・"天空の父・ディヤウスDyaus"だが『リグヴェーダ』では"ディヤウス・ピターDyaus Pitar"と"プリーティヴィーPrithvi(大地の母)"と対を為す神として描かれる。この二神は「宇宙の親」であり「全ての生き物や神々の祖」である。・・後にその位置は主神インドラに取って代わられるが、間違いなくアーリア人の祖先神的だったにちがいない。
その語源である"dyu(明るい、光)"は印欧語族では「天空」や「昼の明るさ」を指しており。同じ語源を持つ人々の神々でも同じく「天の父」を指している。。ギリシャ神話のゼウス(Zeus)やローマ神話のユピテル(Jupiter)は。まさにソレだ。
例えば・・ヤマYamaは人類最初の死者であり、ヴェーダには「死者の王」として登場する。ヤマはアーリア人の伝承では「最初の人間」でありヒンドゥーの中では人類や文化の始祖でもある。ヤマYamaはそのままマヌManuに繋がり、これが『マヌ法典』となってインド亜大陸での生活規範の基礎になっている。
こうして中央アジアから南進してきたアーリア人は、インド亜大陸でヴェーダ文化を産み出し、バラモン教を作り上げ、これがヒンドゥー教となりインド亜大陸を基盤として、南アジアへ拡大した。

・・もうひとつの、イラン高原へ広がった人々だが。
彼らの前にはエラム人Elamがいた。彼らはスサSusaを中心に栄え、独自の言語と文化を持っていた。ところが、このエラム人とアーリア人の間で軍事的な衝突があったかというと、明確な記録はない。もしかすると圧倒的な軍事力の差が二者の間に有ったのかもしれない。BC1100年頃には、イラン高原での支配階級は大きな衝突もなくアーリア人のものになっている。これがペルシャ文明である。これが後にアケメネス朝ペルシア帝国へと進化した。言うまでもないがその勢力の西側にはメソポタミア文化が花開いている。ソポタミアシュメール人、アッカド人、バビロニア人、アッシリア人たちが折り重なって醸し出した文化だ。ペルシア帝国は、BC539年にキュロス2世がバビロンを征服し、メソポタミア全域を支配下に収めている。しかしその方法は融合に近いもので、メソポタミアは消滅しないまま長く伝統として後世まで受け継がれている。
半日ほどかけたオデッサ考古学博物館歩きは、お目当てのヤムナ/アンドロノヴォ/シンタシュタ文化だけではなく、もっと広く古代エジプトのコレクションそして古代ギリシャ・ローマのコレクションまで及んだ。そして中世時代に黒海北海岸で生きた人々が使用した陶器/武器/日用品なども見学できた。黒海の歴史が俯瞰できる素晴らしい体験だった。

いいなと思ったら応援しよう!