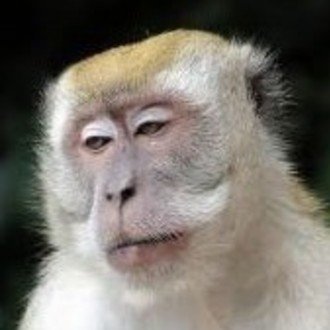バスク紀行: フレンチサイド/スペインサイド その2000年 Kindle版
ピレネーの向こうはヨーロッパではないと言う。
ナポレオンは「アフリカだ」と言いきった。
僕がそれを実感したのは、オルリー空港からマドリッドへ向かうエアフランスの機上からだった。30年ほど前だ。良く晴れた冬の朝便だった。その日、僕は写真を撮るために窓側へ座った。2時間ぐらいのフライトだったろうか。水平飛行に移ると、窓の外/パリのすぐ南に広がる広大な平野は雲海に包まれた。
一時間半ほど飛ぶと、その雲海の間から岩峰が見え始めた。白い岩峰である。ピレネー山脈だ。
しばらく見つめていると、その複雑に連なる頂きの一つを旅客機は越えた。越えると極端に雲が少なくなった。地中海性気候がこの峰々で分断されているのだ。驚くほど極端に、スペイン側とフランス側の景色が違うことは機上からも判った。スペイン側は、明らかに乾いた山肌が折り重りあっている。造山運動と氷河がもたらした奇景だ。
アルプス山系よりも遥かに旧いピレネーは古生代から中生代にかけて形成された大地の襞だ。旧神蠕動の痕だ。そのため、東半分は鋭く立ち上がり花崗岩や片麻岩に覆われている。一方西側は緩やかに立ち上がる。頂上付近は花崗岩が剥き出しだが、低斜面は石灰岩が中心である。つまり遥か太古の海底がそこに横たわっているわけだ。
なるほど。この巨大な壁をフランク人たちは暫く越えられなかった。猛烈な勢いで欧州を席巻したクローヴィスの末裔も、この壁の前では立ち往生するしかなかったのだ。僕は機上でそう思った。
しかしローマ人は、仇敵フェニキア人の末裔の地を滅ぼすために地中海沿いで入った。そしてこの地を一時的だがローマの管理下に置いた。それでも支配までには及ばなかった。ローマは短命だった。その技術と宗教を受け継いだフランク人/ゲルマン人だが、ピレネーの向こうに左程関心を示さなかった最大の理由は、このまるで喉許を区切るように走る山塊のためだろう。そう実感した
ピレネーの山塊は旧いパンゲアの夢を未だ見続けている地だ。その意味では北側(フランス)も南側(スペイン)も同じ地祇の末裔だと云えよう。しかし連なる峰々で分断された気象は、著しく2つの大地の風土を変えている。それに相まって深く氷河の傷口が残るのことがスペイン側の大きな特徴でもある。西部中部の高山には今でも小規模な氷河が残っている。
降水量はフランス側のほうが多い。スペイン側は少ない。その違いが農耕の浸透を決定付けた。フランス側は早くから灌漑方式の大規模農業が定着したが、スペイン側は立ち遅れた。ピレネーの西側では、長い間羊追いが糧の中心として続いたのだ。
これもまたフランク人のたちが、ピレネーの西側に強い関心を示さなかった大きな理由だと僕は思う。移植したとしても、その地で出来る産業はあまりにも貧しいのだ。
フェニキア人も、この地には採鉱以外の価値を見出せなかった。ピレネーは長く貧しい地域のまま放置された。
しかしこれも前世紀半ばを過ぎると、その豊かな水系を利用した工業地帯が幾つも出来るようになり、事態は一変する。技術的な発展によって採掘や採石など地神の血肉を頂く作業が容易になると、スペイン側ピレネーは鉱業地帯として大きく花開いたのである。
考えてみるとスペインの採掘文化は長い。スペインと云う国が生まれる前から産業として確立していた産業である。西アフリカ経由で西進してきたフェニキア人と、北海から下ってたケルト人たちが融合しこの地で錫などを採掘したのだ。青銅作りには錫は必須である。ローマ人たちもこの地の錫を欲しがった。盛んに交易は行われた。そのためスペインでは早くから採鉱技術が定着し大きく育ったのだ。
ローマが国力を付けるようになると、この地を欲しがった大きな理由はそれだ。そして仇敵カルタゴに繋がるスペインを憎んだことだ。
ローマ人は地中海側からこの地を攻めた。膨大な数のゲルマン/ケルト人傭兵を送り込んだのである。傭兵たちは一定期間戦うと、ローマ市民権と共にピレネー東側海岸沿いに土地を与えられる。その自分の土地を得るために傭兵たちは一所懸命・・一つの所(地)を得るために、異郷の地で命を懸けたのである。
スペイン側とローマの攻防は一進一退が長く続いた。それが何時しかモスレム対キリスト教という宗教戦争に変転し、長くこの地を痛め続けた。最終的にはキリスト教勢によって制圧されるのだが、民の気質はそのまま変わらず残ったように思える。その一番大きな理由は、ピレネーを越えてまでフランク人/ラテン人たちがこの地に入り込んでこなかったからではないか?そんな風に思える。確かに支配者は替わった。しかしその支配者でさえ長い時代の変遷の中で地元の地と混ざり合い、何時の間にか非欧州的で無くなって行ったのではないか?そんな風に思える。
そんなふうにピレネー山塊周辺を機上から見つめているうちに、僕はなんとも不思議な感覚になった。それにしても・・少なくともこの山塊に人は住み続けている。それも流浪拡散しないまま、この地に根付いている。もしかすると・・数千年単位で。あるいは万年単位で・・住み続けている。
「ピレネーの向こうはヨーロッパではない」と言う。たしかにそうかもしれない。しかしこの眼下に拡がる境界線ピレネー山塊に潜んで暮らす人々もまた・・実は「スペインでもヨーロッパでもない」のかもしれない。
僕がピレネー山塊周辺の人々に強い興味を持ったのはそのときからだった。そして、彼らが緩衝帯として存在したから、スペインは現在に至るまで欧州化しなかったのではないか?
そう思いつくと、僕は鳥肌が立った。
ここでは、その地に生きる彼らを一括りに「バスクの民」と呼ぼう。
バスク人の定義は、交雑し諸説が走る。それを知った上で彼らをバスクの民と呼びたい。
自分たちだけの言語を持ち、自分たちだけの血を守り、長い間混血しないまま守られた一族。彼らは言葉を持っていたが、文字は持たなかった。彼らの文化の中には、記録しなければ成り立たない文明は現れなかった。たとえば簿記/数的管理は無用だった。しかし血縁は何よりも重要だった。自分たちがフェニキア人やラテン人、ケルト人とは違う「人種」であることを先験的に理解していたのだ。
いいなと思ったら応援しよう!