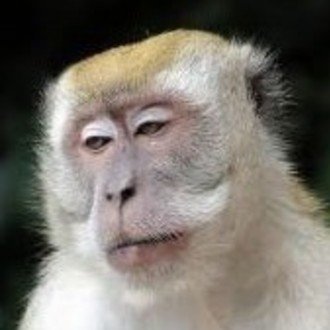夫婦で歩くブルゴーニュ歴史散歩1-6/ガリアの血・古代ボーヌ02
https://www.youtube.com/watch?v=Z2Y1nGznudc
ブゼーズの泉の周囲をゆっくりと散歩した後、フォーブール・マルタント通りRue du Faubourg Saint-Martinへ出て、ボーヌの城壁へ戻った。そしてD974を左へ曲がった。
「ちょい先にテラス席が広いレストランがあるんだ。そこで昼飯しよう。
➀La Table du Square(26 Bd Maréchal Foch, 21200 Beaune)
https://www.facebook.com/p/La-Table-Du-Square-Beaune-100063496093752/
明るい戸外で、爽やかな昼食だった。
「ところで、あなたの話に出てくるガリア人とかケルト人って、ヨーロッパの先住民のことを言ってるの?」
「んんんん、厳密にいうと違う。先住民というのが、新石器時代からヨーロッパに拡散されたヒトの裔で地元に残っていた人々・・というなら違う。黒海周辺で発生した印欧語族の文化を背負った人々だ。部族とか人種とかではない。同じ言語体制を持った人々だ」
「黒海周辺にいた民族が拡散したわけじゃないの?」
「ちがう。部族と云うなら・・部族は無数に折り重なっていた。共通項は(ローマ人が云うところの)ケルト語を話すということだけだ」
「だったら、新石器時代からずっとソコにいて、言葉だけがケルト語になった人たちもいた・・かもしれないの?」
「ん。対立もあったが混血は普通にあったはずだ」
「じゃあ、ガリア人は?」
「カエサルはガリア戦記の中で『ガリア人はケルト人Celtaeと自称する』と書いている。歴史学者ストラボンも紀元一世紀に『現在ガリアともガラトとも呼ばれる民族』という一項をおいて『ガリアは別名としてケルティカがある』と書いている。彼は『イベリアにもケルト人がおり、彼らをケルティベリとケルティシと呼んでいる』と書いている。大プリニウスも『ルシタニアLusitaniaではケルティチが部族の姓として使用されることが多い」と書いている」
「よ~するにガリア人=ケルト人なの?引用が多くて意味ぷーだわ」
「ん。今っぽく言うなら、ヨーロッパ大陸にいるケルト語を話す人々がガリア人。その周辺はケルト人・・ていどでいいかな」
「で。この辺に、ローマ人が入ってくるまでは、此処はガリア人の土地だったわけね」
「そうです。すいません」
「よろしい」
「ローヌ川/ソーヌ川は、ハルシュタットあたりから(ローマ人が云う)ガリアの時代まで、無数のケルト人たちが入れ替わりに取ったり取られたりしていた」
「どうして?」
「水路だよ。水路は重要な移動手段であり、糧を得られる方法だったからだ」
「なるほどね」
「これは新進勢力だったローマも同じだ」
強大な部族として北西部にセノン族がいた。彼らの拠点はゲディンクム(センス)だった。リンゴン人はアンデマントゥヌム(ラングル) を占有していた。マンドゥビア人はオーソワの中央窪地とアレシア周辺を掌握していた。
ちなみに・・アエドゥイ族が当時ソーヌ川/ローヌ川の周辺・要所を押さえていた。しかし東方にいたセカンヌ族が、ジュラ山脈からソーヌ川まで勢力を広げており、アエドゥイ族はこれと衝突した。劣勢に陥ったアエドゥイ族は苦し紛れにローマへ救済を求めた。ローマは、ローヌ川というきわめて重要なロジスティックを失うことは絶対に出来ない。ローマに歯向かう輩は殲滅するしかなかった。
これがカエサルのガリア侵略戦争の切っ掛けになったのである。

いいなと思ったら応援しよう!