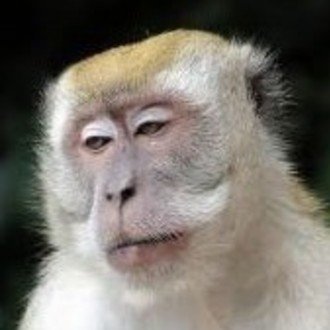石油の話#01/キッシンジャーという人形使いの仕事から話を始めたいと思う
20世紀に入り、突然のように躍進を遂げた「石油」というエネルギーを考えると、進化の過程で特定の身体の一部を異様に発達させた生物たちの姿を連想します。三葉虫やアンモナイト、サーベルタイガーといった生物はその典型例です。彼らは捕食や生存に特化するため、一部を極端に進化させた結果、環境変化への弱さを抱え、絶滅してしまいました。
身近な例としては、戦後の日本の加工貿易産業があります。戦時特需を背景に急成長し、日本経済の中心的存在となりました。しかし、特需の終了や周辺国の台頭による競争激化で急速に衰退しました。特定分野に過度に依存した結果、産業全体が硬直化し、新しい成長分野を見出すのが難しくなったのです。その結果、日本は「おもてなし産業」以外での成長余地が狭まることになりました。
石油を内燃機関の熱源とする仕組みを考えると、これもまた奇形的な進化を遂げているように見えます。この進化は21世紀にも続くのでしょう。しかし、世界が石油を中心に回り続けることには変わりありません。
こうした石油を巡る構造に最初に気づいたのは誰だったのでしょうか。おそらく、その名を挙げるならヘンリー・キッシンジャーです。彼が提案した「石油取引をドル建てで行う」という仕組みは、世界経済をアメリカ通貨であるドルに基軸化させました。このアイデアにより、ドルは不換紙幣でありながら世界の基軸通貨となったのです。
「ペトロダラー(petrodollar)」という言葉を最初に使ったのは、経済学者のイブラヒム・O・シヤーウスでした。この言葉は1973年の第一次石油危機を機に広まり、現在では経済用語として定着しています。
中東の産油国、特にサウジアラビアが「石油取引をドルで行う」という提案を受け入れた背景には、国内外の不安定な情勢がありました。中東諸国は、政治的安定と軍事的保護を得るため、アメリカの軍事力に依存する道を選びました。この流れの中で、1974年にサウジアラビアとアメリカの間で合意が結ばれ、ペトロダラー体制が始まりました。
この仕組みにより、中東諸国はアメリカの支援を受けながら内政の安定を図り、地域全体の安全保障にもアメリカが関与するようになりました。ペトロダラー体制は、冷戦期の国際秩序にも大きな影響を及ぼしました。アメリカはソ連との対立を背景に、中東諸国を自陣営に引き込む戦略を進めたのです。
ペトロダラー体制は、中東諸国に経済的な恩恵ももたらしました。ドルを蓄えることで、輸入品の調達や海外投資が容易になり、経済的な安定を得ることができたのです。しかし、この構造は一方的な利益をもたらしたわけではありません。ドル依存の経済構造は、金融市場の動揺やアメリカの経済政策の影響を受けやすいという弱点も抱えていました。
それでも、中東諸国がペトロダラー体制を受け入れ続けているのは、政治的・経済的な計算が見事にバランスしているからと言えるでしょう。
いいなと思ったら応援しよう!