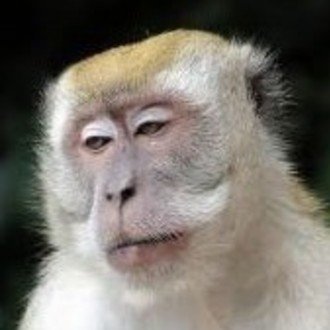石油の話#15/内燃機関の台頭が石油の需要を変えた
ほぼ同じ時期である1860年、フランスでは画期的な発明が生まれました。それは、石炭ガスをシリンダー内で燃焼させ、その圧力を動力へと変換する「ガスエンジン」でした。この革新的なエンジンを生み出したのは、エティエンヌ・ルノワール(Jean-Joseph Étienne Lenoir)というフランスの技術者でした。ルノワールのエンジンは、それまでの蒸気機関とは異なり、外部で水を沸騰させて蒸気を発生させるのではなく、シリンダー内部で燃料を燃焼させ、直接ピストンを動かす方式を採用していました。この技術は、機械の小型化を可能にし、従来の蒸気機関に比べて設備費が大幅に抑えられるという利点がありました。特に、当時の交通手段として急速に発展しつつあった自動馬車に適しており、都市部での移動手段として期待を集めました。しかしながら、ルノワールのエンジンには課題も多く、燃料の燃焼効率が低いため、出力が不十分であり、さらに冷却機構の問題から長時間の連続運転には適していませんでした。
こうした課題を克服し、より高効率な内燃機関を開発したのが、前述、ドイツのニコラウス・アウグスト・オットーでした。彼がガソリンを燃料とする新たなエンジンを開発したことで、劇的にマーケットは大きく変わったのです。
石油は灯火の燃料としての役割を超え、駆動力を生み出すためのエネルギー源としての地位を確立していったのです。彼の内燃機関が実用化されると、石油の需要は爆発的に増大し、これに応じて石油産業はますます発展していきました。
しかしながら、石油市場における競争は熾烈を極めました。需要が拡大する一方で、供給も急増し、価格の乱高下が続きました。そのため、企業間で価格を一定に保つための協定が自然発生的に生まれ、同業種内でカルテル(プール)が形成されるようになりました。それでも市場の競争は熾烈さを増すばかりで、各企業は生き残りをかけて激しい戦いを繰り広げました。この混乱の中で、卓越した経営手腕と強硬な戦略によって覇権を握ったのが、ジョン・D・ロックフェラー率いるスタンダード・オイル社でした。
ロックフェラーは、徹底的なコスト削減と効率化を進める一方で、競争相手を排除するために、強引な買収や市場支配戦略を駆使しました。彼の手法は、単なるビジネス戦略にとどまらず、敵対企業への供給遮断、価格競争による徹底的な締め上げ、さらには政府や鉄道会社との密接な関係を築くことで、市場を完全にコントロールするというものでした。そのため、ロックフェラーは「Robber Baron(泥棒貴族)」と呼ばれるようになりました。この言葉は、かつて中世ヨーロッパで旅人から法外な通行料を徴収していた貴族を指すものですが、ロックフェラーのやり方も同様に、ライバル企業や市場に対して一方的な支配を行う姿勢から、このように称されたのです。
20世紀に入ると、ガソリンを燃料とする内燃機関は、さらに多方面で活用されるようになりました。1908年には、ヘンリー・フォードがベルトコンベア方式を利用した自動車の大量生産システムを確立し、これにより自動車の価格は劇的に下がり、一般市民にも普及していきました。こうして、自動車産業の急速な発展とともに、石油市場はかつてないほどの成長を遂げました。その中で、ロックフェラー率いるスタンダード・オイル社は市場の90%を支配するに至り、もはや完全な独占企業となりました。同時期、アメリカでは鉄道業界や製糖業界でも同様の独占状態が生まれていました。
こうした寡占状態は、自由競争を阻害し、経済の健全な発展を妨げるものと判断したアメリカ合衆国連邦議会は、1890年にシャーマン反トラスト法、1914年にクレイトン法を制定しました。これらの法律は、独占企業を解体し、公正な市場競争を確保するためのものでした。これを受けて、1911年、スタンダード・オイル社は地域ごとの34社に分割されることとなりました。しかし、これは名目上の解体にすぎず、実際には分割後もそれぞれの企業はロックフェラーの支配下にありました。結果として、彼の資産は単に分散しただけであり、むしろ複数の企業の株式を所有することで、リスクの分散とさらなる資産の拡大を図ることができました。こうして、スタンダード・オイルの解体は、ロックフェラーにとっては実質的なダメージとはならず、むしろ彼の影響力をより広範囲に及ぼす結果となったのです。
その後も、ロックフェラーの財閥はアメリカの経済と政治に強い影響を及ぼし続けました。彼の資産は、石油産業のみならず、銀行、鉄道、製造業、さらには教育や医療といった分野にまで及び、アメリカ社会のあらゆる側面に深く根付いていきました。現在に至るまで、ロックフェラーの影響力は脈々と受け継がれ、彼の築いた帝国はなおも存続しているのです。
いいなと思ったら応援しよう!