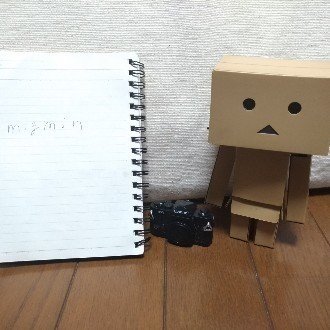インターネットにおける奇妙な癖
ブログやSNSを見すぎたためか、それともインターネットというものを見すぎたためか。最近自分の少し変わった行動を見てしまいました。
それは何かというと「コメント欄を探す」です。ブログやSNSに当たり前にあるこの機能ですが、ニュースサイトや情報サイトのようなところには一部のサイトではあるもののほとんどのサイトではありません。というかついていないことが当たり前のような気がしますが、それでも何かと探してしまいます。
具体的にどういった行動をとっているかというと、まずはメインの情報について読みます。そして読み終わったらブラウザバックやタブを閉じる行為をするのが普通だと思いますが自分の場合、ページを一番下までスクロールをします。そうすることによってコメント欄の有無を探しています。
またこのコメント欄を探すという行為ですが、自分を客観視してみるとコメントの有無を気にしているわけではないらしい。むしろあのコメントをするであろう四角形の入力スペースを確認しているようなのです。
この癖について考えてみると、どうやらコメント欄のついていないサイトでもブログのような感覚で見ているのが原因かなと思います。ということは自分にとって情報とは流し見で見るものとしてどこか定着しているのかもしれません。
もちろん関心のあるものに関してはしっかりと読んでいます。ただそういったものは一部にしかすぎません。大部分は流し見であることがほとんどです。
このように流し見で見るということはどこか情報の価値が希薄化していることにつながっているように思います。1つの情報をじっくり追うというよりは様々な情報にどんどんと触れる時間を増やしているという感覚です。
これは一見するといいことですが、希薄化しているがゆえに個々のトピックについての関心が段々とうすくなっているとも言えます。このままでいくとどんな物事でもありふれた情報の1つとして感じてしまうことに繋がりかねません。
ここまで行くと自分は何のために情報を見ているのかいよいよ分からなくなってきます。表面的な情報を追うだけで一体何を見ているのだろうか。
と、ここまで考えているのかは分かりませんがコメント欄を探すという奇妙な癖からここまで考えを掘り下げてみました。情報についての大きさというか量や価値は様々なのはわかりますし、そういった価値や大きさによって読む時間を変えているので大丈夫だと思います。
ただそういった何を見ているか分からなくなるという懸念もどこかにもつ必要性はありそうです。実際こうした表面の情報しか追っていない人というのをインターネットで見かける機会が増えてきました。そういった人たちに限って奇妙なひけらかしとかどこか残念に感じるものを見てしまうことがありますが、それはまた別の話。
いいなと思ったら応援しよう!