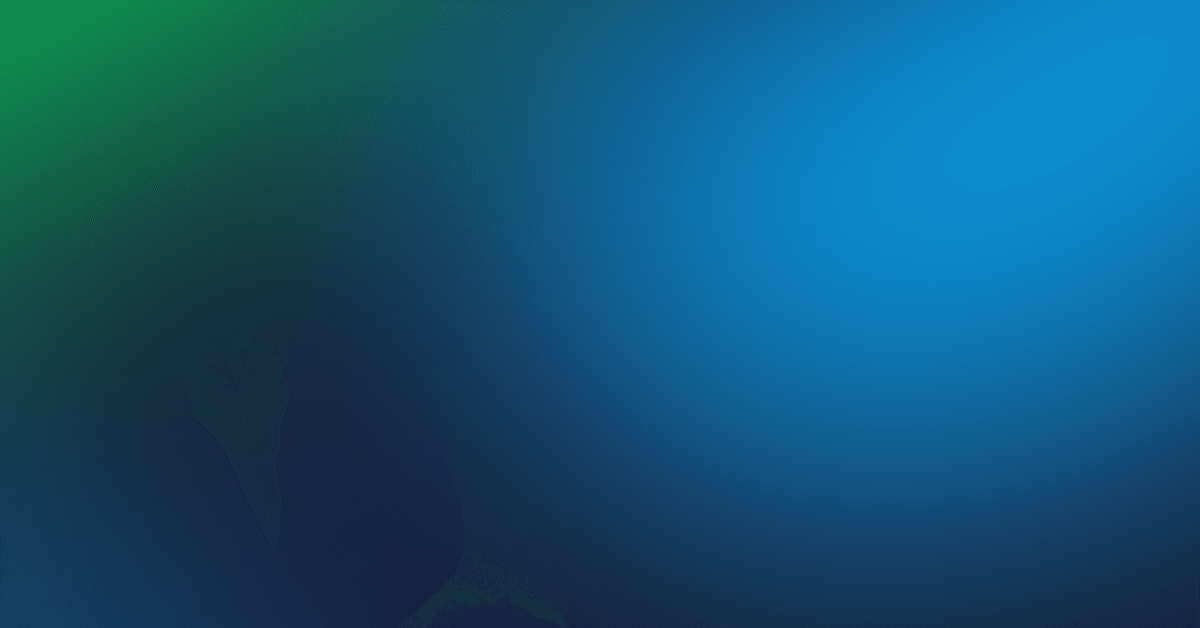
信条 (随筆)
何かを信じれば、何かの矛盾をきたす。
信じることの哀しい副作用である。
たとえば、一人一人を尊重することが大切だと信じる者も、急用ができれば、人混みは肌色の迷宮にみえ、一人一人は肌色の壁にみえ、壁の間をすりぬける感覚で、人混みをかき分ける。人混みの隙間がないほど、周りの壁を押しのけることになる。壁はよくしなって、その者に道を与えるだろう。さて、この段になり、この者の信条、他者を尊重することと矛盾して、他者を《物》として扱ってしまっている。
壁の冷たい印象。
記憶を辿ろうとも、この印象の海である。その者の気は青く曇る。自己矛盾の味は、青黴のようにほろ苦い。
人間はこんなもんだとも云える。全行為を信条に沿って行えるほど、人間はすぐれていない。意識と無意識が移ろう時点で、たかが知れている。全行為を意識で管理することは、ぜんぜん無理である。コンピュータさえも電源のON・OFFがある時点で、推して知るべしである。愚者の創るもの、必ず欠陥あり。全人類は愚者、そういうことだ。
だが、人間、捨てたものでもない。信じることが美を生むこともある。われ信じる、ゆえにわれあり。こうとも云えるかもしれぬ。信条から自分を認め、自認から生きる力を得るのである。
たとえば、他者の尊重こそ大事だと信じる者、先のように急用をみとめ、人を肌色の壁としてかき分けた果、駅の改札口にたどり着いたとする。南無三宝。チャージがない。肌色の壁に舌打ちを浴びせられる。恥辱に汗がにじみでる。チャージ機まで慌てて壁をかき分ける。だが、チャージ機は一台きりである。その者は口をひき結ぶ。腕時計の文字盤を齧り付くようにみつめる。客一人あたり所要時間を推定して、順番が巡って来るまでの時間を計算している。そんななか、前の客が全盲者だったとする。チャージ機から客が去っても、その全盲者、列を詰めない。急いでいる者は血走った眼でねめつける。
(……抜かしてやろうか。どうせ見えないんだろう。抜かそうかいな。)
醜悪にまぶたをゆがめながら、全盲者の横顔を刺すように見ている。してみると、全盲者、客が去ったことを空気で悟る。手探りで前にすすんでゆく。たちまち全盲者の番になる。チャージ機の左上に手のひらを置き、体勢をととのえる。点字を読みとり、画面をあやつる。チャージ機に半歩近づいて縮こまり、両手で財布をとりだし、投入口を手でまさぐり、口にお札をねじいれる。左上に手のひらを置く。体勢をととのえる。ICカードをうけとり、点字ブロックまで後退りをする。
その者、真摯な眼になり、全盲者の動き方をみつめていた。他者を尊重する、その者の信条をとり戻していた。全盲者の生きざまから、自分を内省していた。何を急いで生きてるんだろう? 自分の生きている速度に、自分が呑まれていた。
その者、のんびりとチャージ機をあやつり、改札口をくぐった。肌色の壁にそれぞれの息があり、血があり、家があり、愛があることが感ぜられる。人間の雑踏がきこえてくる。むすうの足音が、心臓の木霊に聞こえる。列車は定刻より遅れていた。その者は列車に乗ってから、その車両の香りを嗅いでいる。自分がここに在るとの哀しい喜びに、えも云われぬ微笑がこぼれる。
(言うこと、すること、の矛盾についての小説です。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
