
写真芸術にも3通りある。
写真はアートか? ー Is Photography Art?
という質問を写真科学生だった頃の僕は、教師だったマーク先生からうけたのですが、あなただったらどう答えますか?
※タイトル画像出典:Andreas Gursky『Rhine Ⅱ』 – Andreas Gursky
……というわけで、こんにちは、あるいはこんばんは!写真・映像作家の九条イツキです。それでさっそく上記の質問なのですが、今から思えばこれってかなり卑怯な質問ですよ。そういう禅問答が好きなんです、マーク先生は。
なぜなら、先のエッセイで述べた通り、そもそも"アート"自体が歴史的に様々な解釈を経てきているわけじゃないですか。だからこれだけでは、なにが"アート"だというのかわかりません。つまり、この"アート"とは誰にとっての"アート"なのか?という問題がまずある。
そのうえで"写真"の方も、腕時計のような工芸品に近い場合もあれば、洒落たデザイン素材という場合もあるし、最近話題の街の落書きみたいなものもあるんです。だから「この写真はアートだ」「この写真はアートではない」というと、必ずどこかから反例がでるという具合なんですよ。
なので結論を先にいってしまうと、"写真"も"アート"の歴史的な解釈変遷の影響を受けている。
つまり写真芸術には3通りある。という他ないのです。
答えは沈黙 ────。
そこでここではアート界隈における不毛な主導権争いに参加することは止めにしまして、歴史的にいって写真芸術にはどういった作品があったかを羅列して、やっぱり3通りあるんだなということをいっていきたいと思います。
……それとも、本当に3通りあると言えるのでしょうか?
0:科学技術としての写真
いきなり疑問形?気弱か!?と思うかもしれません。ですが美術の本流と違って、写真は最初からつまづく要素がてんこ盛りなんですよ。それが「写真芸術……?写真はそもそも科学技術でしょ?」という至極ごもっともな御意見です。


科学技術としての写真が発明されたのは1826年。フランスでジョセフ・ニセフォール・ニエプスという人が、自宅窓の風景を撮影したのが歴史上初めての写真だとされています。アスファルトを金属板に塗布して写した画像だそうです。
この発明の原点となったのは、美術の歴史にも関わってくる「カメラ・オブスキュラ」。「カメラ・オブスキュラ」とは ── 外光が入らない暗室の窓に小さな穴を開けると逆側の壁に上下逆さまになった外の像が映るという現象、そしてそれができるようにした暗室のこと ── です。その記述は写真の発明より300年ほど遡って、あのダ・ヴィンチの手稿にもでてくるとか。
その映像を定着したい、として発明されたのが写真なんですね。
ですから写真の原型を分解すると、外光を取り入れる「カメラ・オブスキュラ」つまりレンズ、そしてその像を定着する「金属板」つまりフィルム、この2つです。
……え?それって「写真」かな?とチラッと思いますが、元々写真を観るということはフィルムを直接観るということでした。
ちなみにこの金属板は1回数時間かかる撮影で1枚しかできず、しかも繊細で、すぐ壊れてしまいかねないものです。すると貴重品にあたる。
ここが重要で、後にこの技術を後継のダゲールという人が銀盤写真術として完成させてダゲレオタイプと命名しました(1839)が、できた銀盤をうやうやしく拝見するというのは変わりません。
つまり写真とは確かに科学技術であったけれども、できたものは職人技術的な工芸品といえるものだったのです。
なるほど?
ところで、歴史の記述では「発明家はこのようにすばらしい天才的なひらめきで新技術が発明されて新時代の幕開けとなったのである、まさに唯一無二」云々と語られがちなことがあります。
ですが実際には、大勢の人によって似たような物が地域を隔てて同時多発的に発明されている。それが皆さん御存知の科学技術の開発競争ですよね。
そんなハァ…ハァ…敗北者?の一人となってしまったタルボットという人は、イギリスで「カロタイプ写真術」というものを発明していました。

しかもその「カロタイプ」の発明時期は、なんと銀板写真術を完成させたダゲールより先んじていたというのです。それだったら写真の発明家はタルボットじゃない?
ところがタルボットはその技術を公開せず、ひとりでひっそりと隠していたそうです。ネガティブ。ネガティブです。今でいう陰キャということなのでしょうか?そうこうしているうちに、「写真の発明家」という称号をポジティブで陽キャのダゲールにとられてしまったとされています。NTR。
ですがタルボットの"しくじり"はそれだけではありません。もっと致命的な"しくじり"があったのです。皆が驚くその"しくじり"とは ────!!
なぜか定着できた画像が、明暗逆転したネガティブ写真だったのです。
写真のネガを見たことがある人は今どき少ないかもしれませんが、もし御興味があれば「写ルンです」を買って自分の顔を撮って写真屋さんにだして作ってみてください。見た目がだいぶ怖いです。
???「ミスターサタンかよォォォ!!」
こうなったら技術を隠すのも無理はありません。こういう残念なところからも、「写真の発明家」という称号はポジティブで陽キャのダゲールが相応しいといわざるを得なかったのではないかと思います。
ですがご安心ください。捨てる神あれば拾う神あり。それでもめげずに研究を続けたタルボットは、後にそのネガ像を反転させてポジ像へ変換する方法を発見します。
そう、ネガをもう一回裏写ししてポジにすればいいってことだったんだよ!な、なんだっ(略)つまりこれが写真の「現像」です。
そして今日から見れば、このネガ-ポジ法の発明こそが、レンズを通した撮像をフィルムを通過点として紙へと定着させるあの"写真"の発明であり、複製像こそが、写真であるという"写真のIDEA"の創造だったといえるのではないでしょうか?
1:IDEAを求める写真
すると写真とは銀盤を造る職人技術・手工芸品として始まり、そこから紙へ写しとった複製像の方を"写真"と規定していったのだと推理できますよね。
事実、タルボットのカロタイプは科学技術として伸びしろがあったらしく、後にネガを映す素材を廉価なガラスに換えた写真湿板(1851)、写真乾板(1871)へと発展します。
その写真乾板でコダックが創業して「貴方はカメラのシャッターを押すだけ。あとはお任せください(You Press the Button. We Do the Rest.)」と宣伝するのが1888年だそうですから、発明からわずか50年で"写真"は工業製品になっていったということです。
歴史の授業では鎖国(最近は「鎖国」って言わないらしいですが)していたはずの幕末日本ですら写真が残っている程ですから、驚きの伝播力ですよ。

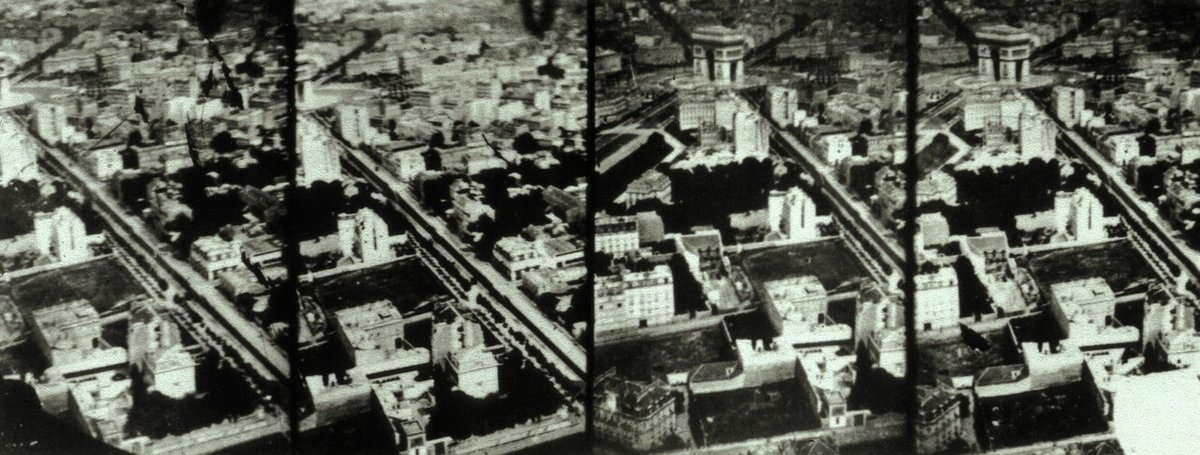
そんな驚きの伝播で広がる写真大衆の中にあってひときわ名を馳せたとされる職人のひとりを紹介すると、ナダールという人がいます。
このナダールという人は気球に乗ってパリを空中撮影したり、地下墓地を人工照明で撮影といったような目玉企画を連発していて、今でもウェブで検索するとその腕を生かしたプロデューサーといった様子を垣間見ることができます。いろいろな創作の元ネタになっている人ですよね。最近だと『Dr.STONE』がまんまそれじゃないですか。要りませんかこういう豆知識?
それはそれとして、こういった純粋な職人技術と冒険、そして造られるまだ貴重な写真を見れば、評論家ヴァルター・ベンヤミンが『写真小史』(1931)で示唆したような、「写真の最盛期は最初の20年であり、1850年代までが本物の写真である」という考え方をもつのも無理からぬことなのかもしれません。
僕はここにひとつめの写真芸術の流派、いわば【IDEAを求める写真】があるように思えます。純粋な職人芸・手工芸品こそが<普遍のIDEA>(*1)であり、写真がそのよういられた期間は非常に短かったという考え方です。
とはいえ時代がくだり写真が工業製品になっていったあとでも、個人の手を入れられる余地が多くある写真を、手工芸品にしたい!とする流れは今日においてすら途絶えておりません。
その代表とも言えるのは、1932年から1935年にかけて活躍したアメリカのf.64グループの人達でしょう。

ちなみにf.64とはカメラの絞りのことを指しており、簡単にいうと絞りは数字が小さい方が焦点以外がぼやけ、大きいと隅々までよりシャープに写ります。通常の一眼レフで見かける絞りは大きくてだいたい22くらいですから、雑にいうとf.64は全てをシャープに写すというような意味です。
なぜそんなシャープにこだわるかというと、当時はボケ味を多用した絵画風写真が大ブーム。それに対して「もうこれ絵なんよ」「現実の複製像であることが絵画に対する写真のIDEA、アイデンティティでしょ?」という批判をしていたアメリカの写真家アルフレッド・スティーグリッツに影響を受けたからだといいます。
つまり彼らはそのような主張でもって、写真を絵画とは異なるものであるとハッキリクッキリさせた訳です。そしてそこから発展し、写真芸術(!)の定義をおこないます。
画家が筆を握るように写真家はカメラを握り、画家がそれで絵を描くように写真家は撮影現像プリント全てを行う、それが写真芸術である!
それをピアノの演奏に喩えたのがf.64メンバーのひとりアンセル・アダムスなのですが、その信念とは、持てる最高の技術でもって現実の複製像造りをおこなう、それこそが写真芸術だということだと思います。
そしてこの観念は今でも、おおよそ全ての写真家の基本的な考え方にあてはまるように僕には思えます。
ちょうど同じ頃、東洋でもフジフイルムの前身たる富士写真フイルムが創業されていることもありまして、そのような観念がカメラやフィルムメーカー、そしてそのユーザーをとおして全世界の共通認識になっていったのではないでしょうか?
そこでこの観念が"写真"における<普遍のIDEA>、【IDEAを求める写真】である。そう規定しておきたいと思います。
2:デザインを問う写真
さて、前項のとおり手工芸としてはごく初期の間に完成したかにみえる写真なのですが、進む工業化はむしろ写真家による個性の探究につながっていきます。
僕はそれが<個性とデザイン>(*1)としての写真の台頭であり、さらにそれには2通りあるとしたいと思います。ひとつが絵画的なデザイン、もうひとつが写真的なそれです。
そのうちごく初期にあったのは、前者。先ほどのスティーグリッツが批判していた工業化が始まった写真に写真家の個性を加え、絵画のようにすることでアウラを保つという手法で、「ピクトリアリズム」といわれています。現代のAdobe Photoshopにもつながるような技法が1880年ごろから目立つようになったそうです。
この頃の作者は特に誰と取り上げられることが少なく僕もあまり知らないのですが、例えばエルンスト・シュナイダー。絵画的なポートレートが印象的で、調子を全体的にボカしてキラキラさせる、要するにインスタ映えです。

といって、「ピクトリアリズム」は今のインスタグラムより遥かに手間がかかって難しい手技が必要だったのでは?と思いますので、よっぽど職人技術による<普遍のIDEA>的な写真のありかたではないのかとも思います。
しかし先述したように、これは"現実の複製像である写真"ではないと喝破されたことで写真芸術としては一時退潮していきます……。
しかしこういったぼかしの美学は広告写真などに脈々と受け継がれ、最新のデジタル技術によって再度大勢力を結成することになるのは皆さま御存じの通り。
ところで。
僕は<個性とデザイン>としての写真には、もうひとつの方向性、写真的なデザインがあると思っています。そしてその代表は、アンリ・カルティエ=ブレッソンとしたい。ブレッソンって誰?という人でも、彼が提唱した「決定的瞬間」というワードは今でも見かけますよね?
この「決定的瞬間」とは一体なんなのか?
僕はただの「テレビが犯罪の瞬間を撮影した、スクープ!」とか「珍しい現象を激写!」とか「すごくきれいに撮れた!」には興味ありません。それも「決定的瞬間」か知れませんが、それだけだとあまりにも志が低すぎる。犯罪を写したいなら監視カメラ24時間つけとけばいいでしょーが。
僕が考える最強の「決定的瞬間」はそういう低俗な話ではないのです。もっと目線を高く持てと。この中に宇宙人、未来人、異世界人、超能力者がいたら、あたしのところに来なさい。以上。
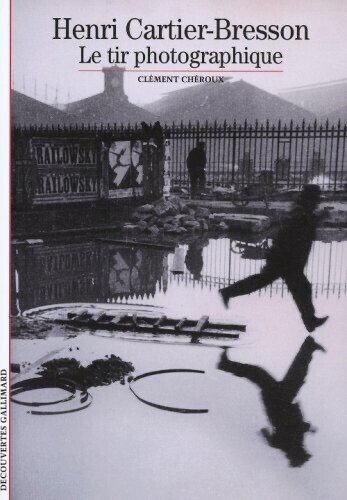
というわけで、そんな手垢にまみれた「決定的瞬間」を考え直すにあたって、もう少し歴史的な文脈から回り道したいと思います。写真が工業化していった時におきた個性の探求とは?その前に写真の工業化で何がおきたか?
それはコダックが宣伝していたとおり、プリントは専門の出力業者に任せるということでした。ブレッソンも自身でプリントはあまりせず、信用のおける人間に任せていたといいます。
もしですよ?もしそんなことをf.64で全盛期のアンセル・アダムスが聞いたら、憤死するのではないかと思います。「写真はピアノの演奏だって言ったよね?」「演奏してないじゃん」「お前は村上隆か?」
「それじゃブレッソン君はどうやって個性をだすのぉ ───ッ?!」
……もちろんフィルム造りで、です。無限に思える時間の中でどの瞬間を切り取るか、どの画を選ぶのか、その切り取り方にこそ個性がでる。それが写真的なデザインであり、その一点突破のために工業化の利点を最大限に活かします。選択と集中というわけです。
改めて考えてみると、これが先の【IDEAを求める写真】とはまた別の"写真"の在り方ではないでしょうか?だって自分ではプリントしないんです。本来なら「アナタ……怠惰ですねぇ」とそしられてもおかしくない。
それでもこれが認められたのには、ライカのようにカメラが小型化・大衆化し、同時に大勢の記者たちが報道や写真雑誌を舞台に脚で稼いで努力した、それらの結果が多大にあったように思えます。
アメリカの写真雑誌『LIFE』の創刊が1936年、ロバート・キャパの有名な『崩れ落ちる兵士』がそこに転載されるのが1937年、1947年にはブレッソンが写真家集団「マグナム・フォト」を創設ということで、その間には世界大戦が挟まっていてルポルタージュが量産されていました。

だからこそ、戦後出版されたブレッソンの『決定的瞬間』(1952)が説得力をもったというわけだと思います。
そして今では、僕達がみている写真のほとんどが、<個性とデザイン>の写真といっても過言ではありません。
写真学生以外で職人芸たる手焼きしたプリントを見たことがある人っていますか?普通の人にとって"写真"とは、写真家の個性とそのデザインをみるものという方が自然じゃないでしょうか?
というわけでこれをふたつめの写真芸術、【デザインを問う写真】とラベルしておきたいと思います。今の主役は【デザインを問う写真】です。
3:複製技術との邂逅としての写真
さて前項では【IDEAを求める写真】を受け継ぐ【デザインを問う写真】についてみてきました。現代はデジタル技術で逆襲する広告写真の「ピクトリアリズム」と、老舗感を漂わせる報道写真の「決定的瞬間」があるのかなと思います。
しかしよくよく考えるに、どちらかというと広告の「ピクトリアリズム」の方が理解しやすくないですか?というのも、こちらは職人技術から直接の発展があるからです。
逆に「決定的瞬間」には疑問符がつきます。幸運だけではない「決定」が本当にあるのか?さまざまな選択も、編集者のような別人が行うこともあるのでは?そこに「個性」はあるのか?……という。これはなぜでしょうか?
僕はその理由として、老舗の「決定的瞬間」屋が実は職人技術出身のものではないからだろう、と睨んでいます。
言い換えれば、「決定的瞬間」が成立する前に、現代アートとしての"写真"の萌芽があったのだろうと言いたいのです。
それは、写真とはなにか?現実の複製像である写真とはなにか?という立脚点から発生している/それは、複製技術であることを改めて自覚した写真、アートと複製技術との邂逅である<動機と進化>(*1)につながるところから派生している。
それがいわば【複製技術との邂逅としての写真】。
その萌芽の一例が、1920年代当時美術界で勢力があった「シュールレアリズム」であり、それを写真で表現しようとした「フォトグラム」だと考えています。

「フォトグラム」とは、印画紙の上に直接物を載せて映していくという意図がよくわからないシュールな作品形式。その作者で有名なのが、例のデュシャンと関わっていたマン・レイです。
まあこれ自体はまだ「やってみた」感が強い。一体なにがしたいんだと言いたい。分かります。ですが写真界の"シュールレアリズム"は、その後人のつながりで面白い進化を遂げるんですよ。
例えば、その一派にデュシャンと親交のあった写真家のアルフレッド・スティーグリッツが与するようになります。そんな彼が創刊した雑誌『カメラ・ワーク』で1917年に「シュールレアリズム写真」と紹介したポール・ストランドがでてきます。
また、あるいは先述のベンヤミンによって再評価されたウジェーヌ・アジェ。このアジェという人は自身で撮影したパリ市街の風景を画家に素材として売っていた一職人だったのですが、この一種カタログ的な写真が"シュールレアリズム"的であると評価されました。
そんな写真界の"シュールレアリズム"をひとことで表すと、現実の被写体をその複製像である写真として提示しながら、その背後に透けて見えるより上位の現実(=シュールレアル)を表現する手法というような意味だといえるように思えます。



さて、ここで先の「決定的瞬間」に戻って見てみるとどうでしょうか?
それは単に衝撃的な瞬間を切り取るというだけでなく、その背後に透けて見えるより上位の現実を見せるという「シュールレアリズム」の考え方が、一部取り入れられているのではないか?と思われるのです。
そんな3つめの写真芸術、【複製技術との邂逅としての写真】はその後アジェがとったようなカタログ的手法を重視していきます。
アウグスト・ザンダーによる戦前のドイツ国民を社会階層の別なくポートレートにしていった作品『Antilitz der Zeit(時代の顔)』(1929)、戦後になりますが同じくドイツのベルント&ヒラ・ベッヒャー夫妻が工業建築物をタイポグラフィーとしてカタログにしていった作品などがあります。
そして生成AIが存在する現在に至る ───。

+0:混乱する時代の複製としての写真
さて、突然のシリアス展開でしたが、以上で3通りあるとした写真芸術が全て出てきました。めでたしめでたし。
……でもちょっと待てよ?
これらの説明には、なにか不自然なところがある。実はワザと目を逸らした部分があるんじゃあないのか?額面通り受け取ることができない問題点があるんじゃあないのか?もしもボックスでは解決してないんじゃあないのか?とそんな風に思われるのです。
ここではその問題点を3つ挙げておきます。
まず1点目。そもそも"アート"自体の問題として、<個性とデザイン>までの考え方と、現代アートたる<動機と進化>には大きな隔たりがあり、誤解を招くことが多いということがあります。
先のエッセイで述べた通り、近代複製技術の普及がそれまでの<普遍のIDEA>・アウラ芸術を押し除けていくという環境の中、当事者としての芸術家がとった進化の道筋という所から<動機と進化>は発生をしています。ですが観賞する側は依然、IDEA・アウラ芸術の文化に慣れ親しんでいるため、そこの把握がしづらい。
それは当事者にも反響し、サルバドール・ダリが描くような美術界の「シュールレアリズム」は、写真界の"シュールレアリズム"とは毛色がことなってしまっています。
個人的な感想ですが、美術界の「シュールレアリズム」は現実に焦点をあてるというより、上位の現実とは夢のような像であるとし、それを絵画的なデザインで表現をすることをいうようになっているからではないでしょうか?


そのせいで過去「"シュールレアリズム"を表現した」と評価された写真作品を今の人がみると、「シュールっていうわりにやけに現実的な写真だなぁ」というゆるい感想になるのだと思います。
しかも、そこに輪をかけて混乱を招いているのが、件のf.64のグループですよ。"シュールレアリズム"派であるスティーグリッツから影響を受けたはずの彼らでしたが、純粋に職人的な作品づくりを推奨しているんですからね。彼らの発展形は、むしろ絵画的なデザイン写真となるはずだったのではないでしょうか?
この辺りだいぶ捻じれています。
続いて2点目。"写真のIDEA"とは"現実の複製像"である、としたことが混乱を招くということがあります。
繰り返しになりますが、"写真のIDEA"は"現実の複製像"であるため、「ピクトリアリズム」が見かけ上、否定されてしまいます。
その反対に、いかにも"現実の複製像"である「決定的瞬間」は、<動機と進化>を根底においていないと成り立たないにも関わらず、全体として<個性とデザイン>に流れていってしまいます。
するとその先には、"総合演出"された報道写真が現実を曖昧にしていくことになります。「決定的瞬間」と目されていたキャパの『崩れ落ちる兵士』は、やらせだったことが判明します。
そのうえ"写真"が"現実の複製"だとするならば、アートと複製技術との邂逅である<動機と進化>になるのか?ただ現実が写っているだけの"写真"は"アート"か?というまた判りづらい立場に【複製技術との邂逅としての写真】を追い込んでいきます。
事態はさらに悪いことに、ここに3点目。混乱を窮める政治の問題が反映されるという問題が絡んできます。なぜなら【複製技術との邂逅としての写真】は社会主義との関わりが深かったとする論調があるからです。
例えば上述したアウグスト・ザンダーのポートレートが制作された背景には事実、平等な社会を実現しようというルソーからの社会主義思想がありました。


しかしこの左翼的かと思われる思想は発展して、国家社会主義、民族主義、そして最終的には極右と目されるナチスが生まれていきます。するとザンダーの写真作品は事実、ナチスから弾圧されます。
とするならば、カタログ的な手法をとる【複製技術との邂逅としての写真】は左翼であって、英雄的な映像を撮る【デザインを問う写真】は右翼なのか?という、かなりキナ臭い話になってきます。
とするならば、写真はプロパガンダとしてだけその存在を許されるのか?「前衛芸術?そんな写真など認めない」「変な写真を撮ってるやつは変なプロパガンダをしている。牢屋に入れましょう」ということになります。
……というようなわけで当初の思惑通りにはいかず、単純に「写真芸術には3通りある。」とするには難点が多々あるということでした。
そしてここに見られる混乱と歪みは、現実社会が見舞われたソレそのものだったのではないでしょうか?僕には現代においても引き続き、これらが「写真」というものを分かりづらくさせている原因たちのように思えます。
そしてそんな混乱と歪みに満ちた現実の複製像・写真がやや落ち着きを取り戻すことになるのは、現代アートたる<動機と進化>が徐々に認知されていく戦後・ポストモダン時代ではないかと考えています。
そこでここからは、3通りあったはずの写真芸術がポストモダン時代にどうなっていくのかを見ていきたいと思います。
+1:ポストモダンとカラー写真
ポストモダンとはいつ頃を指すのか、どのように定義するのかは例によって大きくブレます。ですが近代(モダン)とは<個性とデザイン>が支配した時代であるとすると、現代(ポストモダン)とは複製技術との邂逅である<動機と進化>が徐々に一般化していった時代だといえると思っています。
そしてそれは「個人」の尊厳が奪われる、非人道的な戦争が経験されたことと無縁とは思えません。
たとえ優れた英雄が一人いたとしても、機銃掃射や原爆には勝てないであろうというような事態が現実におこった。それにより「個性」への幻想が消滅し、複製技術の脅威がようやく一般化された結果、現代アートに対する認知が得られた。
そのようなことがあったのではないでしょうか?写真芸術もそれを反映していきます。
また、そこに大きく影響したのはカラー写真の普及もあると思います。「科学技術」の項で述べたように、写真の原型はレンズ+フィルムであり、この稿はフィルムの顛末に着目していますが、白黒フィルムとカラーとではまた大きく異なります。そしてカラー写真がポストモダン的であるというのは、特に日本にとって顕著です。

Adobeによるとカラー写真が発明されたのは、1861年に遡るといいます。
最初のカラー写真は1861年にトーマス・サットンが撮影しました。有名なタータンチェックのリボンを撮影するために、サットンは物理学者ジェームズ・クラーク・マックスウェルが発見した3原色の法則を使いました。マックスウェルは、3色、つまり赤、緑、青のガラスのプレートを使って何枚かの画像を撮影し、いくつかのプロセスを踏めば、あらゆる画像の色を作ることができることを発見していました(中略)1908年、ガブリエル・ジョナス・リップマンが、色に敏感なフィルムコーティング、または乳剤をガラス製プレートの表面に使うという、たったひとつの処理で写真に色を作り出す方法を生み出し、ノーベル物理学賞を受賞しました。リップマンの乳剤はその後、広く使われているカラーフィルムに変わっていきました。これもやはり感光性の乳剤を使っています。レオポルド・マンズとレオポルド・ゴドウスキは、1935年に「トライパック」カラーフィルムを発明し、コダックやポラロイドといった会社が使うようになりました。
実は技術としてはフジフイルムも戦前から持っていたそうなのですが、それはあくまで軍事用。一般に出だしたのは戦後になってからです。1946年、フジカラーサービス(株)の前身である天然色写真(株)が設立され、1958年に一般用カラーネガフィルムが発売されます(*2)。
一方のコダックは1935年にコダクローム(カラースライド)、1942年にはカラーネガを市販しているので一歩先んじています。ですからカラー写真は戦前からなくはなかった。
とはいえ大戦時のルポルタージュはモノクロが大半だと思いますので、一般大衆にとって写真に色がつき始めたのは、ポストモダンに解放された戦後になってからというようなイメージで大体あっているように思います。
そして戦前との大きな違いとして、カラー写真の普及によって"写真"とは現実の複製像であることが鮮明になり、そのうえで"写真"とは工業製品であることが一般的になったと考えられます。
なぜならモノクロ写真は現像もプリントも個人の手作業で手軽に行えるのに対して、カラー現像は劇物を取り扱う必要があって個人では扱いづらい。
するといよいよ"写真"は職人的な【IDEAを求める写真】から遠のいていき、全体が【デザインを問う写真】、【複製技術との邂逅としての写真】にシフトしていったのではないでしょうか?
+2:絵画的なデザインに収斂する写真
こういったことから戦後、ポストモダン時代における"写真"とは【デザインを問う写真】、【複製技術との邂逅としての写真】にシフトしていったと考えますが、再度繰り返すとその過半数は【デザインを問う写真】が占めているように思われます。
そんな新たなデザイン写真のひとつに、作家がその表現のため「素材」として写真を使うという形式を数えたいと思います。工業化により安価でカラー写真を用意できるがために可能となった形式。コラージュ類もそこに分類し、そしてこの表現をつかった有名な作者はアンディ・ウォーホルである、とここでは言っておきたいと思います。
もっともウォーホルはシルクスクリーン、つまり版画なので写真とは異なるという意見があると思いますが、複製像を重ねていく作品形態は写真をベースに元画像が分からなくなるほど加工していった作品、というような感触を抱くのです。
ウォーホルは現代社会と結びつく複製技術をその作品に取り入れているところに特徴があります。

それともうひとつ。戦後資本主義陣営に与した国にとってデザイン写真とは、「ピクトリアリズム」からの流れを汲む「広告写真」ですよね。皆さま御存じの通り、人は「広告写真」が9割。
そしてそこから生まれた写真芸術を「セットアップ」と称するそうです。この「セットアップ」とは、カメラで撮影されてはいても、絵画的に"演出"された写真のことです。
例えばシンディ・シャーマンという写真家は今では当たり前となっているセルフィーの先駆けと目されているのですが、その画面造りは架空の映画の登場人物になったりドラマのワンシーンを模すというものです。それが写真芸術とされる。
そんな自分一人で撮ってる"演出"写真なんかどうするんだ?それに「広告写真」と「セットアップ」の違いはスポンサーがいるかいないかだけじゃないのか?まあ面白いけど。
……と思いますが、よく考えればたいていの自然風景写真やポートレートはこの作り込まれた画面造り、「セットアップ」の系列。ほぼ全員が知らないうちに「セットアップ」派なんですよ。
それを写真芸術としなければ、過半数の人達を無視することになります。
※※※この写真はフィクションです※※※

※※※この写真はフィクションです※※※
ところで、こういう"総合演出"に見覚えはありませんか?……そう、キャパの『崩れ落ちる兵士』ですよね!
キャパのやらせはスキャンダルになりました。ところがシンディのやらせは問題になりません。なぜなら初めからこの写真はフィクションだと分かっているからです。
言うなれば「決定的瞬間」が<個性とデザイン>に流れていってしまう問題は、ポストモダン時代にはこういった ─── 写真という形式でありながらそれはフィクションであるという共通認識をもつ ─── 形をとることで解決されている。
写真であってもそれが現実の複製像とは限りません。嘘かもしれない。今はそれが当たり前の前提ですよ。簡単に信じたらダメ。美少女Vtuberの中身は中年のオッサンかもしれません。
しかしだからこそ、絵画的と写真的の2通りがあるとした【デザインを問う写真】は現在、すべてが絵画的なデザインに収斂していっている。僕にはそのように思えます。
+3:現実の表現方法を模索する写真
……しかしそうすると「現実」はどこへいってしまうのか?
これってすごく"今"の話じゃないですか?そこで「決定的瞬間」の後継にくるのが【複製技術との邂逅としての写真】、現代アート写真ということになると思うのです。
先に述べた通り、【複製技術との邂逅としての写真】はカタログ的手法に見出されてきました。それはカタログ的な表現が"被写体を写すこと"に力点を置いて恣意的な画面構成を行わないからであり、それがより強く現実を意識させるからではないかと思います。
それを色鮮やかに表現したのが、70-80年代アメリカで物議を醸すアートムーブメント「ニューカラー」。カラー写真を初めて写真芸術にしたとされています。
まあ今ではカラー写真を「芸術です!!」といってもそんなに不思議とも思わないかも知れません。ですが、カラー写真とはある意味で<普遍のIDEA>を蔑ろにするポストモダンと密接に結びついていることに留意すると、その衝撃が想像できます。

こんな写真が芸術?……という現代アートでよく見る光景です。
その代表者がウィリアム・エグルストン。撮影当時の南部アメリカの生活、文化あるいはその時代を作品の中にとじこめるため、普通の生活を普通のカメラでただ普通に撮っていくことで、一種のカタログ的表現にするということをします。
それが写真芸術として発表されているところに拒否感を抱く人も多いかも知れませんが、僕には「シュールレアリズム」を旨とする【複製技術との邂逅としての写真】としてはこれ以上ない程ストレートな制作手法をとっているように思えます。アジェの制作手法を、今度は意図的に行なっているんですよね。
それを認めるか認めないかはあなた次第!ということなのですが、留意していただきたいのは、そこに政治的な軋轢はあまり感じられないところだと思います。
むしろアメリカンカルチャー賞揚の気味もある。レッドパージの影響を受けたというような話は聞いたことがありません。これも、戦前とは様相がことなる例として挙げられるのではないでしょうか。
ところで、このようにストレートな制作手法が公開された時、後の人はそことの違いを際だたせる必要に迫られ、その作品に必ずヒネリを入れないといけなくなります。
例えばトーマス・ルフは、一言でいうならありとあらゆる撮影方法を駆使したスタイルですよね。東京で展示会をやっていたので見に行きました。

そして面白いのは、ここまでくるとデジタルフォトが写真芸術に登場することですよ。それに伴って複製技術と不可分になっている「現代」を表現するために、あえて「写真」をその表象として使うということがおきます。ウォーホルを思い出しますね。
そしてこのことは、先に問題としていた ─── 現実の複製そのものである写真はアートと複製技術との邂逅である<動機と進化>になるのか? ─── という疑問が、まさに逆回転になっていることを示しています。
そして生成AIが存在する現在に至る ───。
EXTRA:写真芸術にも3通りあるか?
……ということで。
当初3通りあるとした写真芸術は混乱と歪みに満ちていたのですが、ポストモダンに時代が遷り、それが緩和されていくという様子をみてきました。
現代はかなり希少となった【IDEAを求める写真】、すべてが絵画的なデザインに収斂していっている【デザインを問う写真】、そして様々な手法を駆使して「現実」を写そうとする【複製技術との邂逅としての写真】、この3通りがあります。
しかし改めて上に挙げたポストモダン作品を観てみると、デザイン側に挙げたものを含め、それらがそれぞれの時代の表象ということもできることが分かります。なぜなら時代の表象とは、エグルストンが実践してみせたように、デザインしきれていない、意図されない所にでるからですよ。
すると「上位の現実」、時代を表現するのが【複製技術との邂逅としての写真】であり、現代アート写真と呼ぶべきものであることを考えると、全ての写真が現代アート写真に値するか否かを決定するのは、鑑賞者の態度に還っていくともいえます。
とするならば、果たして本当に写真芸術は3通りあるといえるのか?
それもまた鑑賞者側の判断に委ねられるということになり、現実の複製像である「写真」とは、「アート」の中でもやはり特殊な位置を占めているといえるのではないかと思います。
ーーーーーーーー
*1 『芸術には3通りある。』論より
*2 情報源としたフジフイルムコーポレートサイト閉鎖のため以下の記述は削除「1946年、東宝映画『11人の女学生』のタイトル部分に初めて使用され、1948年にブローニー判富士カラーフィルムが市販されます。」
ーーーーーーーー
※一部加筆修正しました(2024.7.6)
※一部加筆修正しました(2021.3.11)
ーーーーーーーー
参考文献はありません。「アート」は種類分けできるのでは?という考え方も最近になって出てきている意見になります。
例えば
「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考
末永 幸歩 (著)
いま、論理・戦略に基づくアプローチに限界を感じた人たちのあいだで、
「知覚」「感性」「直感」などが見直されつつある。
本書は、中高生向けの「美術」の授業をベースに、
- 「自分だけのものの見方」で世界を見つめ、
- 「自分なりの答え」を生み出し、
- それによって「新たな問い」を生み出す
という、いわゆる「アート思考」のプロセスをわかりやすく解説した一冊。
「自分だけの視点」で物事を見て、
「自分なりの答え」をつくりだす考え方を身につけよう!
