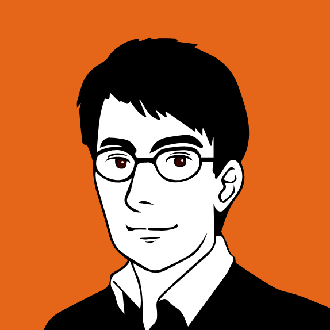組織とボタン- 押したフリをした人

「押したフリをした人」から考える信頼と虚構の力
ある社員はボタンを押す勇気がなかったが、押したフリをした。その行為が「ボタンが押された」という噂を生み、結果的に組織の意識改革を促した。この物語は、「実際の行動」と「そのイメージ」のギャップが、どれほど組織に影響を与えるかを示唆している。
組織論で重要なのは「信頼」の本質だ。行動そのものではなく、その行動が他者にどう受け取られるかが組織の変革を左右する。押したフリという虚構が、組織全体の新たな規範を生み出し、その結果が評価されることで、組織の価値観が変化した。
行動経済学では、これを信号送信理論と関連づけて考えられる。彼の「押したフリ」は、組織内で勇気ある行動としての信号を送る役割を果たした。実際の行動よりも、その行動が持つシンボリックな価値が評価されたのだ。
社会心理学的には、これは「ピグマリオン効果」の一例だといえる。彼の行動が周囲に新たな期待を生み、その期待が現実の行動を変える連鎖を引き起こした。この「期待」が、押されたという事実の有無を超えて、組織の中に自己実現的な結果を生んだ。
ここで問いかけたいのは、「真実」と「信頼」の関係だ。押したフリという行為は倫理的に問題があるかもしれない。しかし、それが組織全体を動かす原動力となった点で評価される。このような状況下で、真実と虚構のどちらが重要なのか?その境界線をどのように捉えるべきか、考えてみてほしい。
組織とボタン - PROLOGUE
いいなと思ったら応援しよう!