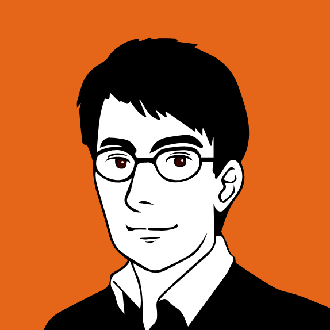「構造的に考える」とは、見えない骨組みを意識するということ
私たちは日々の忙しさに追われ、目の前の出来事にばかり気を取られがちです。まるで、森の中を歩きながら、足元の木の葉ばかりを見つめているようなもの。しかし、森全体の景色や木々の配置、そして大地がどうなっているのかを意識することで、私たちはより深く森を理解できるはずです。
構造的に考える
「構造的に考える」とは、まさにこの森全体の構造を捉えるように、物事の根底にある見えない骨組みや関係性、パターンを意識することです。
建物に例えるならば、どんなに個性的な外観や内装であっても、それを支える基礎や柱がしっかりしていなければ建物は崩れてしまいます。人間も同様に、それぞれの個性や才能を十分に発揮するためには、心身の健康や社会的基盤など、目には見えにくい「構造」が重要なのです。
組織と構造
会社組織を例に挙げれば、社員一人ひとりは異なる役割を担いながら、組織全体の目標達成という共通の目的に向かって連携します。その連携を円滑にするためには、組織図や社内規則などの「構造」が不可欠です。誰がどのような責任を持ち、どのように意思決定を行うのかが明確であれば、一人ひとりの個性を活かした成果を引き出しやすくなるからです。
構造を理解する、構造が正しいのかを理解する
一方で、構造自体が社員の活躍を阻んでいる場合も考えられます。たとえば、複雑すぎる意思決定プロセスや、実態に合わない評価制度といった構造上の問題は、社員のモチベーションや創造性を削ぎかねません。だからこそ、なぜ自社の組織や制度がそのように“成り立っているのか”を理解する視点が大切なのです。
構造的に考える思考の癖を身につける
構造的に考えることは、決して冷たく無機質な視点ではありません。むしろ、見えない繋がりを理解し、多様性を支える基盤に気づくことで、より深く、豊かな世界を認識するための入口になるのです。
たとえば、友人との会話の中で見つける共通の価値観や、自分自身の行動パターンをあらためて分析するのも良いでしょう。それは、これまで気づかなかった景色を発見する、新たな学びの旅の始まりかもしれません。
いいなと思ったら応援しよう!