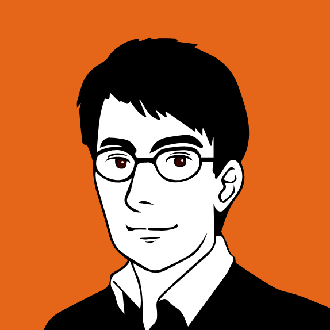誰かが選んだ本を読む読書会
2024年7月に偶然こちらを発見しました。
『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー日本版』「読書会」応援キャンペーンのお知らせ
このコンセプトに心ひかれました。
なぜ「読書会」を応援するのか
今回、英治出版が「読書会」を応援するのには、理由があります。
それは、SSIR-Jというこの雑誌をツールとして、この社会に暮らす一人ひとりがつながり、そこから小さくとも大切な「変化のさざなみ」が始まってほしい、そう願っているからです。
そのためにも、ぜひSSIR-Jという雑誌(そしてそこに掲載されている記事)を真ん中に置いて、対話を始めてみてほしいのです。そうすることで、
・「わたし」が抱えている違和感や興味の背景に気づく。
・周りにいる、他の人のことを知る。
・他の人や世の中と「わたし」がつながる。
ということが起こっていく――そんな風景を、6冊の雑誌をたくさんの人に届けるなかでわたしたちは何度も目撃してきました。
今回、そんな対話のきっかけとなる場を「読書会」と呼び、対話の場づくりを応援することで、「変化のさざなみ」を読者と一緒に起こしたい。それが、今回のキャンペーンを実施する目的です。
これは面白そうだ。「本」を媒介にして対話のきっかけとなる場をつくる。私もやってみたい。と言うことで新しい「読書会」を考えたのがこちら。
誰かが選んだ本を読む読書会
この読書会の特徴は、自分で選んだ本・記事を読むのではなく、他人の誰かが選んだ本・記事を読むことがコンセプトです。
今回はテーマとなる6冊の本から、興味のある記事をタイトルだけ見て選ぶ。それを他の参加者に託す。「誰かが選んだ本を読む読書会」
他社の視点でその記事をどう読むのかを知りたい。
自分で難しそうだから誰かに読んでもらって感想を聞こう。
そもそも自分で読みたい。
そこからが「対話の始まり」。
読書会の意図
読書会の狙いは「本・記事」を通じて、新しい対話の種を見つける事。
この読書会での対話は、単なる感想や意見交換ではありません。他者の選んだ本・記事を読むことで、自分だけでは気づかない新しい視点に出会い、それを受け入れ、他者の視点に自分の理解や感情を加えて話す。この「対話の場」を楽しみたいと考えています。
最初の本は「SSIR Japan」

「SSIR Japan」より6冊の本を対象に行います。スタンフォード大学が2003年より発行を続けている「ソーシャルイノベーション(社会変革)」の専門誌『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー』の日本版です。
これからの「社会の変え方」を、探しにいこう。
01 ソーシャルイノベーションの始め方
02 社会を元気にする循環
03 科学技術とインクルージョン
04 コレクティブ・インパクトの新潮流と社会実装
05 コミュニティの声を聞く。
読書会の流れ
参加者募集と事前準備
参加者は6冊の本から、それぞれ1つ記事を選びます。選ばない場合もあります。
2つのやり方で「誰かに読んで欲しい本の記事」を集めました。
Facebookで知人向けにアナウンスしてgoogle Foamで集計する。
合った人にリストの紙を見て紙にチェックしてもらう。
とある参加者の選択
これからの「社会の変え方」を、探しにいこう。
【選んだ記事】規模の拡大を目指して - 成功したプログラムの「変化の方法論」をどう複製・再現するか?
【選んだ理由】ちょうど自社がリリースしたプロダクトのコンセプトにもかする部分があり、かつわたし自身の興味としてもリクルートのTTP的なものはどうやって広げていけるか気になるから。
01 ソーシャルイノベーションの始め方
【選んだ記事】遠い問題・近い問題 データで見る日本人の社会意識と行動
【選んだ理由】「データで見る」ジャンルが好きです。実際の感覚との違いや、どのようにデータを見るべきかを知ることは、これからの時代にも必要なスキルだと思うから。
02 社会を元気にする循環
【選んだ記事】なぜ子育て支援が「みんなの未来」に役立つのか
【選んだ理由】わたし自身が子育て世代であり、必要な支援と必要じゃない
支援があるということは気になる点だから。
3 科学技術とインクルージョン
【選んだ記事】誰もがその人らしく働ける就業環境の社会価値 デジタル化で生まれる雇用が「人生の選択肢」を増やす
【選んだ理由】テック系はどれも気になります。どうやったらテックがもたらす価値を倍増できるかは知りたいし議論したいです。
04 コレクティブ・インパクトの新潮流と社会実装
この本にはお薦めはありません。
05 コミュニティの声を聞く。
【選んだ記事】コミュニティ・エンゲージメントを高める6つの原則
【選んだ理由】公私ともにコミュニティのあり方にはいろいろと思うところがあるから。
さて、読書会、、、、問題勃発
当初、4~6人で集まってリアル読書会を開催する予定でした。しかし、台風10号の影響や私の体調不良により、予定していた読書会は中止せざるを得なくなりました。
しかし、この予期せぬ事態が、結果的に読書会の可能性を広げるきっかけとなりました。「誰かが選んだ本を読む読書会」という当初のコンセプトは変えずに、開催方法を柔軟に変更することで、新たな読書体験を生み出すことができました。
具体的には、「読書会」は何時でも何処でも開催できるようにSSIR-Jの6冊の本を毎日リュックに入れての日々散歩。タイミング見て本のお披露目。
そして、Aさんが選んだ記事を、Aさんは見知らぬBさんが読む。Bさんが選んだ記事をBさんは見知らぬCさんが読む。さらに『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー』の記事は幾つかネットにもあるのでオンラインでも実験的にやってみる。
例えばこのようにネット上でも読める記事がある。
偶然が生んだ新しい読書体験:誰かが選んだ記事との対話
今回の読書会は、台風や体調不良といった予期せぬ出来事に見舞われ、当初の計画とは大きく異なる形となりました。しかし、そのおかげで、読書会は新たな可能性を見出すことができました。
偶発的な出会いから生まれる対話
「誰かが選んだ本を読む読書会」というコンセプトはそのままに、今回は記事を分け合うだけでなく、オンラインでの実験的な試みも取り入れました。
近いコンセプトではABD(Active Book Dialogue)でしょうか。このように、記事を分け合うことで、予期せぬ記事との出会いが生まれ、新たな発見や気づきにつながりました。誰かが記事を読むことで、間接的な対話の可能性は感じられました。
ソーシャルイノベーションというテーマに絞っているので、人数は比較的絞られている印象はありましたが、魅力的な本と記事のタイトルで、面白そう!と思った方にとっては、新しい可能性に触れる良い機会となったようです。
これからの可能性
「間接的な対話の可能性」=「非同期での開催形式」には想像以上に何か可能性を感じました。運営が個別対応になるので、まだまだ改善事項が多いのですが深掘りしていきたい部分です。
さらに「間接的な対話の可能性」から「直接的な対話の可能性」、つまり人と人を繋ぐイベント。全てオンラインで完結させる。などもですね。
最後に2つほど
今回の読書会は、偶然が生んだ新しい読書体験となりました。これからも、本や記事を通じて、人々がつながり、対話し、共に成長していく場を提供していきたいと思います。この楽しさ、可能性を引き出してくれた英治出版さんには感謝しております。
リアル開催はやりたい、本来の予定であるリアル環境で4〜6人くらいで集まってそれぞれ読んで感想を伝え合う。これは是非実施していきたいと思っています。
いいなと思ったら応援しよう!