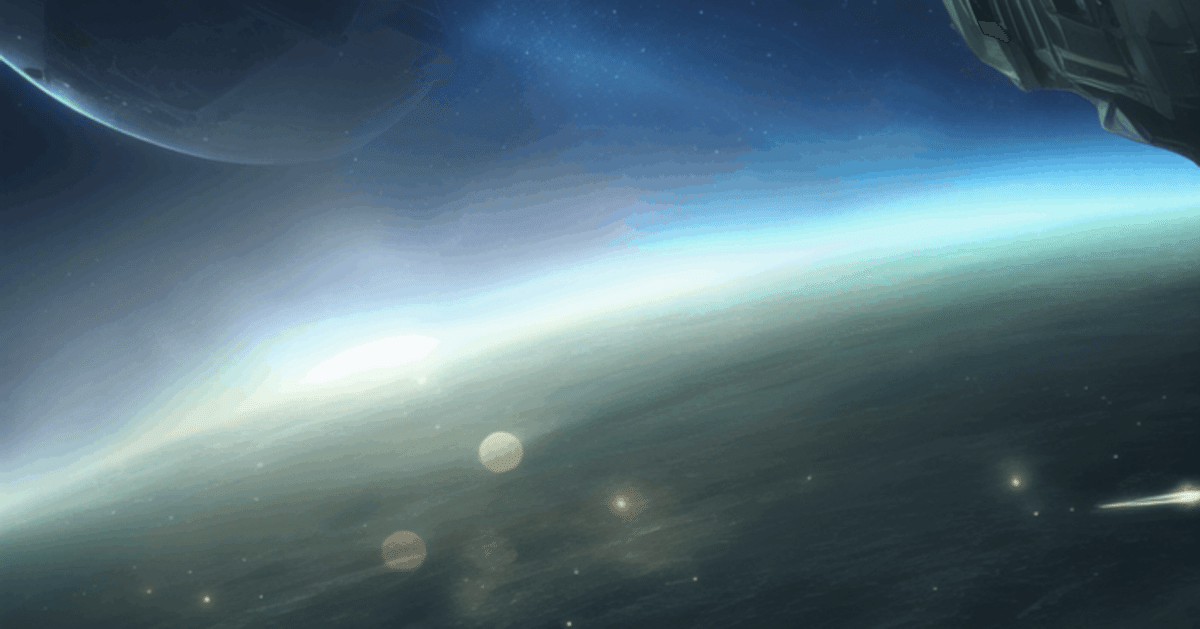
「霊感 ~ 姪っ子との不思議な夜」その2「チャネリング」
「その1」を読んでいない方は、先にお読みください。
この記事は、その続編です。
↓
火事に遭う半年ほど前、いやもう少し前だったかもしれない。私は、高校時代を題材にした小説を書き進めていた。
時は1970年代前半。インターネットが普及する遥か以前。同じ高校、同じ学年の5~6人の親しい仲間で、1冊の大学ノートを回し合い好きなことを書いた「ノートの仲間たち」との思い出を回想したもので、登場人物の中には、当然孝樹もいた。
古い記憶を詳細に辿ろうとするとかなりの集中力が必要で、その作業にあたっている間は、一種独特な精神状態になる。
椅子に掛けデスクに向かっている生身の自分を忘れ、心の中だけが過去を再体験している状態だ。自分のすぐそばに、当時付き合いのあった人物たちが、当時そのままの姿で呼吸し、行動を共にしているかのような錯覚に陥る。
あの時もそうだった。
話しかければ声が返ってきそうなくらい、孝樹たちをそばに感じていた。
目に入るのは、ディスプレイに並んだ文字のみ。文字で紡がれる世界に意識を集中していた。
部屋の天井付近から聞こえるはずのない音が聞こえたり、何かが肩に触れたような錯覚が生じることもあった。
タイピングをやめ、ふと我に返り周囲を見渡す。すると、いつもと変わらぬ静寂の中で、妙にはっきりと部屋の中の様子が目に映る。
それまで想念の世界に入り込んでいた自分に気付かされる。聴覚や触覚までが、目の前の現実とは異なる世界に迷い込んでいたのかと、半ば自分を疑うような気分にもなった。
ワープロから離れ、普段の生活している間も、どこか感覚が浮世離れしていた。
ピアノの高音域を使用した即興演奏を行っていると、その音に引き寄せられたかのように鳥が集まり始め、部屋の外が鳥の声で埋め尽くされたこともあった。
朝早く目覚めると、玄関先に立ち、口笛でスズメの声を真似る。本気でスズメと交信しようとしていた。
しばらくすると、数羽のスズメが、自分を中心にして円を掻くように旋回し始め、その軌道を次第に狭めてくる。その中に、玄関先に留めてあった車のボンネットに降り立ち、嘴でサイドミラーを覗き込むようにつつく1羽の姿を見たこともあった。
換気口から一羽の野鳥が飛び込んできて驚かされたこともある。狭い部屋の中で、慌てふためいて壁にぶち当たっては落下するというパニック行動を繰り返している。アルミサッシの窓を開け放ってやると、そこから南の方向へと飛び去っていった。
またある日、こんなことがあった。家の外の幅の狭い直線道路を、四つ足動物の足音が、考えられないようなスピードで一直線に駆け抜けていった。カーテンが閉まっていたので、その姿は確認できなかったが、一体あれは何だったのかと奇妙に感じた。
このような現実離れしたようなことが、単なる偶然だとは思えないほど、一時期に固まって起こったのは、どういうことなのか。
自分の感覚が普通ではないと感じていた。だが、ピアノのレッスンは普通に行っていたし、人付き合いにも問題はなかった。生活全般に渡って、別段自分がおかしなことをしていたということもなかった。ただ、感覚だけが、妙に研ぎ澄まされていた。
当時、夜になるとよく酒を楽しんでいた私は、ある夜、二人分の酒器を準備し、「今夜は一緒に飲もうや」と孝樹に語り掛けた。高校卒業後の彼はアルコール好きで、私が酒を飲むようになったのも、彼が「一緒に飲もう」と進めてくれたのがそもそもの切っ掛けだった。
目の前に存在しない彼に語り掛ける様子を、もし誰かが目にしたら、気がふれたと思ったかも知れない。そんなことが自然にできてしまうくらい、孝樹のことをそばに感じていた。
またある日、天気の良い静かな午後、私は再び孝樹に語りかけた。
目の前には、鴨井に引っかけたハンガー。薄茶色の薄手のジャケットが吊り下げてあった。
「孝樹、どうも君がそばにいるような気がしてならない。でも僕には霊感が無い。君の姿が見えないんだ。でも、そこにいるんだろ? そこに見えているジャケットを動かしてみてくれないか? 君の存在を感じたいんだ」
言い終わるや否や、ジャケットは少しずつ左右に揺れ始めた。風にはためいているのとは明らかに動きが違っていた。ジャケット本体は、まるで糊で固めてあるかのように一定の形を保ったまま、規則的に左右に揺れている。
私は、ただ黙ってそれを見ていた。
ありえないことが起こっている。だが、私は驚いてはいなかった。何を感じていたのかよくわからない。目の前で起こっていることを、ただ素直に受け入れていた。起こるべきことが、普通に起こっていて、それを静かに見ている。そんな感じだった。
振れ幅は、次第に大きくなっていった。その動きを見ていると、じわじわと嬉しさがこみ上げてきた。彼が喜びをこちらに伝えようとしているように感じられた。
「ありがとう。やっぱりそこにいたんだね。そうやって動かすのも大変だろう。もういいよ、ありがとう!」
そう言うと、ジャケットの振れ幅は次第に狭まって行き、そして何ごともなかったかのように静止した。
物音ひとつしな室内で、しばらく一人でたたずんでいた。
次に何をすべきか、何も頭に浮かばなかった。そのまま日常生活を再開させることにためらいがあった。そのままずっと今起こったことの余韻に浸っていたかった。
次第に時が経過してゆく。それとともに、今確かに見たはずの出来事が遠ざかってゆき、まっさらだった自分の心に、じわじわと疑念が忍び込んでくるのだった。
偶然だったのではないだろうか?
絶対に偶然ではなかったと言い切れるだろうか?
そこで、ふたたび語り掛けることにした。
もし同じことが起こらなかったとすれば、先ほどの現象が単なる偶然だった可能性が高まる。そうでないことを祈った。
奇跡の瞬間を大切な記憶としてそのまま大切に留めておきたい。だから、どうか再び動いてほしい。切にそう願いながら、言葉のひとつひとつを吟味するように、ゆっくりと口を開いた。
「さっきは、ありがとう。嬉しかった。でも・・・、正直に言おう。」
そこで一呼吸置いた。
緊張しつつ次の言葉を絞り出す。
「今、自分を疑い始めている。本当に君が動かしてくれたのか、信じるだけの確信が持てなくなっている。悪いけど・・・、大変だろうけど・・・、もう一度動かしてくれないか? 疑う気持ちを、心の中から完全に追い出してほしいんだ。」
すると、ジャケットは音もなく左右に揺れ始めた。見たばかりの光景が、再び繰り返されている。
静まり返った部屋の中で、ジャケットを見つめていた。
**
孝樹の存在を確信した私は、感動の余韻が冷めやらぬ頃、身近な人間数名に、この出来事を熱っぽく語った。
だが、誰一人として信じる者はなかった。
それどころか、頭がおかしくなったと思われ、それまで築いてきた信頼関係を損ねてしまったのだ。
失意の底に沈んだ私は、再び自分を疑っていた。本当に自分は、頭が変になっていたのかも知れない。そうでなかったとしても、これは他人に話してはいけないことなのだ。強く自分に言い聞かせ、封印することにした。
姪っ子は、言葉を続けた。
「孝樹さんが、あのときは嬉しかったって言ってる。それまでにも、自分のことを気付いてほしくて、音を出したり、肩に触れたりしてみたんだけど、気付いてくれなかった。ジャケットを動かしたときは、初めて気づいてくれて、本当に嬉しかったって言ってるよ。」
胸のつかえが下りた。頭がおかしくなっていたのではなかった。
熱いものが胸に込みあげてきた。
目の前にいる人物が、もはや自分の姪っ子だとは思えなくなっていた。
「それを聞いて安心したよ」
「どうして?」
「この話をしたら、誰も信じてくれなくてね。頭がおかしくなったんじゃないかって言われたんだよ」
「そんなこと言ったら、バチが当たるよ」
「自分でも自分が信じられなくなってたから、おかげ様で、救われたよ。ありがとう」
「孝樹さんが言ったことをそのまま伝えただけだよ。
あれ? 孝樹さんが、久しぶりにビールが飲みたいっていってる」
「ビール? どうやって飲むの?」
「おじちゃんが代わりに飲んでくれれば、中に入って味わうことが出来るって」
「へえ! でも、残念だけど買い置きがないよ」
「買ってきて欲しいって」
「ずいぶん強引だな。そんなところは昔と変わらないね」
これには思わず笑ってしまった。
その後、言われたとおりに外に出て車に乗り込み、助手席に姪っ子を乗せて、近所のスーパーへと向かった。
ビールの陳列棚の前に立つと、姪っ子の口を通して、「左から5番目のやつ」と指定してきたので、それをかごに入れ、レジを済ませて家へ戻った。
プルタブを開け、ビールをひと口、喉の奥に流し込んだ。ひんやりとした炭酸の刺激が心地良い。
その瞬間、姪っ子は目を見開いた。
「あれ? 昔と味が違う」
まるで孝樹がそのまま乗り移っているみたな感じだ。
銘柄を確かめてなるほどと思った。それはビールではなく発泡酒だった。孝樹が亡くなったのは、発泡酒が発売される以前のことであり、その味を知るはずもなかった。
「味は違うけど、これはこれで美味しいって」
「ああ、それは良かった」
「久しぶりにビールが味わえて嬉しかった。ありがとうって。でも、そろそろ僕は行かなければならない。鹿児島に帰ったら是非会いに来てって言ってる。君の顔が見たいって」
「どうやったら会えるの?」
「お墓に来てくれれば、会えるって。そちらからは見えなくても、僕からは君の顔が見えるから、帰ったらすぐに来てって言ってる」
「わかった。帰ったらすぐにいくって、伝えてね」
「言わなくても、ちゃんと解ってるって」
姪っ子は、孝樹にお礼を言い、手を合わせた。
「霊が帰るときは、最後まで丁寧に送らないとダメなんだよ」
誰に教わるでもなく、そんなことを知っている10歳の姪っ子が、神の使いのように見えた。
高校時代の友人との再会がこうして実現した。姪っ子のおかげで一生忘れられない夜となった。
ところで、『千の風になって』という歌を、あなたもご存じのことと思う。歌詞の中にこんな一節がある。
― 私のお墓の前で 泣かないでください
そこに私はいません 眠ってなんかいません ―
これは、間違いだということになる。たぶん、霊感の無い人が、全くの想像で書いた歌なのだろう。
亡くなった人は、ちゃんとお墓にいる。
その後、鹿児島に戻った私が孝樹の墓を訪ねたのは言うまでもない。電話帳で彼の実家を探し出し、お父さんからお墓の場所を詳細に聞いたのが昨日のことのように思い出される。
