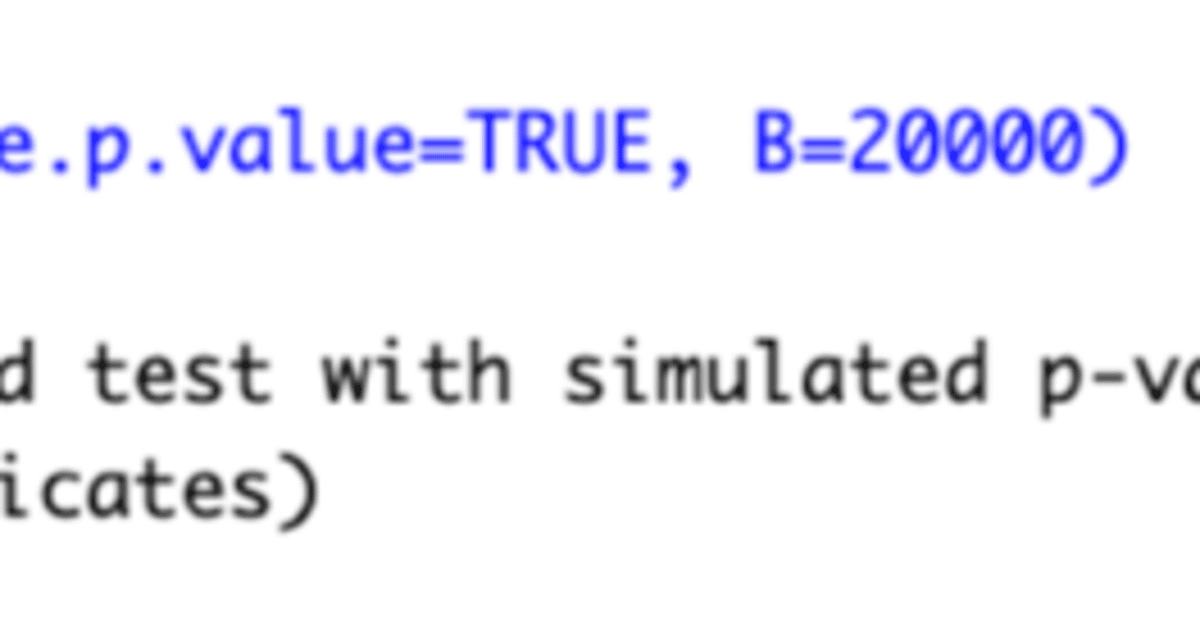
『データサイエンスのための統計学入門』と「say」
「カイ二乗検定:リサンプリング方式」の項目を読んでみた。
訳書129ページに、リサンプリングのアルゴリズムの説明(注1)の中で、1から3までのステップがあり、4番目に「2から3のステップを1,000回繰り返す」とある。なぜ1,000回なのかと疑問に思った。その回数にどのような意味があるのかと思って英文を確認してみると、「say」という単語が省略されて訳されてることがわかった。
「2から3のステップを、たとえば、1,000回繰り返す」ということであった。
Repeat steps 2 and 3, say, 1,000 times.
訳書の次のページでは、1,000回ではなく、2,000回繰り返した例が掲載されている(注2)。つまり、
chisq.test(clicks, simulate.p.value=TRUE, B=20000)を実行した結果である。(設定しなくても、デフォルトがB=20000であるようだ。)

Rでの出力結果を見ると、カイ2乗値(注3)が約1.67、p値が0.4856ということになっている。
[注]
(1) リサンプリングのアルゴリズムの説明がなされているのだが、訳書では、「このリサンプリングのアルゴリズムを次のように検定できる」となっている。アルゴリズムが検定の対象なのだろうか。そう考えると、日本語としてここで検定という言葉を使うのはおかしいと思う。また、次に出てくるのはアルゴリズムの説明であり、「統計的検定」の計算を具体的にやっているわけではない。testという英語は統計学的な文脈の中であっても「検定」という日本語にいつも置き換えられるわけではない。
We can test with this resampling algorithm:
1. Constitute a box with 34 ones (clicks) and 2,966 zeros (no clicks).
2. Shuffle, take three separate samples of 1,000, and count the clicks in each.
3. Find the squared differences between the shuffled counts and the expected counts and sum them.
…
(2) 「例えば、1,000回」となっていれば、実行例が2,000回になっていても、つじつまが合わないことにはならない。
(3) 訳書111ページに、「偶然(帰無仮説)の結果よりも5%極端」という表現がある。α(アルファ)についての項目の中である。この部分は、「5パーセントの確率で偶然に生じる結果よりも極端」(more extreme than 5% of the chance result)という意味になっているだろうか。「偶然の結果よりも5%極端」という訳はおかしい。
[補足]
他にもおかしいところがあった。「リサンプリング手続きは、クリック率が偶然によるよりは大きいことを検定できる」と訳されている部分があるのだが、これは、後から出てくる「検定は、結果がランダムでも容易に得られることを示す」という部分と矛盾する。実際、p値は0.4853という計算結果が表示されている。
ここでは、whetherという単語を無視して訳してしまっていることがわかった。つまり、「リサンプリング手続きは、クリック率が偶然によるよりは大きいかどうかを検定できる」と訳されるべきであった。表現として、「AがBであること」と「AがBであるかどうか」とは、使い分けるべきだろうと思う。そうでないと「検定できる」という表現の意味が不明瞭になる。
A resampling procedure can test whether the click rates differ to an extent greater than chance might cause.
