
建築物石綿含有建材調査者講習(第2章)
7/30から2日間、技能講習を受けに行っています
2日目は試験もあるので、重要なところをまとめながら、学習しようと思いました。
しかし、(ネットカフェにて)書いている間に遅くなるといけないので、基本事項だけの復讐。(240730現在第2章2.1のみ。)
その後、合格後で仕事が落ち着いて、実際に調査に行く直前に再度まとめなおしています。
将来的に、受けようと考えている方、建築、建設系を考えている方も参考になるかと思いますので、まとめなおします。
事前にこちらの知識も必要になります。
私は作業主任者取得したので、この内容は講習受けていないのです。

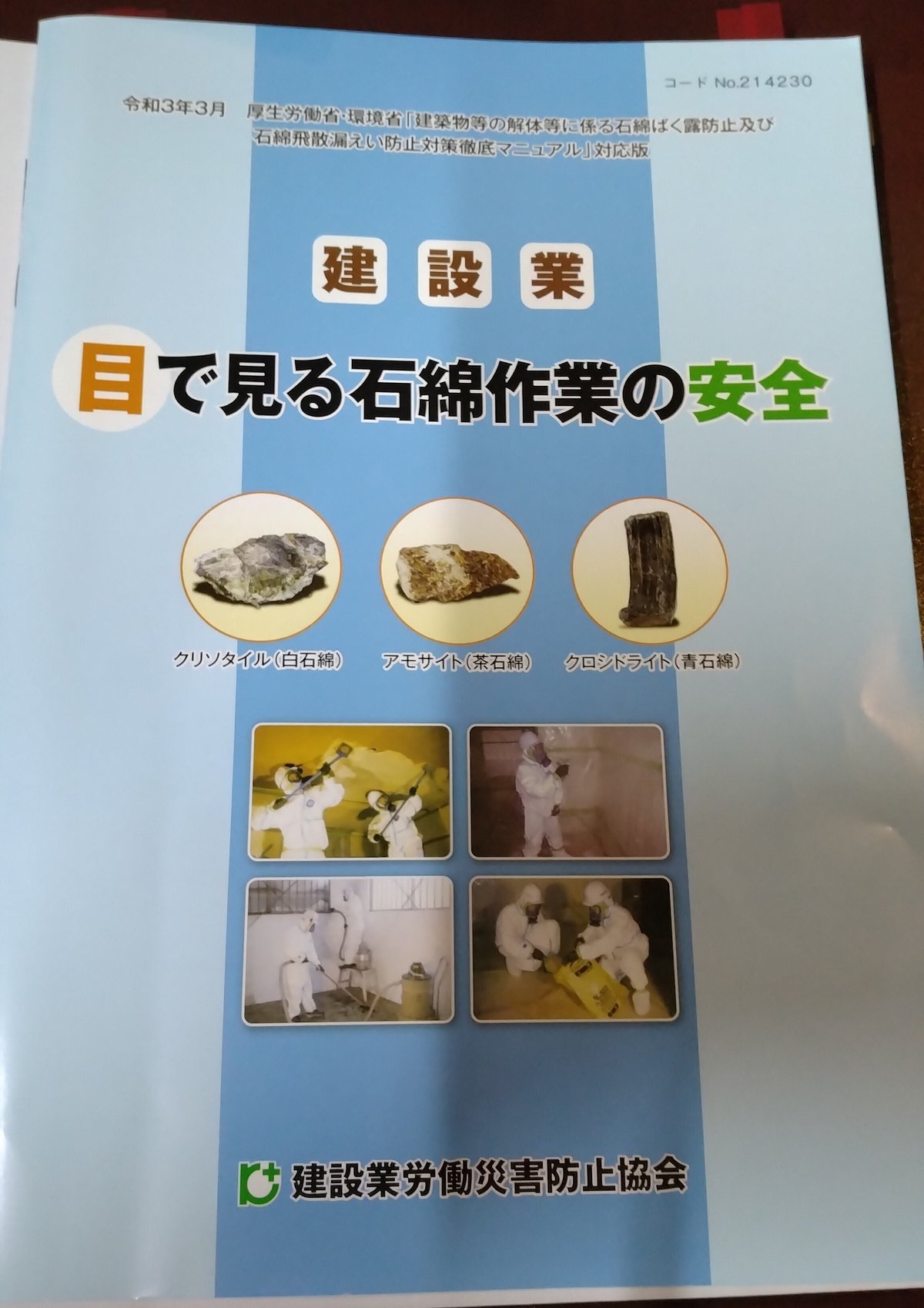
基本箇条書き、テキストの重要なポイントを写し書きです。
※私は石綿作業主任者なので、第1章 基礎知識1は免除なのです。
全てを1回にまとめると長くなり、後進に時間がかかるので、今回は第2章のみまとめました。
第2章 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識 2
2.1 大防法、建築基準法その他慣例法令
建築物等の石綿の使用実態の調査は、安衛法及び石綿則に基づく調査のほかにも、大防法や建築基準法等の関連法令に基づく調査義務の発生や、通常の建築物利用時における石綿含有建材使用実態調査を行う際に必要となる。
なお、このほかにも建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)では、建築物等の分別解体等のための調査が義務づけられており、また、自治体の条例でも調査義務が課せられている場合もある。
(1)大防法
大防法は、大気汚染に関して国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的にし、1968(昭和43)年に制定された。
その後、大防法に施工状況の把握がなされ、建築物等の事前調査で石綿含有が見落とされたり、これまで規制の対象ではなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3)の不適切な除去により、石綿が飛散する事例等が確認された。
こうした状況を受けて、建築物等の解体・改修工事等における石綿飛散防止対策の強化を図るため、令和2年6月に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、規制対象の拡大、事前調査の信頼性の確保、直接罰の創設、不適切な作業の防止が改正された。
<建設物の事前調査にかかわる改正のポイント>
①規制対象に追加する石綿含有建材
大防法の規制の対象は石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料という)が使用されている建築物等の解体、改修等が対象となる。→つまりは全レベルが対象
②事前調査の方法
解体等工事の元請業者又は自主施工者は建築物の解体等を行うときは、あらかじめ特定建材の使用の有無を調査することが義務付けられている。
ただし、解体等工事が平成18年9月1日以降に着手した建築物の解体、回収等の建設工事に該当する場合には、特定建築材料の有無の目視による調査は不要とする。
③元請業者から発注者への説明
事前調査は元請業者が行い、発注者に説明し、記録事項及び記録・説明書面の写しを補完しなければならない。事前調査に関する記録は、解体等の作業にかかわるすべての事前調査を終了した日又は分析調査を終了した日のうちのいずれかの遅い日から3年間保存する。
④事前調査結果の掲示
解体等工事の元請業者又は自主施工者が行う事前調査結果等を表示した掲示板の設置は必要である。→サイズはA3
⑤事前調査の都道府県知事への報告
一定規模以上の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県知事への報告が義務付けられてた。
ア、建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上出るもの
イ、建築物を改造し、または補修する作業に伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計が100万円以上であるもの
⑥特定粉じん排出等作業実施届出(対象レベル1・2)は 発注者または自主施工者が行わなければならない。
(2)建築基準法
建築基準法(第12条)における定期報告の対象となる建築物(物販店舗、病院、ホテルなど)の場合、吹付け石綿及び石綿含有吹付ロックウールの使用の有無、使用されている場合の措置の状況(囲い込み、封じ込めの有無)についても報告事項となっているので留意すること。
(3)建設リサイクル法
一定規模以上の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材)の分別解体等と再資源化等が義務付けられている。
1、建設物にかかわる解体工事→建築物の床面積が合計80㎡以上
2、建築物にかかわる新築工事・増築工事→建築物の床面積の合計が500㎡以上
3、建築物以外のものにかかわる解体工事又は新築工事→請負代金の額500万円以上
4、建築物にかかわる新築工事等にあって、新築または増築の工事に該当しないもの→請負代金の額1億円以上
(4)その他
吹付け石綿などに対する規制などの経緯から、飛散した場合の健康被害への影響の大きさなどに着目して、
①建設時期の古い建築物
②未成年者が長く滞在する建築物
③災害時の緊急利用が求められる建築物
を優先的な調査対象としている。
(240730 ここまで)
2.2 建築物調査結果が導く社会的不利益
(1)建築物の石綿含有建材調査の健康リスクやコストへの影響
◆調査時の判断:石綿あり 石綿含有の実態:石綿なし
×見落としのある調査結果であり、
不要な対策
無駄な財政的負担
建物資産の過小評価
社会的風評被害
のコストが生じる
◆調査時の判定:石綿なし 石綿有無の実態:石綿あり
×見落としのある調査
継続的な健康障害
改修解体工事の飛散事故
後日発覚時の追加財政負担
社会的信用の失墜
建築物周辺への継続的な環境影響
のリスクが生じる
2.3 リスク・コミュニケーション
石綿繊維の飛散に起因する健康障害のリスクは、石綿含有建材の除去作業などを行う作業者にとどまらず、例えば、石綿が使用されている建物の一般的な利用者にも影響を及ぼす。
(2)米国におけるリスク管理の枠組みと利害関係者の関与
「リスク管理は、人間の健康や生態系へのリスクを減らすために必要な措置を確認し、評価し、選択し、実施に移すプロセスである。リスク管理の目標は、社会、文化、倫理、政治、法律について考慮しながら、リスクを減らしたり、未熟に防止するための科学的に妥協で費用対効果の優れた一連の行動を実施することである」と定義している。
6段階のプロセスとして、
・問題の明確化、関連付け:関係者を関与させるプロセスを確立する。
・リスク分析:検討されたリスクに対する関係者の受け止め方を確認する。
・選択肢の検討:リスクに取り組む選択肢を検討。
・意思決定:意思決定に係る関係者を決定する。
・実施:リスク対策で重要な役割を果たす関係者を意思決定過程に関与させることが重要である。
・評価:評価の方法には、環境と健康のモニタリング、疫学調査、費用便益分析、関係者との議論がある。
(3)日本における石綿に関するリスク・コミュニケーションに向けた検討
国内においては、石綿の飛散防止に関して周辺住民等とのリスク・コミュニケーションが図られ、工事が円滑に進むことを期待し、環境省から「建築物等の解体登校時における石綿飛散防止対策に係るリスク・コミュニケーションガイドライン」が2017年(平成29年)に公表されている。
2.4 石綿含有建材調査者とは
2.4.1 中立性
(1)役割
調査者の職責は、限定された責務である。
判断が困難な場合は、適切な試料採取と精確な分析評価を実施しなければならない。
すでに劣化が進んでおり、早期に何らかの対策が必要であれば、その旨の報告も行うことになる。
(2)中立性
調査者は、意図的に事実に反する調査を行ったり、虚偽の結果報告を行っては絶対にならない。
機密保持義務があり、いかなる場合においても情報の漏えいは許されない。
調査においては、常に自らの石綿ばく露に注意することは言うまでもないが、共用中の建築物内部の生活者、労働者党の石綿ばく露を回避・低減するために十分な配慮も必要である。
2.4.2 石綿含有建材調査者の心構え(役割と重要性から調査者に求められること)
①建築物などの意匠・構造・設備に関する知識を有すること
②建築物などに使用されている建材に関する知識を有すること
③建築物などの施工手順や方法に関する知識を有すること
④建築物などの設計図書や施工図などを解析し、必要な情報を抽出する能力を有すること
⑤石綿含有建材に関する知識を有すること
⑥建築物などに使用されている建材の分析資料採取方法に関する知識を有すること
⑦石綿分析技術に関する知識を有すること
⑧石綿分析結果を解析する能力を有すること
⑨石綿含有建材の維持管理方法に関する知識を有すること
⑩石綿含有建材の除去などに関する知識を有すること
⑪石綿の危険性を理解し、調査業務に反映できること
⑫中立性を保ち、精確な報告を実施する能力を有すること
なお、石綿に関する情報と措置技術は日々新しくなっており、調査者には常に情報収集の努力が必要とされる。
事前調査の基本は三現主義の徹底
三現主義:「現場」「現物」「現実」を優先
目視調査せずに書面調査の判断で、調査を確定終了してはいけない。
書面調査結果との整合性 差異あり→現場優先
