
【開催報告】経営ビジネスゲーム体験会2
11月21日、大阪から乾さんをお招きして「研修でも使える経営系ビジネスゲーム」の体験会を行いました。1回目開催から約4ヶ月。落ち葉舞い散る季節となりましが、ゲーム中は白熱して、大いに盛り上がりました!とても楽しく、今回も学び深かったです!
本日体験したゲームは2つ。松下幸之助氏の〈理念経営 実践ゲーム〉と〈No.1ベーカリー〉ゲームです。通常は1ゲーム2〜3時間程度かかるところを(会場利用の都合上)2時間程度の早送りで実施。
経営系シリアスゲームを作りたい!
ウェルビーイングな世界を創りたい。私はウェルビーイング経営について研究しています。その中で、多くの方から組織で動く時の困難さや前提として重視することを伺いました。
多くの方にお話をお伺いするうちに、共通する要素がいくつか見つかります。この重要なことの中でも大切にしたい要素を、誰でも楽しく理解できないかとシリアスゲームの開発に至りました。
プロトタイプについては、今後ご紹介しますので、ぜひご期待ください。
〈理念経営 実践ゲーム〉の魅力
松下 幸之助 氏の想い
松下幸之助氏は、皆さんがご存じのとおり、日本を代表する実業家の一人。
私は書籍「道をひらく(リンクは最下部に)」が好きです。
パナソニックホールディングスを一代で築き上げた経営者である。異名は「経営の神様」。その他、PHP研究所を設立して倫理教育や出版活動に乗り出した。さらに晩年は松下政経塾を立ち上げ、政治家の育成にも意を注いだ。
経営は成功するようにできている
雨を降ったら傘をさせばいい
数々の名言や逸話が残っており、理念経営 実践ゲームは、それら経営に対する想いや姿勢が凝縮されているゲームです。ゲームの箱を開けると、冊子が2冊入っています。1冊はルールブック。もう1つは松下幸之助氏の顔写真が入った「振り返りガイドブック」です。
自主経営を心がけること
振り返りガイドブックでは、松下幸之助氏が大切にした経営のあり方や、ゲームに登場する「仕入」「営業」「製造」の要素と「個人の使命」「チームの使命」について詳しく解説されています。
私はゲーム終了後に「振り返りガイドブック」に目を通しています。ゲームで登場した「個人の使命」はどんな意味を持つのか、改めて深く理解をすることができました。
マダミス(マーダーミステリー)にも「エピローグ」のような物語が綴られていることがありますが、この「振り返りガイドブック」を通して、ゲーム中の自分の行動と他者への関わり方を内省することができます。
「ゴールできなかった原因を探るケーススタディ」の中に示されていた内容には胸が痛くなるトピックが掲載されており、日常の自分の振り返りとしてもおすすめでした。

誰がどこの国にいく?会議勃発
進行方法は、1人づつ順番にサイコロを振り、出た目の数づつマスを進む "すごろく型" です。順番にサイコロを振り、元のプレイヤーに戻ってくるまでの1巡を「ターン」と呼びますが、参加人数によって、1ゲームのターン数が変わります。
ルールが分かり、ゲームの目的が私たちの中にやっと浸透する頃に、ゲームの終わりが見えてきます。すると、共に互いのありのままの姿も現れてきました。
移動ルートを考えてすべきことを指示する人、最終目的の達成状況から逆算して作戦を提案する人、全員の意見を見守る人、さまざまです。
特に最後の3ターン目からは、白熱。3つのサイコロを振って出る目の数を予想しながら、誰がどこの国に契約書を持って行くか、誰の工場に何個仕入れて何を製造するか、互いの相談が、止まらなくなります。
ゲームのマスの中にも「社内会議(1分間)」をする場所がありますが、会議の前の会議などと言いながら、わいわい相談が盛り上がっていきました。
シリアスゲームのつぶやき
今回の体験会は、様々な業界でご活躍されている方にご参加頂きました。研修コーチさん、海外事業を立ち上げたばかりの経営者さん、企業ブランディングをメインに事業を展開するクリエイターさん などなど。
それぞれの視点で多くの気づきがありました。
変数が多くて頭が回らないけれど、実際の経営も同じように複雑ですね。全体を常に俯瞰して理解する姿勢が必要だね。
互いの部署は協力すべきはずなのに、ついつい自分の部署が活躍することに力が入ってしまう。それぞれの部署は特色を持って、みんな違うことをして初めて世に貢献できるね。
契約書や商品、そして雇用も各部署情報を出し合い相談しながら進めると大きな貢献につながるね。
みなさんも、ぜひ機会があれば体験してみてください。

〈No. 1 BAKERY-儲かるパン屋を作ろう-〉の魅力
2ゲーム目は「No. 1ベーカリーゲーム-儲かるパン屋を作ろう-」。時間の都合上、エッセンスだけ体験しました。このゲームは売上や利益などキャッシュフローとお客さんのニーズを深ぼるマーケティングが学べるゲームです。
発注と廃棄のよしあしは運ではなく観察力
ゲームの流れは簡単です。まずはお客さんに3つ質問をします。その答えから売れ筋を予想して、売れそうなパンと個数を発注します。発注が終わったら、実際にお客さんに販売して利益を計算します。売れ残ったパンは廃棄処分するから、身をもって発注と売れ方の動向把握の重要性を実感するのです。

キャッシュフローの前に大切なこと
このゲームの最大の学びは「顧客ニーズを質問でひき出す」ことです。店主のターンが巡ってくると、お客さん1人に対し「3つの質問」をしながら仕入予想をします。目的の回答につながる質問を試行錯誤しながら捻り出していきました。
どんな飲み物に合うパンですか?
ーみんなコーヒーや紅茶と答えたため、目的の回答が得られなかった。誰と食べますか?おひとりですか、それとも家族で?
ー家族のイメージも異なるため、目的の回答が得られなかった。
普段の行動パターンを理解する
ターンが重なるにつれて、次第にお客さんに「率直な欲求」が現れてきました。例えば、ランチの時に買うパンは、スイーツ系のパンかお惣菜系のパンか、選択は人それぞれ。質問に対して「がっつり食べたい」と答えても、大きめのシナモンロールを選ぶか焼きそばパンを選ぶかは異なります。
あるいは自分の好みではなく「このパンは高校生が選びそうなパンです」とペルソナを設定して答える人が増えましたが、生まれ育った地域性や今の立場から思い描く人物像が異なるため、「この方の中の高校生のイメージ」を引き出すことが必要です。
最高収益を得たヒントは、素直さ
今回体験したゲームでは、最初にパン屋の店主を務めた方が最高収益を獲得しました。お客さん参加の方の質問の回答と、商品の選択の仕方も「初めてだから」と素直に直感的、そして選ぶ種類も1種類に偏る傾向がありました。
プレーンなパン、お惣菜パン、スイーツパン。その中で原価が低く売価が高いものを選択していったところ?全ての商品が売れて廃棄もなく、最高収益となったようです。もちろん質問の仕方も答えやすかったです。
朝ご飯に食べますか?
あなたなら何時頃食べますか?
糖度だけではなく、サイズやボリューム感も把握することができますね。しかし、ターンが重なるにつれて、お客さんはパンの種類とサイズやボリュームをミックスして購入するようになっていきました。
本当に、今食べたかった商品を注文する人も。
感謝
最後になりましたが,今日ご参加された方をはじめ、幅広い業界に人脈をお持ちの乾さん,場所を提供してくださった FabCafe NAOGOYAさん,本当にありがとうございました!次回もお願いいたします!
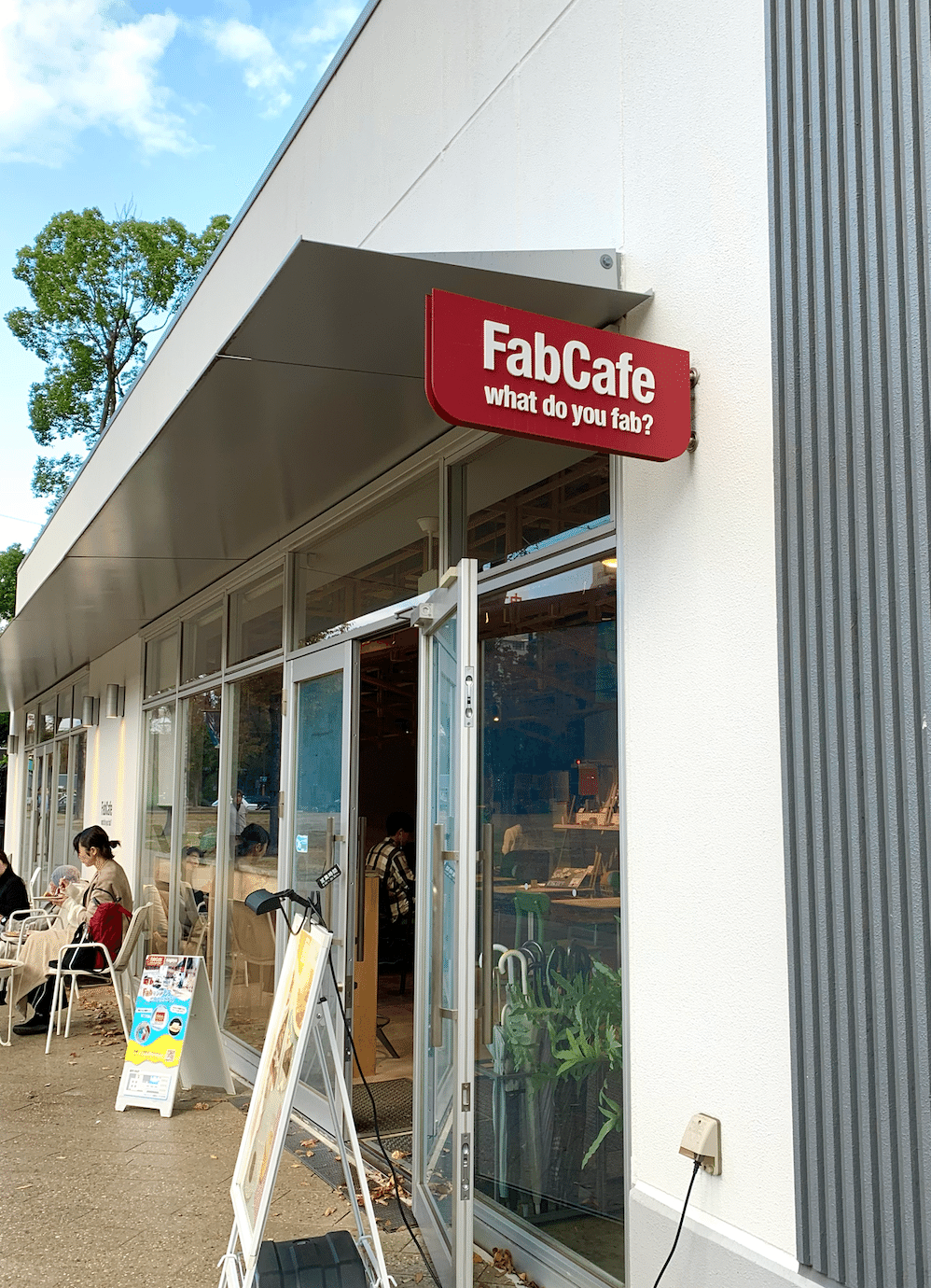
文責 豊川真美
引用 ご紹介した書籍とゲームを,ご紹介しますね。
