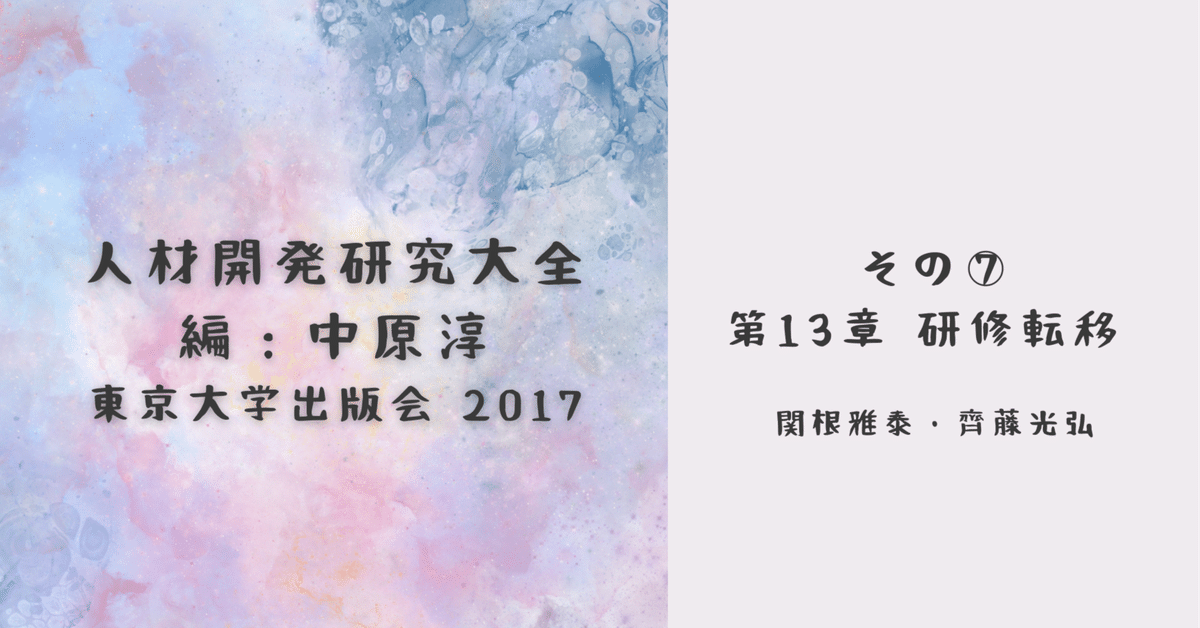
【人材開発研究大全⑦】第13章 研修転移 関根雅泰・齊藤光弘
ようやく7回目の今回は、研修転移についての論考を取り上げたい。
研修転移の先行研究を概観した上で、研修転移研究の展望について述べている。
読むことはそれほど時間がかからないが、まとめるのに時間がかかってなかなか前に進まずである。
研修転移とは?
研修って、お金と時間かけてもなかなか職場でほとんど役に立ってないよねという感覚があるが、研究結果も同様である。
研修内容の職場での実践度合いについては、様々な先行研究があり、本章で紹介しているが、著者らはこうまとめる。
研修内容の職場実践度合いに関する先行研究をまとめると、研修で学んだ内容の10~20%ぐらいしか職場では実践されないと言える(Roussel 2014、Kontoghiorghes 2014)。つまり、研修が「やりっぱなし」となり、職場ではほとんど実践されていないということである。
そんな「やりっぱなし」の研修状態を防ぎ、研修後の職場実践を促そうとする試みが、「研修転移」研究である。
研修転移とは、「研修の現場で学んだことが、仕事の現場で一般化され役立てられ、かつその効果が持続されること」(中原 2014)
「一般化」と「持続」というのが、転移研究では強調されてきたという。
Roussel(2014)では、4つのメタ分析研究をレビューし、研修転移の定義には、「運ぶ(Transport)」と「類似度(Degree of similarity)」2つの要素が入っているとする。
研修転移とは、研修現場と仕事現場の間の通路を通って、学習した内容を運ぶことであり、その運ぶ際には、研修現場で学習した内容と、仕事現場の状況の類似度が影響する
確かにその通りだなあと思う。会社の研修で使わないこと学んでもね。逆にすぐに実践できる形でデリバーするというのもポイントかもしれない。
研修転移研究のルーツとしての研修評価研究
研修転移研究のルーツは研修評価研究にあるとして、研究評価研究の歴史をたどる。その中でも研修評価研究の発展に寄与したカークパトリックの4ステップモデルを取り上げる。
4ステップモデル
ステップ1 反応(Reaction)研修受講者が感じたことを問う
ステップ2 学習(Learning)研修受講によりどの程度受講者の態度が変わり、知識が増え、技術が向上したのか測る
ステップ3 行動(Behavior) 研修を受けたことにより、受講者の行動がいかに変化したのか測る
ステップ4 成果(Results)離職率の低減、生産性の向上、利益増加等の事業への成果を」測る」
このモデルには、理論というより分類と考えた方がふさわしい(Holton,1996)という主張を筆頭に様々な批判も多い。
例えば、
・いかに受講者が楽しみ、満足するような研修を設計し運営するかという満足度が過剰に重視されるようになった。(Sitzmann &Weinhardt 2015)
・受講者のレディネス、意欲、研修デザイン、個人特性、仕事とのつながりといった複数の学習要素が含まれていない(Donovan 2014)
一方で、シンプルで使いやすいことから実務者のみならず研究者にも活用が広まり、研修転移研究でもこのモデルを基盤にしたものが多いという。様々な検証結果を紹介する。
中でも、カークパトリックの息子のジェームス・カークパトリックは、レベル3の「行動」評価こそが、研修による「学習」と現場での「成果」」をつなぐミッシングリンク(失われた環)であると考えた。
彼が、妻のウェンディとともに「新カークパトリック・モデル」を提唱する。親子で理論を精緻化していくというのは、素晴らしいことだなあと思う。
「新カークパトリック・モデル」は、以下のような特徴を持つ。
①レベル4の成果とは「ROE=Return On Expectation(期待に対sる成果)であり、ステークホルダーが何に期待をしているかを事前に把握し合意しておくことが重要である
②レベル4の成果を起点にして、レベル3行動→レベル2学習→レベル1反応
へとつないでいく
③なかでもレベル3の行動を明確化することが重要である
またLim& Nowell(2014)も行動の重要性に着目して、以下の図の通り、最も単純な研修評価である「反応」「学習」と多くの説明変数が存在し最も複雑な状況となる現場での「成果」をつなぐのが、レベル3「行動」であり、この現場での行動こそが、研修転移であると考えた。

研修転移を考える枠組み
多くの研修転移研究が基盤とする、2つの枠組みを紹介する。
まずは、Baldwin&Ford(1988)の「研修の転移プロセスモデル」である。
彼らは、転移を一般化(Generalization)と維持(Maintenance)であると定義付けて以下の通図の通り、モデル化する。

またBroad&Newstrom(1992)は、研修転移に関する先行研究から「役割者」と「時間」の2軸から「転移マトリックス」を提示した。これは、講師に対するインタビューをもとに順位付けしたものである。

研修「前」のマネジャーによる働きかけが、最も影響度が高いとする。確かに職場からの送り出し方は重要だろう。
研修転移を促す働きかけ
この二つの枠組みをもとに、「研修」「職場」「個人」(本人)が各々研修の前・研修の最中・研修後にできることについて以下の図の通りまとめている。

これを見ると確かに上司を中心とした職場の研修前後における関わり方が、研修転移を左右する重要な要素になっているというのは、よくわかる。
また様々な先行研究の中で、Hoskell(1998)では、今までの研究者や実務家の文献双方から抜け落ちているのが「転移魂(Transfer spirit)」とも呼ぶべき受講者個人の態度の重要性を主張する。
たしかに研修で学んだことを現場で実践しようとする、受講者個人の意欲・意志も重要だと思う。
研修転移研究の展望
本章は、以下の2つの観点から、研修転移研究の今後の展望を論じることで終える。
職場学習論との接続
職場学習とは「組織の目標達成・生産性向上に資する、職場に埋め込まれた様々なリソースによって生起する学習」(中原2012)である。
著者らは、職場での支援が必要な研修転移にとって、職場学習論との接続が大きなヒントになるとしている。
例として、今後、どのような支援や相互作用が、マネジャーと部下(受講者)間で担われれば、研修転移の促進要因足りうるかなどの研究が考えられるとしている。
行動と成果の接続
レベル3の行動からレベル4の成果をつなぐミッシングリンクはなにかについての論考がとても興味深かった。
一つは、バランススコアカード(BSC)と結びつけである。
BSCは、4つの視点「財務」「顧客価値の提供」「内部プロセス」「学習と成長」の戦略目標間の因果関係を明らかにして戦略を記述するが、レベル3の行動として、「内部プロセスの橋上」と「顧客価値の提供」を行うと、レベル4の成果に結びつくとする。とても面白い論考である。レベル2の学習は、まさに「学習と成長」である。
また元ミスミの経営者、三枝匡氏の「創って、作って、売る」という事業のサイクルの、「創って、作って、売る」という行動こそが、レベル3の行動であると結びつける。
なかなか、結びつけづらいレベル3の行動とレベル4の成果を結びつける考え方としてヒントになる。
とはいえ、著者も述べるように、この部分のよりクリアな解明は、今後の研究の発展に期待するところかなと思う。
感想
正直、研修を生かすも殺すも自分次第と思っていた部分も強いので、研修転移という分野で様々な研究が行われていることを知れたのは大きな収穫であった。
少し話は変わるが、どう行動に結びつけるのかは、「知行同一」という言葉に代表されるように東洋思想でも重要視されている。自分自身にとっても課題であるが、自分の意識のみに頼るのではなく、どのような環境に自分を置くのかも大切だなというのは考えた。
なお、研修転移については、以下の本を読むと本章の内容+αのことまで書かれていて理解促進に役に立つ。
