
英語とフランス語両方を学んで気づいたこと
一昨日無事に人生初TOEIC受験が終わりました。
手応えはなんとも言えませんが、とりあえず全部の問題を回答できたので良しとしましょう。
TOEICに備えてここ1,2ヶ月は語学強化月間と称して毎日コツコツ英語の勉強に励んでおりました。
しかしずっと英語の勉強ばかりをするというのもちょっと飽きてしまうというかバリエーションが欲しかったので英語に疲れたらフランス語を学ぶなどしていました。
詳しい勉強法はまた後日書けたらと思いますが、英語やフランス語の底力を上げるために使っていたのはこちらの二冊。
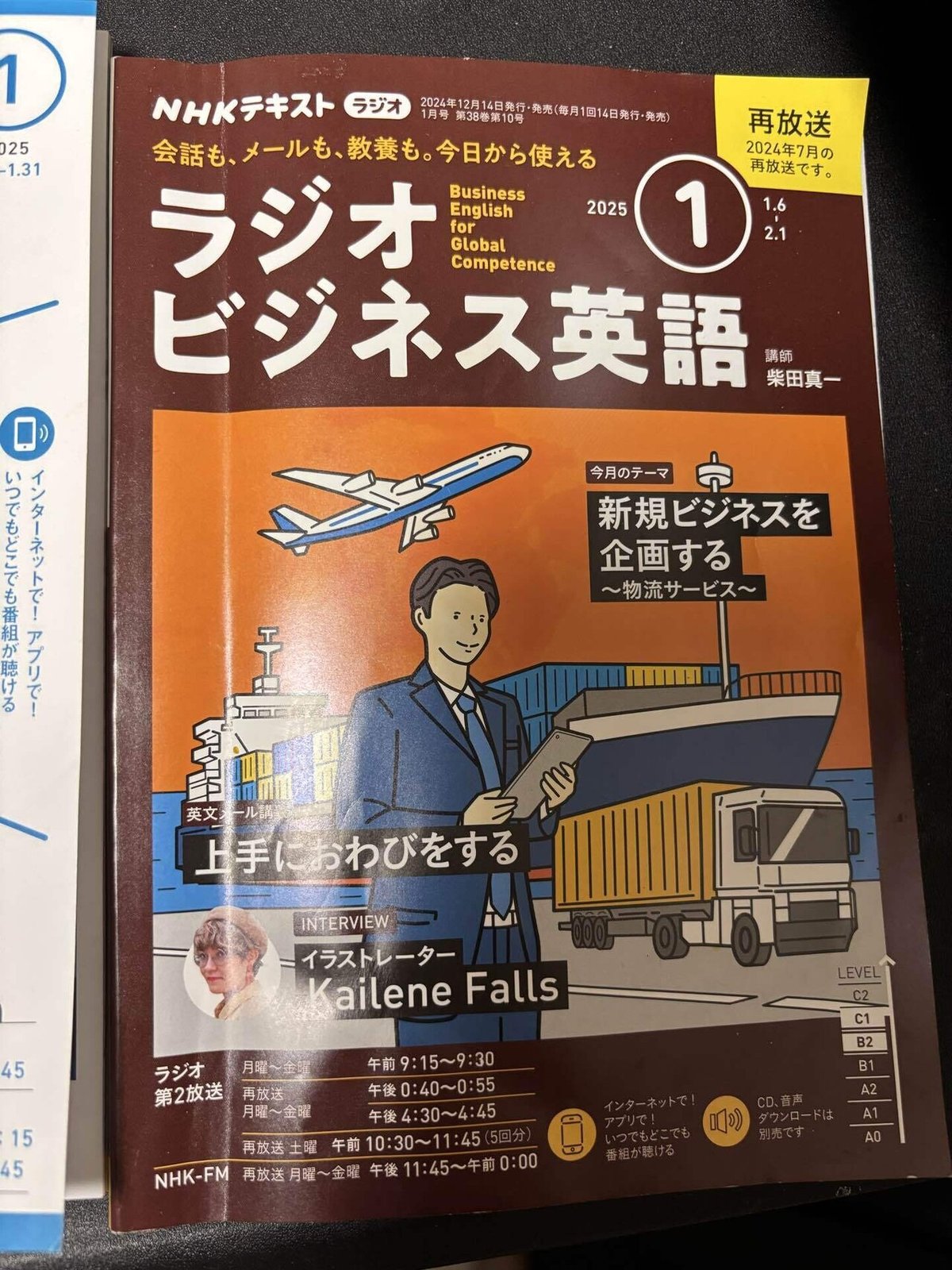

NHKのラジオ講座です。
1日15分と決して長くはありませんが侮るなかれ。
週に5回放送がありますので、毎日聞けば75分、1ヶ月聴き続ければ5時間を超えます。
言語学習も筋トレと同じで、1日にブッパするよりも毎日コツコツが大事です。
歴史といい筋トレといいアニメといい、ハマるととことんハマるタイプの私は、だんだん語学を学ぶことそのものを楽しいと感じるようになってきました。
勉強していく中で、英語とフランス語という二つの言語は似ているところもありながら「全然違うなあ」と感じることもあり、その関係性が面白いと感じました。それに関する私なりの分析・考察もどきみたいなことを書きたいと思います。
なお、私は限界法学部生ゆえ言語の成り立ちに関する知識は素人同然なため、有識者の方はお手柔らかな袋叩き、訂正、そしてご指導のほどお願いいたします。
似ていると感じるところ
①単語
まず単語そのものに似ているものがちょくちょく見受けられます。しかしまるっきり同じという訳でもないのが面白いところ。
例えば、「難しい」という意味を持つ英語のdifficultに相当するフランス語はdifficileですし、「不可能」を意味するimpossibleに至ってはスペルも同じ
(英語は「インポッシブル」、フランス語は「アンポシーブル」と読みます)。
他にもまだまだありますが、挙げ始めるとキリがないのでここまでにします。
にわか調べで恐縮ですが、おそらく「英語がフランス語の影響を受けている」というのが正しそうです。実際、英語の語彙の6割近くはラテン語もしくはフランス語からの借用だとのこと。
歴史を踏まえると、ラテン語→フランス語→英語と分化していった(この言い方が正しいのかは分かりませんが)のでしょうか。
②文法
これはとくに助動詞系が顕著だと思います。
例えば英語のwant(~したい)はフランス語のvouloirに意味合いが近いですし、英語のcan(~できる)はフランス語のpouvoirに意味が似ています。
さらに、英語では"I want to~"という言い方は「要望」の感じが強く出てしまうのであまり好まれず、"I would like to~"という言い方をすることが多い気がします。
フランス語でもJe veux~(Jeはフランス語の一人称)という言い回しはまず使われず、代わりにJe voudrais~と言うことが多い。
他にも、英語の5W1Hに相当するものがフランス語にもあります。
what←→que
who←→qui
where←→où
when←→quand
how←→comment
文法体系もこのように少し似ているので、フランス語をやっていて「ん?」と思ったときは日本語に直すよりも「英語でいうとこれか~」というように英語を仲介させた方が頭に入りやすいと感じます。フランス語学習者のためのライフハックです。
似ていないと感じるところ
①名詞
まず、フランス語は名詞が「男性名詞」「女性名詞」の二種類に分かれています。「名詞に性別がある」というのは日本人にとってなじみのない感覚ですが、ヨーロッパ言語だとよくある話(ドイツ語ですとさらに「中性名詞」なるものがあるようです)。
どちらかというと、名詞が分かれていない英語のほうが珍しい気もしています。これは大きな違いですね。
②発音
言語が異なるので当たり前っちゃ当たり前ですね。
たまに英語の単語をフランス語読みしたり、その逆もやったりします。
顕著に違うのは「フランス語は語末の子音やhの音を発音しない」ということ。
これはなんか理由があるんですかね…?
ただ発音しないならまだしも、アンシェヌマン(発音される語末の子音が、次の単語の頭の文字とくっついて発音される)という現象があって頭がぐるぐるしそうになります。
結論・考察
前にネットで、「英語はフランス語に似ているが、フランス語は英語に似ていない」という意見を見つけて、最初「どゆこと」状態だったのですが、歴史を見てみると合点がいきました。
まず前提として、英語はドイツ語や北欧の言語、オランダ語などに近いゲルマン語派に属する一方、フランス語はスペイン語やイタリア語などに近く、口語ラテン語が変化して生まれた言語でロマンス語派に属します。ですので、くくりは異なります。
しかし、英語もフランス語も「インド・ヨーロッパ語族」に属するため、遠縁の親戚くらいの関係ですね。
これくらいの関係なのにもかかわらず、「似ている」と感じるがあるのは、イギリスが昔フランス人(便宜上こう呼びます)に支配されていたことがあるからでしょう。
1066年に、ノルマンディー公ギヨーム(英語読みはウィリアム)がイギリスの王位を奪ったことでノルマン朝が立てられます。
それをきっかけに2万人のフランス人がイギリスへと渡り、政治の要職を占めました。
そのため、14世紀ごろまでイギリスでは政治や裁判、教会など公的な場ではフランス語を使い、日常言語として英語が使われるという構造になりました。
さらにノルマン朝を引き継いだプランタジネット朝もフランスにルーツがあったため、プランタジネット朝最後の王リチャード2世に至るまで、イギリス王でありながら母語はフランス語という不可思議なことになったのでした。
こうした背景から、「英語→フランス語は似ているが、フランス語→英語は似ていない」という状況に至ったと考えられます。
言語と歴史の関連を調べてみると面白い話がざくざく出てきそうなので、これからも勉強・調査を続けてみようと思います!
