
九鬼の記事vol.22(2020.05.10)
0.今週の記事のレビュー
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
「今週の記事のレビュー」では、本記事を簡単にまとめています。★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
1️⃣今週の学び:今週の学びは、暑さ対策に関すること。応用的なことを理解するためにも、基本的な生理学について学んでいます。専門ではないので、新しい情報に触れられて新鮮な気持ちに。是非読んでみてください🙇♂️ それから、前回のスプリント❌バイメカの勉強会での質問に対する回答です。勉強会中に質問が採用されなかった人は、是非ご覧くださいね。
2️⃣今週の陸上部・巧のトレーニング:今週もなわとびを使ったエクササイズ。これで前に進んだり、方向転換してみたりすると、股関節を使いながら色々な運動への準備として使えます。
3️⃣今週のオススメ論文:今週の学びと連動させて、暑熱順化の論文を。6日間という短期間での暑熱順化によって、高温環境でのパフォーマンスの変化を検討しています。キーワードは、皮膚上の血管拡張。
4️⃣時事ネタ・記事の紹介とコメント:練習再開後のトレーニング負荷の漸増について。一般的な指針だけれども、こういうのは本当に役に立つと思います。
5️⃣Q&A:
1.今週の学び
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
「今週の学び」では、今週のできごとから九鬼が感じたことについて述べています。主にトレーニング・コーチングの現場での気づきを発信したいと思います。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
今週の学びは、「暑熱順化」です。いわゆる、暑さ対策とか暑さ慣れ、というようなことですね。
大阪経済大学の長距離チームは、全日本学生駅伝に出場することを大きな目標として設定しています。その中で、その予選会は6月の中旬に行われます。しかも、例年は京都。夏の京都の暑さは、独特で、湿気というか無風というか、なんとも言えないような暑さがあります。
そんな中、暑さを考慮して夜に試合を設定しているのですが、それでも10000mを走るのは正直きびしい。暑さで本来の力を出しきれない選手はもちろんいて、その一方で、暑さに強くて本来では勝てないような選手に勝ってしまう選手もいます。
そういう話を竹澤さんとしていて。暑熱順化について、勉強しましょう!と盛り上がりました。そこで、僕の筑波大学時代の後輩で、生理学の研究に取り組んでいる友人とZoom会議。そこで、勉強したことを少し共有させてくださいね。
そもそも、ヒトが走ることで一歩一歩の着地で大きな地面反力(反発)が生まれています。筋肉や腱で、それらを弾性エネルギーというものに変換して、効率よく運動を行うなどもよく知られていますが。それはほんの少しで、大部分は筋肉で熱エネルギーへ変換されます。
一説によれば、安静時のヒトの産熱は60%が筋肉で行われており、運動時にはもっと多くの熱が出されているとも言われます。
そうすると、今度はいかに熱を放出するかというのが重要になってきて。これは発汗が20%、皮膚上の血管を流れる血流と気流との差で放熱するのが20%だそうです。発汗はイメージつきますが、皮膚上の血流でかなり体温を下げるというのは案外知られていないのではないでしょうか(恥ずかしながら、九鬼は知りませんでした。😭)
そうすると、皮膚上に流れる血流量を多くすると体温を下げられるのですが、その局所だけ!というのは無理なので、全身の血流量を増やそうとして心拍数が高くなります。暑いところで心拍数が上がる理由の一つがこれらしい。
じゃあ、それで一件落着じゃないか!と思いますが(笑)。
皮膚の血管に血流が多く流れると、その分、筋肉に流れる血が少なくなってしまって、酸素供給量が少なくなってしまうらしい。それによって、筋のパフォーマンスが低下してしまうので、なるべく心拍数は低いにこしたことはなし!
しかも、酸素供給量が少なくなってしまうので、エネルギーの供給も脂質代謝から糖代謝に変わりやすくなってしまうらしい。LT値が下がってしまう可能性も。竹井くんの勉強会でもあったとおり、マラソンとかはいかに糖を使わないギリギリのところでペースをおしていけるかが勝負のカギになるので、この糖代謝への変換は致命的。
じゃあ、暑熱順化をどうすんの!?というのを、もう少し勉強したいと思います。💪
ってかね。ここまで読んでいただいて、この一連のお話おもしろくないですか!?(←自画自賛ではありません。笑)
僕は、生理学を専門としていないので、このような話はあんまり知らなかったんですが。聞いていると、身体が全て繋がっていて、とても面白い。しかも、こういうメカニズムを知っていると、単一的な方法論だけの暑さ対策じゃなくて、その「理由」もちゃんと説明づけられる👏
しかも、暑さ対策は多くのスポーツ、本当に多くスポーツで重要になってきます。例えば、持久的な要素が皆無な陸上競技の100mでさえ、暑さ対策はとても重要。
なんでかというと。
例えば、夏のインターハイなんかでは、真夏に予選・準決勝・決勝と3本走ります。それぞれのレースに向けてアップを1時間程度していくと、それだけでも最後の決勝ではバテ気味に。しかも、昨年なんかは沖縄だったので、それはもう熱いのなんのって...
レース間で選手の疲労をなるべくとって、フレッシュな状態でレースに挑ませるには、少なからず暑さ対策(体温を下げる方法)が必要になってきますよね。これは、中学生でも大学生でも同じ。
もっというと、より持久的な要素の高いサッカーやバスケには重要性が高まるでしょう。
と、いうことで暑熱順化や対応調節に関するオンライン勉強会も開催したいなー、と竹澤さんとゆるーく企画していきたいと思います🙇♂️
さて、次は。
前回行われたスプリント❌バイメカ勉強会の第二弾における質問とその回答です。
勉強会では、毎回多くの質問が寄せられ、講師の先生に全て答えていただけないので、このようにしてnoteで紹介しています。残念ながら勉強会中に質問が採用されなかった人も、以下のところで取り上げられているはずです。ご覧ください🙇♂️
Q. 腰部トルクが生み出されるのは筋収縮のみからですか?運動エネルギーからは生まれませんか?
A. 力学的エネルギーはセグメントの動きなどは生みますが、関節トルクを直接は生みません。なお、細かい説明はしませんでしたが、筋以外にも靱帯などの様々な組織が存在し、これらの組織は関節トルクを生みます。筋腱複合体やその他粘弾性を有する各種組織に蓄えられ、放出するという意味では起きるかもしれませんが、基本的には“力”の世界なので、運動エネルギーがトルクを生む、は違うと思います。
Q. 今回のお話は直線のスプリントを想定されていると思いますが、コーナーを走る時も伸展屈曲方向については同様の結果になるのでしょうか?
A.データはないため断言はできません。何らかの差は生じるとは思いますが、同様のメカニズムは存在すると予想されます。
Q. 片足支持(走っている時)に地面反力を適切に得る事と腰仙伸展と股関節伸展のバランスが取れる事はどちらが先だと思われますか。
A. どちらが先ということはありません。適切な股関節伸展トルク発揮のために腰仙関節伸展トルク発揮が必要と考えられます。
Q. 下肢を動かすために骨盤を安定させる必要がある。つまり、腰部の伸展トルクが出ているという結果ですが、もし意識するのであれば、骨盤を動かすというよりは安定させる意識の方が良いのかなと感じましたがいかがでしょうか?
A. バイオメカニクスの観点からは意識については言及できない、ということを申し上げます。
“矢状面に限定して”言うならば、骨盤の動きが小さいのは事実です。
A. 加速と疾走の局面で大きく作用する関節トルクは異なると思いますが、腰仙関節の伸展トルクに着眼するとどのような違いがありますか?
A. これは、勉強会でも話しましたが、スプリントの2歩目くらいから関節トルク発揮パターン自体は類似します(分析の技術的な話で、衝撃局面の処理によって少し変わってはくるのですが)。下肢も、足関節は底屈、膝はおおよそ伸展トルクで離地直前に屈曲に移行、股関節トルクは中盤から後半の辺りで伸展トルクから屈曲トルクへ移行していく…といった感じです。腰仙関節も発揮パターンに大きな違いはありません。
Q. 腰仙関節伸展トルクは接地後期では遊脚の屈曲動作が大きくなる分小さくなると思うのですがどう思われますか。
A. 遊脚股関節では屈曲動作しながらも伸展トルクに移行するため、どちらかというと遊脚の作用は腰仙関節伸展トルクの要求を大きくします。一方で、支持脚股関節については伸展トルクから屈曲トルクに移行します。
ぜひ、トルク(実施者がしている力発揮)と見た目の動きでは違う、ことを復習してください。
Q. スプリントそのものと話はズレるかもしれませんが、スプリントやスタートにおける股関節・腰仙関節トルクの傾向は、ハードルの踏切時にも同様の傾向があるような気がするのですが、いかがでしょうか?
A. 拮抗して固定という意味では片脚踏切動作も類似します。ランニングジャンプでもそうでした(Sado et al. 2018 Int J Sport Med)。ただし、ハードルはディップするための屈曲トルクの要請がある気がするため、少し違う可能性もあるかもしれません。
Q. 腰仙関節の伸展トルクや股関節の伸展トルクを現場で簡便に評価する方法はありますか?
A. 今のところは走っているときのトルクを簡便に測る技術は私が知る限りは難しいと思います。あとは、ウェイトトレーニングのMAX測定や各種のコントロールテストなどを組み合わせて評価していくのがよいかもしれませんが、その辺も今後のエビデンスが待たれるところです。
Q. 実際のトレーニング現場では、「スクワットは強いがデッドリフトは弱い」という形で現れる可能性が高いという事でしょうか?
A. ちょっと違うと思います。デッドリフトでもスクワットでも、体幹が負けて重量が上がらなくなるという現象は起きます。ただし、スクワットは重量の挙上をより膝で代償することが可能な分、膝優位のスクワット動作によって重量が上がってしまうという競技者ではそれが起きるかもしれません。
Q. 股関節伸展トルクが強く、腰仙関節伸展トルクが少ない場合、腰仙関節の伸展トルクの強化に特化したトレーニングとしては何が有効でしょうか?
A. スクワットやデッドリフトなどを両脚で行うことでかなり負荷をかけてあげることができます。これらの種目は下肢より体幹がリミットファクターとなって重量が挙げられなくなることが多いです。ただし、腰痛にお気を付けください。。。
Q. スクワットやデッドリフト以外で腰仙関節に効果的なトレーニングはあるのでしょうか?
A. “関節トルク発揮能力”あるいは筋力ですね。関節に効果的なトレーニングはありません。
基本的には“姿勢を保持しつつ股関節伸展トルク発揮が求められる”エクササイズは腰仙関節伸展トルクおよびその筋群への負荷がかかると思っていいと思います。特に両脚でやるとその負荷は大きくなります。
Q. 接地時間の話で、疾走速度が上がると下肢の長さによって接地時間が決まるという認識でよろしいでしょうか?また、そうすると疾走中の接地時間を短くしようとする練習は必要ではないということでしょうか?
A. そのご理解で結構かと思います。疾走中の接地時間を短くする練習は実質いらないと思います。短い接地時間の中で地面を押すための力発揮能力により、あまり幅がない接地時間に対し結果的に必要以上な接地時間はなくせるかもしれません。
Q. 股関節伸展トルクを大きくするトレーニングを行っても、腰仙伸展トルクが小さいと意味がないと言う認識で大丈夫ですか?そのときは、伸展トルクを高めるトレーニングを先に行う方がいいですか?
A. 多くの股関節伸展トルク発揮能力を鍛えるトレーニングは腰仙関節伸展トルクの発揮能力を鍛えることになります。先に行うかどうかに関してはその人の課題から逆算したプライオリティに応じて決定するのがよろしいかと思います。
Q. 研究者として指導者に持っていてほしい思考などをお聞かせ頂きたいです。
A. 非常にいい質問です。
ぜひ、スポーツ科学の基本的なエビデンスを使えるようになっていただきたい。ただ速かった人・強かった人が持っている情報というのは、貴重な“資料”ではありますが、一つのcaseであって、エビデンスレベルとしてはかなり低くなります。一方で、私や竹井君が出したような情報は科学的な作法に則って出されたエビデンスです。
医学の世界で、“自分が病気から治癒した元患者”と“病気を治すために必要な知識を得るために学んだ医者”のどちらに治療を依頼しますか?後者ですよね。これを前者にしてしまう人があまりに多いのがスポーツの世界のあまりに残念な現状です。
たしかに経験は役に立ちます。医学で言うところの、実際にその病気になった経験は病気を見つけるヒントになりうるからです。スポーツでも同じで、上位競技者としての競技経験が価値ないわけではありません。しかし、強かった選手がコーチとなって自分の経験を選手に押し付ける指導だけは絶対にしないでほしい、しっかりと最新の知見に触れるという姿勢でいてほしい、というのが切実な願いです。
Q. 本日も貴重なお話ありがとうございました。やや本題とずれますが、現場的には短距離長距離共に疲労によって足が流れるという場面が良く良くありますが、どのようなメカニズムで足が流れるという現象が起きているかについて、見解を教えていただきたいです。
A. 一口に疲労と言っても多様な要因があります。力学的なメカニズムを言うのであれば、考えられるのは屈曲トルクを発揮するタイミングの遅れやそのトルク自体の小ささが要因になると思います。さらには、接地時に支持脚が十分にCoMの下方速度を受け止めきれず、CoM高を接地中に戻すことが不十分なためにこの後の滞空時間が短くなって…などの間接的なメカニズムもあります。そして、回復動作が遅れたために接地瞬間の姿勢が十分に整わず接地時に…といった連鎖が生じます。
ただし、中枢疲労から末梢疲労までそれを惹起する要因がたくさんあります。これらすべてが理解されているわけではないと思います。
Q. 本日は貴重なお話ありがとうございました。
A. 今回は支持期のお話でしたが、ぜひ滞空期の腰仙関節と体幹部の動態についてご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
ここだけで説明するのが非常に難しいのですが、簡単にいうと滞空期は主に捻転トルクが出ます。ぜひSado et al. 2019 J Biomechをお読みください。
Q. 股関節伸展トルクと同等の腰仙関節伸展トルクが必要ということでしたが、股関節伸展能力の向上をメインに考えたトレーニングでもOKC的な股関節伸展運動や単関節で股関節伸展動作のトレーニングするのではなく、スクワット動作などの骨盤腰部複合でトレーニングすることで適切な走パフォーマンスの向上につながるという解釈でよろしいでしょうか。
A. task-dependentな話であり、どちらかがいい、という話ではありません。それぞれに短所長所があり、合目的的なトレーニングの選択が重要になります。
Q. 腰部と股関節伸展筋のどちらを強化した方がいいのかは、どの部分を見て評価することができますか。
A. 実際に弱いとどうなるかというエビデンスがあるわけではありませんので、断言することはできません。
ただし、例えば、片脚エクササイズで両脚エクササイズのMAXの70%を挙げられる人と80%挙げられる人では、後者の方が腰部の伸展筋群がリミッティングファクターとなり得ると思います。
Q. 一次加速で歩隔が広い場合はカッティングのように中殿筋よりも遊脚の脊柱起立筋や支持脚の内転筋が重要となるのでしょうか
A. 可能性はあります。どの程度その傾向が強くなるかは調べてみないとわかりません。
Q. バイオメカニクスを勉強するにあたりおすすめの本はありますか?
A.
深代ほか スポーツ動作の科学―バイオメカニクスで読み解く(東京大学出版会)
阿江と藤井 スポーツバイオメカニクス20講 (朝倉書店)
金子と福永 編著 バイオメカニクス―身体運動の科学的基礎 (杏林書院)
スプリントでしたら
日本トレーニング科学会 スプリントトレーニング―速く走る・泳ぐ・滑るを科学する (朝倉書店)
Q. 腰仙関節の進展トルクの発揮について、頭部のポジションは阻害因子にはなりうりますでしょうか? 顎が上がっている等、走るパフォーマンスに置いて悪影響ではないのか⁉
A. 力学的な影響は小さいと思いますが、頸反射などの影響はニューラルにはあるかもしれません。走行中の影響を見たエビデンスは私が知る限りはありません。
本当に多くの方に参加いただくことができて、嬉しく思っています。ありがとうございました🙇♂️
ここから先は
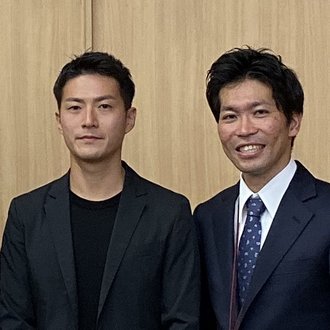
市民ランナー高速化プロジェクト
✅市民ランナー✅指導者・トレーナー✅スポーツ科学を勉強する人、へ役立つ専門情報を届けます👍 知識をアップデートしたい方、僕たちと「オモロイ…
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
