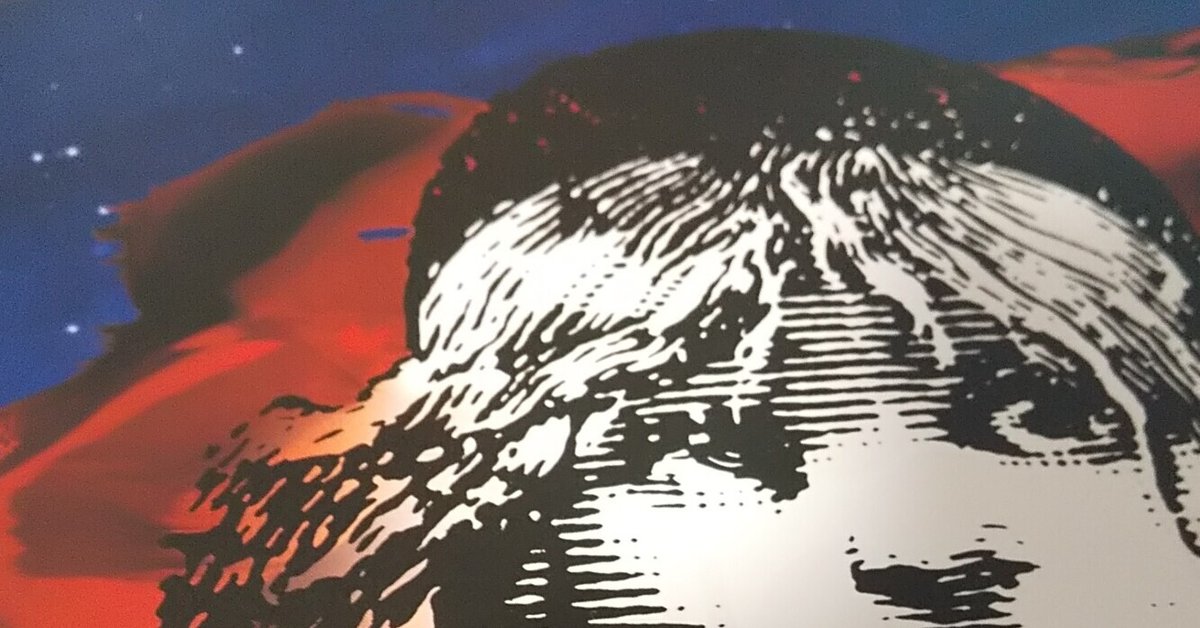
その一音に、魂が宿る。
ようやく見れました、2021年のレミゼ。

もう何回も見てる作品だけど、何度見てもやっぱり素晴らしい…!
最後の民衆の歌がリプライズで流れるときは、しっかりうるっときました。
今回、後方の席だったので、初めてオペラグラス有りで観劇したのですが、
見終わって思うのは、オペラグラスなくてもよかったかな〜ということで。
もちろん細かい表情を見て楽しめる部分もあるのだけれど、
基本的には歌をちゃんと聞いて、ステージ全体で繰り広げられる群像劇をちゃんと捉えたほうが、しっかり物語の世界観に入れる気がしたんですよね。
ミュージカルだし、広い帝劇でやってるということもあるし、
細かい顔の表情を追わなくても、音と身振りでちゃんとすべてが伝わるようにつくられているのだなあ、と改めて実感。
以前「クラシックTV」でトレエン斎藤さんが「レミゼはまずは音譜通りしっかり歌えばちゃんと物語になる」的なことを言われた、とおっしゃっていたのが、ようやく腑に落ちました。
その上で、同じ稽古を受け、同じ役、同じ歌を演じていても、
キャストが変わると、あるいは同じキャストでも、細かな感じ方、役に対して感じる印象が毎回変わってくるのが、やっぱり奥が深いなあ、と。
複数のキャストが同じ役を演じているのを見比べると、
もともとそれぞれのキャストの方が持ってる声質の違いもあるし、
一音一音、細かいところの揺らぎ、声の張り具合、そんな違いからも、
その登場人物の持つキャラクター、性格みたいなものが変わって見えるんですよね。
今日のコゼット(加藤さん)は、一般的にある清廉なイメージというよりも、マリウスとの出会いにどこか浮かれてるような印象を感じたし、
二宮愛さん演じるファンテーヌは、死を直前に衰弱してなお、母親としての強さ、矜持みたいなものを失うものかと必死に振る舞っているような感じ。
生田さんのエポニーヌも、「ナチュラルボーンコゼット」たる生田さんが演じるからこそのエポニーヌ像を勝手に感じてしまって、すごく印象的だったのですが、書き出すとこれだけで1記事になりそうなのでこれは別稿で…!
その一音の伸びやかさが、音の強弱が、清濁が、
舞台上にある役に魂を吹き込み、今その場にしかない一期一会のキャラクター、人物像をつくりあげる。
だからこそ、舞台に立つ役者の方々は、その一音にこだわって、日々鍛錬を重ねられているのだなあ、と。
見れば見るほど、そういった細かいところへの気づきとか、
舞台上のいろんなものに目がいくようになるからこそ感じることもあって、
これはもう、順調に沼にハマってますね。笑
でもそれだけハマりがいのある、素敵な作品だなあ、と改めて感じた、帝劇からの帰り道でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
