
《初泣、初虹.》
京都の街が、いつもとは全くちがってみえたのです。神々しくて、痺れるほどおもしろくて、崩れ落ちるほどに粋で。

「光悦会(こうえつかい)に行きましょう。」お茶の先生が、そう提案してくださったのは、今年の春先でした。
まだ茶道の世界に入って二年のわたしがポカンとしている中、先輩方は「え〜〜〜!!!」と悲鳴をあげていらっしゃいます。伺えば、「光悦会」は日本最高峰の会員制のお茶会。登山でいえばエベレスト登頂のような会に、総勢20名の弟子を招待してくださるというのです。ご自身の傘寿(さんじゅ/80歳)のお祝いに合わせてと、実に贅沢なお誘いをしてくださったのでした。

さて、ずいぶん先と思っていた霜月(しもつき/11月)の光悦会が目前に迫っておりました。早々に準備を始めなくてはなりません。一番いい着物で来るのよ、という先生のお言葉通り、母が結納で着たわが家で一番華やかな着物をスーツケースに収めます。また、予約したホテル、会場の「光悦寺」の場所をあらためてGoogle Mapで確認します。
いよいよ京都に向かう日がやってきました。旅程としては、このような具合です。
一日目:大徳寺(だいとくじ)見学、
先生傘寿のお祝いのパーティー
二日目:「光悦会」
三日目:瓢亭(ひょうてい)にて朝食、
金地院(こんちいん)見学
鈍色の空のもと、色とりどりのお着物纏う先生や先輩方と、旅は始まりました。まずは、大徳寺の見学から。大徳寺は千利休ゆかりの禅寺なのです。

もっとも印象深かったのは、境内にある小さなお寺「黄梅院(おうばいいん)」の「直中庭(じきちゅうてい)」。千利休が豊臣秀吉を想いつくった日本庭園です。秀吉軍の軍旗「瓢箪(ひょうたん)」を象った空池には、凛々しい鶴と亀の石が添えられています。また襖の引手もよくみれば瓢箪型。茶の湯のおもてなしの心が、随所に詰まった枯山水庭園に、何度感嘆のため息をこぼしたことでしょう。

その余韻に浸りながら、向かったのはパーティー会場。ホテルのレストランのシックな壁が、先生や先輩方の煌びやかな装いを引き立てます。まずは乾杯、キャンドルゆれるケーキも運ばれてきます。その後は、先生へのお祝いを一人ひとり伝える時間。先輩方からは温かいながらもきりっとしまった言葉が続きます。
そして、わたしの番。「先生傘寿、おめでとうございます。」というと、涙が溢れてくるではありませんか。大いに詰まってしまう言葉を、「うんうん。」と聞いてくださる先生のまなざしの優しかったこと。最後に思わずこぼれた「先生、長生きしてください。」は会場に大きな笑いを起こしてしまいました。
その後も続く、朗らかな雰囲気。美味しいお料理に、ちょっぴりかかるお酒の魔法、毎回素晴らしいお稽古をしてくださり、こうして今日京都へ招いてくださった先生への感謝の気持ちに、いつになく愉しいひとときとなったのです。

翌日。
ついに「光悦会」に向かう時がやってきました。あいにく今にも雨が降りそうなお天気です。待ち合わせ場所から、先輩方とタクシーに乗り込みます。しばらく北へと走っていると、空が明るくなってきました。
お茶会に、待ち時間は必須。雨が止んでくれたらいいのになと思いながら窓の外に目をやると、なんと虹がかかっているではありませんか!広い道路を走っていたため、交差点では端から端まで半円に近い虹が綺麗にみえたのです。「幸先がいいわね。」と話しながら、光悦寺へと向かいます。

ところが、光悦寺に着くと雨はひどくなるばかり。この季節の晴れた日は着物を着ていると心地よく感じられる気温のはずなのですが、凍える寒さなのです。テーマパークで各アトラクションに並ぶのと同じように、四箇所で長時間列をつくることを考えると、ますますガクガクと震えてきます。

寒さの中30分ほど待ち、ようやく初めの席に入ることができました。何やら読むことが難解な掛け軸が迎えてくれます。それでも、この正体を知りたいという欲求がふつふつと湧いてきて、少しずつ気持ちが前のめりになってまいりました。
その気持ちに拍車をかけたのがお菓子。この日初めて口にしたそれは目がまん丸くなるほどの絶品だったのです。朝つくったばかりという半透明のおまんじゅう。今まで味わったことのない軽やかな弾力と今にも溶けそうなやわらかさを持ち合わせていて。続いて運ばれてきた熱々のお茶は、待ち遠しくて仕方なかった人に逢えたような喜びをもたらしてくれました。
その後も感動の嵐。「たまらぬものなり」とのちの人が呼んだ「乙御前(おとごぜ)」という名のお茶碗にふれると、その愛称にひどく納得してしまいました。手の中にぴたっと収まるなめらかな、人肌のような温もり。あとで、会記(お道具の一覧)をみると、「重要文化財」とあり、ひっくり返りそうになったこともつけ加えておきましょう。
そうなのです。この光悦会というのは、普段美術館のケースの中に入っている名品を直にみることができる、とっても貴重な場なのです。お茶碗に限っては、ふれさせていただくことも叶うのでした。

時間を追うごとに身体は冷えてゆきますが、心と頭はポカポカに。そして、青空もみえてまいりました。めくるめく四席の旅を終え、最後には、老舗料亭「瓢亭(ひょうてい)」さんのお弁当をいただきます。心尽くしの季節の品々に、名物の半熟卵。
色づき始めた紅葉、その向こうで広がる山並みを時折ふりかえりながらいただきます。晩秋から初冬にかけてパラパラとふる「時雨」がきらきら輝く様子もまた、大変なおごちそうでした。

さらに、なんと帰りに先輩方と立ち寄った神社では、また虹がかかったのです。時雨と紅葉の景色、日に二度もみられた虹、憎いほど粋な演出ではないでしょうか。
日頃はきっちり8時間眠ってしまうわたしですが、この日は眠れぬ夜となりました。あまりに興奮していたのでしょう。電気を消し布団にもぐっては、電気をつけ、会記をひらく。これを数回繰り返し、ほんのちょっと居眠りをしたのちには、もう朝と呼んでもいい時間になっておりました。
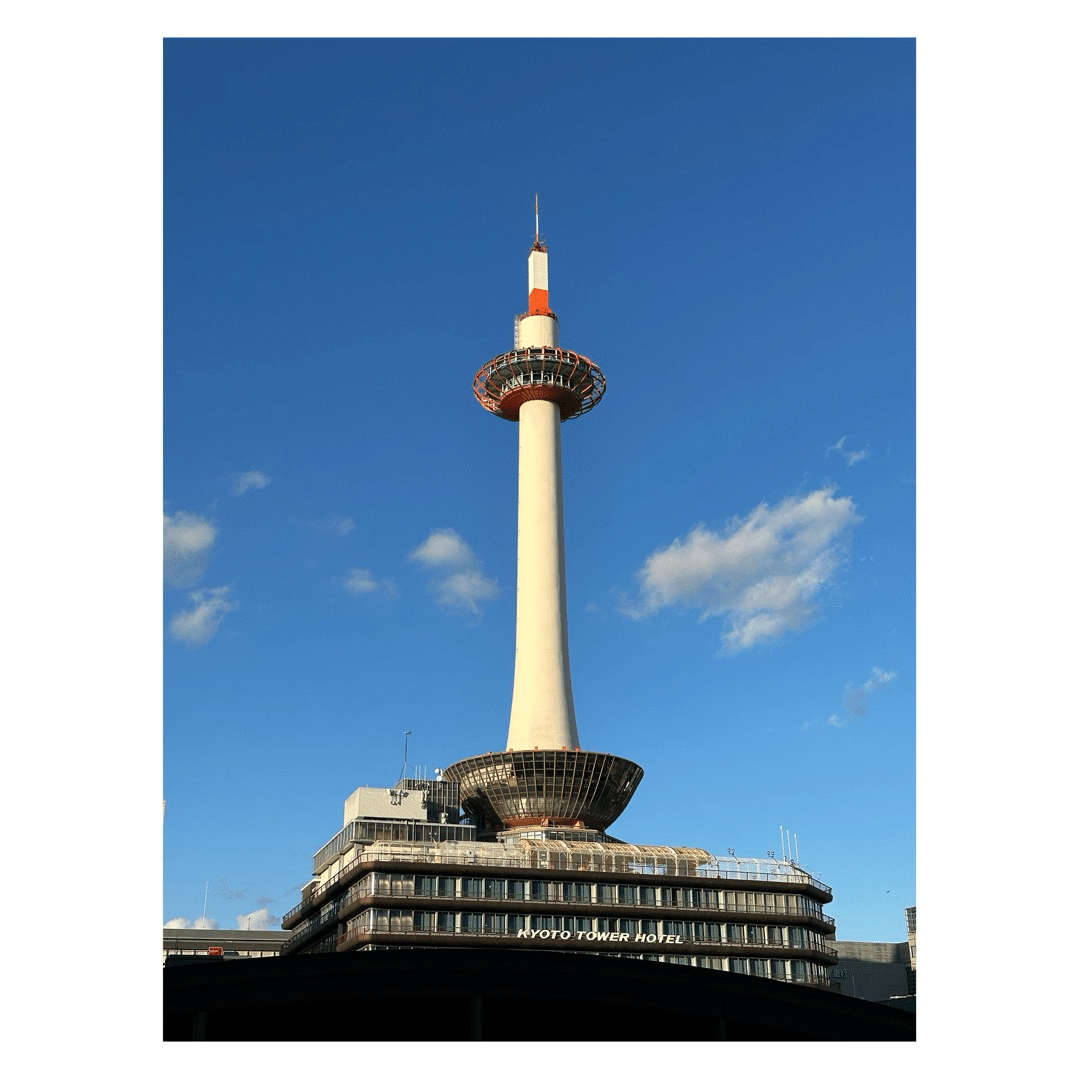
荷物をまとめて早朝の京都駅に預け、先輩方と待ち合わせをしている南禅寺にある「瓢亭(ひょうてい)」さんの別館へと向かいます。昨日お弁当をいただいたあの老舗料亭の朝粥をいただくのです。
昨日の雨がうそのように、きりっと晴れたさわやかな朝。先輩方とほのぼのとしたひとときを過ごすことができました。

そして、京都最後に訪れたのは、金地院。こちらは「南禅寺」の一角にある徳川家と縁の深いお寺です。その特別拝観のお茶室のまたおもしろかったこと。八つの窓に由来する「八窓席(はっそうせき)」と呼ばれるお茶室は、武家好みなのです。身分によって、入口も座る場所もことなる。
千利休の時代の「茶室に入れば皆平等」の精神とはちがった趣向となっているのです。また一つ、勉強になった金地院での午後でした。

こうして濃密な三日間に終止符を打つべく京都駅に向かうと、大勢の旅行者の姿。久しぶりに現実をみたような気持ちにさせられました。
物好き?いえ、お茶好きしか集まらないような場所を巡っていたせいで、京都がとても静かな街に感じられていたのです。そこで感じられた京都は、驚くほどエキサイティングだったのですが!

結びに、帰りの新幹線のお話を。先輩方とわたしとでは別々に打ち合わせもなく、席の予約をしていました。にもかかわらず、同じ列車の同じ車両、その続きの席を偶然にも取っていたのです。最後の最後にこの痺れるサプライズ。どの瞬間も一生忘れることのできない旅となったことは、いうまでもないようです。

