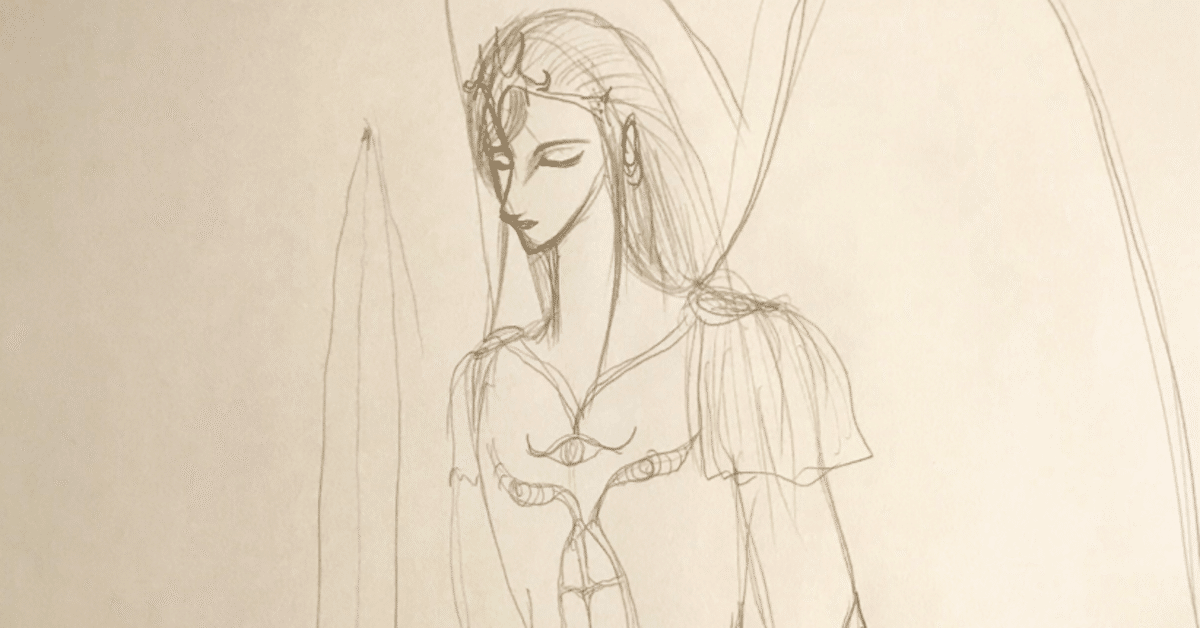
Photo by
mamezouya
9月15日 意味の深みへ
井筒俊彦「意味の深みへ」 をぽつぽつ読んでいる。ほとんどページは進まない。一行一行が深すぎてなかなか進まないのだ。
神が存在するというただ一事で世界がそこにある。そこでは手紙の最初の一行も最後の行も、最初の一字も最後の一字も全部まったく同じ資格で「神の顔」の前に立っている。というより、「神の顔」によってそこに仮象的に存在させられている。
私はいままでイスラムの文化や宗教に関してほとんど知識がなかったが、井筒さんの本ですこしだけ触れることができた気がしている。
命を懸けて自身の神との距離を述べざるを得ないことは、もちろん現代でもあるだろうが、相対的に神、というものの重さが現代と過去では全くいうものの気持ちと”気合い”が違う気がする。
そのときのメインの宗教に逆らう、ということは、あるいは本人にはそのつもりがないにしろ、その宗教で政治や稼ぎや生業を行っているものにとっては、その土台を根底から揺らがすことが危機感とともに直観でわかり、その結果為政者やその宗教のトップは苛烈に発言者を抹殺し続けてきた、という歴史が続いた。
そこからさまざまな形で採集された言葉や断片や決意やつぶやき。
ソクラテスにしろ、「若者を惑わせた」ということで死刑である。
この日本、いろいろあるが、思想で死刑にはならないし、経済犯で死刑にはならない。基本2人以上の殺人(時に一人)でなければ死刑にならないと認識している。
そのことは、端的にはありがたいことである。
だが死刑が目の前にあっても敢えて問う、というまさに死を賭した言葉の重みもまた、見ることはないのであろう。
(本でそういった言葉に接することができるのは、ありがたいですね)
いいなと思ったら応援しよう!

