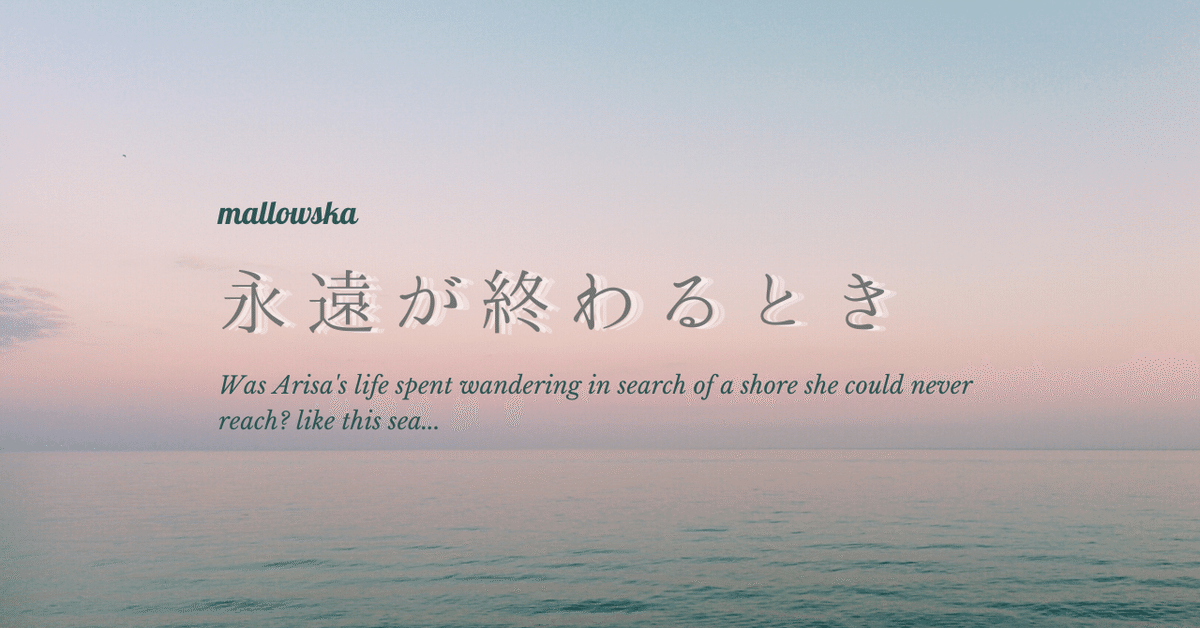
【連載小説】永遠が終わるとき 第一章 #3
それからはこれまでの苦労話やどうしようもない話、飯嶌さんが突如熱く未来について語りだすなどして盛り上がり、結局私の終電がなくなる時間まで飲み、語った。
野島次長と飯嶌さんの住まいは会社からそれほど離れていないのでタクシーでも大した距離ではないけれど、私はそれよりは少々離れている。
「次長、マジで前田さん送りまひょ。ね!」
すっかり真っ赤になって千鳥足・呂律も怪しい飯嶌さんの勢いに、野島次長は小さくため息をついた。
そして私を見て申し訳無さそうに言った。
「うっかりしてたな。俺もちょっと調子に乗ってしまった」
「いいんです、とても楽しかったですし」
「じゃあ、約束通り送るから」
「えっ…」
ドキリとしたものの、タクシーに乗ったのは3人。
奥に飯嶌さん、真ん中に野島次長。そして先に降りる私が最後に乗った。
後部座席に3人だから、野島次長と身体がぴったりと密着する。
乗り込むなり飯嶌さんは次長の肩に持たれて、口を開けて居眠りし出した。
その様子に野島次長が笑う。
「優吾らしいな」
「憎めませんね」
「本当に。羨ましいよ」
愉快そうな顔して野島次長は言った。
タクシー後部座席の密着したひととき。
こんなことが以前にも一度あった。
3年近く前のこと。次長が暴漢に襲われ、顔と肩に怪我を負った。
当時野島次長の周辺に不穏な気配があった。
よろしくない行為とわかっていながら、野島次長の後をつけたことがあった。次長もまた、誰かに後をつけられていることを知ったからだ。
そして若い男性に野島次長が襲われている現場を私が目撃したのだ。
私の悲鳴で犯人は逃げ、次長は左肩から血を流していた。
治療後の病院の帰り、2人でタクシーに乗った。
あの時次長は「この事は誰にも言うな。優吾にも言うな」と私に口止めした。
墓場まで持っていくと誓い、怪我のせいか虚ろになった野島次長が、今の飯嶌さんのように、私の肩にもたれ掛かった。
次長の家に着いて車を降りる際、ふらついた野島次長を支えた際に鼻先が触れ合うほど近づいた。
次長は腕を伸ばし私を車の中に押しやると、再びタクシーは走り出した。
あの時を思い出す。
野島次長は、思い出しているだろうか。
触れている身体の側面が熱くなる。
何を話してよいかわからない。
「前田」
不意に呼ばれた。
「は、はい…」
野島次長はアルコールのせいか表情は緩やかだったが、前を見つめたままだった。
「離れた場所になるけど…仕事では絡んでいくと思うし。2人には期待してるよ。よろしく頼むね」
「はい…。次長もどうかお身体にはお気をつけて」
「そうだな…もうそろそろ無理できない歳になるしな」
「まだ早いですよ」
そう言うと次長は目をこちらに向けた。その目尻は下がり、優しい顔をしていた。
その顔を一度飯嶌さんの方に向け、相変わらず口を開けて熟睡している様子を見ると、またこちらを向いて苦笑いした。
一呼吸ついた後、私は言った。
「出会えてよかったです…」
ピクリと次長の眉が動く。「お2人に」と付け加えると、次長は口角を上げた。
「よくやったよな、3人で。本当に」
「3人だから良かったのかもしれません」
「2人が優秀だったからな」
「次長のお陰ですよ」
「俺は別に何も」
タクシーは国道を北上し、徐々に私の住む街に近づいていく。
私は恐る恐る右手を伸ばし、私の身体に触れている境界…次長の腿の辺りを小指の背で触れた。
故意か偶然かわからないはず、と思ったけれど。
野島次長は左の指で私の小指を捉えた。
息を呑む。言葉はない。
指先がわずかに絡み合う。
まるで指切りをするように。
涙が一滴、落ちる。
「前田は酒が入ると相変わらず泣き上戸だな」
少し視線を落として野島次長は言った。
左手で涙を拭う間も、指切りは離れない。
その薬指には指輪がしっかりとはめられているというのに。
その手を見、顔を上げた時。
次長も私に顔を向け、見つめ合う形になった。
これまで何度も私たちは、目だけで交わし合った想いがある。
超えてはいけないことはわかっている。
でも。
野島次長もあの "事件" 以降、今までになかった気持ちが生まれたことを感じていた。
言葉にしたらきっとおしまいだ。
だから、見つめることしか出来ない。
でも私は理解できた。
次長もまた、私が理解しているとちゃんとわかっている。
野島次長の瞳は、どこか哀しみを湛えているように見えた。
「どこら辺で停めましょうか」
運転手の声が現実に引き戻す。指はパッと離れた。もう家の直ぐ側まで来ていた。
「あ…、2つ先の交差点を右に入ってください」
息が止まりそうなほどの切ないひとときがもうすぐ終わる。
交差点を曲がり、更に路地に入ったところで停めてもらった。
車を降りる。
運転手に「ちょっと待っていて」と告げ次長も降りた。飯嶌さんは熟睡中。
「家はすぐ近く?」
「はい、すぐそこです。もう見えてます」
「建物に入るまでここで見てる。おやすみ」
このまま離れることをためらい、次長を見つめた。私を見下ろす次長の目ですら、あの夜を思い起こさせる。
私は腕を伸ばし、次長を抱き締めた。
彼はうっ、と息を呑む。
「前田…」
「ごめんなさい。これで最後ですから」
すると次長の腕が私の背中に回された。なんて暖かな腕なんだろうと思った。
きつく、抱き締めあった。
「向こうでもこの香りがしたら思い出してしまうんだろうな。俺は弱い人間だから」
再び思い出す。
あの “事件” から更に1年ほど経って…、そう、野島次長の気持ちも動いていると感じていたあの頃。
2人で飲みに行った時に私のつけている香水を褒められた。
そして帰りの駅で…口づけを交わした。
あの時、ほんのひとときだけ。
その日以降、互いに何の変わりもなく過ごした。
結局次長が私を選ぶことはないし、私も次長との個人的なやりとりは全て『秘密』として胸に沈めた。
あの時以来のハグだ。
「次長…」
「元気で」
けれど今回は唇が重なることはなく身体が引き離される。
私は家に向かって歩き出す。
途中振り返ると、言った通り私のことを見ていて、手を振ってくれた。
頭を下げ、建物に入る。
部屋に入り、明かりも点けずに窓を開け通りを見ると、タクシーは来た道を戻っていく所だった。
けれどそれはすぐに滲んで見えなくなる。
さよならと呟く事さえ出来なかった。
第二章#1へ つづく
