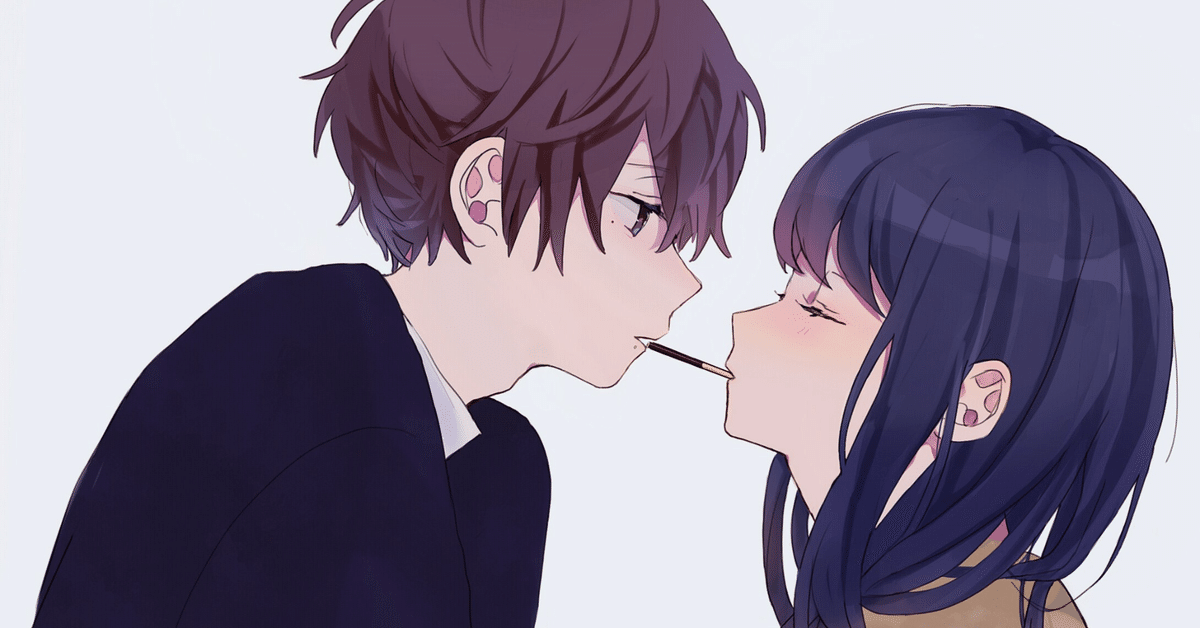
【連載】運命の扉 宿命の旋律 #21
Cantata - 交声曲 -
稜央にとって萌花はかけがえのない大切な存在になった。
一度家に来たこともあったし、家に呼んでピアノを聴かせたりしたい、と思った。
「母さん、萌花を家に呼んでもいい?」
桜子が夕食の支度をする背後から、稜央は声をかけた。
「それはどういうことを意味しているの?」
「深い意味はないよ。外で会うとお金もかかるし、ここだとピアノもちょっと聴かせられるし、と思って」
稜央の目が微かに泳いだのを察したが、桜子は落ち着いて言った。
「稜央、避妊はちゃんとするのよ」
母からのストレートな言葉に、稜央は戸惑った。
「まだ稜央も子供のようで、すぐに大人になるんだから。それに彼女が出来たのなら尚更しっかりしておかないと」
「まるで家でHしてもいいって言ってるように聞こえるんだけど…」
「そこまでは言ってない。家に呼ぼうが呼ぶまいが、彼女が出来たのならきちんと話しておこうとは思ってた」
包丁を動かしながら桜子は言う。
どこの母親もこんなにストレートに言うのだろうか、と稜央はぼんやり考えた。
萌花の兄貴も、親からこんな風に言われたのかな、とか。
“そういえば萌花の兄貴って、どんな奴だったんだろう…”
自殺した、という話以降、萌花の口から兄の話が出ることはなかった。
彼女がその話をした時の自分の態度がいけなかったのかもしれない、と稜央は反省した。
* * *
早速稜央は萌花を家に呼んだ。
母はパートで、妹も保育園だ。
「お邪魔します…」
萌花はぎこちなく足を踏み入れる。玄関脇にあるドアが稜央の部屋で、そちらに直ぐ通された。
普段は寝るスペースだけ空いていて、あとは楽譜や本や床に散らばり、それに埋もれているような暮らしだったが、この日ばかりはさすがに片した。
「部屋、結構きれいになってるね」
「めちゃくちゃ片付けた」
稜央が照れ臭そうに言うと萌花はプッと吹き出した。
「ピアノ。これでいつも練習しているのね」
萌花は窓際にある電子ピアノに近寄った。
「うん。団地だから音出せないから、普段はヘッドフォンを付けて弾いてるんだけど、今日は音を小さくして少しだけ」
そう言ってピアノの前に座った。萌花も床に正座した。
「何かリクエストある?」
「ん…そしたら、ショパンのポロネーズがいいな」
「ポロネーズ…『英雄』ね」
稜央は少しは整理された譜面の山から1つを引っ張り出した。
指を鍵盤の上に置いて目を閉じ、鼻から小さく息を吸ってイントロを弾き始める。
萌花は中学の頃から軽やかながらも雄大なこの曲が大好きだった。
20歳という若さで祖国ポーランドを離れたショパンが、どれだけ祖国を愛しく思っていたかが伝わった。
そんな曲を今稜央が弾いている。
楽譜を置いたものの、ほとんど目を閉じて弾いている。暗譜でもしているのかと思う。
出逢った最初の頃、稜央からこんなに陽のパワーを感じることはなかった。
今、こうして『英雄ポロネーズ』を活き活きと弾く稜央はまるで別人のようだた。
曲が終わると引き続いて次の曲に入った。同じくショパンの『スケルツォ第2番』だった。
こちらは完全に暗譜のようだった。
この曲も冒頭…第一主題が印象的な曲で、非常に優雅で華麗な曲だ。
こちらの曲の方が稜央のイメージに合っている気がした。
弾き終えた稜央はゆっくりと目を開き、萌花を見ると照れたように目を逸らした。
「稜央くん本当にすごい…聴いてて心が洗われる」
「よせよ、言い過ぎだろ」
萌花はこんな時、自分の貧困なボキャブラリーが心の底から悔しく思った。
稜央は照れながらも萌花と視線を交わす。
右手を伸ばし、萌花の頬に触れる。
萌花の心臓がひときわ大きく跳ねる。
やがて2人の唇が重なる。
舌を絡ませ、稜央の右手は萌花の頬を滑り、首筋を撫でた。
シャツの下から手を滑り込ませ、胸を揉みしだいていく。
「稜央くん…お家の人帰ってきたら…」
「大丈夫」
2人は床に倒れ込み、お互いの身体の隙間がもどかしいほど密着させた。
桜子に言われた通り稜央はきちんとゴムを着け、萌花の中に深く沈めていった。
場所が場所だと萌花は必死に声を我慢し、それがなおさら稜央の欲情を煽動した。
「萌花…どうしてそんなにかわいいんだよ?」
そんなことを言われた萌花もまた陶酔してしまう。
嬉しくて嬉しくて、全身で稜央のことをきつく抱きしめる。
すぐに果ててしまったが、それでもまだ足りない稜央は身体を起こすと壁に背をあてて座り、萌花を上に跨がらせた。
「ゆっくり、腰を下ろしてきて…」
稜央の先端があてがわれると、萌花は言われるがままに腰をゆっくりと沈めた。
稜央は思わず声を漏らす。
「うわ…やばい…なんか包まれてる感がすごい…」
萌花は萌花で、普通よりも深い稜央の感触に悲鳴を上げそうだった。
稜央は両手で萌花の腰を動かしながら、うわ言のように呟いた。
「萌花…お前はもう俺のものだ…誰にも渡さない…」
「稜央くん…私…稜央くんのもの…」
「俺も萌花のものだよ…ずっと…ずっと一緒にいような…」
やがて稜央は萌花の奥深くで果てた。
* * *
制服を着たままだったから、汗で張り付くのが気になったけれど、それでも2人はしばらく余韻に浸りながら抱き締めあって過ごした。
「萌花、いっこ訊いてもいい?」
「…なに?」
「萌花の兄貴って…どんな人だったの? 嫌だったら答えなくていい」
「お兄ちゃん…」
萌花は途端に涙が溢れそうになった。悲しみというより、稜央の声の温かさに。
稜央はそんな萌花の頭をそっと撫でた。
「思い出してつらくなった? ごめんな」
「ううん、そうじゃない。なんかあったかいような、優しいような気持ちになって…」
稜央が萌花の涙を拭うと、萌花は濡れた大きな瞳で稜央を見つめた。
なんて美しいのだ、と稜央は改めて感動する。
「お兄ちゃん…物静かで勉強できる人だった。ずっと大人のお兄ちゃんって感じだったから、一緒に遊ぶことはなかったけど、すっごく優しかった」
「そっか…。それなのにどうして…」
「自殺した理由は両親も濁してて、お父さんは事故だって言った。でも進路のことでお父さんたちと言い合いしているのを一度だけ聞いたことがあって、それかなって思ったけど、遺書もなくて本当の所はよくわからないの」
「…」
稜央は黙って萌花をきつく抱きしめた。
けれど萌花は言った。
「訊いてくれてありがとう」
今度は稜央の方が泣きたい気持ちになった。
あの頃…。11歳、小学校5年生だった俺たち。
この街のあっちとこっちで、兄が自殺したのを発見し、継父に殴る蹴る好き勝手やられていた、俺たち。
出会って良かったと稜央は思った。
いや、出会うべくして出会ったんだ。
俺たちは互いの傷を埋め合うために出会ったんだ、と。
初めの頃は強く萌花を拒否した分、これからは誰よりも何よりも大切にしていこうと誓った。
#22へつづく
※ヘッダー画像はゆゆさん(Twitter:@hrmy801)の許可をいただき使用しています。
