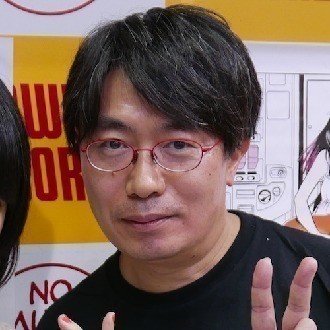DJI RSシリーズ向けリモコンのファームウェアをバージョンアップ。撮影・配信現場で役立つ機能も追加しました
以前、以下のnoteでも紹介しました、DJI RSシリーズ向けのPTZリモコン(有線LAN版)のファームウェアをアップデートしました。
正確には、日々現場で自分達で使う「ドッグフーディング」のなかで、徐々に改善を重ねてきていて、特に操作性についてはさまざまな現場で使ってみないと改善点が見えないところもあって、日々課題を認識しては改善するという繰り返しでした。特にDJI RS 4、RS 4 Proが出たことで、互換性の問題でご利用のみなさまにはご面倒をおかけしたこともあって、それらを含めた対応を繰り返してきた2024年でした。
ここにきて、ようやくファームウェアとしては完成した感もあり、以前からご案内はしておりますが、すでにお使いのみなさまには、あらためてファームウェアのアップレートのご案内をしていきたいと思います。バージョン履歴やお問い合わせ先については、以下をご覧ください。
とりあえず勝手に動きつづけるカメラほしくない?
日々のライブ配信や撮影現場で、予算的な都合やカメラマンが立てない場所に仕込むためなどのために、固定の無人カメラを置くことも多いのですが、人が振っているカメラと違って動きがないため、どうしても「温度差」が出てしまうという問題があります。
編集では、4Kなどで撮影したものからフルHDの領域を切り出すかたちでズームワークなどの動きをつけたりすることもあり、DaVinci Resolveには「ダイナミックズーム」という機能があるなど、そうしたニーズが大きいことがわかります。
ライブ配信の場合でも、僕らの現場ではATVのA-PRO-1という4Kスイッチャにある「ROI(Region of Interest)機能」を活用して、4K映像から一部を切り出すことで、ズームワークを実現したりもしています。そうした例については、以下のnoteも併せてご覧ください。なお、A-PRO-1については、とにかく不安定すぎなのを、改善する方法を発見したりもしたので、それについてはまた別のnoteで(とりあえず、標準のACアダプタとライブハウスの電源の相性が悪すぎて、特定のライブハウスではしょっちゅう固まることが確認できている……というのがヒントです)。
音楽モノのライブ配信などでも、ステージ面に超広角のレンズをつけたカメラを固定で置いているケースなどもありますが、ちゃんとカメラマンがジンバルやトラッキングレールでワークしているものには、まったく及びませんし、広い画角を維持したいポジションですから、ROI機能にも向いていません。
僕らも電動スライダーとかいろいろ試してみたものの、どうもダメだなというのが結論です(電動スライダーは物撮りなどでゆっくりしたエモい動きをつくるのが目的の製品が多く、速い動きはできないので、まぁ当たり前なんですが)。
フロアのお客さま越しのステージなどの画も、レールやジンバルでカメラマンがワークすべきなのですが、そうはできないケースもあります。
そんなときに、とりあえず動き続けるカメラがあると助かる。ということはないでしょうか?(僕らはいつもそんなのがあるといいね。と常々現場で話していました)
無人で特定の動きをしつづける「シーケンス制御」機能を追加
そんなわけで、追加したのが「シーケンス制御」の機能です。具体的には、設定した複数のプリセット位置を順に呼び出す操作をひたすらループしてくれるというものです。
DJI RSシリーズにも「トラック」という機能はあるのですが、これは設定した「ウェイポイント」を順次呼び出しながら「録画」して、最後までいったら停止するというものです。これだと、「動き続ける」という用途には残念ながら使えません(目的が違うので当たり前ですね)。
とりあえず、「シーケンス制御」でどんなことができるのかは、実例を見ていただくのが早いのですが、実際のカメラの動きと、それを利用したライブ映像です。
上記のライブ映像は、カメラマンは2人だけで、有人カメラはステージ面の上手と、フロア後方(下手寄り)の2台のみ。あとは、完全な固定カメラが3台でそれらは4Kから編集時にフルHDを切り出してズームワークをしています。
今回のシステムは、ステージ面(フロア最前)の中央にDJI RS 4に、SIGMA 14-24mm F2.8 DG DNをつけたα7cを載せて、広角端固定で、ひたすら左右に振っています(若干ロールさせながら)。画角は、リハーサル時に決めたプリセット位置を利用していて、本番中は一切調整していません。そのため「使えない」画角のタイミングはもちろんあるのですが、編集にせよ配信にせよ「使える」ときだけを使えばいいという割り切りです。
もちろん、有人のジンバルやレールが入ったほうがいいのですが、意外と善戦しているのではないでしょうか? 今回の会場では、柵の構造からカメラマンが左右にまったく動けないこともあって、このシステムの登板となりました。
また、以下の例では、RS 4に載せた1台とカメラマンによる1台の合計2台のみでの撮影で、4Kからの切り出しなどはせず、4Kの撮影映像のまま仕上げています。RS 4で勝手に動いているステージ面上手のカメラの映像をモニタでみながら、それを補完する形で下手フロア中ほどの有人のカメラを振るという形で実現しました。
このシステムは、長時間のフェスなどの配信のときにも有効で、以下の例のようにステージ面の中央のカメラ(このときは、α7sIIIにFE12-24 F4 Gでした)と、2階からフロア全体を狙うカメラの2台を仕込み、2階のカメラはフォーカスモータでズームリングを操作することでズームワークも行いました。
この例ではフェスであったため演者さんによって、ある程度速度や動作範囲などの調整が必要になります。もちろん、標準のリモコンで速度やシーケンスを随時調整することもできますが、後付けで機能を追加したのもあって、操作性は最善とはいえず、スイッチングしながらだと調整も限界があります。そんなわけで、Stream DeckとCompanionでさまざまなプリセットとシーケンスを、いろんな速度を簡単に呼び出せるようにしておくのがオススメではあります。
すでに、お持ちのお客様にはファームウェアアップデートの対応をいたしますし、ここ最近お買い求めのお客様にはすでに本機能が載った製品を納品しております(マニュアルが間に合っていなくて、ご説明もできていなかったのですが)。該当のファームウェアの製品がすでにお手許にあるようでしたら、最新のマニュアルを参照して試してみていただけると幸いです。
いいなと思ったら応援しよう!