
ADHDについて知ろう
この記事では、学童期のADHDのお子さんに焦点を当て、
ADHDの現れ方の特徴
ADHDの子が学校生活で困りがちなこと
サポート方法の一例
療育というツールを活用することの意義
について書いています。
学校での様子を事例にしていますが、考え方自体は社会で過ごす大人の方にも当てはまります。
ぜひご覧になってみてください!

自分をADHDと感じる大人たち
最近、大人の方がご自身を「自分はADHDだ」と定義づけて語る場面をよく見聞きするようになりました。
正式にADHDの診断を受けられたというわけではなく、ネット等で発信されるADHDの状態像を見て、自分にも当てはまると感じられた、ということが多いようです。
実際にその方がADHDと定義される状態であるかどうかは別として、こうした枠組みを受け取ることで自分自身を整理することができ、建設的に次の一歩を踏み出せるならば、とても意味のあることだと思います。
知ることが力になる
ご自身をADHDと感じるということは、少なからず生活の中で、なぜかいつもうまくいかない、いつもこういう時に困る、といった実感がおありだったということでしょう。
こうした場合、ADHDの人々の特徴や関わり方の事例を知ることが、自分自身と向き合う上でも、周囲に理解を求める上でも、大変役に立ちます。
そこで本記事では、ADHDについてざっとまとめてみます。
三輪堂には未就学~学童期のお子さんのご相談が多いので、学校でのお子さんの困りごとに焦点を当てて取り上げますが、場面を読み替えれば大人の方にも同じことが言えます。
この記事を読んで、
(自分にもこういうところがあるかも)
(うちの子もこういうタイプかも)
と、気になるところが見つかった方は、専門書等でより詳しい情報を見つけていただけるとよろしいかと思います!
では早速、次の項から参りましょう(^ ^)
ADHDの現れ方 3つの特徴
ADHDの症状の現れ方には大きく分けて3種類の特徴があります。
1.頭の中が多動
⇒ 不注意、忘れっぽい、天然ボケと言われる
2.身体が多動
⇒ 動きが活発、落ち着きがない、感情のコントロールも苦手
3.両方が混じっている
ー ー ー ー ー
ADHDとしてよく知られているのは2の「身体が動き回る」という様子のほうではないかと思いますが、1に挙げたような方もおられます。
衝動的に身体が動く子と、不注意でぼんやりしているように見える子とでは、教室内では真逆の状態像のように見えることもしばしばです。
どちらの状態も捉えてあげられると良いですね(^ ^)
ADHDの子が学校生活で困りやすい5つの場面
こうした状態像の子供たちには、学校生活の中で特に困りやすい場面があります。
代表的な5つの場面を挙げてみましょう。
ー ー ー ー ー
1.じっとしていることが苦手
「動かないでいる」ことに神経を使うため、じっとしていることでエネルギーを消耗したり、苦痛を感じたりします。
教室内では、席を立って立ち歩いたり、教室を出て行ったりするかもしれません。
2.気が逸れやすい
受け身の活動、一斉指示を受ける活動、自分にとって興味のない活動などで集中力が続きません。
退屈な(と本人が感じる)授業中には、関係のないことをしたり、周囲にちょっかいを出したりして、先生の注意を受けやすくなるかもしれません。
3.目先の利益を優先しがち
中長期的な損益を考えることが苦手で、後先のことを考えず、今この瞬間の楽しさ・喜びを追求する力が強いです。
「いま宿題を頑張れば後でゲームができる、だから先に宿題を片付ける」といった発想が苦痛だったり、授業中に何かを思いついたら先生のお話中でもすぐに発言したり、一呼吸置いて待てなかったりするかもしれません。
4.忘れ物が多い
物や時間をよく忘れます。
授業の持ち物、プリントの提出、友達との約束などを忘れて、先生に注意されたり、お友達とトラブルになったり、だらしない・嘘つきといった不当な評価につながったりするかもしれません。
5.整理整頓が苦手
ものを整える・片付けることが苦手です。
隅々まで丁寧に掃く・拭くといった作業も雑になりがちです。
机やカバンにプリントを押し込んでしわくちゃになったり、筆箱の中がめちゃくちゃだったり、落とし物・失くし物が多かったりするかもしれません。
本人も周囲の大人も困っている
こうした状態のお子さんは、学級に一人や二人はいても珍しくありません。
彼ら自身が困りを実感している場合はもちろんのこと、困っている自覚がなくても、話を聞くと「先生や親に怒られないで済む方法があるなら、そのほうがいい」と思っていたりするものです。
また、親御さんや周囲のお友達が、彼らの無軌道さ(と周囲には見える)に困ってしまっていることもしばしばあります。
ご本人も周囲の人々も、お互いにスムーズに生活できるよう、サポートし合っていきたいものですね。
現実的に状況が整うサポートを
さて、それでは、どのようにサポートしていけば良いのかということですが、、、
多くの方が想像されている通り、感情的に叱ったり、「ちゃんとしなさい」と漠然と注意したりするだけでは、こうした状態は改善されません。
お互いに理解し合い、現実的に状況が整っていくようなサポートを工夫したいものです。
前回の学校生活の事例をもとに、サポートの一例を挙げてみます。
ー ー ー ー ー
1.じっとしていることが苦手な子には
我慢させるのではなく、発散する時間を取ることが大切です。
休憩時間中には思い切り身体を動かしましょう。
授業中に我慢できない時は、無理におとなしくさせるのではなく、リフレッシュスペースに行って落ち着いてから帰ってくる、等の方法を検討しましょう。
また、イスの座面に不安定なクッションを置いたり、足裏でゴツゴツしたものを踏んだりして刺激を与えると、座り姿勢を維持しやすいことがあります。
授業中に離席して別のスペースに行く支援は大変効果的ですが、クラスの合意を形成しておくことが大切です。
クラスの合意がないと、「アイツだけ授業をさぼってずるい」といった不満が生まれてしまう可能性があります。
人にはそれぞれ特性があること、誰かにとっては何気なくできることも誰かにとっては苦痛になりえることを説明し、先生はクラス全員にとってより良い環境を模索し続けていること、不満や意見があれば隠さずまずは先生に伝えてほしいと伝えてあげましょう。
こうした働きかけを続けることで、自分も辛いことがあったら先生に相談できる、一緒に解決策を見つけてもらえる、(だからこそ他の子の辛さも理解しようと思える)、といった前向きな空気感をクラスに醸成することにもつながります。
2.気が逸れやすい子には
穏やかに声をかけて(叱責ではなく)注意を引き戻します。
指導者が話し方に強弱をつけたり、黒板のどこに注目すればいいのか視覚的なサインを強化したりできると理想的です。
▼ 先生のお話に合わせて黒板に注目する練習方法の一例はこちら ▼
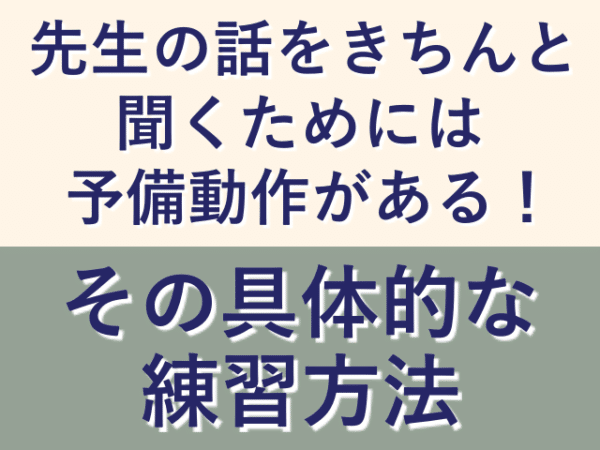
3.目先の利益を優先しがちな子には
なぜ今これをやるのか、将来どのように良いことがあるのか、物事の因果関係をわかりやすく整理して伝え続けましょう。
ただし、一度で納得できることは少ないので、大人は諦めずに根気よく働きかけることが大切です。
褒めるときはできるだけ即時に行うと、活動の成果を感じてもらいやすくなります。
4.忘れ物が多い子には
メモを取る、スマホのリマインダー機能を活用するといった習慣がつけられるよう練習しましょう。
忘れてしまったときには、
誰かに借りる
お道具箱に予備を置いておく
目につきやすいところに片づける
など、現実的な処世術も複数身に着けておきたいものです。
5.整理整頓が苦手な子には
整理しやすい道具や手立てを工夫しましょう。
人によって取り組みやすいと感じるやり方が違います。
持ち物の整理では、プリントはすべて一つのファイルに入れる、筆箱を大きなポーチに替えて何でも入れておく等、「とりあえず全部ここに入れる」系の発想だとうまくいく人が多いようです。
教室の掃除などは、手順を明確化した上で、ゲーム形式で速さや正確さを競うといった工夫も良いかもしれません。
ADHDの支援が効果を発揮しやすいタイプは
ここまで、ADHDのお子さん向けの支援の一例を書いてきました。
特に、
不真面目
乱暴
ガサツ
天然ボケ
ぼんやり
などと評価されがちなお子さんには、ADHD向けの支援が効果を発揮することが多いようです。
クラスの全員にメリットがあります
こうした工夫が効果的なのは、ADHDのお子さんに限ったことではなく、クラスのすべてのお子さんにも当てはまります。
ADHDのお子さん向けに設けたクールダウンスペースがクラスの子供たちの憩いの場になったり、ちょっとした(大きな問題になる前の)辛さを先生に伝えてくれるようになったり、といったように、クラス運営に良い影響を与えてくれる例もたくさんあります。
配慮された環境は誰にとっても過ごしやすい
特別な困りを実感していない人が、配慮された環境で過ごしてみると、その過ごしやすさに驚く、という場合もしばしばあります。
たとえば、
「しんどくなったら退室していい」
「課題をやりたくなったら戻っておいで」
というルールで教室を運営すると、きちんと席についていることに慣れた子供たちは最初は困惑しますが、やがてのびのびと行動し始め、表情がいきいきと輝き始めます。
じっと席に座りながら行う課題と、身体の欲するままに自由に行動しながら行う課題とでは、生み出されるものもおのずから変わってきます。
わたしたち大人も、退屈な会議の席で必死にひねり出すアイディアと、自由にリラックスしているときにふと脳裏に浮かぶアイディアとでは、雲泥の差があることを体験していないでしょうか。
全員の過ごしやすさを探るツールとして
療育の知恵は、どんなお子さんにも当てはまる関わり方の知恵です。
今回はたまたまADHDをテーマに取り上げましたが、ADHDそのものはあまり関係ありません。
(実際、療育的な関わりが本質的で上手な支援者の方ほど、診断名や症例には捉われなくなっていく傾向が強いように思います。)
大切なのは、その人にとってどうすれば過ごしやすいか/周囲にとってどうすれば過ごしやすいか、常にその間のポジショニングを探っていくことです。
そのためのツールとして、療育の知恵はたくさんのヒントを与えてくれます。
発達障害の有無に関わらず、大人の方にも子供たちにも、ぜひ活用していただけたらと思います。
特別な配慮が「特別」ではなくなるような環境を目指して、皆で一歩ずつ進んでいけると良いですね。
それでは、また。
いつもあなたに明るい風が吹きますように。
