
積読を増やしに増やした1年(前編)
共同運営マガジン「いりえで書く」、12月のお題の一つは「今年どんな1年だった」。最初は「今年買った本をすべて紹介するのはどうだろう?」と考えたのだがどう考えても無謀なので、韓国の原書のみ取り上げることにした(それでも40冊あって気絶しそうになった)。
買っただけで読めていない本のほうが多い。そもそも日本語の本だけで大量の積読があるのに、韓国にまで目を向けたらもう際限がない。自分はどうするつもりなのだろう。とりあえず年末年始も読書三昧だ。
ということで、20冊ずつ、前後編で載せていこうと思う。画像は韓国の大型書店チェーン「教保文庫」の通販サイト(購入したのもほとんどそのサイト)から引用。
『どうして書かずにいられましょう』

副題は「この不安な、騒がしい世の中で」。良い文章を書くためのハウツー本ではなく、「書く人生」についてのエッセイ集だ。著者は、教師、新聞記者を経て現在は編集者として働きながら、自身も習慣のように文章を書く。
目次は、1.距離が必要だから書く、2.苦痛に負けないように書く、3.悪い大人にならないように書く、4.小さく失敗するために書く、5.よりよいつながりを夢見て書く、6.孤独の楽しみを知るために書く、7.忘れないように書く。これだけでもなんだか勇気が出てくる言葉たち。
『大人の日記』

日本では日記本がブームとなって久しいが、韓国ではどうなのだろうと思って検索したら出てきた本。正確には著者が登壇する講演を先にYouTubeで見て、その言葉に感銘を受けたのだった。
私は、共感と労いは他人からもらうものだと思って生きてきました。でも日記を書く過程で、「誰かに言ってほしかった言葉を自分自身にかけられる人になろう」と思えるようになりました。なぜなら、私の人生の同伴者は結局のところ私自身だからです。
この本は、日記を書く人生がいかに豊かなものなのかを著者の経験を交えながら書いたエッセイ。ただ、ものすごくマメかつ(語弊があるかもしれないが)自己啓発的な内容も多く、ずぼらな自分には高尚すぎると感じる部分もあった。でも副題にある「私のための一番ちいさな誠実」という言葉もそうだし、丁寧に生活を続けていくことの大切さはとてもよく分かる。
『小説万歳』

個人的にとても好きな作家で、かつてYouTubeで見つけた講演内容をすべて翻訳したこともあるチョン・ヨンジュン作家のエッセイ(翻訳の内容は以下から読めます)。
チョン・ヨンジュン作家の小説も、小説について語る言葉も、その言葉づかいも、文章に滲むユーモアも好きだ。エッセイなんて贅沢すぎる、絶対に読みたいと思い、他のいくつかの著書と一緒にまとめ買いした。
「小説とはなんなのか、小説で大切なのは何か」という質問に対する答えを、作家は以下のように書く。
たった一人の側に立ってそれを説明し、その人の味方になってあげること。
動画を通して話を聞いていても、作品を読んでいても、やっぱりこういう思いから出発した作家なのかなと思う。小説に救われて、だから小説が大好きで、小説についてはいくらでも考えたい、そして語りたいというような気持ちが伝わってくる本だった。
ちなみに、チョン・ヨンジュン作家を知ったのは2年前、『宣陵散策』という以下の本を通して。メルカリで見つけて、韓国の原書が出回っているのは珍しいと思い購入。表題作がすばらしく、その瞬間に好きな作家になった。

そして今年、『宣陵散策』がなんと邦訳出版されていることを遅ればせながら知り、「間借り書房 いりえ」でも色々なお客さんに紹介したのだった。
『行くの』

同じ作家の短編集。もともと吃音のある子どもだった経験から、彼の作品には言葉をうまくあやつれなかったり、言葉自体を発しなかったり、他者との疎通が難しい人物がよく登場する。吃音持ちの主人公が出てくる「떠떠떠,떠」(トトト、ト)という作品を読みたくて購入したが、実はもったいなくてまだ読んでいない。
『僕が話してるじゃないか』

同じ作家の、こちらは長編小説。言語矯正院に通い、心理的要因からくる言語障害を克服しようとする14歳の少年を描く。上記同様、もったいなくてさわりしか読んでいない。
『ジャスト キディング』

こちらは読了したもの。短い小説が13編収録されている。「ジャスト キディング」は、日本語で言うと「なんちゃって」とか「ただの冗談だよ」というようなニュアンスらしい。
表題作はどんな楽しい話なのだろうと思ってわくわくしながら読んだら、期待を大きく裏切られる内容で(軽いネタバレだが人の悪意が浮き彫りになるような作品)驚いた。
これまでは何かを被ったり声を封じられたりしている側の人々を描くことが多かった印象なので、それと対になるような人物について、皮肉をきかせながら書いているのが新鮮だったのだ。
『イコ』

上で紹介した『宣陵散策』に収録されている「イコ」という作品が単独で冊子になったもの。韓国の若手イラストレーターが描きおろした挿絵とともに物語を楽しめる。文学作品をより多くの人に、気軽に手に取ってほしいとの意図で企画された「テイクアウト」シリーズの第18作目だという。
トゥレット症候群の男性が主人公の物語。周囲から「病気」「変態」「悪魔」とはやし立てられ、「サイコ」から派生して「イコイコ」というあだ名までつけられた学生時代。決してそのようには呼ばなかった同級生との、唯一心安らげた時間。しかしある日、その同級生は彼の前から姿を消す。10年以上経って、偶然再会した二人は——。
分かりやすいハッピーエンドに回収しないところにチョン・ヨンジュン作家らしさが感じられる。切ないながらも、ほのかな希望が感じられるラスト。
『俺たちは家族じゃないか』

同じ作家の短編集。これは途中まで読んだ。表題作は、かつて殺人を犯した実の父と、大人になって再会する(それも看護師と透析患者という立場で)物語。
透析患者が栄養をつけるために食べるゆで卵を欲張っていくつもほおばる父、それを憎らしく見つめる息子。ディテールが生々しいがゆえに、状況の可笑しさが際立つ。
『アンニョン、平壌』

「アンニョン」は韓国語のあいさつ。おはよう、こんにちは、こんばんは、すべてこの一言で済ませられる(ただし目上の人には失礼になる、少しくだけた言い方である)。
この本は、韓国の小説家たちによるアンソロジー。かつて一つだった朝鮮半島は1948年に朝鮮民主主義人民共和国と大韓民国に分断されてしまう。以降、双方は近くて遠い国として存在してきた。ときの情勢によって敵対視したり、友和を志したりしながら。
2018年には両国の首脳が肩を並べ、歴史的な会談を行った。その頃に発表されたのが本書だ。朝鮮民主主義人民共和国(韓国では“북한=北韓”と呼んでいる)という、まだぎこちなく見慣れない対象への思いを、6人の作家が小説に昇華させた。ここにチョン・ヨンジュン作家が参加していることを知り、迷う間もなく購入した。案の定、収録作のうち、まだ彼の短編しか読んでいない。
『小説創作論』
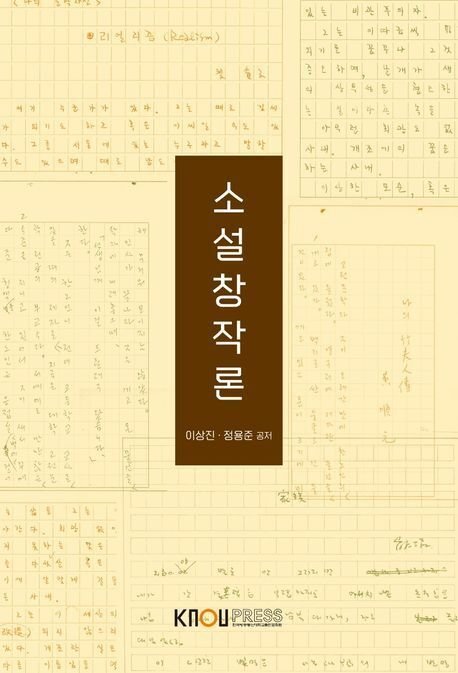
結局、チョン・ヨンジュン作家がらみの本を一気に8冊も買っていた。これは物語ではなく、その名の通り小説創作についてのテキストだ。イ・サンジンさんという大学教授との共著である。
これは付箋をばっちりつけて最後まで読んだ。小説を書くために知っておくべき基礎に触れながらも、やっぱりチョン・ヨンジュン作家の哲学というか、小説に向きあう姿勢が感じられてとても良かった。
『小説創作講義』

小説を書きたい。今年のはじめ、全5回の小説教室に通って5000字ちょいの作品をどうにかこうにか書き上げることができたが、引き続き書き続けたい。でも一人になると何も書き進められない…という悩みがあり、今年は小説についての本をたくさん買って読んだ。
日本語の本だけでは飽き足らず、韓国語のものも何冊か手に入れようと思って読みやすそうな本書を購入。内容が整理されており興味深く最後まで読んだ…が、肝心の作品執筆にはまだ至っていない。
『小説書いて座ってらあ』

小説家である著者はプロローグで、「앉아 있다=座っている」という表現が普段、悪口や軽蔑を込めて使われることが多いと書く(「ただただ座っているだけ」みたいなニュアンスなのだろうか)。
さらに辞典によると、「小説を書く」は「作り話をしたり嘘をつくこと」という意味を持った慣用句だと出てくるそう。そうなると、小説家が日常的にしている行為はとても愚かで恥ずかしいことのように聞こえてくる…。
しかし、小説はまず机に座らないと始まらない。この本は、「机の前で」「机で」「机の外で」と3つの段階に沿って小説の書き方をレクチャーする。まだ本格的には読み進めていない。
『毎日書くこと、なんでも書くこと』

副題は「まるで世界が私を好いているとでもいうかのように」。これは日記本だ。上のほうで『大人の日記』(日記を書くことについて綴っている本)を紹介したが、実際の日記本も読んでみたかったので購入。こちらもところどころ拾い読みだけして、まだ本格的には読み進めていない。
『企画会議 600号』

特集は「韓国出版マーケティングの現在と未来」。私は現在、週3で都内の出版社に通って業務委託で仕事をしているのだが、やはり課題は「いかに本(特に既刊)を売るか」だ。ざっと調べてみると韓国では「出版マーケティング」という言葉が日本よりも広く使われているような気がして、どんなノウハウが共有されているのか知りたく、勉強のために買った。
ニュースレター、SNS、読者との対面イベント、書評団、コンテンツマーケティング…。日本でも様々な出版社が類似のことをしていると思うが、韓国では各出版社のマーケ担当者たちが自らの知見を惜しまず寄稿し、組織を越えて積極的に共有している。業界全体を盛り上げていこうとする姿勢からはエネルギーが感じられた。
『もっといい文章を書きたいあなたのための筆写本』
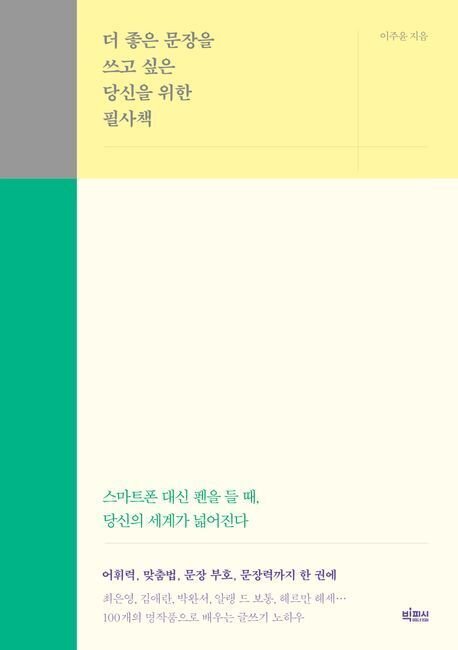
韓国国内外の様々な小説、エッセイ、詩から印象的な一部分を抜粋し、紹介する本。左側のページに文章が印刷されており、右側は罫線のみ引かれている。読者は多彩な名文を書き写すことで、豊かな言葉の数々をゆっくりと自分の中に染みこませる。
自分だけの関心範囲では読むことのできない文章に触れられる、良質なブックガイドにもなるなと思い購入した。
『とにかく、タングンマーケット』

당근마켓(タングンマーケット)とは、韓国の地域生活情報アプリ。日本でいうジモティーのようなもので、主には中古品の売買のために利用する人が多い。당근は「당신 근처의(あなたの近所の)」という言葉の略語。同時に、ニンジンも韓国語で당근という。だからタングンマーケットのロゴにはかわいいニンジンが描かれている。親しみやすい名前もあって、韓国では多くの人が利用しているようだ。
本書は、そんなコミュニティサイトのヘビーユーザーである詩人が、サービスを通して出会った人たちとの様々なエピソードを紹介するエッセイ集。副題は「私たちはそのように出会うこともできる」。軽くて小さめの本なのでお出かけの時などに読もうと思い、積読コーナーに控えている。
『書くことの最前線』
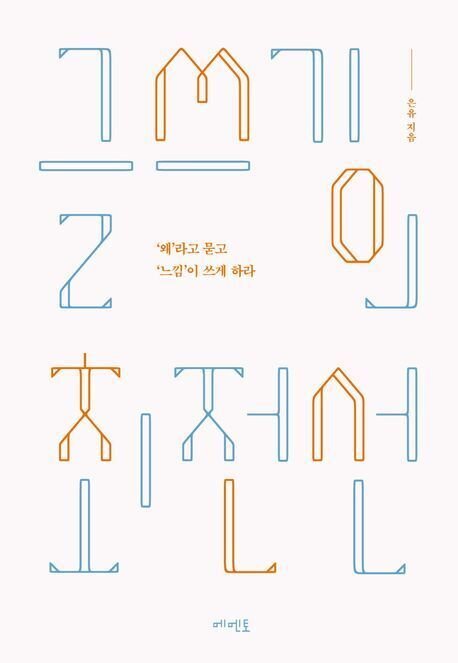
書くことや文章に関する本を数多く出している著者。この本は2015年に初版が発売され、2022年に改訂版が出たそう。その後も地道に版を重ねている。ということは古びない強さがあるということだと思う。
タイトルの「書くことの最前線」は、著者が実際に運営していた文章教室の名称だという。
途中まで読んだ印象はなんというか、硬派。言葉以前に、まずその後ろにある思考や意思を深く掘り下げたうえで、とてもストイックに書くことに取り組んでいる印象がある。
既存の文章講座が「記者になるため」または「小説家になるため」または「自叙伝を書くため」といった目的がはっきりしたものだったならば、<書くことの最前線>は目的にとらわれない授業だった。(中略)だからといって近ごろのイシューであるヒーリングや治癒といったものとも距離があった。社会構造的なマトリクスから自身を分離させたまま、性急な反省や和解、あるいは自分の正当性を確保するような文章を書いてしばしのあいだ心安らぎ、爽やかに日常へ復帰していくのではなく、自分自身について、その人生について、この世界について根源的な疑問を投げかけながら少しずつ気まずさを感じ、目覚めていくことが目標といえば目標だった。
世の中を変える必要のない者たちの言語では、この世界の矛盾と不幸を説明することは不可能なのだ。
この強度。なんかちょっと、出てくる言葉にいちいち打ちのめされて一気に読むことはできず、1/5くらいまで読んで一旦止めている。逆に言うと、まだ1/5でこんなに強いパンチがぼんぼん飛んでくるすごい本なのだ。
『勤勉な愛』

韓国でも、そして近年日本でも(韓国のカルチャーや文学が好きな層で)人気の新進気鋭の作家、イ・スラさんによるエッセイ。週に1回、子どもたちを集めて開いた文章教室での気づきや生徒とのやり取りを記録している。
さぼらずに書くことは自分への勤勉な愛である。そんな思いがプロローグで明かされる。そしてひいては自分だけでなく、周囲や、世界をも守っていくのだと著者は書く。ゆっくり読みたくて、プロローグのあとにはまだ手をつけていない。
『シムシムとヨルシム』
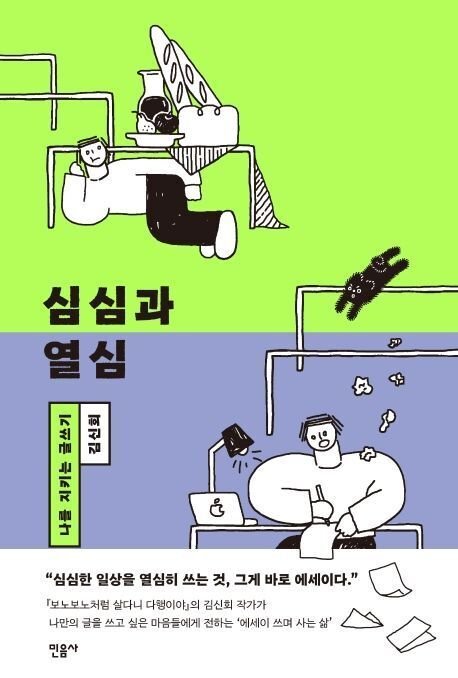
帯には、“심심한 일상을 열심히 쓰는 것, 그게 바로 에세이다.”=退屈な日常を懸命に書くこと、それがまさにエッセイだ、と書かれている。タイトルはそこから取られたのだろう、심심(シムシム)は「退屈」、열심(ヨルシム)は「懸命」という意味。
正直、たまたま表紙が目に入り、この帯文だけ読んですぐにカートに入れた。いつか絶対に読むが一旦積読コーナーに。
『セッ、セッ』

2024年「ソウル新聞」の新春文芸賞に選ばれた作家たちの小説と詩が収録されたアンソロジー。タイトルに入っている「셋」には二つの意味がある。一つは数字の3。もう一つはセッティングする、のセット。
作家・出版社・読者という“3”者の出会いを“セット”するというコンセプトがあるらしい。だから「셋, 셋」(3、セット)。こちらもやはり積読だ。
***
前半20冊は以上。ほとんどが積読だ。それなのに、油断するとまた教保文庫のサイトを開いて面白そうな本はないかとスクロールを繰り返している。
私の父は結構な買い物好きで、靴やスーツはもうたくさんあるのにどこかへ出かけるとすぐに新しいものに手を出そうとする。これまでは「無駄遣い甚だしい」と顔をしかめてきたが、対象が違うだけで自分も大概だな…と一瞬顔が曇った。
※後編もアップしました。
