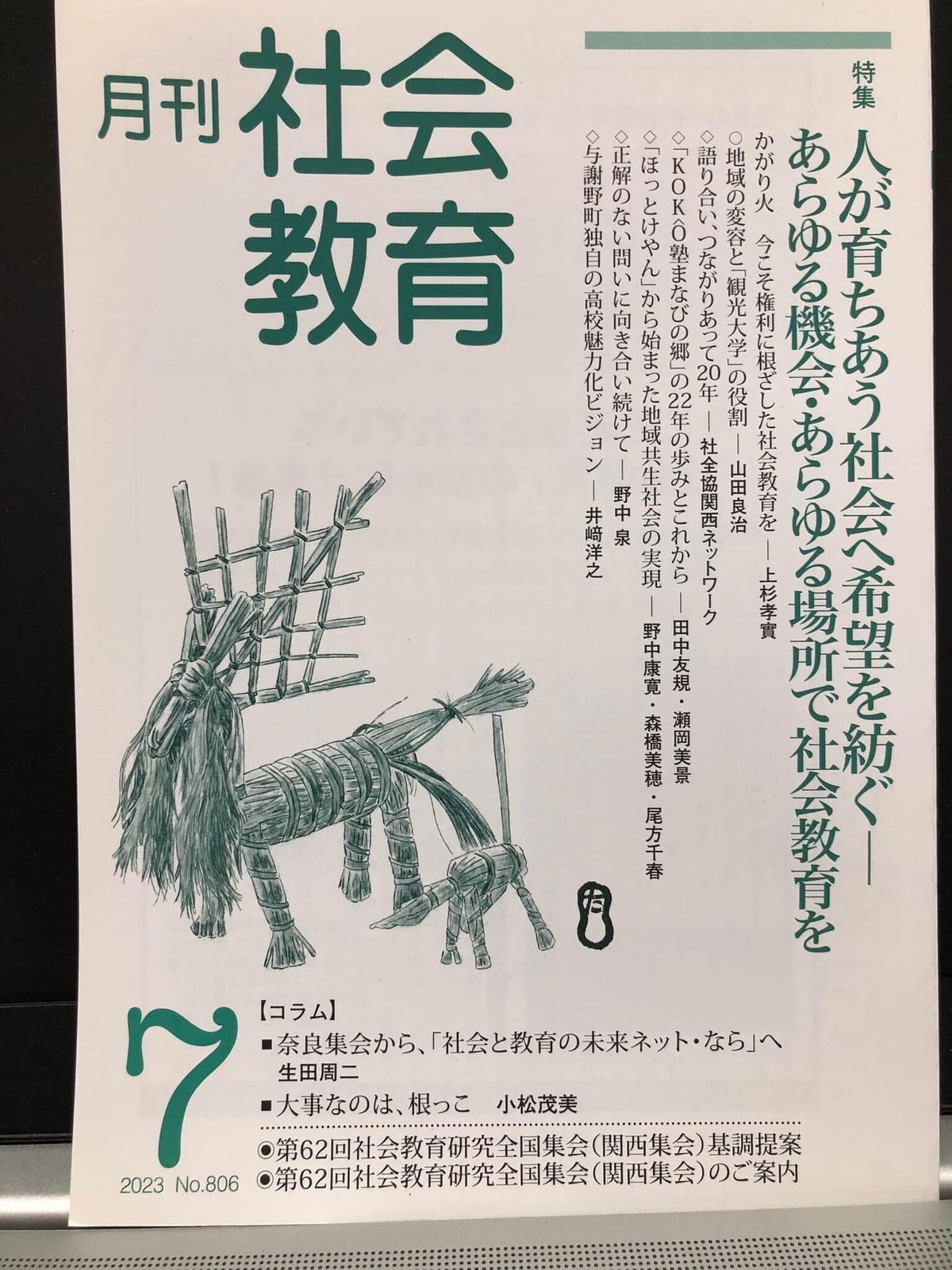自己開示①『大事なのは、根っこ。』
2023年夏に行われた『第62回社会教育全国集会(関西集会)』のお手伝いを少しだけさせて頂いた。
そのことをきっかけに、文章を投稿する機会を頂いた。
『私は、何を大事にしているのか?』を考え、文字にする機会を頂けたこと、感謝しなければと思う。
以下、2023年7月号『月刊社会教育』に投稿した内容です。
大事なのは、根っこ。
私は、1995年、子育て真っ只中の頃に大阪狭山市に移ってきました。そして、その頃は直営だった公民館で、家庭教育学級をはじめ、親子講座、自己表現セミナーなど、色々な講座に参加するようになりました。どの講座も初めてのことがいっぱいで、とにかく楽しかったです。そして、楽しいからまた別の講座に参加してみるということを繰り返していました。
そんな中の一つに『街のすぐれもの大学~健康運動科~』という全6回、カラダを動かすプログラムを楽しむ講座がありました。そして、この講座の最終回の時に、職員さんから「『専科』としてどれかやってみたい内容があれば、講座の企画に関わりませんか」というアナウンスがありました。私は6回のうちの一つ『山歩き』を選び、他にも同じように選んだ方々と一緒に企画、下見、チラシづくりなどをさせてもらい、当日も一緒に行くということを一年間させてもらいました。私にとって、この企てる側の経験は、とても楽しかった思い出であり、今、仕事として公民館に関わる私にとっては、ただ“講座をする”だけでない社会教育施設の役割として、大事にしている記憶です。因みに、私が選んだ『山歩き』は、サークル化しませんでしたが、同じタイミングで太極拳を選んだ方々が企画した講座からは、サークルが立ち上がり、今も活動が続いています。
指定管理者制度が導入され、ご縁から公民館に勤めることになった時、地域活動の諸先輩から『カルチャーセンター化したらあかんで』というお声がけをよく頂きました。
勤め始めた当初、カルチャーでない事業って何かを考えた時、社会課題や地域課題を事業にしなくてはと思って事業企画をしていました。でも中々参加してもらえない、“大切なこと”という想いだけでは、参加者を募るのは難しかったです。
今も、社会や地域の課題、時代の流れにアンテナを持っておく方が良いと思っていますが、事業の見え方は、カルチャーと見えるものがあってもよいのではと思うようになりました。
大事なのは、根っこ。何故この事業(講座)をするのか、対象となる人に、この事業(講座)を通してどうなってほしいかという目的であり、そのための材(プログラム)が、カルチャー的な要素があるものであっても良いのではということです。
私が楽しくて、色々と参加するようになったように、受講される人にとって、楽しい、実のある良い時間にすることが、“最初の一歩”をつくることになるのだと思います。
今、担当している事業の一つに、今年度で6回目の開催となる『くらまな大学~この街での暮らしを楽しむ学びの時間』という年間事業があります。この事業は、この街のことを知る、この街で行われている活動への参画のきっかけをつくる、生活への様々な提案を目的に実施しています。今年度の内容では、暮らしの提案として、スワッグづくり、薬膳などを取り入れつつ、「ふつうって?」を考える人権をテーマにした回や防災センター見学、介護制度を知る回など、知ってほしい内容を挟み込んでいます。例えば、『「ふつう」って?』という講座を単発で参加者募集しても一人も来て頂けないかもしれない、でも、この講座の一コマにすることで30人の方に大切なことを知って頂ける機会をつくることができています。
また、直営の頃から継続している中高生年代を対象にした青少年セミナー『表現倶楽部うどぃ』は、ダンス、役者、バンドといった表現活動を年間通して毎週土・月で行っています。表現活動自体が目的のように見られることもありますが、この事業の目的は、子ども達が斜めの関係の中で自分らしく、そして安心して居ることができる居場所づくりです。現在、この事業の卒業生が、コーディネーター、指導者として、自分達が感じたこの場所の意味を大事にしながら関わってくれています。見え方も大事な時はありますが、まずは根っこが大事だとこの事業からも思います。
そして、根っこの大事さを思いながら、社会教育に関わることで、人権、まちづくりに関心をもち、まちのファシリテーターでありたいと思うようになりました。人と人をつなぎ、対話の場をつくること、人が集う場が、より豊かになるように関わりたいと思っています。多様性が広がる中、みんな違ってみんなイイだけでは、一緒に動くことはできません。たまには、お互いの想いをぶつけ合い、選ぶことや新たな方法を見つけることが必要です。お互いの凸凹をいかしあい、フォローしあい、共により良い社会をつくる。そんな場にこれからも関わっていきたいと思っています。