
国家社会主義化した日本経済|保阪正康『日本の地下水脈』
資本主義の本質が誤解された日本社会では財界人を狙ったテロが頻発するようになる。/文・保阪正康(昭和史研究家)、構成:栗原俊雄(毎日新聞記者)

保阪氏
国家=軍事が先導する資本主義
江戸時代の日本の経済秩序は、それぞれの「藩」のなかで完結していた。各藩がそれぞれ独自の法体系を持ち、原則としてその藩内だけで通用する藩札を発行していた。
しかし欧米列強に倣う帝国主義国家を新しい国家像のモデルとした明治新政府は、藩を廃止して中央集権を推し進めた。列強に伍する軍事力と経済力を持つため、富国強兵政策の道を進むことになった。
欧米列強が到達した帝国主義は、日本とは異なる長い歴史の中でたどり着いたものだった。列強各国は、共和制や議院内閣制など政体の違いはあったが、いずれも成熟した市民社会があり、資本主義の下で企業が営利を求めて活動していた。企業は株式公開などによって市民から投資を募り、利益を還元するシステムが機能していた。その延長線上に、欧米型の帝国主義があった。
そうした歴史的土壌のない日本がいきなり欧米型の資本主義をめざすのは、そもそも無理があった。必然的に、日本は国家=軍事が先導するかたちの、欧米列強とは異質の資本主義の道を歩むことになった。
軍事が先導する日本型の資本主義は、国家社会主義に近い性質のものであったとも言える。そして時代が下っても、国家社会主義的な思想は日本の地下水脈として脈々と流れ、現在の日本経済にまで至っているとみることもできる。前回に引き続き、今回も近代日本の資本主義の成り立ちについて見てみたい。
安田善次郎の合理的禁欲
明治維新の後、日本には政治と密接な関係を保つことで急成長した企業が多かった。いわゆる「政商」である。国有財産を破格の安価で払い下げてもらうなど、政府から特権的な保護を受けて成長し、のちに財閥にまで発展した例もある。政商の系譜は、たとえば三菱の祖として知られる岩崎弥太郎などであった。
一方で、個人の才覚によって事業に成功し、財閥を築いた者もいた。たとえば、安田財閥の祖である安田善次郎がその典型と言える。日本の資本主義の基礎を築いた一人である善次郎はまさにたたき上げの財界人であり、一代で三井、三菱、住友と並ぶ四大財閥の安田財閥を築いた実業家であった。
天保9(1838)年、富山藩下級藩士の子として生まれた善次郎は、20歳で江戸に出て日本橋小舟町の両替店に奉公し、金融を学んだ。元治元(1864)年、鰹節小商兼銭両替店の安田屋を日本橋人形町で開業した。幕末で江戸の世情は混沌としており、同業者の休業や廃業が相次いでいたが、善次郎はこの商売をやめなかった。
明治維新後、善次郎は新政府が発行した太政官札を積極的に取り扱った。だが、太政官札は不換紙幣であり、政府が転覆するかそれに近い危機に陥ればただの紙くずになる。当時は不平士族らの反乱が相次ぐなど、政権は不安定であり、リスクの高い商売であった。さらに善次郎は新政府が次々と発行した公債を買い集めた。いずれも維新政府の将来に賭けたのだ。善次郎の読みは見事に当たり、巨万の富を築くに至った。明治9(1876)年、善次郎は第三国立銀行の創立に参加し、明治13年に安田銀行を開業。明治15年には、創立されたばかりの日本銀行の理事に就任している。晩年には東京帝国大学の安田講堂、日比谷公会堂への寄付を申し出るなど、善次郎は社会貢献にも力を入れた。
善次郎は起業を志した時、以下の3つの誓いを立てたという。
一、独立独行、決して他人を頼らぬこと。一生懸命働くこと。
二、嘘を言わぬこと。曲がったことをせぬこと。正直に世を渡ること。
三、生活費、小遣銭などはすべて収入の8割以内とし、2割は非常の時のために貯蓄すること。また住宅には身代の1割以上の金を決して使わぬこと。
この誓いからは、善次郎のストイックな勤労観、人生観が窺える。
ドイツの社会学者マックス・ヴェーバーは『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の中で、プロテスタントの厳格な倫理的生活態度(エートス)のなかに、資本主義の精神が胚胎していると指摘した。強欲と結びつけて語られがちな資本主義であるが、本来は合理的禁欲主義が資本形成に一定の役割を果たしたというのである。これは日本においても当てはまると考えられる。近代日本の実業家のなかには、江戸時代からの商人道徳を引き継いで、禁欲的な振る舞いを是とした者が数多くいた。そうした実業家は、善次郎のように大きな成功を収めている。
こうした足跡をたどってみると、善次郎は資本主義の本質を体現した日本型実業家の代表例であったと言える。

安田善次郎
大原孫三郎が目指した理想の企業
安田善次郎よりやや時代は下るが、同じ明治期に独自の企業経営をし、社会貢献にも力を入れたユニークな企業があった。岡山藩士の血筋をひく大原孝四郎らが立ち上げた倉敷紡績所(現・クラボウ)である。同社もいわゆる政商とは一線を画す存在であったが、経営理念に「藩」の地下水脈が見て取れるという点においても注目される。
2代目社長の大原孫三郎は東京専門学校(現・早稲田大学)を卒業して明治39(1906)年、父孝四郎の跡を継いだ。26歳の青年社長となった孫三郎は、事業の多角化を進め、倉敷毛織、倉敷絹織(現・クラレ)、中国合同銀行(現・中国銀行)、中国水力電気会社(現・中国電力)などを設立。その一方で、従業員とその家族たちの教育に惜しみなく財をつぎ込み、職場環境改善を進めた。
当時の紡績工場の主力は農村から出稼ぎに来ていた女工たちだったが、長時間労働や劣悪な作業環境で体を壊すことが多かった。「女工哀史」の世界である。そうした中、孫三郎は大正10(1921)年、倉敷労働科学研究所を設立した。心身の病気や衣食住のあり方などを研究させ、女工たちの待遇改善に役立てた。
さらに大正12年には、倉紡中央病院を開院した。このころ同社グループの従業員は1万人近くになっていたが、従業員の健康管理と診察を十分に行うため、最先端の設備を整えた総合病院を設けることにしたのである。同病院はのちに従業員だけでなく一般にも開放された。これらに先立つ大正8年には大原社会問題研究所(現・法政大学大原社会問題研究所)を設立し、社会科学研究の拠点を作った。昭和5(1930)年には日本最初の西洋美術館となる大原美術館も開館させている。
「資本も経済も産業も技術も、すべて人間のため」というのが孫三郎の信念であり、本業だけでなく医療や福祉・慈善、教育、文化など各方面に投資を行った。重役らは強く反対したが、孫三郎は「事業に冒険はつきもの、儂(わし)の眼には10年先が見える」と、一顧だにしなかった。
孫三郎の経営理念を見てみると、ひとつの企業グループが、従業員やその家族を養い、人材育成や文化発展までを担うことを理想としている。これは維新後の近代日本が取りえた国家像のうち、「連邦制国家」と親和性があった。企業グループという小国家の中で従業員の生活すべてが成り立つという理念は、江戸時代の「藩」の地下水脈にもつながるとも考えられる。
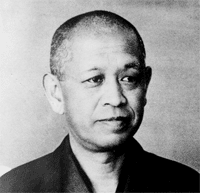
大原孫三郎
資本家がテロの対象になった日本
だが、資本主義の思想が近代の日本社会であまねく理解されたとは到底言えなかった。
大正10(1921)年9月、安田善次郎は神奈川県大磯の別荘で、国粋主義者の朝日平吾に刺殺された。その場で自殺した朝日の斬奸状には、こう書かれていた。
「奸富安田善次郎巨富ヲ作スト雖(いえど)モ富豪ノ責任ヲ果サズ。国家社会ヲ無視シ、貪欲卑吝ニシテ民衆ノ怨府タルヤ久シ、予其ノ頑迷ヲ愍(あわれ)ミ仏心慈言ヲ以テ訓フルト雖モ改悟セズ。由テ天誅ヲ加ヘ世ノ警メト為ス」
この斬奸状からは、資本家は民衆の利益と相反する存在であるという思いが透けて見える。
暗殺事件の当時、日本は第1次世界大戦後の不況の真っ只中だった。大戦では未曽有の好景気に沸いたが、それは主に海外市場の影響によるものだ。日本の資本主義は戦争によって発展してきた。日清戦争以来、軍需産業の占める比重が大きく、平和になると需要は当然減少する。また国内市場が狭く、海外市場への依存度が高かった。
戦後、主要国の生産力が回復すると、輸出は減少した。大正8年には輸入超過に転じ、大正10年には株式が大暴落した。外貨の稼ぎ頭だった綿糸と生糸の価格も暴落した。紡績・製糸業は操業短縮などに追い込まれ、多くの女工らが職を失った。社会が深刻な不況にあえぎ、財閥を見つめる目は厳しくなっていた。
財閥の栄華は庶民の苦しい生活の上に成り立っていたという側面——たとえば農村が抱えきれない労働力を都市の企業が安く働かせていたことなど——もあっただろう。これを「搾取」とみる者がいるのも自然である。
ただ、善次郎が目指していたのは、資本を投下して利益を社会に還元するという、近代資本主義の営みそのものであった。それがテロの対象になってしまったのである。安田善次郎暗殺事件は、昭和に入っての右翼による財界人へのテロと共通する。その後の日本の資本主義の方向性を示したものであるとも言える。
金融恐慌と財閥の支配強化
安田善次郎暗殺から2年後の大正12年、関東大震災が発生した。京浜地帯の産業は壊滅的な打撃を受け、銀行が持っていた手形の多くが焦げついた。いわゆる「震災手形」である。これによって、日本の資本主義に歪みが生じた。
日銀は4億3000万もの特別融資で急場をしのごうとしたが、昭和元年末の時点で2億円が未決済となった。このうちおよそ1億円の震災手形を抱えていたのが、国策銀行である台湾銀行(台銀)であった。台銀は台湾の金融の中心であり、中国や南洋諸島への経済的進出の拠点として設立されたが、総合商社・鈴木商店との関係が深かった。鈴木商店は明治前期に貿易商として創業したが、第1次大戦中は台銀の融資を受けて事業を拡大し、一時は三井や三菱に迫る勢いであった。
だが大正7年の米騒動で神戸の本店が焼き打ちに遭い、戦後恐慌と関東大震災でも深刻な打撃を受けて経営は悪化した。台銀からの巨額の融資は不良債権となり、台銀本体までが危機を迎えていた。
時の政権は憲政会の若槻礼次郎内閣である。内閣は震災手形の処理を進めるべく法案を議会に諮った。その過程で、震災手形を保有している銀行の経営内容が悪化していることが明らかになってゆく。昭和2年3月、不安を覚えた預金者が預金引出しのため銀行に殺到し、取付け騒ぎが発生。30行以上が休業した。
若槻内閣は台銀救済のため緊急勅令を公布しようとしたが、枢密院が反対し否決された。内閣は総辞職に追い込まれた。台銀に融資を打ち切られた鈴木商店は倒産したが、台銀は大幅な減資により何とか倒産を免れた。
憲政会の若槻内閣に代わって昭和2年4月20日、立憲政友会の田中義一を首相とする内閣が成立し、高橋是清が大蔵大臣に就任した。高橋は、思い切った手を打った。まず全国の銀行を2日間休業させた。さらに3週間のモラトリアム(支払猶予令)を発した。政府は日銀に対して20億円近い非常貸し付けを行わせた。国が全面的に救済に乗り出すことによって、何とか恐慌を鎮めたのである。
この恐慌で金融界の再編が進んだ。三井、三菱、住友、安田と第一の五大銀行が経営難の中小銀行を吸収し、寡占化が進んだ。中小銀行の消滅は、取引先の中小企業にも深刻な影響を及ぼした。当然、そこで働く者たちの失業につながる。都市の中小零細企業などは、農村の余剰労働力を吸収する役割も果たしていた。このため恐慌は農村にとっても大きな打撃となった。
一方、大銀行を持つ財閥は産業資本と密接に結びつき、財界における支配力を強めていった。また三井は立憲政友会、三菱は憲政会(のち、立憲民政党)との関係が深く、政治資金などによって政治的発言権も強めていく。こうした政治と財界の結びつきは「癒着」とみられ、右翼からも左翼からも批判されることになる。
「金解禁」という選択
昭和4年7月、対中国政策の行き詰まりなどから田中内閣が退陣し、民政党の浜口雄幸内閣が発足した。当時、世界経済は安定から上昇に向かっていたが、第1次大戦の戦勝国でありながら日本は不況にあえいでいた。財政再建と景気回復は、浜口内閣にとって大きな課題であった。
ここから先は

文藝春秋digital
月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…
