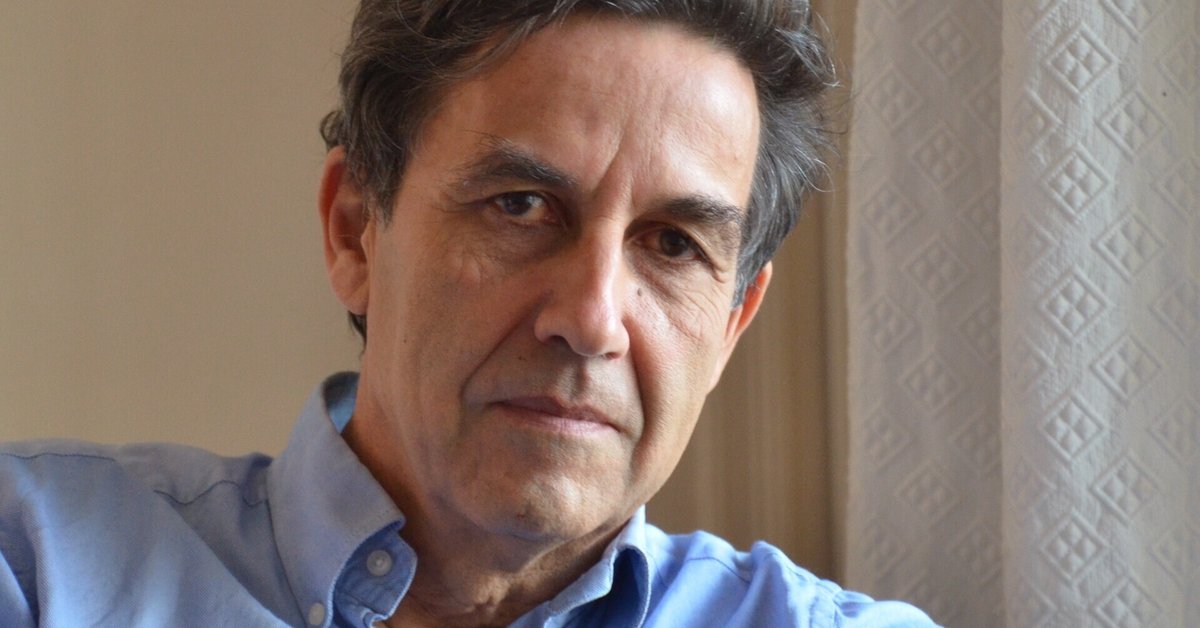
「老人支配国家」に明日はない E・トッド
日本は台湾や韓国よりマシだが、中国と同じくらいやばい。/文・E・トッド(歴史人口学者)

トッド氏
新型コロナが「老人支配」を明らかにした
今回の新型コロナウイルスのパンデミックは、歴史の流れに何か新しい変化を加えたわけではない、と私は見ています。しかし一種の“スキャナー”のように、世界各国の状況を浮き彫りにする役割を果たしました。
まず見過ごすべきでないのは「世代間の問題」です。新自由主義が推進してきた数十年にわたるグローバリズムで恩恵を受けてきたのは「先進国の高齢者(戦後のベビーブーマー世代)」で、産業の空洞化で最も犠牲を強いられたのは「先進国の若い世代」です。あくまで冗談めいた比喩ですが、コロナによる死者が高齢者に集中しているのは、あたかも「グローバル化のなかで優遇されてきた高齢者を裁くために、神がウイルスを送り込んだ」と見えなくもありません。
ただ同時に、新型コロナは「老人支配」が依然として続いていることも明らかにしました。「死者数」は膨大でも、その大部分は高齢者。現役世代の死者はわずかで、コロナ以前に想定されていた高齢者の寿命を縮めはしたものの、人口動態全体に与えるインパクトは大きくありません。要するに「老人」の「健康」を守るために「若者」と「現役世代」の「生活」に犠牲を強いたわけです。日本のように「高齢者の死亡率」を抑えた国でも、今後「出生数の減少」と「自粛生活が全世代の平均寿命にもたらす悪影響」の方が明らかになってくるでしょう。社会が存続する上で「高齢者の死亡率」よりも重要なのは「出生率」であることを忘れてはいけません。
フランスでは、現在、50歳以上ではなく、健康リスクがほとんどない12歳以下の子供を対象にしたワクチン接種の義務化が議論されています。社会全体で感染を抑えることは健康リスクのある高齢者には有益ですが、これなども「老人支配」の極みと言えます。
ベストセラーの最新刊
先進国に共通する「老人支配」
「老人支配」は先進国共通の現象です。2020年時点での各国の中位年齢(推定)は、日本48.9歳、ドイツ47.4歳、フランス41.9歳、米国38.6歳(総務省統計局「世界の統計2016」)です。こうした「高齢化」は社会にどんな影響を与えているのでしょうか。
私は『老人支配国家 日本の危機』(文春新書)において「英米のアングロサクソン社会が常に世界史を牽引してきた理由」についてこう述べました。
「『創造的破壊』という概念と深い関わりを持っています。『創造的破壊』とは、自分が作り出したものを自分自身で破壊し、新しいものを創ることです。英国人と米国人はそれに長けているのです。しかし、それはフランス人、ドイツ人、日本人には難しい。ではなぜ、英米は『創造的破壊』が得意なのか。その深い理由は、英米の伝統的家族形態、すなわち『絶対核家族』にあります。絶対核家族においては、子供は大人になれば、親と同居せずに家を出て行かなければならない。しかも、別の場所で独立して、親とは別のことで生計を立てていかなければならない。これらのことが、英米の人々に『創造的破壊』を常に促していると考えられます」
しかし現在、アングロサクソン社会でさえ、高齢化により「創造的破壊」にブレーキがかかっています。
従来の政治哲学は「中位年齢が30歳程度の社会」を前提に議論してきましたが、もし「中位年齢が50歳の社会」となれば、そもそもの前提が異なってきます。
例えばフランスは、個人主義的で「普通選挙」が大きな役割を果たしている国です。しかしその「普通選挙」が事実上「老人支配」の道具と化しています。有権者の高齢化で「何も生産しない老人」が力をもち、「生産をする若者」が疎外されているのです。「普通選挙」を信奉する私でも「70歳にもなる私のような高齢者からは投票権を剥奪すべきではないか」と思うほどです。「労働する人々」「子供をつくる人々」こそ社会の中心にいるべきで、政治権力も彼らに戻すべきなのです。
2022年4月に大統領選を控えるフランスは、マヒ状態に陥っています。右派候補者ばかりで、右派の支持率が合計で約8割を占めているのです。「無秩序」と「革命」の国であるフランスがこれほど右傾化しているのも「老人支配」の現れです。有権者が高齢化しているだけでなく、「老人的思考」が支配的になり、若者も「老人のように考える」ようになってしまったのです。かつての若者は退職後の生活やアパルトマンの購入について思い煩うことなどなかったのに、今はそうではありません。こうした若者の傾向は先進国共通の現象です。
儒教文化で強まる東アジアの「老人支配」
「絶対核家族(親の遺言で相続者を指名)」の米国や「平等主義核家族(平等に分割相続)」のフランスより「直系家族(長子相続)」の日本やドイツの方が「高齢化」が進んでいます。しかしまず指摘したいのは「直系家族社会だから老人支配から脱却できない」と考える必要はないことです。「直系家族」は権威主義的な社会ですが、その強みは、明治維新のように“上からの改革”が得意な点にあります。つまり「老人支配」の問題をエリートが意識さえすれば、方向転換できるチャンスはあるわけです。
ところが現実の日本は“自国の危機”に向き合えていないようです。「家族」を重視することで、勤勉で秩序ある日本社会の基礎が築かれてきたわけですが、子育てや介護のすべてを「家族」で賄うことなどできません。「家族」の過剰な重視が「家族」を殺す——「家族」にすべてを負担させようとすると、現在の「非婚化」や「少子化」が示しているように、かえって「家族」を消滅させてしまうのです。「家族」を救うためにも、公的扶助で「家族」の負担を軽減する必要があります。
日本だけではありません。韓国、台湾、中国といった東アジア諸国も同様の“危機”に直面しています。欧米諸国における「老人支配」が「普通選挙」を通じたものだとすれば、東アジア諸国では「儒教」の存在が「老人支配」の度合いをさらに強めています。
「儒教」が誕生した約2000年前の中国は「直系家族」(現在は「外婚制共同体家族」で「兄弟間の平等」という価値観が加わる)社会で、「直系家族の価値観」を正当化するイデオロギーが「儒教」です(中国は核家族→直系家族→外婚制共同体家族、日本と韓国は核家族→直系家族と変遷)。「親」と「老人」を敬う儒教社会では「成人した子供」が「親の世話」を担います。しかし「親の世話」の負担が過大になれば、「子供を産み育てる」エネルギーは削がれてしまいます。東アジア諸国では「一人も子供を産まない女性」が25~30%にも達し、出生率が異常に低く、日本と中国は1.3程度、韓国と台湾は1.0程度です。出生率は2.0に近い水準でなければ、社会は現状の人口規模を維持できません。
さらに今日「経済至上主義」が世界を席巻し、我々は眼前にある“危機”に知的に無防備な状態に置かれています。思想が現実に追いついていないのです。「老人支配」の下で「経済」ばかりが論じられていますが、「人口」こそ真の問題です。その点で最も思想的に後れをとっているのが、韓国と台湾。「経済的に成功した国」として持て囃されていますが、「人口学的な自殺」を遂げつつあります。いくら経済で成功を収めても、出生率が1.0程度では、社会自体が存続できません。

韓国の文大統領
米国は台湾を守らない/守れない
議論が喧しい「台湾をめぐる地政学」も、私には馬鹿げたものに見えます。台湾にとって真の問題は「人口」だからです。米中対立がどうなるにせよ、このままでは台湾は、50年後に存在できない。ですから、台湾をめぐって軍事的挑発を繰り返す米国の振る舞いは、むしろ“日本にとっての危機”の一つだと私は考えます。
これまで米国は「中国が台湾を攻撃した場合、どう対応するかは意図的に明示しない」という「あいまい戦略」を採用することで一定の均衡を保ってきました。ところがバイデン大統領は、米国の台湾関係法に明記されていない「台湾防衛義務」について繰り返し言及しています。「中国を牽制するために失言を確信犯的に繰り返している」と、発言の戦略的意味を強調する議論もありますが、私には言葉自体が空虚に聞こえます。
まず米国が多大な犠牲を払ってまで台湾を守ることはないでしょう。他国にそこまでした例はないからです。つまり「台湾を守らない」。それだけではありません。そもそも「台湾を守れない」のではないでしょうか。
1996年春、台湾に向けてミサイル発射演習や軍事演習を繰り返す中国に対し、クリントン政権が2つの空母打撃群を急派した時、中国には為す術がありませんでした。しかし現在、状況はまったく異なります。軍事テクノロジーの革新で米国の空母は時代遅れになっている可能性があり、元戦闘機設計者ピエール・スプレイなどが指摘しているように、戦闘機F35の実戦での性能も疑わしい。中国が膨大な数の対艦弾道ミサイルを保有していることを考慮すれば、米国が空母を派遣しても、台湾の裏側で待機せざるを得ない可能性が高いのです。そこで米国の空母が効力を発揮できないことが判明すれば、「米国の軍事力」に対する信頼は一挙に崩れるでしょう。しばしば言葉は現実とは逆のことを表しますが、「台湾を守る」という言葉も「台湾を守らない/守れない」という“現実”を示しているように思うのです。
ウイグル、チベット、香港に対する弾圧、デジタル技術を駆使した監視国家体制など、中国は多くの問題を抱えていますが、こうした政治体制は「外婚制共同体家族(兄弟間は平等で親子関係は権威主義的で女性の地位が低い)」という家族構造に起因しています。つまり、それなりの歴史的理由があり、中国がそのような社会であることを家族構造の専門家として私は理解できます。しかし個人的には、「自由」や「民主主義」という価値観を共有する「西洋社会」——広い意味では私はここに日本も含めます——の一員として、中国の政治体制に共感できません。ですから、トランプ政権時に米中対立が始まった当初、私は米国寄りの姿勢をとっていました。
しかし、2021年5月に公表された中国の人口統計を見て考えを改めました。1.7とか1.5程度と思っていた出生率が1.3だったのです。いつからこんなに低かったのか、今後、人口学的な検証が必要になりますが、いずれにしても、中国は「人口学的な自殺」を遂げつつあるのであって——しかも人口規模からして人口減少を移民で補うことができません——、これ一つをもってしても、中長期的に中国が世界の覇権を握るような脅威になることはない、と断言できます。

台湾の蔡総統
「民主主義の守護者」ではない米国
と同時に、米国に対しても私は悲観的な見方をするようになりました。米国はすでに「民主主義の守護者」でも「信頼できる同盟国」でもない、と。
ここから先は

文藝春秋digital
月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…

