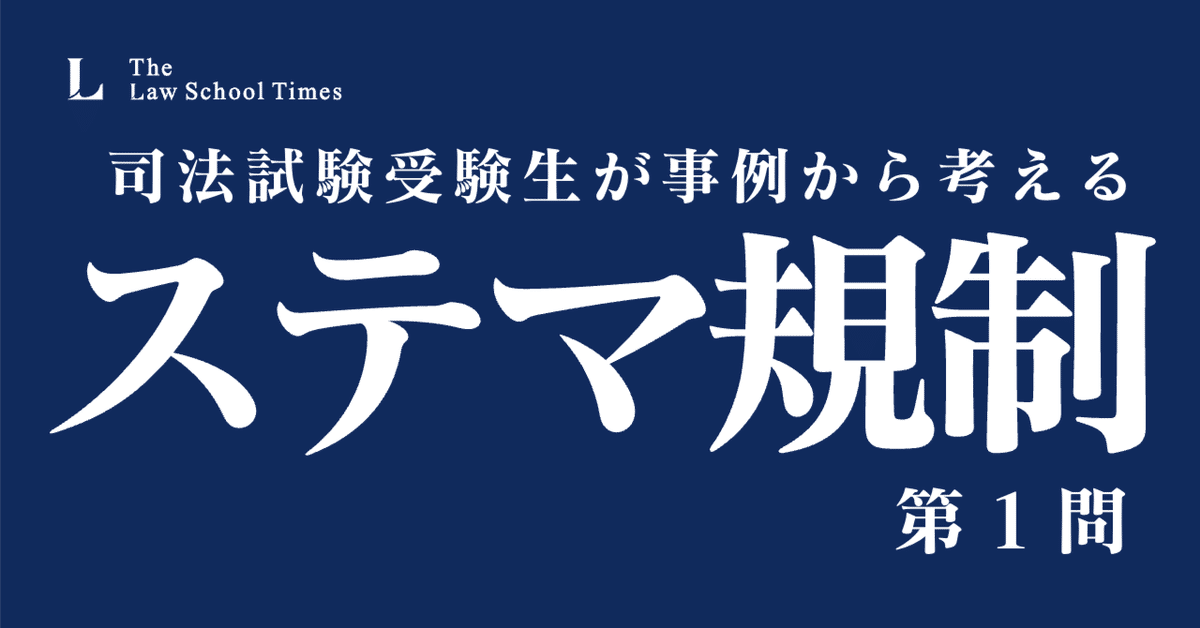
司法試験受験生が事例から考える、ステマ規制・第1問
ステルスマーケティング(以下、「ステマ」)とは、消費者に広告・宣伝とわからないように商品・サービスの利用を促す発信をすることをいう。
ステマ規制とは一般消費者が、商品を自主的かつ合理的に選択できるようにすることを目的とした、消費者庁が定める不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」)第5条第3号に基づく規制であり、2023年10月から施行されている。
本記事ではステマ規制について、令和6年司法試験受験生(令和5年予備試験合格者)が、事例を用いてその解釈と適用を試みる事例検討を行う。(ライター:サカモト/The Law School Times編集部)
自分のポストがステマになるかも?
先週、大手企業に対する措置命令があったことなどから、最近再びインフルエンサーの特定の投稿がステマに当たるかどうかが話題になっている。
ステマ規制は昨年から施行されたばかりで、なぜステマが許されないか、どのような表現がステマに当たるかを知らない人も多いだろう。
ステマは一般消費者の自由な選択を阻害する可能性が高い悪質なマーケティング手法であるために規制されている。
一方で、インフルエンサーの実に41%がステマを依頼された経験があるというデータもあり、非常に身近に存在しているものでもある。SNSが普及した現代においては誰もがこの悪質なマーケティング手法に加担してしまうことになりかねないのである。
※ステマ規制の対象は事業者であり、インフルエンサーは対象外

消費者庁は令和6年8月8日、RIZAP株式会社の「chocoZAP」と称する役務(以下「チョコザップ」)に対して、いわゆるステマ規制の措置命令(景品表示法7条1項)を行った。
そこで今回は、ステマ規制の趣旨と要件を改めて確認した上で、チョコザップ事例の規制該当性を検討することを通して、どのような表現がステマに当たってしまうのかを考える。
事例


・RIZAPは、チョコザップを一般消費者に提供するにあたり、上記のように、自社のウェブサイトにおいて、第三者のSNSの投稿を抜粋して表示した(以下「本件表示」)。
・RIZAPは、上記第三者に対し、対価を提供することを条件に、チョコザップについてSNSの投稿を依頼していた。
「ステマ規制」に関する法令の検討
ステマ規制の根拠法令
ステマを規制している法は、景品表示法5条3号である。
景品表示法
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一(略)
二(略)
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)
事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの
事業者が商品について表示を行っているのに、一般消費者がそれを事業者の表示であると判別することが困難である場合には、ステマとして景品表示法5条3号の規制対象となる。
例えば、化粧品メーカーが女優に対価を支払って自社商品の特徴を伝え、女優が自己のインスタグラムにおいて当該商品について、広告であることを表示していないでメーカーの意向に沿った内容の表示を行うことがその典型例となる。
規制の趣旨
消費者庁によれば、規制の趣旨は以下の通りである。
「一般消費者は、事業者の表示であると認識すれば、表示内容に、ある程度の誇張・誇大が含まれることはあり得ると考え、商品選択の上でそのことを考慮に入れる一方、実際には事業者の表示であるにもかかわらず、第三者の表示であると誤認する場合、その表示内容にある程度の誇張・誇大が含まれることはあり得ると考えないことになり、この点において、一般消費者の商品選択における自主的かつ合理的な選択が阻害されるおそれがある。
そのため、告示は、一般消費者に事業者の表示ではないと誤認される、又は誤認されるおそれがある表示を、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として規制するものである。事業者は、自らが供給する商品又は役務についての表示を行うに当たっては、一般消費者に、事業者の表示であるにもかかわらず、第三者による表示であるかのような誤認を与えないようにする必要がある。」
本規制の趣旨は、消費者は事業者の表示であれば誇張があることはあり得ると考えるが、そうでない場合には誇張があるとは考えないことから、自主的かつ合理的な選択が阻害されるおそれがあり、それを規制することにある。
例えば、Xでインフルエンサーが対価を受けて、事業者の依頼通りに当該商品についてのポストを行えば、それを見たフォロワーは、ポストがインフルエンサー自身の表示であると誤認するおそれがある。
インフルエンサー自身の表示であればそこに誇張が含まれるとは考えないことが通常であるところ、実際には事業者の誇張や誇大が含まれる表示(ステマ)である場合、それに気付かない一般消費者の自主的かつ合理的な選択が阻害されることになる。
こうした状態を規制するのがステマ規制の趣旨である。
要件
上記法令の記載からすれば、ステマ規制が適用される要件は以下である。
➀「事業者が…行う表示」であること
➁一般消費者が事業者の表示であることを「判別することが困難である」こと
要件➀「事業者が…行う表示」であること
告示の対象となるのは、外形上第三者の表示のように見えるものが事業者の表示に該当することが前提となる。…事業者の表示に該当するとされるのは、事業者が表示内容の決定に関与したと認められる、つまり、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められない場合である。
(ボールドは筆者)
そして、判断基準は以下の通りである。
◦事業者と第三者の間の表示内容に関する情報のやり取りの有無
◦表示内容に関する依頼・指示の有無
◦事業者から第三者への対価の提供の有無
◦事業者と第三者の関係性(表示内容の決定に関与できる程度の関係があるのか)
これに当たる典型例は以下の通りである。
(ア) 事業者が第三者に対して当該第三者のSNS上や口コミサイト上等に自らの商品又は役務に係る表示をさせる場合。
(イ) ECサイトに出店する事業者が、いわゆるブローカーや自らの商品の購入者に依頼して、購入した商品について、当該ECサイトのレビューを通じて表示させる場合。
(ウ) 事業者がアフィリエイトプログラムを用いた表示を行う際に、アフィリエイターに委託して、自らの商品又は役務について表示させる場合。
また、事業者が第三者に対して表示を明示的に依頼していない場合にも以下の場合には➀の要件に該当する。
㋐事業者と第三者との間に事業者が第三者の表示内容を決定できる程度の関係性があり、客観的な状況に基づき、㋑第三者の表示内容について、事業者と第三者との間に第三者の自主的な意思による表示内容とは認められない関係性がある場合
そして、㋑の判断基準については、以下のようにされている。
事業者と第三者との間の具体的なやり取りの態様や内容(例えば、メール、口頭、送付状等の内容)、事業者が第三者の表示に対して提供する対価の内容、その主な提供理由(例えば、宣伝する目的であるかどうか。)、事業者と第三者の関係性の状況(例えば、過去に事業者が第三者の表示に対して対価を提供していた関係性がある場合に、その関係性がどの程度続いていたのか、今後、第三者の表示に対して対価を提供する関係性がどの程度続くのか。)等の実態も踏まえて総合的に考慮し判断する。
要件➁一般消費者が事業者の表示であることを「判別することが困難である」こと
これについては、一般消費者の観点から、表示の内容等を実質的に判断することになろう。
事例の検討
1.要件➀「事業者が…行う表示」であること
(1)上記の通り、事業者が第三者の表示内容に関与したと認められること、すなわち客観的に第三者の自主的な意思による表示内容と認められることが必要である。
(2)本件において、RIZAPが㋐対価を提供することを条件に、第三者にチョコザップについてSNSの投稿を依頼し、その投稿をさせたこと、㋑当該SNS投稿を個人の感想であるとして、自社のウェブページに掲載したことの二つの行為が問題になると思われる。
ア ㋐SNS投稿をさせたこと
本件のSNS投稿は、「24時間365日利用でき」ること、および「月額2,980円」であることをその内容として含んでいる。そして、以下のように同じウェブページ上に掲載された他の者のツイートにおいても同様の内容が含まれている。また、かかる内容はチョコザップの売りとして直後にウェブページ上に掲載されているものであり、RIZAPが投稿者に対してその内容を指示した上でその投稿をさせたことが一定程度推認される。
また、消費者庁の発表によると、投稿に当たって対価が供与されていたことは明らかであるが、その対価がどのような内容であるかは明らかにされていない。もっとも、対価が供与されたこと自体は、SNS投稿について第三者の表示内容の自主性を否定する要素となるものであり、対価が大きければ大きいほど、表現内容の自主性は否定されやすいと考えられる。
なお、消費者庁は、上記㋐と㋑の行為を一体として判断して、RIZAPが第三者の表現内容に関与したものとして、本件表示を事業者たるRIZAPの表示であると判断している(消費者庁:「RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」参照)が、上記からすれば、㋑がなくとも第三者に投稿を依頼し、投稿をさせたこと自体がステマ規制の対象となりうる。
イ ㋑SNS投稿をウェブページに掲載したこと
本件表示は形式的には第三者の投稿という体裁をとっているが、実質的には、RIZAPがその表示内容に関与していたのであり、その投稿を自ら自社のウェブページに投稿している。したがって、本件表示は事業者の表示であり、㋑は事業者の表示にあたる。
2.要件➁一般消費者が事業者の表示であることを「判別することが困難である」こと
まず、本件表示内の第三者のポスト自体には、PRであることや事業者の表示であることを表す文言は一切見られず、一般消費者がこれを事業者の表示であると判断することは困難である。
そして、本件表示には「@…」という記載がある。これは一般消費者から見れば、本件表示は個人のSNSアカウントからそのまま引用してきており、事業者がその表示内容に関与はしていない、と誤認するおそれがある表示である。
また、「※個人の感想です。」との表示も、一般消費者に本件表示が事業者の表示ではないと誤信させるものである。
したがって、㋐㋑はともに➁の要件を充足する。
3.以上より、RIZAPの上記行為はステルスマーケティングとして、景品表示法5条3号に該当する。
罰則等
消費者庁の調査の結果、違反行為が認められた場合、事業者に対して、措置命令が行われる(景品表示法7条各号)。措置命令については、その内容が公表される。
措置命令の内容(例)
・違反した表示の差止め
・違反したことを一般消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講ずること
・その違反行為を将来繰り返さないこと
ステマ規制に当たらない表示の方法
広告である旨が一般消費者から見て分かりやすい表示になっているもの、一般消費者にとって事業者の表示であることが社会通念上明らかなものは、告示の規制対象外である。
<具体例>
・「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」といったSNS等で広く一般に利用されている文言による表示を行う場合
・「A社から提供を受けて投稿している。」等のように文章による表示を行う場合
・テレビCMのように広告と番組が切り離されている表示を行う場合
・事業者の協力を得て制作される番組や映画等において、スポンサー等の名称等をエンドロール等を通じて表示を行う場合
・新聞紙の広告欄のように「広告」等と記載されている表示を行う場合
・商品又は役務の紹介自体が目的である雑誌やその他の出版物における表示を行う場合
・事業者自身のウェブサイトにおける表示(特定の商品又は役務を期間限定で特集するページも含む。)を行う場合
・事業者自身のSNSアカウントを通じて表示を行う場合
・社会的な立場・職業等(例えば、観光大使等)から、事業者の依頼を受けて広告宣伝していることが社会通念上明らかな者を通じて、事業者が表示を行う場合
したがって、ある事業者から商品の宣伝を依頼された場合においても、その依頼をされた旨や「広告」「PR」等の文言を自身のポストの内容として表示すれば、ステマには当たらない。

景品表示法違反に関する情報提供窓口
消費者庁表示対策課(情報管理担当)
TEL.03-3507-8800㈹
〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
オンライン又は郵送にて受け付けております。詳しくは受付窓口ページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/
次回予告
The Law School Times編集部は、今話題になっている司法試験予備試験用教材のステマ問題についても検討の上、消費者庁への問い合わせを行った。
次回は、これがステマに当たるか、The Law School Times編集部と消費者庁の見解を示す。
The Law School Timesは司法試験受験生・合格者が運営するメディアです。「法律家を目指す、すべての人のためのメディア」を目指して、2023年10月にβ版サイトを公開しました。サイトでは、司法試験・予備試験やロースクール、法律家のキャリアに関する記事を掲載しています!noteでは、編集部員が思ったこと、経験したことを発信していく予定です。
