
新聞滅亡へのプロセス(10)~8月15日の紙面を読み解く~2
10回目のブログとなる。引き続き、8月15日の在京紙面について書く。同日、図書館に行った。新聞閲覧台を使い5紙をメモしながら読むのはつらい。珈琲店に移動し、続きの作業をした。
通訳案内士の仕事に就く前に、30年ほど働いていた職場では(海外駐在中は除き)自席から10メートルの範囲に、日刊一般新聞5紙プラス日経が置いてあり、すぐに紙面や記事を比べ読みできる環境にあった。(注1)
毎年元旦には、自宅から最寄り駅のキオスクまで出かけて、普段とは異なる「分厚い」新聞6紙を買い込み、自宅で読むのが恒例だった。正月は、各紙「スクープ」を競うのが新聞社の「伝統」となっていた。スクープがなければ、新年の大型企画記事となる。正月にどんな新しい「事実」があぶり出されるのか。読むのが楽しみだった。
元旦の新聞は、セクションと呼ばれる「別刷り」紙面のいくつかで構成されるので、1年中で最もページ数が多い。新聞によってバラつきはあるが、100ページの新聞も発行されていた。以前は40ページあった通常の朝刊のページ数は、いま28から30ページ程度だろうか。
新聞の経済状況、新聞用紙値上がり、人手不足による販売網への負荷などの諸理由で、新聞のページ数は減少している。読者の高齢化に伴い、文字を段々と大きくしてきたので、記事の文字数と分量も減少してきた。こうした状況下、新聞購読価格を値上げすれば、購読数が減るのは当然といえる。(注2)
戦後79年、「終戦の日」の紙面展開
「終戦の日」の前後に「戦争」に関する企画連載記事の掲載が恒例となっている。「8月のジャーナリズム」と多くのメディアは呼ぶ。筆者は「8月15日のジャーナリズム」に的を絞ることにした。
前回、8月15日各紙1面の「岸田退陣」記事の「画一性」を指摘した。「終戦の日」記事にも、その傾向がいっそう顕著に見られる。
読売、毎日、産経、朝日、東京の各紙が8月15日「終戦」の日を取り上げた「見出し」と記事のリード書き出しは以下のとおり。
きょう終戦の日 終戦から79年となる15日、・・・(読売・毎日)
きょう戦没者追悼式 終戦から79年となる15日、・・・・(産経)
終戦の日に 79回目の終戦の日を迎えた。 (産経)
きょう終戦の日 きょう15日は戦後79年の終戦の日です。(東京)
今日79回目終戦の日 きょう15日は戦後79年の終戦の日です。(朝日)
見出しと書き出しがまったく同一の新聞もある。もちろん、リード冒頭後の記事内容はそれぞれ異なるが、いくら何でも「似すぎ」ではないだろうか。
「終戦の日」という言葉は、一般日刊新聞では、いま、当たり前のように使用されている。なぜ「敗戦の日」と言わないのか、といった指摘が過去からなされてきた。「終戦」と「敗戦」は同じ文字数だ。「終戦の日」は、戦争が終わった日との意味だが、戦争に「勝った」のか「負けた」のかを曖昧にしている。8月15日、「いまの若い人は、日本がどこと戦争をし、どういう結末になったのか知らない」、とテレビのコメンテーターがしたり顔で言うのを見た。
ところで、「終戦の日」には別の指摘もある。8月15日付毎日新聞の1面コラム「余録」にはこうある。
「今では当たり前のような終戦記念日への見方も当初はさまざまだった」
「終戦の詔書への署名は8月14日。大本営の停戦命令は8月16日。ミズーリ号での降伏文書調印は9月2日。14日を重大な区切りと考える識者も少なくなかった」
沖縄戦の「慰霊の日」は、6月23日だ。この日は沖縄での「組織的戦闘」が「終結」した日とされる。しかし沖縄の南西諸島について日本軍が降伏文書に署名したのは、大日本帝国政府による戦艦ミズーリでの降伏文書調印の5日後、9月7日だった。
旧満州や樺太、大日本帝国の他の占領地域では、いつまで「戦争」が続いたのだろうか。旧陸軍少尉の小野田寛郎の「終戦」はフィリピン・ルバング島で、終戦から29年後の1974年3月9日だった。
ところで、筆者にはひとつ気になることがある。「終戦の日」企画記事を書いた記者たちは、自紙の1945年8月15日の新聞を読んでから、特集記事を書いているのだろうか、との疑問だ。
1945年8月15日、「終戦の日」、正午にNHKラジオから「玉音放送」が流れた。新聞は放送終了まで配達を差し止められていた。各紙ともに1面に大きく、ポツダム宣言を受け入れ、無条件降伏に応じる天皇の「詔書」を掲載した。
朝日と読売報知の1945年8月15日の社説の一部を引用する。
朝日新聞 「一億相哭の秋」
大東亜宣言の真髄も、また我国独自の特攻隊精神の発揮も、ともに大東亜戦争の経過中における栄誉ある収穫といふべきであり、これらの精神こそ(中略)我が国民性の美果としなければならない。
読売報知新聞 「大御心に帰せん」(読売新聞と報知新聞は戦時報道統制の一環で1942年8月5日に統合した)
大東亜戦争は宣戦の詔勅を炳(へい・光輝くの意)として明(みょう・明らか)なるが如く、正義の戦であり、自衛自存の戦であった。
長くなるので2紙のみをとりあげたが、各紙社説はすべて、内務省と情報局がポツダム宣言受諾後に向けた「言論報道指導方針」に沿って書かれている。(注3)
筆者がここで指摘したいのは、国家の方針によって8月15日の社説が書かれているという周知の事実ではなく別の点だ。15日付の新聞には、例えば読売報知新聞の2面には、本州東方海上や朝鮮半島での「激戦」の様子が掲載されており、各紙も同様の記事が掲載されている。
大本営の停戦命令は、8月16日だった。従って新聞が、8月15日の一面紙面の「詔勅」や「社説」をもって「終戦の日」とするのは一面に過ぎない、と筆者は考える。
朝日、東京の1面掲載「政府広報」
今年8月15日の新聞には政府広報として、今年も次の広告が掲載されている。朝日新聞や東京新聞は、1面にこの政府広報を掲載している。
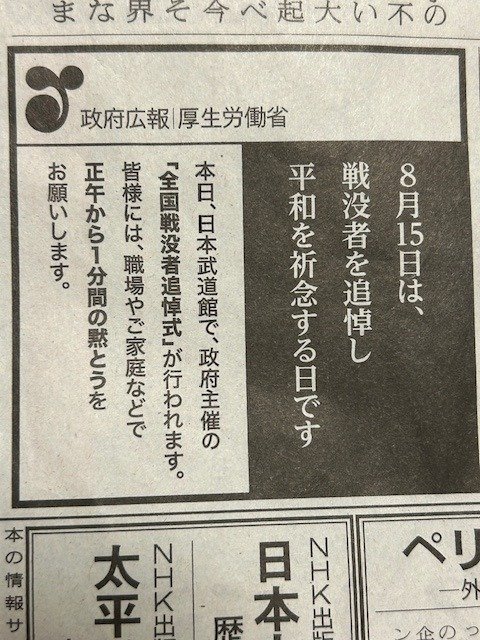
8月15日は、戦没者と追悼し
平和を祈念する日です
本日、日本武道館で、政府主催の
「全国戦没者追悼式」が行われます。
皆様には、職場やご家庭などで
正午から1分間の黙とう
をお願いします。
「戦没者追悼式」は厚生労働省の所管だ。前述の「余録」には、こう書いてある。
「戦後初の全国戦没者追悼式はサンフランシスコ平和条約の発効で独立を回復した直後の52年5月2日。政府主催の追悼式を8月15日に実施するようになったのは63年からで今年の式典は62回目になる」
「『戦没者を追悼し平和を祈念する日』という正式名称を閣議決定したのは、82年。多くの犠牲者を出した戦争を追悼する日の法的根拠が閣議決定というのは心もとない」
広告には「職場やご家庭などで、正午から1分間の黙とうをお願いします」とあるが、国民への「黙とう依頼」も毎日「余禄」が指摘する「閣議決定」に依拠しているのだろうか。朝日新聞と東京新聞には記事で、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」と閣議決定の内容との関係について「記事」で取り上げてもらいたい。
筆者が気になるのは最近流布している「先の大戦」という言葉だ。8月15日の紙面にも見られた。事実に基づいているのであれば、新聞あるいは記者個々にそれぞれに「第2次世界大戦」に対する「見解」があるのは当然だ。
しかし、戦争の名称すら曖昧にすることに、どういう意味があるのだろうか。各新聞社は、それぞれの記事で「第2次世界大戦」「大東亜戦争」「太平洋戦争」「15年戦争」と言葉の使い分けをしてほしい。そして言葉を使った理由について、新聞や執筆した記者は記事中で示してほしい。社内での議論も記事化してほしい。もちろん、どの言葉を使うかは、その新聞社や記者の自由だが、読者が記事を読む上での重要な情報だと筆者は考える。
「岸田首相 退陣へ」の記事が1面に掲載される中、「終戦の日」の記事が他紙より多く1面の紙面に掲載されていたのは、産経新聞と東京新聞そして朝日新聞の順だった。
産経新聞は、1面肩に黒抜き横見だしで「終戦の日に」とあり、榊原智論説委員長の署名記事が掲載されている。この記事の見出しは2本。「すべての御霊 安らかなれ」「靖国神社参拝は戦没者との約束だ」
1面ヘソ(中央)の記事にも2本の見出し。「きょう戦没者追悼式 5年ぶり通常開催」「遺族高齢、記憶継承に課題」
そして、「産経抄」は、靖国神社の資料館である「遊就館」での特別展を紹介し、戦争の記憶の継承の難しさを訴える内容とともに、パリ五輪卓球女子メダリストの早田ひな選手が、鹿児島の知覧特攻平和会館を訪ねたいと帰国時の記者会見で語ったこと、若い人たちが「遊就館」の展示に「熱いまなざしを向けていた」ことを挙げ、頼もしい世代が戦争を語り継ぐバトンを受け取ると指摘した。(注4)
東京新聞は、1面で大きく紙面を割いて、「平和の種まき 8歳の願い」。小学生作の「平和の俳句」を写真入りで掲載した。特集は「つなぐ 戦後79年」。もう1本は「苦難乗り越える絵描く」。100歳の影絵作家のインタビューを掲載した。平和の俳句特集は9面、インタビューは8面紙面の全面を使い、詳しく報じた。
朝日新聞は、2段の記事2本を1面に配した。見出しは「きょう79回目 終戦の日」「旧軍人恩給 近く千人下回る」の2本見出しの記事。そして「戦争体験世代の声 継ぐ」でゼネラルエディター兼東京本社編集局長春日芳晃の署名原稿を掲載した。
「終戦の日」特集の画一性
社会面など一面以外に展開する記事も各紙ともに「画一的」といえる。
前述のように各紙の「終戦の日」の特集内容は、戦争体験世代の急激な減少の中での証言、そして戦争世代の体験を若い世代が語り部として受け継ぐ、という内容がほとんどだ。主な見出しを見てみよう。
読売 戦後79年 「声続く限り 語り継ぐ」
引き挙げを語る 「戦争とは大渦潮 抜け出せず 誰でも鬼に」ちばてつやさんに聞く
日経 「戦禍の伝承、私の役目」 最後の空襲の日に生まれて詩人
朝日 戦後80年へ 戦場の肉声 いつまで
住民虐待 過酷抑留 語り部は99歳
記憶受け継ぐ ネットも活用
産経 絶えゆく大戦口頭伝承
「終戦時20代」人口の0.3% 戦後世代も語り部に
安保の歴史 受け継ぐ
「軍事」関係者の証言 自衛隊教育など活用
国主導で記憶の「整理と保存」を 中尾知代・岡山大准教授(社会文化学)
8月31日付、毎日新聞専門編集委員伊藤智永コラム「土記 do-ki」は「8月ジャーナリズム」との見出しで、小津安二郎の戦争体験と映画について述べ、続けてこう書く。
「今年の8月15日は前日、岸田文雄首相が退陣表明した騒ぎにかき消されたが、そうでなくてもメディアの8月報道は低調だった」
「戦争体験には勝者と敗者、そして死者の三つの声がある。最も悲惨な死者は言葉を持たない。生存者も真実はついに語り得ない。だから小津は映画を作った」
「8月のジャーナリズムも、記憶の偏りと改変を免れない生存者の証言を「真正かつ神聖」とあがめすぎる惰性から、自覚的に脱却すべき時期を迎えている」
「戦争の悲惨さ」の「証言」は、周辺国の軍事的脅威を訴え、「台湾有事」の危険性を指摘し、敵基地攻撃能力の整備や「抑止力」強化を訴える新聞にも、平和憲法の維持を訴え、急激な防衛予算の拡張に疑問を呈する新聞のどちらにも、その主張の「論拠」となる。
朝日の9月6日付オピニオンページの「EYE モニターの目」は「戦後79年の報道」がテーマだった。モニターの4人が意見を寄せている。「小説のようなアパート物語」「子どもに被爆の歴史どう語る」「なぜという視点で分析 大切」。東京都の55歳の女性の意見には「未来につなげる記事をもっと」との見出しがついた。
そこにはこうある。
”戦後79周年に関する記事は、例年と同じく「日本人の責務」として一通り読んだが、今回は「似たような記事を何度も読んだ」感があり、あまり心に響かなかった”
”「過去」をただ振り返るだけでなく、現在に生きている読者を「未来」とつなげるような記事を、もっと読みたい”
取材の労力を「過去」「現在」「未来」をつなげるような記事を書くために投入する。筆者はこの「声」に同感する。
こうした意見に対し、ゼネラルエディター補佐・田村隆明は、「戦後80年」へ 過去から学ぶ取材を」との見出しで、自らの家族の戦争体験をふまえ、「歴史とは為政者のみによって紡がれるものではありません」と書き、こう続けた。
”いま起きていることを理解し、これから起こることを見渡すためには、過去に学ぶ必要があります。来年に向けそのことを強く意識しながら、メディアの責務として、複雑な断面を持つ「歴史」取材に取り組んでいきます”
戦争生存者の証言、それを伝承する「若い」語り部たちの活動は重要だし、もちろんそれを報道する価値は高い。しかし、筆者は東京の一般日刊紙すべてが、8月15日に同じテーマの「特集」を組む「画一性」に疑問を持つと同時に、ある種の「怖さ」を感じる。
「広島平和記念資料館」「長崎原爆資料館」「沖縄県平和祈念資料館」「知覧特攻平和会館」など「平和博物館」と呼ばれる施設は日本に60以上あるといわれる。そこには、戦争で悲惨な目にあった数多くの人々の多様な証言がすでに収集され、展示されている。
また、例えば「名もなき人々の戦争」など戦争の実像を伝える優れたドキュメンタリー映画も多数ある。そこには、戦争に巻き込まれた人たちのナマの声が残されている。「8月15日」が「終戦の日」でなかった人々の声もある。
「8月15日は、平和博物館に行こう。戦争のドキュメンタリー映画を見よう」
単に「新たに発掘した証言」の報道だけでなく新聞メディアには、戦争を知らない「若い人たち」に「平和博物館」に行ってほしい、戦争を記録したドキュメンタリー映画や過去のテレビ番組を見てほしい、と呼びかけるキャンペーンを展開してほしい。
本紙だけでなく、「若い人たち」にアプローチするため、「特集」を組み、ウェブでの発信も積極的に活用して人に「とどく」ようにする努力が必要だ。テレビやネットとも連携し、こうしたキャンペーンを手掛けてくれる新聞はないだろうか。
「8月のジャーナリズム」はジャーナリズムか
ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルによるパレスチナのガザ地区「蹂躙」が続く中で、戦後79年目の「終戦の日」に新聞ジャーナリズムは何を報じるべきなのか。
近年、日本の新聞は、公共の関心事として、中国、北朝鮮の軍事動向と脅威を大きく紙面を割いて報道してきた。その中で、米国シンクタンクのシミレーションをもとに「台湾有事」がクローズアップされた。「閣議決定」による5年間43兆円への軍事費増大。最近は、日米軍事司令部の「統合化」も報道された。
アジェンダとして「敵基地攻撃能力」確保の是非、「殺傷兵器」の海外輸出も論じられた。
それなのに、なぜ、8月15日の紙面は、過去の「戦争の悲惨さ」に焦点を置いた記事のみに占められているのか。そこに筆者は疑問を持つ。
例えば、筆者であれば、「台湾有事」が現実のものとなった際に、日本は米国の意向に従わず、「参戦」しない選択肢があると考えるのか。日中両国が、南西諸島での部分的戦闘状態に入った場合、米国は「中国との全面戦争も辞さず」と「参戦」するのか。ハリス民主党政権とトランプ共和党政権では、「台湾有事への関与」に対する考えに差があるのか。「戦争」を考える日にこうした疑問に答える特集記事を読みたい。
例えば、ワシントンに駐在したことのある外交官、ジャーナリスト、研究者などの識者の考えを知りたい。「台湾有事」の際に、米国が本当に「参戦」」すると考える専門家がどれほどいるのか。なるべく多くの専門家の「本音」を属性による「匿名」でアンケート調査してほしいと思う。
各新聞社と系列放送局が組んで行う、内閣支持率の世論調査には、正直、飽き飽きしている。新聞もテレビも経済的に苦しいという。ではなぜ、5つも6つものグループが、同じような調査をしなければならないのか理解に苦しむ。こんな調査が、重複し多数行われても国民・オーディエンスにメリットがあるとは思えない。「内閣支持率」のみであれば、政府から独立した調査がふたつもあれば、十分だろう。
新聞社は、不動産再開発などで「協業」せず、経費削減、収益増大のため、世論調査などを共同で行えばいいと筆者は考える。米国のピューリサーチセンターやギャロップ社のような日本版調査会社を各社の共同出資で創設することはできないか。
もちろん独占化を避けるため1社だけは好ましくない。2社を創設し、社会状況を反映しネット調査に比重を移し、若く優秀な統計調査の専門家を結集すべきだ。例えば、全国紙は時事通信の中央調査社を母体にしてもいいし、地方紙と全国紙の一部は通信調査会を活用して共同通信社がまとめる形で設立してもいいだろう。
第3極としてNHKは独自で世論調査を継続する。そうすれば調査の確度もあがり、調査ごとの比較もできるはずだ。
監視どころか権力と一体化
筆者は、これまでブログで、ジャーナリズムの構成要素について3点を挙げてきた。
①公共の関心事となる情報を提供し
②アジェンダ(解決すべき課題)を設定し
③権力を監視(ウォッチドッグ)する
3点目の「権力の監視」については、日本の「組織ジャーナリズム」は「絶望的」な状況と言える。
政府は2022(令和4)年に「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」を創設した。有識者会議のメンバーには3人の元を含めた著名な新聞関係者が含まれていた。
読売新聞グループ本社代表取締役社長山口寿一、日本経済新聞社顧問の喜多恒雄、そして国際文化会館グローバル・カウンシル・チェアマンで元朝日新聞主筆の船橋洋一だ。
この「有識者会議」は岸田政権が2022年12月16日に閣議決定をした「安保関連3文書」の「露払い」の役割を担った。このブログの読者の方には、時間があるときに以下のホームページにアクセスし、議事録をお読みいただきたい。
国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議|内閣官房ホームページ (cas.go.jp)
2022年12月16日付朝日記事にはこうある。
「岸田政権は16日、国家安全保障戦略(NSS)など安保関連3文書を閣議決定した。NSSは安保環境が「戦後最も厳しい」とし、相手の領域内を直接攻撃する「敵基地攻撃能力」を「反撃能力」との名称で保有すると明記。2023年度から5年間の防衛費を現行計画の1・5倍以上となる43兆円とすることなどを盛り込んだ。憲法に基づいて専守防衛に徹し、軍事大国とはならないとした戦後日本の防衛政策は、大きく転換することになった」
民主主義、法の支配、価値観を共にする「同志国」。安倍政権の時代によく聞いた言葉だ。「有識者会議」の資料にも出てくる。筆者は、欧米の民主主義国家と日本が、本当の意味で「価値観」を共にしているのか、疑問に思うところがある。少なくとも民主主義の維持に必須の役割を果たす「ジャーナリズム」が、日本とG7など欧米諸国で同じ「価値観」を共有しているしているとは、言い難い。
ジャーナリズムがジャーナリズムとして成り立つ所以は、最低限、報道機関、ジャーナリストが「権力」と距離を置き、決して「権力」のプレイヤーとならないことだ。意見、評論の表明は新聞、雑誌、書籍、テレビそしてウェブサイトに厳に限るべきだ。そうでなければ、ロシア、中国といった強権国家の「広報メディア」と変わらない。日本を代表するメディアである読売新聞グループの代表取締役社長、日本経済新聞の顧問、朝日新聞の元主筆がそろって政府の「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」のメンバー入るなど、国策に協力していった戦前の新聞界を彷彿とさせる。
「憲法改正」など新聞が紙面を通じて「主張」するのは、ジャーナリズムとして何の問題もないし、言論の多様性の確保は重要だ。一方、対立軸として「護憲」の新聞の存在も議論を深める上で必要だ。問題は「公共圏」の「フォーラム」でお互いが論戦を行わないことだ。確かに、かつて朝日新聞は、同業新聞社から苛烈なメディア批判の対象となった。朝日新聞側にも瑕疵はあったが「まとも」な論議だったのか、筆者には疑問が残る。(注6)
日本メディアの最大の問題点は、主要なアジェンダに関するメディア間の主張の違いに関し、論戦が起きないどころか、「権力」にすり寄り、「権力と一体化」する主要メディア経営者に対し、他のメディアが、何の批判もしないことにある。政府の「審議会」「研究会」に大手新聞社(特に読売新聞社)から委員が選ばれるのは、過去、多くの例があり、この是非についての議論はメディアの側でほぼ行われていない。これは日本組織メディアの構造的な問題で、具体的事例については「新聞~新たな戦前への道」で詳しく説明する予定にしている。
さて、今回の論考を書く上で、朝日新聞が「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」をどう報じているのか。時間をかけて読み解いた。筆者が認識した2022年の9月8日から関連記事は64本に及ぶ。ここでは、詳細な説明は避けるが、朝日新聞の主要な主張と問題意識は、読売新聞と大差ないとの結論に筆者は到達した。(asahi.comのサブスクライバーは「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」で検索していただき、読んだ感想をお教えいただけるとありがたい)
「有識者会議」は9月30日、10月20日、11月9日、11月21日の4回のみ開催された。議事録を読むと、議論はなく、それぞれの委員が意見の表明する形で行われた。11月22日には報告書が発表された。「防衛力の抜本的強化」「反撃能力」「防衛産業の育成・強化と装備品の他国への移転」「総合的な防衛体制の強化」「財源の確保」などを骨子としており「安全保障関連3文書」の改定に向けた「地ならし」の役割を担った。
議事内容は当初、個々の意見について「議事要旨」として、だれの発言か伏せた形で公表されていた。政府は、有識者会議報告書発表から1か月を経ずして、12月16日に安保関連3文書を閣議決定した。翌23年1月24日、「有識者会議」の発言者を明記した議事録を内閣官房のホームページで公開した。
読売社長の防衛力有識者会議での発言
公開された議事録から、読売新聞グループ本社代表取締役社長山口寿一の発言の一部を以下に抜粋する。
第1回 〇山口委員
「岸田首相は、日本の防衛力を抜本的に強化するという歴史的決断をされました」
「防衛産業について申し上げますと、防衛産業を国力の一環として捉え直して、自由で開かれたインド太平洋の安全保障環境の整備につなげるといった大きな視点に立って、防衛装備品の輸出拡大を、日本の安全保障の理念と整合的に進めていくための対策が検討されるべきです」
「財源については、つなぎ国債はよいとしても、恒久的な財源を確保していかなければなりません。既存の歳出削減と併せて具体的な論議が急務といえます」
第2回 〇山口委員
「防衛力の抜本的強化につきましては、防衛大臣のご発言のとおり、スタンドオフミサイルを配備して反撃能力を保有すべきでありまして、無人機の導入、継戦能力の向上も進めて戦える自衛隊へ変革していくことが急務と考えます」
「5年以内というタイムラインを考えますと、例えばスタンドオフミサイルは国産の改良は数年以上かかって、2027年までに間に合わない可能性もあります。国産の改良を進めるのは重要ですが、当面は外国製ミサイルの購入を進めることも検討対象になると思われます」
「防衛に資する研究に大学の予算を分厚く配分するといった運用も必要ではないか、10兆円のファンドをこうしたことに活用してもよいのではないかと考えます」
第3回 〇山口委員
「折木元統合幕僚長が報告されたように、日本は、目前の脅威に直面しています」
「国力としての防衛力を強化するには、経済力を強化する必要があります。それには、日本が官民一体の推進力を取り戻して、変化に挑戦する機運を高めて、新しい形の資本主義を推し進める体制を作らなければならないと考えます」
第4回 〇山口委員
「報告書の内容には異存ありませんので、今後の取り扱いに関しましては座長一任ということで異議はございません。
若干付け加えますと、この報告書は議論の入り口を提供したにすぎないものと思っております。ここから国民的合意を築き上げていくのはかなり大変であります。国の行方に係る重要な論点が幾つもありまして、日本を取り巻く環境は安全保障、経済情勢、いずれも厳しい時であります。国会、地方自治体、産業界、大学、世論の理解を得られますよう、政府が文字どおり一丸となって取り組んでいただきたいと思っております。
委員の先生方の御発言を伺いながら、メディアにも防衛力強化の必要性について正確で、かつ深い理解が広く広がるようにしていく責任があると、この会議を通じて自覚した次第です」
このブログで掲載する写真は、すべて筆者が通訳案内士、ネーチャーガイドとして各地で撮影した。今回は、2024年8月15日の大和市図書館(シリウス)前で撮影した夏空。
(注1) 前回、今回と日本経済新聞については、対象からほぼ除外した。その理由は、日経は他紙と異なり「終戦の日」を1 面で扱っておらず第2社会面の肩の記事だけとなっているためだ。経済紙なので、「終戦の日」に大きなニュース価値をおいていないためと思われる。
(注2)
補稿 日米の新聞販売を比べる
ニューヨークタイムズ、ワシントンポストなどの米国の新聞は、夕刊はなく、朝刊だけの発行だ。ニューヨークタイムズの「紙」の新聞発行部数は、昨年9月発表の半年間で27万部程度、最盛期の部数は120万部程度だった。一方、デジタル版の世界での購読者は650万を超える。デジタルと「紙」を合わせた新聞メディア購読者=「サブスク」者数は、この20年で5倍に成長した。
ニューヨークタイムズの平日版は4セクション40ページの時もあるが(例えば、今年の8月19日)、土曜日は毎週7セクション、96ページ(8月25日)、日本の元旦の新聞と同じページ数が毎週1回宅配される。
米国の新聞は、宅配のエリアが限られている。発行部数の減少に伴い、よりきめ細かい宅配システムを採用している。読者は、特定の複数の曜日、土曜日のみなど宅配される日を選べるなど柔軟性が地域もある。
前回のブログで指摘したとおり、日本の新聞発行部数は米国に比して多いが、紙面のページ数の少なさ、情報量も米国の朝刊日刊紙と比べると大きく違う。比べる対象があるとすれば、「USA Today」だけだろう。
同紙は、衛星通信を使用して各地に印刷拠点を持ち、米国で広範に新聞販売をしていた。タイムズやポストのような重厚さはなく、記事は短く、ページ数も少ないため「マックペーパー」と揶揄された。同紙やマクドナルドには申し訳ないが「ファストフード」のような「チープ」ですぐ読める「お手軽な新聞」との意味合いだ。
ついでに書いておけば、米国には「紙」の新聞の「月極」購読という概念はない。4週間を最小とするなど週単位だ。4の倍数なので、「年間購読」という考えもなく「52週購読」となる。
うるう年を除けば2月は28日、その他の月は、30日と31日。細かく合理的に考えれば、新聞紙面がどどく日数が異なるのに「月極」の同一料金は「不合理」とも言える。
「新聞休刊日」もない。日本の新聞関係者には、米国の新聞販売システムは「奇妙」に映るだろうが、米国の新聞関係者から日本のシステムを見ると「不思議」に映る。インターネット出現以前、「休刊日」に大事件が起きたらどうするのだ、と聞かれたことがあった。
日本の新聞販売は、複雑なシステムとなっている。筆者は、前職で新聞社の販売局働く人や販売店主と仕事を通じて多くの接点があった。かつて「インテリが新聞を作り、ヤクザが新聞を売る」といわれたが、筆者には、そうした感覚はない。
新聞販売のシステムは複雑で、ここでは説明しないが、新聞販売の人たちは「義理」がたい人たちだった。話は、時には新聞記者から聞く話よりも興味深く、とても役立った。
新聞購読者は、近くの新聞社販売店とは接点はあっても、新聞社の販売局で働く人の仕事内容についてはほとんど知らないと思われる。
発行本社販売局担当者の仕事は、コンビニのテリトリーマネージャーに似ているとも言える。新聞販売店が、セブンイレブン、ローソンなどの各店舗に当たる。コンビニの店舗、新聞販売店は、コンビニの経営会社や新聞社でなく、本社から「権利」を買い営業する、個人や小規模の経営主体からなっている。販売局は、コンビニのテリトリーマネージャーと同様に、担当するテリトリーの「販売店」が、発行本社販売局の方針に従い、他社との競争の中で最大の「利益」を得ようと努力する。テリトリー内の販売店に経営的トラブルがある場合は、販売店を「改廃」し、テリトリー内の販売部数を維持する仕事もある。
マーケットが飽和状態となった以降も新聞には長年、「再販売価格維持制度」「特殊指定」など優遇措置が維持され、「全国紙」間、「全国紙」と「地方紙」間でプッシュ型販売の「過当競争」が激化し、強引な新聞販売が社会問題化した。読者の奪い合いだ。
営業を担当する販売局が、部数最大化に全力を投入するのは当然であり、過当競争とその弊害は、新聞社販売局のみの責任に帰するべきでなく、むしろ編集出身の新聞経営者の責任が重い、と筆者はみる。「再販」「特殊指定」でロビー活動を行い「政治案件」化することで、「新聞社」と「政治」の関係が強化され、「消費税軽減税率」適用により後戻りできない状況となった。
考証はいずれ「新聞~新たな戦前への道」で取り上げたい。
(注3)朝日新聞が森恭三による著名な宣言「国民とともに立たん」(大阪・西部発行の紙面では「起たん」)を掲載したのは、敗戦後2か月半以上が経過した1945年11月7日付紙面だった。
参考文献
「戦後50年 メディアの検証」 朝日新聞取材班著 三一書房 1996年
「検証 戦争責任 上下」 読売新聞戦争責任検証委員会 中央公論 2009年
「戦争と新聞 上下」 朝日新聞「新聞と戦争」取材班 朝日文庫 2011年
「近代日本メディア史II」 有山輝雄著 有斐閣 2023年
(注4)筆者は博物館学芸員として歴史展示を担当した経験があるが、靖国神社の「遊就館」と「知覧特攻平和会館」を同列に論じてよいものか、疑問を感じる。
(注6)参考文献
「抵抗の拠点から 朝日新聞「慰安婦報道」の核心」 講談社 青木理 2014年
「朝日新聞政治部」 鮫島浩 講談社 2022年
