
本の記憶。 晩年の川端文学
川端康成の『山の音』、『眠れる美女』を読んで、あらためて、【文学】ということを考えさせられた。
『山の音』は昭和29年、『眠れる美女』は昭和36年に書かれた作品である。川端康成は1899年(明治32年)の生まれだから、『山の音』を書いたのが55歳のとき、『眠れる美女』は61歳のときの作品である。
川端康成は、自分が若いころからいろんな形で読んできていて、『山の音』も『眠れる美女』も過去、なんらかの形で読んでいた作品である。それが、あらためて読み直してみて、ショックに近い読後の感想を抱いたのは、自分が年老いて、これらの作品のなかに登場する主人公の男と同年齢、あるいは年上の男になって、年老いた男の情念のようなものや、性への未練、生理的な願望というものに正面から向き合わなければならなくなっているからだと思う。
『山の音』は文芸評論家の山本健吉氏によれば、「戦後の日本文学の最高峰に位置する作品」なのだが、内容は、不美人の女房と結婚した初老の男の若いころ、好きだった美しい女への思いを断ち切れずに暮らす、こもごもの記録、と要約すればいいだろうか、読んでいて身につまされた。前に映画で『山の音』をみたことがあり、これは成瀬巳喜男監督作品で、主演が山村総、その不美人の奥さんが長岡輝子、息子が上原謙、嫁が原節子という配役で、映画は舅と嫁の禁じられたプラトニック・ラブの物語のような色合いの作品だったが、本体の小説は、もっと厳しく初老の主人公の荒涼とした精神模様を描いたもので、自分がそういう年齢になって、共感しながら読んだせいか、川端康成ってこんなすごい作家だったのかと見直した。これまでは川端の文学者としてのイメージを、戦前は横光利一の相棒で、戦後は三島由紀夫の併走者みたいに思っていた。
『山の音』は年をとった自分を真正面から見つめながら、自分の生活の精神模様を連作の小説にしていった、極めて〝私小説性〟の高い作品だった。救いようのない精神の営為ということを思った。

『眠れる美女』の方は『山の音』よりもっと衝撃的な、幻想小説といってもいいような作品だった。睡眠薬で眠らされている全裸の若い娘たちを老人の男たちに添い寝させる曖昧宿の物語、ただし、性交などの性行為は禁止されている。そこに通う、まだ、老いぼれてしまっていないという自覚のある男の、一種の精神劇である。これも、昔、読んでずいぶん衝撃的な設定だなと思った記憶があるが、あらためて読み直してみて、ものすごく文学性の高い、ぬかるみのなかに半身を付けたような性の泥沼を描いた小説だと思った。こういう虚構で枠を作りながら、物語のなかの現実をリアリティのあるままで文章に変えるのは大変なエネルギーが必要なのだ。
考えてみると、いまこういう、半ば自己告白的な、私小説の臭いを漂わせながら、老人の精神性の頽廃、老人の性そのものの状況を自分の世界からえぐり出すように描くことの出来る作家がいない。売れることばかり考えているからこういうことになってしまったのだ。純文学は滅びたといわれる所以である。とにかく、この二冊、面白かった。
純文学が滅びた原因は、大衆の変質と出版界の衰亡、作家の側の市場性の喪失、大きく分けると、そんなところが理由だろうか。
オレはどうしてこうなったか、理由は自分ではよく分からないが、いま幸運にも、大金は入ってこないが、好き勝手なことを書いていられる立場にいる。読後の率直な感想だが、70歳過ぎて、青春は永遠だとかいって、女の後を追い回しているような年齢じゃないな、まじめにならなきゃな、と思った。
★★★★★★★★★★★★★★
そして……。実は上の文章を書いた後、『眠れる美女』についてはこういうことがあった。先日、行きつけの古本屋さんで、三冊200円のコーナーで、安原顕さんのこの本を見つけて、見捨てておけずに買ってしまったのだ。
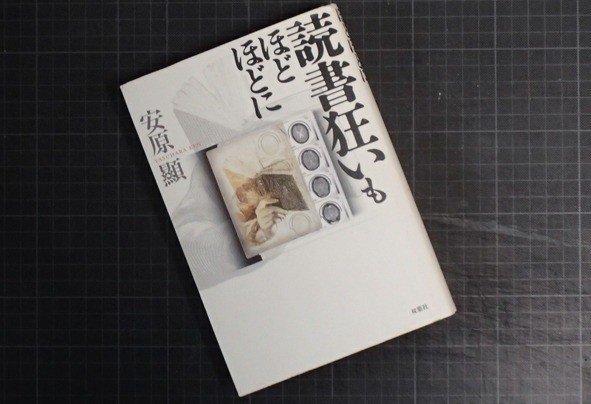
双葉社刊、2001年発行、いまから20年前、彼の書評を集めた本である。
安原さんの書評は、気に入ったものはそれなりにほめるのだが、気にくわないと、そこまで罵倒しなくてもいいのにと思うくらい、罵詈雑言を書き連ねるので有名だった。もう亡くなられてからずいぶん立つ。
パラパラと拾い読みしていて、川端康成の『眠れる美女』の書評を見つけたのである。前段で説明した通り、60年前に書かれたもの、老人が若い娘たちが全裸で眠る、怪しい〝曖昧宿〟を訪れる話。実は、出版された当時も大きな話題になった。安原さんが書評に取りあげた時点からでも40年前の本だ。
★
安原さんの書評は気に入らない本を徹底的にこき下ろすので当時から有名で、何人もの作家たちをそれで怒らせていた。『眠れる美女』の書評が、正確にいつ書かれたものかまでの、出典の記載がないのだが、文中に「四十数年前の……」という文章がある。まず、最初に、三島由紀夫が書いた文庫本(おそらく新潮文庫)の解説を引用する。
『眠れる美女』は、形式的完成美を保ちつつ、熟れすぎた果実の腐臭に似た芳香を放つデカダンス文学の逸品である。(……)ふつうの小説技法では、会話や動作で性格の動的な書き分けをするところを、この作品は作品の本質上、きわめて困難な、きわめて皮肉な技法を用いて、六人の娘を掻き分けている。六人とも眠っていて物も言わないのであるから、さまざまな寝癖や寝言のほかは、肉体描写しか残されていないわけである。その執拗綿密な、ネクロフィリー[死体愛好症]的肉体描写は、およそ言語による観念的淫蕩の極致と云ってよい。(……)私はかつてこれほど反人間主義の作品を読んだことはない。
★
安原さんはこの作品について、こういうことを書いている。
(この作品が)いまなお有効かどうか知りたくて再読する気になった。……
ぼくの意見はこうだ。アイディアは多少面白いにしても、ただそれだけのことで、とてもぬるい小説に思える。本書が書かれてから四〇数年だが、世界では老いも若きもみな狂気の度合いが増し続け、中でも日本のような無政府、無法社会に暮らしていると、川端康成が『眠れる美女』で描いた世界など「デカダンス文学」でも「ネクロフィリー」でも「死の舞踏」でも「反人間主義」でもないからだ。むろん表層的にはこの批評、間違ってはいない。しかし、ここに悪も悪意すらも皆無、小金と暇を持て余し、漠然とではあるが死の恐怖も感じる有閑爺の妄想があるだけだ。川端康成は三島の師、それゆえの過大評価はわからぬではないが、そこそこの眼力もあり、これより三三年も昔の一九二八年、凄まじい背徳小説『眼球譚』を書いたバタイユの存在を知らぬ筈もない三島由紀夫が、この程度の牧歌的お伽噺を『反人間小説』の傑作として激賞していることに、これまた不可解なものを感じた。
まず、安原さんの2001年の日本社会を無政府、無法社会と書いている神経がよくわからないが、トレンドに乗った筆の勢いというのはそういうものなのだろう。時代の検証をすると、三島由紀夫が亡くなったのは1970年、川端康成の自殺は1972年だったと思う。二人ともが存命中にこの作品が文庫本化され、その解説を三島が引き受けた、という事情だろう。文庫本の解説なのだから、悪口を書くわけがないという、編集的な常識があるはずなのだが、安原さんはそのことを考えに入れず、悪口を書き散らしている。この悪口も、もし彼が新潮社から「この作品の解説をお願いします」と頼まれたら、こんなことは書かないだろう。そういうことからいうと、時間経過の問題をそっちに置いても、三島は当然、出版社の編集者から「推薦的な解説をお願いします」と頼まれたはずで、それを[不可解なものを感じた]と書くのは編集的に頑迷すぎる。三島がこの解説を書いたのでさえ少なくとも五十年以上前のことなのである。
安原さんは八十年代にかけて、中央公論社などで一花咲かせた編集者なのだが、この文章の書き方では住む世界が徐々に狭くなっていったのもやむを得ないな、と思う。あまりダラダラこのことについて書き連ねるのも消耗なので、安原さんの書評の問題点を簡潔に指摘しておく。
●
①まず、1961年(昭和三十六年)に書かれた作品であるならば、当然のことながら、1960年代初頭という時代背景を鑑みながら批評すべきで、いきなり2001年のもの差しを持ってきて、こんなものはぬるい小説だ、などと論評すべきではない。このやり方は、戦国時代の織田信長は人殺しだった、と論難するのと同じような手法である。
その時代には、その時代のものの考え方と判断の基準がある。何十年も経過しているのだから、当然、当時の事情を配慮するべきである。
昭和三十年代にはその時代の大衆的な〝性意識〟があり、このころというのは、安保反対運動が一息ついたあとで、所得倍増計画が発表され、西田佐知子の『アカシヤの雨が止む時』が大ヒットして、謝国権の『性生活の知恵』という新しい性のマニュアル本がベストセラーになって、中央公論社が発行していた『婦人公論』に袋とじ(だったと思う)で、セックスのマニュアルが図解付きで登場した時期なのである。これらの風潮と、川端さんのこの作品が無関係であるはずがない。
②もうひとつは、安原さんの批評の基準が創作小説的な、つまり、本人の主観に基づくフィクションであること。安原さんは川端さんの『眠れる美女』を妄想というが、わたしから見ると、安原さんの書評も妄想なのではないか、という気がする。彼のモチベーションの中には政治的な発想がかなりあるのではないか。コイツに噛みついたら面白いとか、悪口を書いても差し障りないとか、客観的な基準をもち、評論としての確固としたもの差しをもって作品の位置付けを目指すという方法が採れていない気がする。レストランの客が出された料理をそのときの懐具合や気分で美味いとか不味いとか云っているような感じ。それはそれで、その場では面白いのだが。
わたしはすべての創作小説は作家の妄想から始まっていると考えているから、こんなのは作家の妄想にすぎない、などということは絶対に書かないようにしている。
映画の話だが、黒澤さんが作った晩年の『夢』以降の三作品をあんなものはダメだ、黒澤は耄碌したといってこき下ろす人がいるが、そこのところであれらの作品を壟断しても、作品の本質はなにもわからない。簡単にいうと、あれらの映画は老人映画なのであり、川端さんの『眠れる美女』も昭和三十年代という状況下で書かれた老人文学なのである。
もちろん、現実の日本社会は2001年の状況があり、私たちがいま生きている2020年の状況があって、昔と大違いの性の状況があるのだから、あんなものはだめ、と考えるのも自由だが、私はやっぱり、川端さんの『眠れる美女』に時代を超えた老人の肉体の悲しみを痛切に感じる。川端さんがこの作品を上梓したのは六十三歳のとき。安原さんが癌で亡くなったのもたしかそのへんの年齢だと思う。冒頭の本が出版されたすぐ後のこと。何年か前からの闘病生活だったというから、この作品に対する書評もやけくそで、破れかぶれだったのかもしれない。
川端さんがガス自殺したのは七十三歳のとき。わたしが好きな作家の一人、辻邦生さんも73歳で亡くなられている。わたしももうじき73歳になる。老人には老人にしか書けない悲しみがある。『眠れる美女』は不気味な小説だけど、良かったら一度読んでみてください。
★
1961年に書かれた小説と、2001年に書かれた書評を、2020年のわたしが二つ並べて、後出しジャンケンの極みのような書評を書くのも、考えて見ると、ちょっと変かも知れない。
………
人の批判をするときは、自分がなにを基準にものをいっているかを、明確にしなければならない。それが、陽明学でいう言行一致。わたしが沈黙主義者として、歴史の中にある基準でしかものをいうのをやめようと考えている、
つまりノンフィクション作家であろうと考えている大きな理由である。終。
