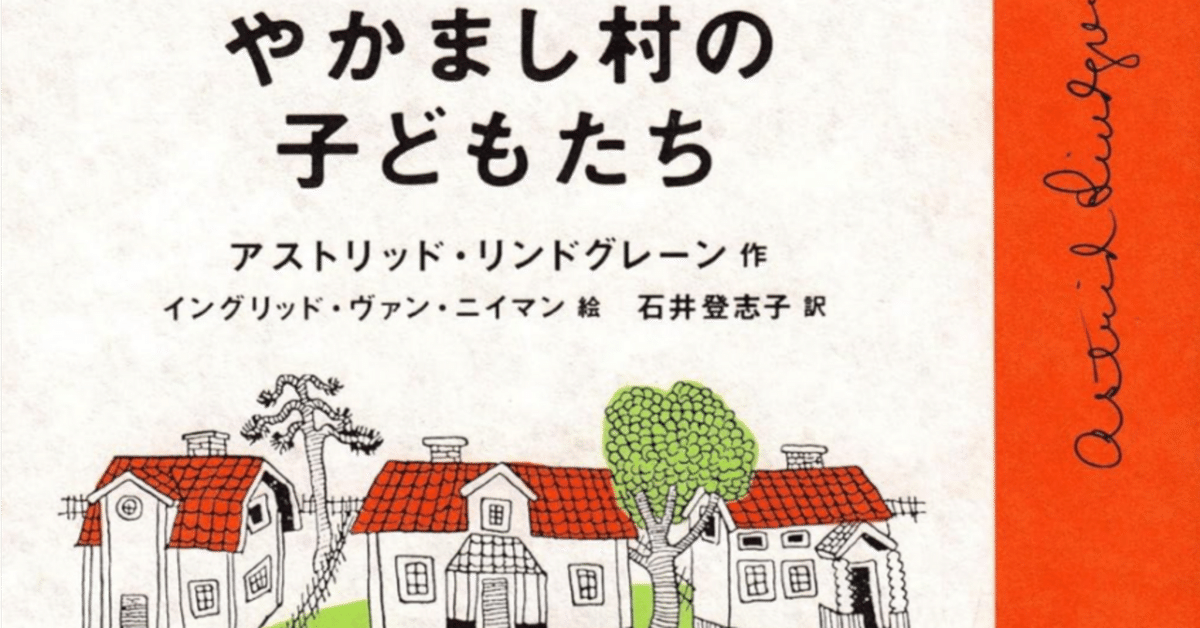
アストリッド・リンドグレーン 『やかまし村の子どもたち』
僕にとっての本書:
ほのぼのしている。田園。こどもの視点。こどもを見守る、あたたかい保護者たちの視点。ひたすらに。
2019年の出版。
リンドグレーン・コレクションという復刻版のようなものでしょうか。
翻訳は石井登志子氏。リンドグレーンの翻訳を多くてがけている方。今回、初版の訳出時の「やかまし村」という訳を大事にして採用したとのことでした。
作品の原著は Alla Vi Barn I Bullerbyn , 1947年。
最初の邦訳は1965年でした。
アストリッド・リンドグレーン(Astrid Lindgren 1907-2002)は、スウェーデン出身。1945年に刊行された『長くつ下のピッピ』が最も有名なものかもしれません。「やかまし村」は、彼女のキャリアのごく初期の作品。40歳くらいのころの作品。
リンドグレーンは、教師だった時代もありました。親近感がわきます。僕も歴史教師(40歳)。
リンドグレーン氏の故郷を思わせるのどかな風景描写、人間模様、家族愛などが特徴の作品。こころあたたまる、という感じ。
作品からは、こどもが試練を乗り越える、ひたすら生きる、というリアリズムが感じられません。どちらかというと、こどもの理想郷を描いたような…その描写への注力は強く感じられます。リンドグレーン氏は、こどもの権利の擁護者でもありました。
こうした読み方が正しいのかどうかわかりませんが、「こども時代」を失った子どもたちに、それを回復させようとする作品、というような印象を持っています。
こどもが経験すべき遊び、それを本を読むことで追体験させる、そんな感じがしました。実際の、終戦直後のスウェーデンのこどもたちが、「子ども時代」を喪失していたかどうかはわからないのだけれど…
ただ、そういうこどもに対する眼差し、著者の思いみたいなものは、それなりに普遍性があるはずですよね。だから、室内でオンラインゲームに熱中する2020sのこどもたちにも、たぶん響くのでしょう。コロナ世代のこどもたちにも。たぶん、みんな「こども時代」を失っているのだろうから。
このあたりは、生き抜くことや運命を描写したサトクリフや、こどもに試練を与えていく作家たち(ケストナーなど)とは、一線を画す感じがあります。サトクリフなら、コロナ世代のこどもたちに何というでしょうか。
それから、北欧だからってわけじゃないでしょうけれども、「ムーミン」には何やら同じ感覚がある…
訳者の石井氏は、「訳者あとがき」の中で、作品にみられる「男女平等」の先見性を指摘しています。1947年当時、それは新鮮なものだったと。また、作品中の学校の式典などが教会で行われるところに、ルター派を国境とするスウェーデンの文化が見られるとのこと。へえ、そうなのか。
僕はたぶん幼い頃に本書は読んだと思いますが、あまり記憶にありませんでした。
読んでみると、田園でのあそびの描写が、あまりに無邪気で、いっしゅんでファンになってしまうこどもや保護者が大勢いることがよくわかります。のびのびしていて、美しいのです。
こどもの目線で書かれている、というところがこの作品の大きな功績だったのかもしれません。こどもが語り手でもある。それは、そうした作品が当たり前のものになっている現代において、この分野のパイオニア、という位置付けになるのかも。
スウェーデンは、ロシアのピョートル大帝との北方戦争に敗れて以降、つねにヨーロッパのなかでどの位置を占めるかに苦心してきた国のように思われます。そして、中立のイメージは強いものの、現代史においてはいつも独ソの脅威にさらされてきた国。「福祉国家」のイメージ、平等の北欧のイメージは、強い国家の指導力、強権政治の時代(おそらく左派の)があったことの証左かも。
それに、NATOに加盟する積極策を打ち出すこともできる、強い一面をそなえているのですね(2022)。
有名な作品で近い時代のものは、
サン・テグジュペリの『星の王子様』(1943)でしょうか。
このノートで初期にとりあげた
ケストナー『飛ぶ教室』は、1933年でした。
北欧ということで、
ヤンソン『たのしいムーミン一家』は、1948年。
本 note でしばしばとりあげるローズマリ・サトクリフは1920年生まれ。
まだこのころは作家デビューをはたしていないころです。
児童文学において、北欧ならではの傾向、そういうものがあるのでしょうか。国民性、お国柄と児童文学など、新しい関心が生まれてきました。ありがとう、リンドグレーンさん。
そろそろ、児童文学史に関する何かまとまった本などを読んでみたいのですが、いいものを見つけられずにいます。何か良い概説書はないのでしょうか…国際アンデルセン賞、リンドグレーン章、カーネギー賞などの多くの賞が児童文学の世界のいっしゅの縦糸なのだと思われますが、そういう情報を地道に整理するのもいいのかもしれません。
