
本の読み方をアップデート- NotebookLM×NotionではじめるAI読書
ここ数年では珍しく仕事がスムーズに収まったので、意外とゆったりした年末年始を過ごすことができた。ただ、何もしないでゴロゴロ過ごすのは性分に合わないようで、気がつけば休みの半分くらいをNotionというクラウドメモアプリを使った趣味のデータベース作成に費やしてしまっていたw
さらには、世の中に続々と登場している生成AI系サービスをあれこれ試してプライベート用途で比較するという、オタク的趣味にも勤しんでいた。
その過程で思い至ったのが、「読書体験のアップデートがヤバい」ということ。僕はわりとビジネス書や自己啓発本など、「実用」を目的とする本をよく読むのだけれど、気がつくと積読(つんどく)になっている本もあって(実際にはiPadの中)、しかも買ったことすら忘れてしまうことも多い。でも、今はAIの時代。AIを活用すれば、もっと効率よく—orもっと楽しく読書ができるかもしれない、と思ったのが今回の話の発端である。
どんな「読書」のハナシ?
まず、ここでいう「読書」とは、ビジネス書や自己啓発本など、“知識を吸収する”ことを主目的とした読書だ。いわゆる「ノウハウ本」や新書、解説書などの実用的な本をいかに効率よく読みこなすか。逆に、純粋にストーリーを楽しむタイプの小説や文学作品は、時間をかけて物語世界にどっぷり浸るのが一番の醍醐味だと思うので、範疇外。今回は、あくまで“情報摂取”と“活用”に特化した読み方について語ってみたい。
「速く、多く読みたい」理由
仕事柄、新しい業界や分野の動向を短期間でざっと把握しなきゃいけない場面がしばしばある。例えば、顧客が新規参入を検討している業種・市場について、自分の専門外でもまずは相談に乗らねばならないこともあるし、そこからさらに社内の専門家を巻き込んで議論しなきゃいけないことも多い。こんなとき、最低限の知識がないと仕切れない。そこで、限られた時間でガッと情報を頭に入れる必要があるのだけど、それには「速読」「多読」のスキルが大事になってくる。
実は10年くらい昔、フォトリーディングという速読メソッドの講座に10万円くらい払って参加したことがある。一時期ちょっと話題になっていたやつで、「周辺視野を使って、パラパラと写真を撮るように本を読む」と言われていた、ちょっと怪しい(失礼)メソドロジーだ。でも実際に体験してみると、「なるほど、そういう考え方でスピード読書を実践するのね」と腹落ちするところがそれなりにあった。当時は「クイズ番組に出てる速読の人」とか、「速読セミナー」なんかがちょっと流行っていたけれど、僕の印象としてはフォトリーディングは単なる速読とは少し違う。むしろ「本を読むハードルを下げて、一気に実用知識を手に入れる」というやり方だという感覚だった。
フォトリーディングとは何だったのか
フォトリーディングについて詳しくは下記の書籍などを参照してもらえればいいのだけれど、僕がその講座で印象に残ったエッセンスをざっくりまとめると、だいたい以下のようになる。
読む前に目標設定をする
「この本から何を得たいか」「どんな悩みへの答えを探したいのか」といった自分としての問いを明確にしておく。“おまじない”で気軽にページをめくる
本を触ったり、パラパラとめくったりして、本に対する心理的なハードルを下げる。要するに、「まじめに一行一行読まなきゃ!」というプレッシャーを外すわけだ。シーケンシャルに全部読まない
いわゆる拾い読みを繰り返しながら、求めている答えに近いパートを見つけるというアプローチ。逆に不要な部分にはあまり深入りしない。読み終わったら歯止めとしてアウトプットする
たとえばマインドマップなどを作成して、本の要点や“問いに対する答え”を自分の頭の中で整理する。
正直、「周辺視野で本を読む」とかいう部分だけを見ると、なんだかオカルトじみていて「ホントにそんなことできるの?」って思うかもしれない。でも実践してみると、結局は「まずは本の全体像をつかみ、目的の情報にピンポイントで当たりにいく」というのが肝だった。おかげで数冊〜10冊くらいの本を短期間にガーッと斜め読みして、それなりに必要な知識を吸収できるようにはなった。これだけでも、けっこう役に立ったなと思う。
フォトリーディングのコンセプトを生成AIでアップデートする
ところが、昨年末にいろいろ試した生成AIアプリ――ChatGPTやPerplexity、Claude、そしてGoogleが提供しているNotebookLMなど――を使ってみて、気づいてしまった。。「このフォトリーディングの考え方、今ならもっとスムーズに自動化できるんじゃね?」
僕がたどり着いた(現時点での)読書ステップは、ちょっと手間がかかるけど、その分ガツンと読書へのモチベーションが上がるやり方だ。具体的には以下のような流れになる。
書籍をテキストデータとして用意する
文字認識済みのPDFを入手する。実はこれが今は一番面倒。
書籍の購入は最近Kindleに寄せてたんだけど、それでは生成AIにぶち込めないので、紙の本を購入して自炊。もしくは自炊サービスに向かってAmazonから直接本を送り付ける。Google NotebookLMにPDFをアップロードする
Google NotebookLMはまだプレビュー版だけど、無料で書籍PDFをアップロードしてAIに読ませてRAGにすることができる。NotebookLMのチャットインターフェースで、本の要約を出させる
書籍のサマリを「中学生にもわかるレベルで」「なるべく専門的に」など、好きなテイストで出力してもらって要旨をつかむ。質問を投げかけて、対話を繰り返す
自分が知りたいこと(フォトリーディングの手法を活かすならば、あらかじめその本から得たいモノについての質問を考えておき、ここで尋ねてみるのがベスト)を聞くと、AIが書籍内容を踏まえて答えてくれる。「内容をまとめて」以上の具体的な質問を準備しておく方が理解が深まるのと、NotebookLMはRAGとして機能するので、本に書いていないことを適当に答えてくるようなことがないので助かる。必要ならPDFの原文を開き、深堀りする
興味が出た部分は原文を確認して「元ネタ」をチェック。納得いくまで質疑と原文チェックを繰り返す。サマリをマインドマップ化&Notionに保存
気が済んだらw、読書の「歯止め」としてAIに出力させた要約をマークダウン形式に変換し、たとえばMapifyというサービスでマインドマップにする。さらにChrome拡張機能のSave-to-Notionで書籍の基本情報(カバー画像とか著者・出版社とかね)をデータベースに送り込み、マインドマップや簡単な感想、評価コメントと共に保存して終了。
いやもう、僕の中では「これは新時代のフォトリーディングじゃないか!」と興奮してしまったわけで。目的がはっきりしている本なら、まさに「拾い読み」の自動化だし、マインドマップ化というアウトプット作業まで、一気に片づけられる。これは最高の読書体験だと思う。
調子に乗って、年始から1カ月で20冊以上の本を読破?してしまった。
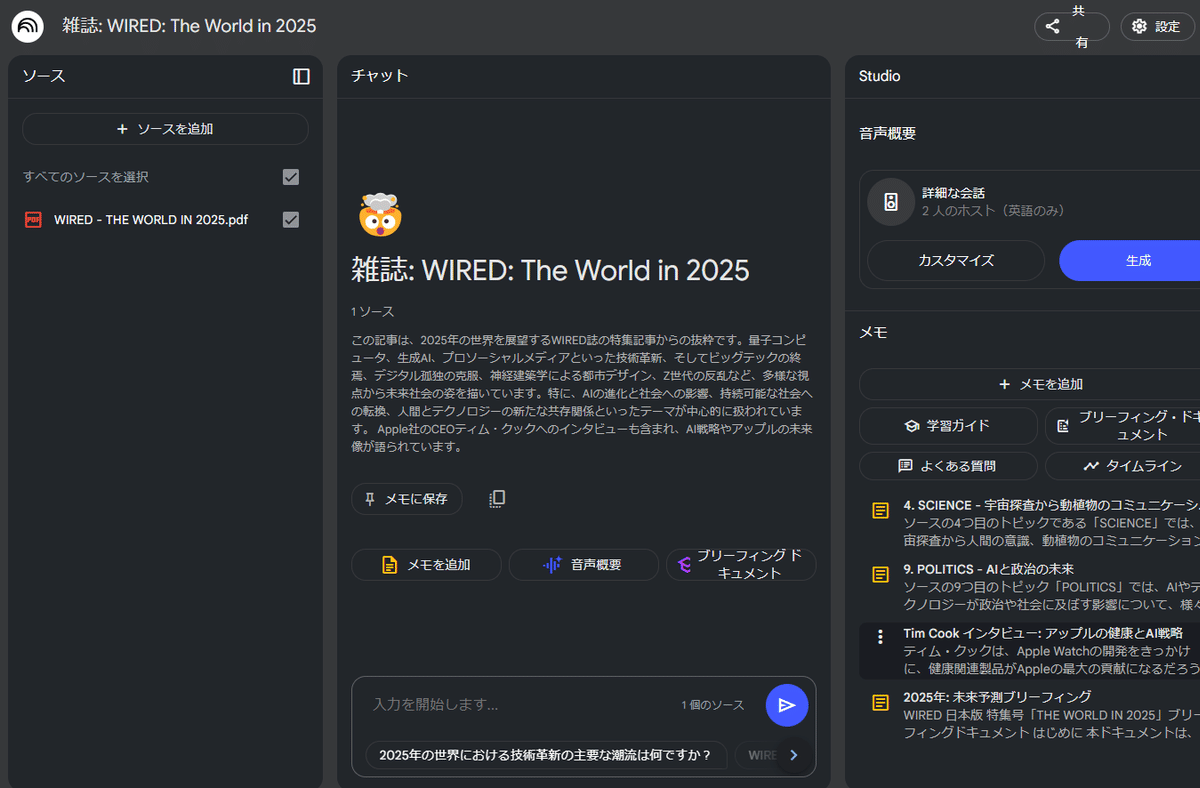


これまでのやり方と比べて何が嬉しい?
僕も以前から、紙の本を使うにせよPDF版を使うにせよ、なんとなく目次を見て拾い読みしながら必要箇所をかいつまんでいた。だけど、今回の方法はやはり圧倒的に便利だ。たとえば、こんなところが優れている。
複数の書籍を一度にまとめて相手(RAG)にできる
たとえば関連する2〜3冊の本をまるごとAIに突っ込んで、「このテーマについて各著者はどう言ってるか?」とQ&A形式で答えてもらうことも可能だ。洋書でも日本語で中身が読める
テック系の書籍とかって、分野によっては最新は洋書で、みたいなところがありますが、洋書のPDFをアップロードすれば、日本語で要点の引き出しから、詳細な読み込無しまでできる。これなら英語が苦手でも腰が引けなくて済む。紙をめくらないので、本が積み上がらない
物理的に場所をとらないし、読み終わった本を置き場所に困ることもない。紙の本も好きだけれど、実用だけを考えるとデジタルが断然ラクだ。アウトプットに流用しやすい
結果をそのままサマリとして保存しておけば、あとで自分の資料作成なんかにも使える。これが紙ベースだと、付箋貼っておしまい、みたいになりがちだ。
まとめ
そんなわけで、僕にとっては「フォトリーディング的なコンセプト」と「生成AIツール」が組み合わさることで、読書体験ががらっと変わった。しかもNotebookLMは今のところ無料で使えるし、ChatGPTなど他の生成AIだって、PDFの内容を上手に読み込ませる方法(いわゆるプロンプト設計)を工夫すれば、ほとんど同じようなことが実現できると思う。
目的を持った読書で「必要な情報を最短で手に入れる」ことに加え、僕は結果をNotionに蓄積しておくのが最近のマイブームだ。マインドマップも添付しておけば、後から復習するときに相当見やすいし、「あれ、この本のどこに書いてあったっけ?」というのがすぐにわかるようになった。個人的には、これが年末年始の大きな収穫だったと思う。
もちろん、冒頭に書いた通り、小説やエッセイなんかを「じっくり味わって読む時間」を否定するつもりは毛頭ない。それはそれで、紙の本やiPadをパラパラとめくりながらコーヒー片手にのんびり読むのが正解。でも、やっぱり仕事や実用目的で読む書籍は、できるだけ効率よく知識を吸収したいもの。そんな時にこのAI+デジタルツールの“読書体験アップデート”を取り入れてみると、結構面白い世界が広がるんじゃないかと思う。
というわけで、新しい読書体験を紹介してみた。興味を持った方はぜひ一度試してみてほしい。10年前、「怪しい速読セミナー」なんて言いながらフォトリーディングを受けていた自分が、まさかAIを使ってさらに進化させる日が来るとは思わなかった。これからも生成AIの発展とともに、読書の概念そのものがどんどん変わっていくんじゃないかな。
皆さんも、是非生成AIを使った読書スタイルにチャレンジしてみてはいかがだろうか。
(2025年1月25日)
参考URL:
関連記事:
