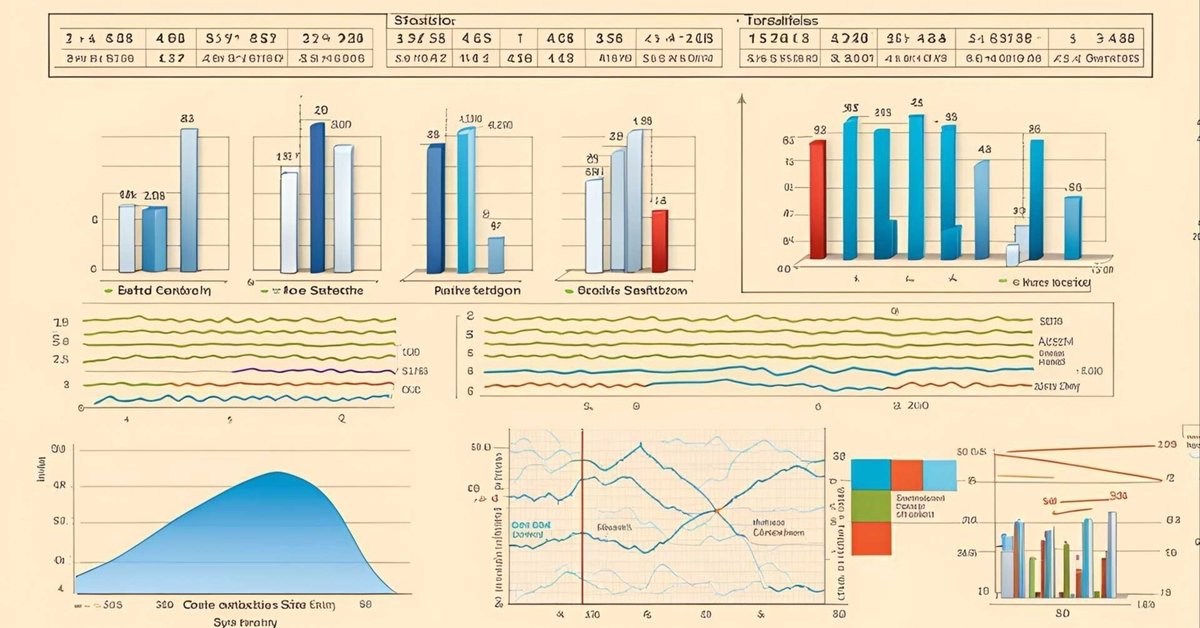
📕統計初学者が東大出版『統計学入門』(通称、赤本)を眺めて学び方を探る
おはようございます、 紅崎玲央です。
趣味で数検1級の学習と、統計学の学習に取り組んでいます。
【趣味の数学ノート】
— 紅崎玲央 Leo📚趣味の数学ノート (@leo_koo0130) November 23, 2023
noteで数学の学習記録を書き始めてから、数学がより楽しくなりました!
現在は数検1級〜準1級範囲をメインに学んでます。大人の数学の学びについてのトピックにも触れてます。毎週日曜更新。
趣味の数学ノート|紅崎玲央 Leo @leo_koo0130 #note https://t.co/6G7Y6JKqYA
先週から、統計学の学習をはじめました。「すうがくぶんか」さんの5ヶ月間の授業に途中参加して、いまは確率変数・確率分布についての授業を受けています。参加時期が遅くだいぶ遅れをとっているので、がんばります。
ここ1週間の学習記録はこちら。
ヘッダー画像はDream by Womboで制作しています。
Style:Dreamland v3
はじめに
今月から「すうがくぶんか」さん開催の「統計学入門【統計検定2級対応】」の集団授業を受けることになりました。
こちらの授業は東大出版『統計学入門(基礎統計学Ⅰ)』通称、赤本とよばれている書籍を題材にして、数学の前提知識があまりなくても統計学の基礎をじっくり学べるような授業と伺っています。
僕は今は統計を必要としていませんが、もしかすると仕事につながりそうな機会があるので、いずれ基礎から学びたいなとは思っていました。そんな時に学びたい内容・学習時期などちょうどタイミングが合ったため、途中からですが受講させていただくことになりました。
今回の記事では書籍『統計学入門』について調べたり冒頭を眺めたりしながら、この書籍を使った学び方を探っていきたいと思います。
書籍『統計学入門』について
東京大学出版の『統計学入門』(以下、赤本と呼びます)。初版は1991年ということでまあまあ古く、統計学を本格的に学ぶ際の王道であり良書として名前が挙げられています。
僕はまだなんとなくパラパラと眺めている程度ではあるものの、数式がしっかり使われつつ歴史や動機づけみたいなところも説明されており、現実の現象に即した例、練習問題が豊富にあるため、かなりやりごたえがありそうな書籍だなという印象です。
入門向けの本なのか?
こちらの書籍、タイトルに「入門」とありますが、本当に入門向けなのでしょうか?
ざっと調べてみた感じだと、全くの初心者が統計を学ぶ第一歩として取り組むには敷居が高そうな感じです。統計学の入門を一通り学んだ人が、さらに理解を深めたい時に読むと良い書籍、という位置付けで取り組むのが良いかもしれません。
また、数学の前提知識としては高校2年生(数検2級)レベルはあった方が良さそうです。数学の知識がなくても数式は読み飛ばすという読み方も不可能では無さそうですが、それなら別の入門書で学ぶ方が身になるのではないでしょうか。逆に大学数学レベルの前提知識までは無くても、読み進めることはできそうです。
入門者はどう読めば良さそう?
では統計を全くはじめて学ぶ入門者は、どう赤本を読めば良いでしょうか。これは①他の入門書から始める ②必要なところから少しずつ読んでいくのどちらかの方針をとるのがよさそうです。
①他の入門書から始める
赤本の紹介をしておいてなんですが、入門者はまず数学の前提知識がない方は数式の優しい入門書から始めるのが良さそうです。特に次の「必要なところ」「読み飛ばすところ」がそもそもわからない方は、急がば回れで他の本から学びましょう。
②必要なところから少しずつ読んでいく
それでも赤本を使って統計学に入門したい場合は、全てを理解しようとしないで必要なところから学んでいくのが良さそうです。たとえば冒頭の「本書の使い方」では「色々と深いことも書いてあるけどここは読み飛ばしてね〜」という著者の親切なメッセージがあり、学習の進め方の参考になること思います。
いかに、「本書の使い方」の内容をざっと恣意的に拾ってまとめてみました。
①対象は理系・部系の両方
・理系は全体が必要(7-8章は図表を中心にしてもよい)
・文系は1-4章、9章、11-13章が特に重要(5-6章は部分的に用語を拾えば良い。7-8章はとばしてもよい)
②数式にこだわらず図表をたどり大局をつかむという使い方もできる
③練習問題や現実的な実例が充実している
・できれは自力で解答するのが望ましい
・レベルの高いものは略解を見ながら学習するのも良い
文系、理系に限らず「統計をツールとして使いたい人が全体を俯瞰して知識を得るための使い方」もできますし「数学的な理解を深めるための使い方」もできる、いろんな読み方が書籍なのかなと感じます。
一方で、調べた情報の中には「赤本には余計なことが書かれていない、読み飛ばすところがない」という情報もあります。それほど統計学のエッセンスが詰まった書籍のようですね。
なかなか本格的な教科書なので、やはり本当の初心者にはハードルは高いのかもしれません。ですが良書という評価は非常に多い書籍なので、授業の力を借りて進められるのはすごくありがたいかもしれません。
書籍『統計学入門』の目次を眺めてみよう
では、このような書籍の読み方を踏まえて、赤本の目次を眺めてみましょう。
【目次】
第1章 統計学の基礎
第2章 1次元のデータ
第3章 2次元のデータ
第4章 確率
第5章 確率変数
第6章 確率分布
第7章 多次元の確率分布
第8章 大数の法則と中心極限定理
第9章 標本分布
第10章 正規分布からの標本
第11章 推定
第12章 仮説検定
第13章 回帰分析
第1章で統計学の歴史や概要をざっと知り、第2-3章で記述統計、第4章で確率を学びます。この辺りは統計学(推測統計)に本格的に入っていく前の心構えと前提知識を準備する、という感じでしょうか。
そして第5-6章で学ぶ確率変数や確率分布が、まず中盤の山場となります。そして第9-13章で推定や検定、そして回帰分析まで行うのが推測統計の本番みたいです。楽しみですね。
ちなみに第7-8章については、前項の「本書の使い方」で書かれていることを見るに、かなり込み入った難しい内容に触れるのかなと思います。入門の段階ではあまり深入りせずに、読み飛ばすか気軽に流し見しながら進めるのが良いように思いますね。
参考記事
赤本を使っての学び方を調べるにあたり、こちらの記事を大変参考にさせていただきました。
またこちらの記事では、赤本の各章末に記載されている問題の解答がまとめられているそうです。これはありがたいです。
おわりに
統計学の良書といわれる東大出版『統計学入門』通称、赤本について、この書籍を使った学び方を探ってみました。
まとめると赤本は、本当に統計学がわからない人がはじめて学ぶにはハードルが高いものの、基礎をしっかり身につけて本格的な統計学に「入門」するための書籍としてとても良さそうです。
僕は、第1章での統計の歴史的な話を読んでいてなんだかワクワクしましたね。すうがくぶんかさんの授業もわかりやすいので、これを機に楽しく統計に入門したいと思います。
