
プロフェッショナルが語るミネルバ式リーダーシッププログラムの魅力~斉藤 晴久氏のインタビュー~
プログラム講師にインタビューを実施しました。
ミネルバ式リーダーシッププログラム「Managing Complexity」では、講師をファカルティと呼んでいます。
現在26名在籍しているファカルティは皆、自身も複雑化する時代をリードする経験豊富なプロフェッショナル。ファカルティの存在がプログラムのクオリティを支えてくれています。
そんなファカルティがこのプログラムについて語る「ファカルティインタビュー」。第3回目は株式会社AnyWhere 代表取締役CEO 斉藤 晴久さん(Isaさん)にお話を伺いました。
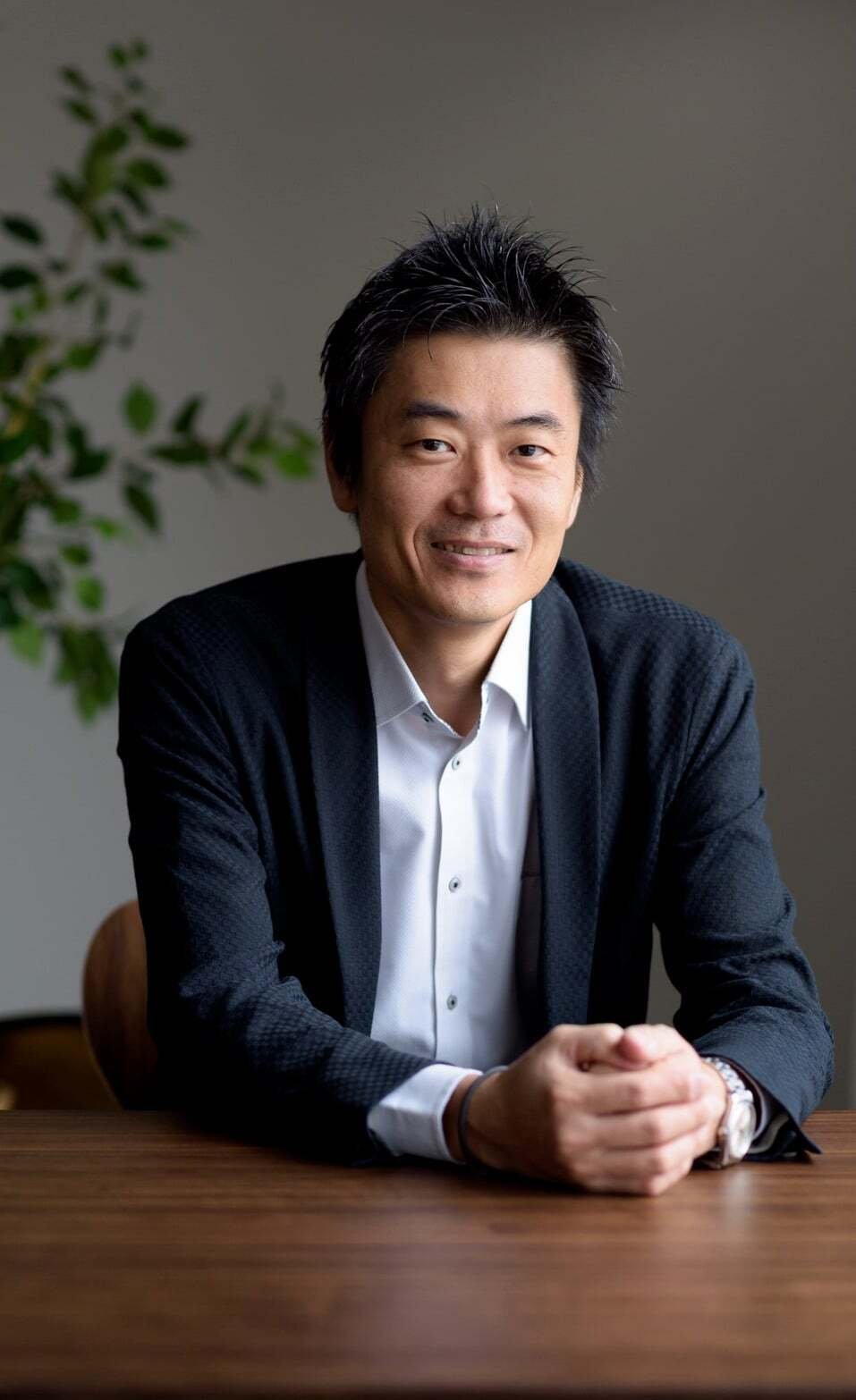
斉藤 晴久 Haruhisa Saito 株式会社AnyWhere 代表取締役CEO
一般社団法人コワーキングスペース協会 理事
SCSKにてERP導入コンサルティングに従事し、2007年にアマゾンジャパン入社。Amazon出品サービスの日本事業立ち上げに貢献。2015年スペースマーケットにて、創業期の事業成長を牽引。その後数社を経て、2020年AnyWhereを創業。働き方や空間コンサルティング、システム開発、ワークプレイスプラットフォームTeamPlaceを運営し、豊かな働き方実現のサポートを行う。早稲田大学商学部卒。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q1. ファカルティになられた動機、またファカルティとしてこのプログラムについて魅力を感じるポイントをお聞かせください。
斉藤:今まで日系、外資、ベンチャー、起業と一通りの経験をしてきました。規模も数人から数万人、組織の立ち上げからスケールまでと、社会人としての経験をしてきた中、改めて学び直しの機会を模索していたところで、ファカルティの機会をご紹介いただきました。
Flipped Learning(※)やともに学ぶ姿勢など、まさに自分が求めていた「これだ!」と思うプログラムでした。これから多くの方とセッションをご一緒できることが魅力的で、何より自分が一番学びの機会をいただけることが楽しみです。
※Flipped Learning=反転学習。ミネルバ式リーダーシッププログラムでは、全ての授業をFlipped Learningで行います。
Q2. ファカルティトレーニングを終えて、または実際にプログラムを教えられて、ご自身の考えや行動に変化はありますか?
斉藤:ミーティングの進行に関して、参加するメンバーが極力参加できるよう、より意識してファシリテーションするようになりました。またFlipped Learningの形で事前に考えておき、当日の議論をより活発化できるように進行を変えていっています。
Q3. ビジネスの最前線を知る立場から、どのような場面でこのプログラムの学びが実践に活きると思いますか?ご自身の体験もあれば、教えてください。
斉藤:外資で働いていた時、グローバルなチームで国籍もバックグラウンドも様々でした。当時は体系的に学ぶ機会が少なく、ただがむしゃらに日々日々を対応していました。
もしこのプログラムの学びができていたら、より効果的なチームワークや組織運営ができていたのではと感じます。
理由としては、多様なメンバーへの共感やシステム思考の視点を取り入れる力が活用でき、課題の本質を捉えやすくなり、短絡的な意思決定を防げたのではないかと思うからです。多国籍なメンバーや不確実性を伴う場面でも柔軟に対応し、チームの力を最大限に引き出すリーダーシップが発揮できていたのでは、とも考えます。
私のこれまでの経験を通じても、活動や顧客とのプロジェクトにおいて、全ては複雑性の中にあり、不確実性を受け入れるアダプティブリーダーシップの重要性を感じています。ナビゲート、共感、自己修正、ウィンウィンの特性を意識し、チームの能力をいかに引き出していけるかを念頭に活動しています。
Q4. このプログラムを通じて、どんな人にどのような変化が起きることを期待しますか。
斉藤:様々なセッションを通じてともに考える内容は、自分のチーム活動で実践や応用のできることが多いと思います。それによりチーム活動がより円滑になりチームの能力が上がり、チームメンバーもプログラムに参加される流れができ、みながそれぞれリーダーとして活動する流れができることを期待しています。
Q5. 実際の参加者の変容例で印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
斉藤:同じ企業内で受講生が複数いる場合に、事前に社内で予習を一緒にやることで今まで接点のなかった社内での交流が生まれたり、また社内の受講者が増えていき、共通言語が話せる社内メンバーが増えて会話の質が上がったという声を伺いました。
どのように浸透させていくかがとても大事な要素だと思っていたので、とても良い流れだと感じました。
Q6. Isaさんにとっての理想のLearnerとは誰でしょうか?その方のどんなエピソードから理想とされているのでしょうか?
斉藤:私にとっての理想のLearnerは、常に新しい知識を追求し、自らの学びを他者の成長に繋げる人物です。
例えば、アメリカの教育者ジョン・デューイのエピソードが挙げられます。彼は教育を「経験と社会の架け橋」と捉え、実践を通じた学びを提唱しました。
デューイのように、自分の学びが他者や社会全体の発展に寄与する姿勢が、自分や周りの時間を豊かにする、私の理想とする学びの在り方です
Q7. Isaさんにとっての「学ぶ」とは何でしょうか?
斉藤:私にとって「学ぶ」とは、自分自身を知り、世界を深く理解し、それを通じて成長し続けるプロセスです。
学びは単なる知識の蓄積ではなく、実践や経験を通じて他者と関わり合いながら意味を構築していくことだと考えます。
このプロセスは、個人の成長のみならず、社会に新しい価値を生み出す原動力でもあります。
Q8. 株式会社Learner's Learnerでは、Managing Complexityを通じて適応型リーダーシップを広めていくことで、世の中のリーダーシップの在り方を変え、教育にも影響を与えていきたいと考えています。Isaさんのご意見をお聞かせください。
斉藤:世の中は複雑であるということを理解した上で、どのようにしなやかに物事を捉えて対処していくのかが、これからの時代に大変重要なことだと思っています。
そのためには他者の理解、自分との対話など、いかに「問い」を立てられるのかが大事で、この「Managing Complexity」を広めることで、すべてを自分事として捉え、自ら問いを立てて考えていける人材が増えていくと強く感じています。
複雑性への理解は、教育やリーダーシップにおいて不可欠な要素です。それを体系化し実践に落とし込むことで、個人と組織の変革が可能になります。
Learner’s Learnerの取り組みが、新たなリーダー像を描き出し、日本の教育にも革新をもたらすことを期待しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(編集後記)
学びの質を高めるには安全・安心の土台が欠かせません。Isaさんは動じない。焦らない。ゆっくりと自分のペースに引き込み、対話モードを場にもたらしてくれます。“人” でつながる仕事場のサブスクリプションプラットフォームを世に生み出したIsaさんだからこそ作れるのでしょうか。
Isaさん、ありがとうございました!
