
第25回 「System of a Down - Prison Song」の思ひ出
「ホルモンはシステムのパクリ」
「いや、確かに影響は受けているが、恋のメガラバはシステムを超えている。あれはシステムには作れない」
「システム知らずにホルモン語ってる奴はニワカ」
マキシマム ザ ホルモンについてインターネットで調べていると、必ず遭遇するワードがあった。
System of a Down
いわゆる「洋楽」というやつで、どうやらマキシマム ザ ホルモンはこのバンドから多大なる影響を受けているらしい。そういえば、マキシマムザ亮君もこのバンドについて言及していたような。

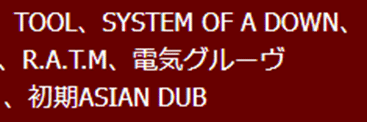
ハケ━━(σ゚∀゚)σ━━ン!!
マキシマムザ亮君も「好音」のひとつとして挙げており、これを知らずにホルモンを語るのはニワカだというのであれば、さっそく聴いてみるしかないだろう。
TSUTAYAの視聴コーナーへGO!
重低音の効いたギターサウンド、デスボイスの多様(英語圏ではグロウルやスクリームと呼ばれるゾ☆)、変態的なツイン・ボーカルの掛け合わせ、緩急のある変則的な展開、言葉遊びや発音へのこだわり、ヘヴィネス一辺倒ではないメロディアスなポップさ、リスナーに訴えかけるポリティカルなテーマ……確かに、これがホルモンの元ネタのひとつであることは間違いないようだ。ただ、ホルモンは基本的にパンク・ロックと歌謡曲をルーツとしており、システムよりもパンキッシュで歌謡的なサウンドを奏でているので、「パクリ」とまでは思わなかったが、これを知らずしてホルモンを語ることは許されないというのはその通りだと感じた。
要するに……
超カッケェ!!!!!
最も好きなアーティストが最も好きなアーティストなのだから、おれも好きでないわけがない。好きなアーティストが好きなアーティストを聴くのは、音楽をディグるうえでの基本中の基本である。ただし、「システムってヘヴィーでノリノリでいいよね」といったふうに、音楽の表面だけを掠め取るような聴き方は許されない。なぜなら、マキシマムザ亮君は「おれが楽曲に込めた深い意義を汲み取ろうとせず、表面だけをアッサリ消費するような連中に褒められても嬉しくない!」といったスタンスで活動しており、おれはその薫陶を受けていたからだ。
「音楽で大事なのは音楽なのだから、歌詞なんか聴かなくてもいい。おれは洋楽が好きだけど、外国語はただのサウンドとして聴いている」
こういったスタンスのリスナーは多いが、おれはこのような考え方にはあまり同意しない。確かに、言語の壁を越えることができるのが音楽の良いところであるし、別に我々は「メッセージ性」のようなものを求めて音楽を聴いているわけではない。そもそも歌詞をあまり重視していないアーティストも多いし、リズムとメロディーとサウンドによって人間の新たな扉を開くことそのものが、音楽の持つ「メッセージ性」の核心であるとも言える。
だが、こうした考え方は「音楽」と「詩」を分離して捉えすぎており、偏狭な認識であると言わざるを得ない。たとえナンセンスで「メッセージ性」が皆無であるような歌詞であったとしても、歌がある限りそこには言葉がある。ナンセンスな言葉の選び方や配列の仕方にもその人の言語的センスが試され、それによって音楽が与える体験の質は大きく変わってくるのである。まったく意味不明であったとしても、なんだか良い感じの気分になれる日本語の歌、なんだか不思議な気分になれる日本語の歌、というものを誰しも体験したことがあるだろう。別に歌詞を知らなくても音楽を楽しむことはできるが、言葉を理解したうえで歌を聴いたほうがより深く音楽を楽しむことができるのだから、余力があるなら歌詞を知る努力をしたほうがいいに決まっている。日本語の歌だけを聴く人よりも、サウンドを重視して洋楽を聴く人のほうが「音楽好き」というイメージがあるかもしれないが、これは一面的な見方である。好きな楽曲を骨の髄までしゃぶり尽くして楽しもうとしているのはどちらか、という観点からすれば、前者のほうが「音楽好き」であるとも言える。言葉を理解したほうがより楽しめるのに、その道をあえて放棄しようというのであれば、その「好き」は「そこそこ好き」という程度に留まるだろう。
また、中には「メッセージ性」を無視することができないような楽曲も存在する。いわゆる「レベル・ミュージック」というやつで、音楽には歴史的に自由や正義を求めるための強力な武器として用いられてきた側面がある。たとえば、ブッシュ政権への批判が込められた楽曲を、ブッシュの熱烈な支持者が意味も分からずに「大好きな曲だ!」と言っていたら、流石に間抜けすぎるだろう。差別のない平等な社会の実現を願う楽曲を、韓国人がどうのクルド人がどうのと害毒を撒き散らしている人間が、意味も分からずに「この曲ってノリノリで良いよね~」などと言っていたりすれば、お前はいったいこの曲のなにを聴いているんだと言いたくなるだろう。まあ、人を殺そうがなにをしようが究極的には人間は自由であるという観点からすれば、楽曲の持つ「メッセージ性」を捨象して音楽を己の快楽のために利用することもまた自由ではあるのだが、そんな程度の低いクソみたいな自由を堂々と誇られても困る。
さて、当該のシステム・オブ・ア・ダウンについても、歌詞を無視することが難しいアーティストのひとつであると言ってよいだろう。2020年にナゴルノ・カラバフ紛争が勃発した際には、祖国アルメニアの窮状を世に訴えるために15年ぶりの新曲を緊急リリースしたことからも分かるように、彼らの作品の中にはその「メッセージ性」を無視してはいけない楽曲が確実に存在する。もちろん、システムは政治的なだけではなく、バカバカしくて笑える要素もあるユーモラスなバンドなので、すべての楽曲を正座して生真面目に聴く必要はないが、政治的ではない部分に関しても言葉遊びや発音の面白さが含まれているわけだから、やはり原詩を理解したうえで聴いたほうがより楽しめることに違いはない。
というわけなので、さっそくCDに付属している対訳を見ながら「Prison Song」を聴いてみる。
うーん
さっぱり分からん\(^o^)/オワタ
いや、もちろんリテラルな意味は分かる。要するに「刑務所がたくさん作られていて、たくさんの人が収監されているよ」ということを歌っているのだが、なぜそれが問題であるのかが分からないのだ。だって、刑務所って悪いことをした人たちが収監されるところでしょ? 悪い人たちが捕まることのなにが問題なの?
中学3年の時点では、刑事司法に対してこのような素朴な印象しか抱いていなかったことを思い返してみると、日本でなかなか刑事司法改革が進まないのも、うべなるかなという気がしてくる。昨年、冤罪によって死刑判決を受けていた袴田巌さんが、逮捕から58年の時を経てようやく無罪判決を勝ち取ったことからも分かるように、日本においては前近代的な司法制度を如何にして改革するかということが最重要課題のひとつとなっている。しかし、「司法って犯罪者の話でしょ? おれは犯罪者じゃないから関係ないよ」というのが市民の素朴な感覚である。近代司法の理念はにわかには理解しがたいものであるので、これは義務教育でしっかりと教えるしかないのだが、おそらく公民を担当する教師さえ近代司法の理念を理解していないのが実情である。ならば、多くの市民が「司法? なにそれ美味しいの?」となってしまうのも致し方ないのだろう。
こうして「よく分かんない歌詞だなあ」と長らく放置していたのだが、10年後にNetflixで以下のドキュメンタリー映画を見た瞬間、「あ、これPrison Songのことだ!」とたちどころにすべてが分かってしまった。

せっかくなので、今回は映画『13th』を参照しながら「Prison Song」の歌詞を解説していこう。まあ、実際にNetflixで『13th』を鑑賞すれば誰でも分かる話なので、わざわざおれが解説する必要などないのだが、ワイも乗りたいんや、大考察時代のビッグ・ウェーブに。
13thの要約
1865年、アメリカ南北戦争は奴隷制に反対する北軍の勝利に終わり、憲法第13条の修正案が可決され奴隷制は廃止された。こうして人種に関係なく「すべてのアメリカ人」に平等な自由が与えられたわけだが、条文をよく読んでみると、この修正案には実は抜け穴があることに気づく。
第1節 奴隷及び本人の意に反する労役は、当事者が犯罪に対する刑罰として正当に有罪の宣告を受けた場合以外は、合衆国内又はその管轄に属するいかなる地域内にも存在してはならない。
第2節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条の規定を施行する権限を有する。
この抜け穴はすぐに利用された。南部の経済は黒人の奴隷労働に依存していたため、もともと「所有物」に過ぎなかった400万人の労働力が急に「自由な市民」になってしまうことは、ビジネス上の大きな打撃であった。そこで南部の各地では、「徘徊」や「浮浪」などを理由として黒人を大量に逮捕し、再び奴隷として労働させるという事態が発生した。なぜなら奴隷労働を禁止されているのは「犯罪者を除くアメリカ人」であり、「犯罪者」であれば奴隷労働をさせてもよいと修正条項に記載されているからだ。
だが、次第にこうした「囚人貸出制度」の存続が困難になってくる。すると、それは「ジム・クロウ法」と呼ばれる一連の人種隔離政策に取って代わられ、黒人は「安価な労働力を提供するが政治的な発言権を持たない二級市民」の地位へと「合法的」に追いやられた。「隔離は差別ではない」という理屈によって理不尽な差別は正当化され、それに違反する者は「犯罪者」として扱われたのである。こうした差別的な制度の下支えとなったのは、「黒人は抑制が効かず暴力的で危険な存在である」という差別的なステレオタイプであり、特にKKKをヒロイックに描いた1915年の映画『國民の創世』が与えた影響は計り知れず、南部では罪なき黒人が暴徒によってリンチされ殺される事件が多発した。こうした奴隷解放後も続いている人種差別を撤廃するため、1950年代後半から公民権運動と呼ばれる黒人の解放運動が始まった。その成果は1964年に公民権法として結実し、1865年の奴隷解放から100年の時を経てようやく真の平等が実現したかに思えた。
だが、こうした動きを快く思わないレイシストたちによってバックラッシュが起こる。それには犯罪者数が増加しているという統計が利用された。実際のところ、これはベビー・ブーマーたちが成人したことによる人口動態の変化が原因に過ぎなかったのだが、レイシストたちは「公民権運動によって犯罪者数が増加している。黒人を自由にすると大変なことになるぞ」という根拠のない恐怖を世間に流布した。時の大統領であるリチャード・ニクソンは「法と秩序」を建前として「犯罪との戦争」を宣言したが、これは今で言うところの「犬笛」であり、実質的には60年代に起こった様々な社会運動への反撃を意味していた。「犯罪との戦争」において主な標的とされたのは「薬物問題」であり、ドラッグ中毒は「健康問題」ではなく「犯罪問題」として扱われるようになった。マリファナの単純所持などの軽微な犯罪によって黒人は次々と刑務所に収監されていき、1970年に35万人だった囚人の数は、1980年には51万人にまで増加する。
それをさらに推し進めたのが、80年代のロナルド・レーガン政権だ。レーガンは「War on Drugs」というスローガンのもと、貧しい黒人コミュニティーの間で広まっていた「クラック・コカイン」を標的として定める。これは吸引できる新しいタイプの安価なコカインであり、5gのクラックを所持していると、それは従来の粉状のコカイン500gの所持と同等の罪の重さになった。量刑には強制的最低量刑(Mandatory Minimum Sentences)が適用され、犯罪が行われた背景は裁判で一切考慮されず、仮釈放なしの5年の最低量刑が課された。「War on Drugs」とは、実質的には人種的マイノリティーとの戦争であり、貧困層との戦争だったのだ。黒人たちが逮捕される様子はテレビで過剰に報道され、「黒人=犯罪者」というステレオタイプはますます強化されていく。こうして刑務所に収監される囚人の数は、1985年の時点で75万人へ、1990年の時点で117万人へと急速に膨れ上がっていく。
このような共和党政権下における薬物犯罪への厳しい取り締まりは、民主党への政権交代が起こっても引き継がれた。すでに「危険な犯罪者どもは刑務所に収監しろ!」という風潮が広まっており、「犯罪者に甘い」ような政治家は当選することが難しくなっていたからだ。こうして1994年に、ビル・クリントン政権のもとで「スリー・ストライクス法」が制定される。これは過去に「重罪」で2回の有罪判決を受けている者が新たな罪を犯した場合、問答無用で終身刑にするという法律であり、もちろん薬物犯罪にも適用された。囚人の数は増加の一途をたどり、2000年にはついに201万人に達する。すると刑務所が足りなくなってくるので、次々と新たな刑務所が作られていった。
その一翼を担ったのが、監獄ビジネスを展開する私企業だ。監獄ビジネスが最大の利益を得るためには、常に刑務所を満員にする必要があるので、監獄企業はロビー団体と協働して囚人がより増加するような法律の制定を推し進めてきた。こうした監獄ビジネスの恩恵を受けるのは、刑務所を運営する企業だけではない。たとえば、電話会社は囚人が刑務所から利用する電話に多額の料金を課すことで利益を生み出し、あらゆる製造業者は囚人を安価な労働力として酷使することで利益を生み出すことができた。そのビジネスの餌食となるのは貧しい人々だ。豊かな人々は罪を犯しても保釈金を払うことで拘束を免れることができるが、貧しい人々は無実の罪で捕まっても保釈金を払えずに収監されてしまうのである。検察官からは「罪を認めるなら3年で勘弁してやるが、裁判を起こす気なら30年ぶち込んでやるぞ」などと脅されるので、たとえ無実であったとしても、ほとんどの囚人は裁判で闘うことを断念して司法取引に応じてしまう。「裁判を受ける権利」は最も重要な人権のひとつだが、そんなものは名ばかりで実質的にはそうした権利など存在しないのだ。こうした刑務所が生み出す利権に群がる組織たちの総体は「産獄複合体」と呼ばれる。薬物使用者たちが本当に必要としているのは適切な医療や教育であるのに、実際に与えられるのは狭いケージの中での人間以下の生活であり、出所しても「元犯罪者」として様々な権利を剥奪されるため、まともな市民としての生活は送ることは不可能となる。
このように、かつて「囚人貸出制度」や「ジム・クロウ法」として存在した差別的な政策は、異なる形で蘇り続け、現在も存続しているのだ。黒人がアメリカの人口に占める割合は6.5%であるにもかかわらず、全囚人に占める黒人の割合は40%となっている。そして、憲法修正第13条に定められている通り、奴隷扱いを受けない権利を有しているのは「犯罪者以外」の人間だけであり、ひとたび「犯罪者」になれば、彼ら彼女らは奴隷として搾取されることになるのである。
歌詞解説
Following the rights movements, you clamped down with your iron fists
Drugs became conveniently available for all the kids
公民権運動の後、政府は強権的な方法で取り締まりを強化した
ドラッグの入手は容易になり子どもたちでさえ利用できるようになった
公民権法の制定によって真の自由と平等が実現されたわけではなく、「War on Drugs」という名目で人種的マイノリティーへの抑圧が続いたことは先に説明した通りだ。もともとコカインは高価で裕福な層でなければ利用できなかったが、80年代になると安価で即効性のある吸引タイプのコカインが登場する。
I buy my crack, my smack, my bitch
Right here in Hollywood
おれはクラックを、ヘロインを、そして女を買う
ここハリウッドで
それが「クラック・コカイン」である。クラックは都市部の貧困層や黒人コミュニティーの間で瞬く間に広まり、ロサンゼルスはその中心地のひとつとなった。クラックが黒人コミュニティーを破壊していく当時の状況を描いた作品としては、アカデミー作品賞を獲得した2016年の映画『ムーンライト』がある。
Nearly two million Americans are incarcerated
In the prison system, prison system of the U.S
約200万のアメリカ人が刑務所に収監されている
このアメリカの監獄システムの中で
The percentage of Americans in the prison system
Prison system has doubled since 1985
監獄システムの中に収監されているアメリカ人の割合は
1985年から2倍になった
『13th』で示された統計によれば、1985年の時点で75万人が、2000年の時点で201万人が刑務所に収監されているということだった。人口に占める割合で言えば、それぞれ0.3%と0.7%になる。この楽曲が発表されたのは2001年なので、だいたい2倍になっている。もちろんこれは、今までと比べて悪い人間が2倍に増えたからでも、それまで野放しになっていた犯罪者を2倍検挙できるようになったからでもない。公民権運動へのバックラッシュとして、囚人がたった15年で2倍以上に増えてしまうような異常な監獄システムが構築されてきたからだ。このあたりはピンと来ない人も多いかもしれないが、「法」も「犯罪者」も人間が作り出した構築物に過ぎないということは肝に銘じておいたほうがよいだろう。たとえば「明日から我が国では飲酒を違法とします」ということになれば、日本人の大半は明日から犯罪者になるのである。
Minor drug offenders fill your prisons, you don't even flinch
All our taxes paying for your wars against the new non-rich
軽微な薬物犯罪者が刑務所を埋め尽くしても、お前たちは尻込みしない
我々の税金はお前たちの新しい貧困層との戦争に使われる
レーガン政権は貧困層や黒人コミュニティーの間で蔓延していたクラックを狙い撃ちにし、単純所持のような軽微な犯罪者であっても次々と刑務所へ収監していった。「War on Drugs」というスローガンの正体は、貧困層との新たな戦争だったのであり、それには大量の税金が注ぎ込まれたのである。
They're tryna build a prison
For you and me to live in
奴らは刑務所を作ろうとしている
お前とおれを住まわせるために
こうして、次々と新たな刑務所が作られていくことになる。政治家は「犯罪者を徹底的に取り締まる」という断固とした姿勢によって票を獲得し、刑務所の運営や囚人の労働に関わる私企業はそこから莫大な利益を獲得した。「産獄複合体」の批判が難しいのは、それに多くのステイク・ホルダーが関わっているからである。
All research and successful drug policy
Shows that treatment should be increased
And law enforcement decreased
While abolishing mandatory minimum sentences
すべての研究と成功した薬物政策は、治療こそ増やすべきだと示している
そして法の執行を減らすと同時に、強制的最低量刑は廃止すべきだと
現代の薬物政策においては、薬物使用を厳罰化の対象としないことが国際的なトレンドとなっている。当たり前の話だが、薬物中毒に陥っている者が必要としているのは、刑務所に閉じ込られることではなく、薬物による悪影響を減少させるためのトータルな支援だからだ。このようなアプローチは「ハーム・リダクション(害の低減)」と呼ばれる。こうした最新のトレンドからすれば、薬物使用者に問答無用で厳罰を与える「強制的最低量刑」の制度などはもってのほかである。ちなみに現在は、オバマ政権下で制定された「2010年公正刑罰法」によって「強制的最低量刑」は廃止されている。
Utilizing drugs to pay for secret wars around the world
Drugs are now your global policy, now you police the globe
世界中の秘密の戦争の資金源として薬物が利用されている
薬物は今やグローバル政策であり、それで世界を取り締まることができる
『13th』にはこのあたりの話は出てこなかったが、これはおそらく、1980年代にアメリカがニカラグアの共産主義政権と闘う反政府組織「コントラ」を秘密裏に支援していたことに言及している。コントラが資金源を得るために行っていた麻薬取引をアメリカが黙認したため、主要商品であるコカインがアメリカ国内に流入したという疑惑があるのだ。また「War on Drugs」という名目でアメリカは他国に介入した例としては、1989年のパナマ侵攻などがある。薬物政策はもはや治安維持の範囲を超え、政治的・経済的利益の追求や、地政学的パワーゲームのために利用されているのだ。
以上が「Prison Song」の歌詞の内容になるが、あくまで『13th』と「Prison Song」はこのような認識を共有しているという話なので、細かい事実関係については各自でご判断を願いたい。
さて、司法の問題は日本も他人ごとではない。アメリカの薬物問題においては、長期勾留されるリスクを恐れて多くの者が無実の罪を認めてしまうということを書いたが、日本においても「人質司法」は深刻な問題となっている。先に挙げた袴田事件において、袴田巌さんが無実の罪を認めてしまったのは、長時間の拘束と尋問による事実上の拷問が原因であった。そしてこれは今とは無関係な「昭和」の話ではない。2012年の「パソコン遠隔操作事件」では、遠隔操作によって犯罪予告の書き込みをさせられた4人が誤認逮捕されたが、なんとそのうちの2人は「自白」によって無実の罪を認めている。無実の人間が4人いれば2人が「自白」をしてしまう国、それが日本という国なのだ。2020年の「大川原化工機事件」では、無実の罪で拘束された会社幹部のうちのひとりが、医療を受けさせてもらえず死亡するという事件が起こっているし、「人質司法」の違法性を巡っては、贈賄罪の疑いで7ヵ月間も不当に拘束された角川歴彦が現在進行形で訴訟を起こしている最中だ。こうした人質司法の問題については、2007年の映画『それでもボクはやってない』がドラマを通じて詳細に描いている。
最後に、『13th』は次のような印象深い言葉で締めくくられる。
人々はいつも次のように言う。
「どうして昔の人々は奴隷制度など許容することができたのか、とても理解できない。どうしてそんなものと折り合いをつけることができたのか? どうして人々はリンチを見に行き、それに加わることができたのか? どうして人々は人種隔離を合理的だと思うことができたのか? 白人専用や有色人専用の水飲み場など、どうかしている。もし私がその時代を生きていれば、そんなものは絶対に許容しなかっただろう」
だが真実は、私たちはまさに「その時代」を生きており、それを許容し続けているのだ。
おわり
