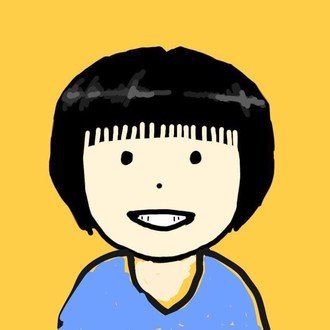Photo by
ia19200102
好奇心と疑問を持つだけで、クラシック音楽の歴史がわかるエラい時代
今日は「好奇心と疑問を持つだけで、なんでも学べるエラい時代になった」ってお話です。
なぜクラシックには「調性」がタイトルに入ってるのか?
長男は、突然、クラシック音楽にハマっています。
我が家は、夫婦共々クラシックオタクです。大学のオーケストラで知り合っています。しかし、クラシックは他人に押し付けるとまず100パーセント嫌がられる趣味。
この機会を待っていた感じです。
「いろいろ聞かせて」と言うので、一緒にモーツァルトからロマン派、現代音楽まで一通り、スコアをみながら聞いてみました(今はネットでフルスコアが見られるんです!!)。
モーツァルト交響曲31番「パリ」交響曲40番
ベートーヴェン 交響曲2番ニ長調 交響曲9番ニ短調
ブラームス 交響曲3番ヘ長調、4番ホ短調
マーラー 交響曲7番「夜の歌」
ブルックナー 交響曲9番
サン・サーンス 交響曲3番「オルガン」
ラヴェル ピアノ協奏曲ト長調
メシアン トゥランガリラ交響曲
ガーシュイン「ラプソディ・イン・ブルー」
などなど。翌日は夫がストラヴィンスキー「火の鳥」、マーラー交響曲9番を聞かせてました。
長男はとくにマーラーが気に入ったようです。そして、「なんでクラシック音楽は題名にホ短調とかニ長調とか、わざわざ調性を入れるのか?」と言い出しました。
確かに!
なんだか「調」が他のジャンルに比べて特別扱いされている。
そんなに調性って大事なんだろうか?
そういえば、ハ長調は単純な感じがするし、変ロ長調は不思議な感じがする。
だからかな??
調性には「色がある」という説
調べてみると、吉松隆さんの面白い文章に出会いました。
でも、クラシックの場合は、「作品」の性格がその「キイ(調性)」によって決定されている…と言って良いほど、「作品」と「調」は密接な関係にある。 作曲家は、「絶対このキイでなければならない」と念じて作曲し、作品はその調以外のキイではあり得ない「宿命」を持って生まれてくるような気さえする。
昔から、「調性」にはそれぞれ「色」があると言われてきた。 例えば、ハ長調なら「白」、ト長調なら「青」、ニ長調は「緑」などなど。人によっては「薄い緑色」とか「淡い黄色」とか、「透明なブルー」とかいろいろな感じ方があるようで、音階は虹のような色合いに満ちている。 確かに、音階(スケール)というのは虹の七色と同じく7音で出来ているし、そこに「色」を感じるのは当然のようにも思える。 長調の音階が「自然倍音」に近いため「明るく」「澄んだ」「鮮やかな」印象を与え、対して短調の音階が(短三度という)「微かな不協和音」を含むため「悲しい」「暗い」「くすんだ」印象を与えるのも、理にかなっている。
そして調性には実は時代によって流行があるようです。
ここから先は
743字
この記事のみ
¥
100
期間限定!PayPayで支払うと抽選でお得
これまで数百件を超えるサポート、ありがとうございました。今は500円のマガジンの定期購読者が750人を超えました。お気持ちだけで嬉しいです。文章を読んで元気になっていただければ。