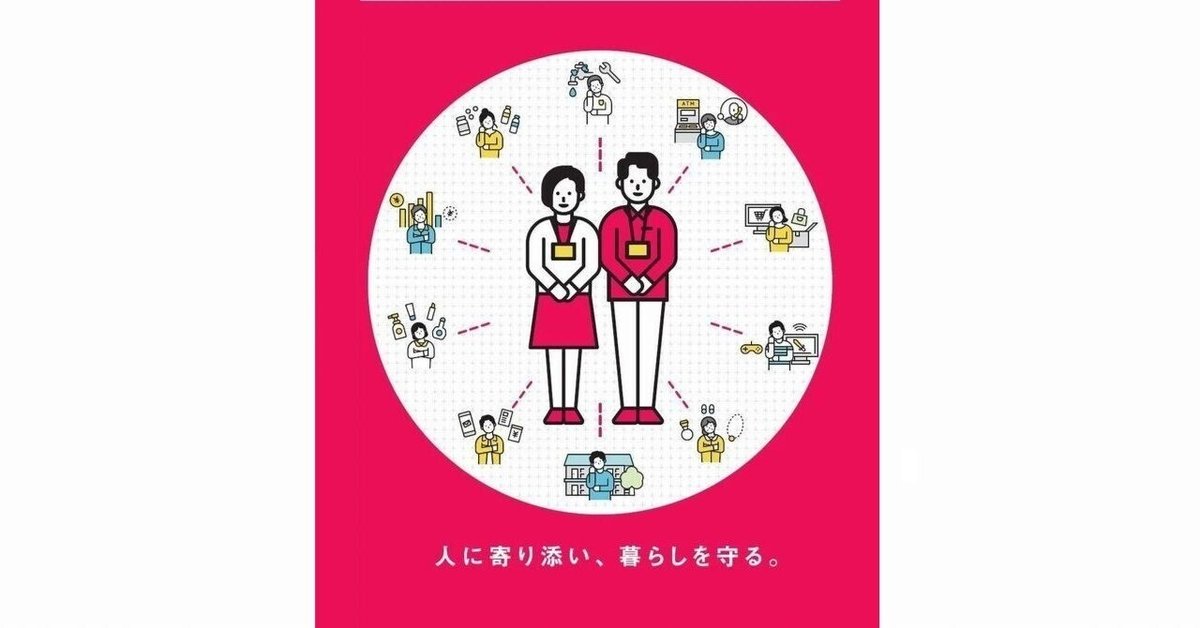
消費生活相談員資格試験にチャレンジ2024(3)
2023年度消費生活相談員資格試験(独立行政法人国民生活センター実施)の問題・正解に簡単な解説等を付した記事シリーズ第三弾です。今回は第5問と第6問をお送りします。
5. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
① 防虫剤のうち、ナフタリンとしょうのうを併用すると、衣類に染みがついたり、変色したりする場合がある。
正解:○
〔参照URL〕衣類を守るための防虫剤の基礎知識(全国クリーニング生活衛生同業組合連合会)
② レーヨンは、光沢と吸湿性に富み、濡れると強度が落ちる性質を持つ動物繊維である。
正解:×
〔コメント〕レーヨンは、「化学繊維」である。
〔参照URL〕【国民生活センター】国民生活2021年4月号https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202104_05.pdf
③「クリーニング事故賠償基準」において、クリーニング事故による損害賠償額算定の基準となる「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するのに必要な金額をいう。
正解:○
〔参照URL〕改訂・クリーニング事故賠償基準(全国クリーニング生活衛生同業組合連合会)
第2条(定義)
(3)に「物品の再取得価格」が規定されている。
④ 食品添加物の品質の規格や使用量の基準について、日本独自の規格は設けられておらず、国際規格に合わせた規制がなされている。
正解:×
〔参照URL〕【消費者庁】食品添加物
⑤ 食品の販売者は、腸管出血性大腸菌に汚染された生食用食品を市場に供給した後、自主回収したときは、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を都道府県知事に届け出なければならない。
正解:○
〔参照URL〕【厚生労働省】食品等の自主回収を行った場合の届出に関する事業者向け資料
https://www.mhlw.go.jp/content/000781907.pdf
⑥ 食品表示基準によれば、和菓子店は、製造した和菓子を容器包装に入れ、その店頭で消費者に直接販売するときは、原材料名、内容量、原料原産地名の表示をしなくてもよい。
正解:○
〔コメント〕包装されたお菓子を製造場所で直接販売する場合は、原材料名、内容量、栄養成分量、製造者、原料原産地名の省略が可能。(食品表示基準 第五条(義務表示の特例)「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」)
⑦ 特定保健用食品の中には、カルシウムによる骨粗しょう症の予防効果の表示が認められているものがある。
正解:×
〔コメント〕カルシウムについては、「歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減する可能性がある」という表示は認められているが、「予防効果がある」とまでは認められていない。
〔参照URL〕【消費者庁】特定保健用食品について/特定保健用食品制度の概要https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_specified_health_uses/assets/food_labeling_cms206_221110_03.pdf
⑧ 我が国の食料自給率は、長期的には低下傾向が続いてきたが、2000 年代に入ってからは概ね横ばい傾向で推移している。
正解:○
〔参照URL〕【農林水産省】日本の食料自給率
⑨ 住宅の高気密化等が進み、建材等から発生する化学物質等による室内の空気汚染等と、それによる健康への影響が指摘されているが、この影響は、「ハザードマップ」と呼ばれている。
正解:×
〔コメント〕問題文の内容は「シックハウス(症候群)」と呼ばれるもの。
〔参照URL〕【京都府】シックハウス症候群について
⑩ SDGs は、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指す世界共通の目標であり、国連サミットにおいて採択された。
正解:○
〔参照URL〕【消費者庁】持続可能な開発目標(SDGs)の推進と消費者政策
⑪ 小型家電リサイクル法では、携帯電話端末などの小型家電について、テレビ等の家電製品と同様に、製造業者に対し再商品化を義務づけている。
正解:×
〔コメント〕同法では、設計、部品、原材料の工夫による再資源化費用低減と再資源化により得られた物の利用が製造業者の責務とされている。
〔参照URL〕【経済産業省】小型家電リサイクル法の概要について
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/pdf/027_01_01.pdf
6. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
① 宅地建物取引業法に基づく重要事項の説明は、テレビ会議等のITを活用して行うことはできず、実際に対面して行わなければならない。
正解:×
〔コメント〕一定要件のもとで、ITを活用した重要事項説明(IT重説)も可能とされている。
〔参照URL〕【国土交通省】ITを活用した重要事項説明 実施マニュアル
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001397149.pdf
② 消費者が売主となる宅地又は建物の売買について、宅地建物取引業者が買主となった場合、消費者は、宅地建物取引業法に基づきクーリング・オフをすることができない。
正解:○
〔コメント〕宅地建物取引業法に基づくクーリング・オフができるのは、宅建業者が売主である場合に限られる。
〔参照条文〕宅地建物取引業法
(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
第三十七条の二 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
2~4 (省略)
③ 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、賃借人が飼育していたペットにより生じた、柱やクロスのキズや臭いの付着に関する原状回復費用は、原則として賃借人の負担となる。
正解:○
〔参照URL〕【国土交通省】原状回復にかかるガイドライン
https://www.mlit.go.jp/common/000991391.pdf
P20の表の記述より抜粋:特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾や尿の後始末などの問題でもあることから、ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合は賃借人負担と判断される場合が多いと考えられる。
④ 借地借家法によれば、定期借家契約の賃借人は、契約期間の途中であっても、当該契約を自由に解約できる。
正解:×
〔参照条文〕借地借家法
(定期建物賃貸借)
第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2~6 (省略)
7 第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
8~9 (省略)
⑤ 建設業法によれば、住宅リフォーム工事を請け負う事業者は、原則として建設業法に基づく建設業の許可を受けていることが必要であるが、500 万円未満の住宅リフォーム工事のみを請け負う事業者の場合には、例外的にその必要はない。
正解:○
〔参照URL〕【京都府】建設業許可申請の手引き(令和5年8月)
https://www.pref.kyoto.jp/kensetugyo/kensetugyoukyoka/documents/tebikiyou.pdf
「P1 軽微な建設工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業の許可は必要ありません。」

⑥ 建築基準法で定める「建ぺい率」とは、「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」であり、「容積率」とは、「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合」である。
正解:×
〔コメント〕「建ぺい率」は「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合」であり、「容積率」が「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」。問題文では入れ違いになっており誤り。
⑦ 全国の土地は、都市計画法に基づき都市計画区域と都市計画区域外に分けられている。都市計画区域のうち市街化区域は、用途地域に分けられ、建築基準法によってその用途地域ごとに建築できる建物が定められている。
正解:○
〔参照URL〕【京都府】都市計画区域等
⑧ 老人福祉法に基づく有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用のほかに、権利金その他の金品を受領することができる。
正解:×
〔参照条文〕老人福祉法
(届出等)
第二十九条
1~7 (省略)
8 有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
9~19 (省略)
⑨ 賃貸住宅管理業法は、特定転貸事業者(サブリース業者)が賃貸住宅の所有者との間で特定賃貸借契約を締結しようとするときは、サブリース業者が賃料減額請求権を有すること等について書面を交付して説明することを義務づけている。
正解:○
〔参照URL〕【国土交通省】賃貸住宅管理業法ポータルサイト/適正化のための措置
⑩ 住宅瑕疵担保履行法は、事業者に対して、新築住宅に関わる瑕疵のうち、構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ、瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保措置を義務づけている。
正解:×
〔コメント〕構造耐力上主要な部分に加え、「雨水の浸入を防止する部分」の欠陥も対象。
〔参照URL〕(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会/住宅瑕疵担保履行法とは
