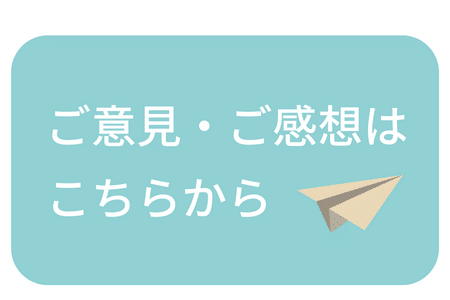長期化する避難生活、ウクライナの人をどう支えるか - 取材記者座談会【前編】
ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから1年。現地では今なお激しい戦闘が続き、多くの人が国外へ避難しています。
日本では昨年3月から避難民の受け入れが始まりました。出入国在留管理庁によると、今年2月までに来日した避難民は約2300人に上ります。
戦火に見舞われる母国から遠く離れたこの国で、彼らは何を思い、どのように過ごしているのでしょうか。
関西で暮らす避難民を取材した3人の記者に聞きました(※前編と後編に分けてお伝えします)。
(聞き手= note 担当・禹)
■ 記者のプロフィール

丸田 晋司(まるた・しんじ) 1983年生まれ、横浜市出身。2007年入社。山口支局、社会部などを経て現在は大阪社会部で行政担当。
小林 磨由子(こばやし・まゆこ) 1981年生まれ、京都市出身。2008年入社。佐賀支局、さいたま支局で勤務後、家庭の事情で一時退職。21年に復職し、現在は大津支局で県政などを担当。
小島 拓也(こじま・たくや) 1995年生まれ、新潟市出身。2018年入社。札幌支社、旭川支局を経て、現在は大阪社会部で検察担当。
■ 伝統料理の「おもてなし」
――まずは皆さんがどんな方を取材したのか、経緯も含めて教えてください。
小林 私は滋賀県彦根市に避難したイリーナ・ヤボルスカさん(51)を取材しました。娘のカテリーナさん(32)とその夫の菊地崇さん(29)が元々、彦根市に住んでいて、イリーナさんたちを呼び寄せたんです。
今は家族や友人らと一緒に、キッチンカーで母国料理を販売されているんですが、準備段階から今に至るまで継続的に取材させてもらい、何度も記事を書きました。
小林 私がイリーナさんと最初に出会ったのは、昨年の3月末、来日直後の記者会見でした。後日、個別取材の機会をいただいたのですが、その時にはすごく歓迎してもらって。記事にも書きましたが、クレープに似た伝統料理の「ブリンチキ」をごちそうになり、なぜかこちらがおもてなしを受けてしまいました(笑)

小島 避難民の中には、あまり取材を受けたがらない人もいますよね。イリーナさんたちがそんなに好意的だったのは何か理由があるんですか。
小林 どうしてなのかなぁ。カテリーナさんと菊地さんが、事前によく話をしてくださったのかもしれないです。あと、私はその時に記者会見を取材した際の記事を持って行ったんですね。それをすごく喜んでくださっていたという話は後で聞きました。

――小島さんは大阪府に避難してきた9歳のアナスタシア・プロチコさんの取材をされたんですよね。
小島 そうです。アナスタシアさんに話を聴くことになったのは、以前一緒に仕事をしていた元上司からの連絡がきっかけです。その人は、僕が学生時代にロシア語を専攻していて、今回のウクライナ侵攻にも関心があることを知っていたので、メールで連絡をくれたんです。「NHKで、大阪に避難しているこんな少女が紹介されていたから、小島も取材してみないか」って。

ちょうどその頃、僕は大阪府八尾市にある「日本ウクライナ文化交流協会」の取材をしていました。会長の小野元裕さんはウクライナに何度も行っている人で、知り合いも多いんですね。だから、小野さんならアナスタシアさんのことも知ってるかなと思って尋ねたところ、案の定「知ってる知ってる」と。そこから彼女とそのお母さんを紹介してもらい、お話を聞くことになりました。
――丸田さんは、お笑い芸人の祭典「M―1グランプリ」に挑戦したウクライナ人女性について記事を書いていますよね。この方は、どのような経緯で取材することになったんですか。
丸田 私が記事にしたユリヤ・ボンダレンコさん(31)は、ウクライナでは画家をされていた方で、両親と夫を国に残し、昨年6月に単身で来日されました。お会いすることになったきっかけは、十年来の付き合いがある取材先からの紹介です。「いま避難民の支援をしているんだけど、こんな女性がいるよ」と言ってユリヤさんの話をしてくれて。面白い人だなと思ったので、私から「ぜひ取材させて下さい」とお願いしました。
■ 言葉の壁、どう乗り越える?
――避難民の皆さんの母語はウクライナ語ですよね。皆さんは、どのようにしてコミュニケーションをとったんでしょうか。
小林 私の場合、最初はイリーナさんたちに支給されていた携帯型の通訳機を使おうとしたんですが、全然うまくいかなくて。だから、基本的には菊地さんやカテリーナさんに通訳してもらいました。
私が菊地さんに質問したことを、菊地さんはカテリーナさんに英語とかで伝えるんですね。それを聞いたカテリーナさんがイリーナさんとウクライナ語で会話して、その内容をまた逆の順番で返してくるという流れです。
「日本語→英語→ウクライナ語→英語→日本語」です。
全ての言葉を通訳してもらっているわけじゃないんですけど、雰囲気で伝わる部分もあるので、何とかコミュニケーションは取れるという感じですね。
――アナスタシアさんへの取材はどうでしたか?

小島 僕は彼女のお母さんとメッセンジャーで連絡をとっています。今は英語でやりとりしているんですが、僕は最初、ロシア語でメッセージを送ったんですよ。その方が伝わりやすいかなと思って。
そしたら、お母さんからは「英語の方が良い」と言われたんですね。元々、ロシア語があまり使われていない地域に住んでいたのか、ロシア語を使いたくなかったのか。詳細は聞いていませんが、もっと配慮すべきだったなと思います。
アナスタシアさんも英語はできるんだけど、僕が直接やりとりすると、あまりきちんと伝わらないんですね。だからお母さんを介してコミュニケーションをとることが多いです。
――小さいお子さんだし、細かいニュアンスまで伝わっているのかな、という不安はありませんでしたか。
小島 そうですね、たしかに不安はあります。でもその分、彼女のお母さんがこちらの意図を正確に理解して、アナスタシアさんにしっかり伝えようとしてくれるんです。「それはこういう質問なの?」って僕が逆質問されることもあるし。お母さんに結構助けられていますね。
――丸田さんはコミュニケーションで苦労したことはありましたか。
丸田 ユリヤさんはある程度、日本語がしゃべれるんですよ。東日本大震災などをきっかけに日本に興味を持ったらしく、ウクライナでも日本語を学んでいたそうです。だから、基本的には日本語でのコミュニケーションになりました。
それでも、やっぱり込み入った話になると、ユリヤさんも言葉が出なかったり、あるいは私が話した単語の意味を理解してもらえなかったりすることが結構ありました。時間も限られていたので、あまり突っ込んだやりとりはできなかったなというのが正直な感想です。

丸田 ただ、つたないながらも、彼女が日本語の勉強をしているからこそ出てくる言葉っていうのがあって、そういう一言に私もハッとしました。
例えば「ウクライナに帰りたいと思いますか?」という質問をした時なんですけど、私は「イエス」か「ノー」を想定していたんですね。でも、彼女が考えながら口にしたのは「その質問は難しいです」という言葉だったんです。
当然、望郷の念はあるでしょうけど、一方で、破壊されてしまった故郷には帰りたくない、という気持ちもあるのかもしれない。あるいは、今の日本での暮らしを続けたいのかもしれない。彼女の本意がどこにあるのか、細かいことは確認できませんでしたが、その一言を聞いて、こちらもいろいろと考えさせられました。

■ 支援制度の課題
丸田 私からも小林さんや小島くんに質問したいんですけど、避難民の身元引受先の登録とか、そういう制度的な部分ってどうやって調べました?役所に事前取材したのか、あるいは避難民の方とやりとりする中で知ったのか。
小島 たしか身元保証人がいるかいないかで、受けられる支援が違うんですよね。住居探しのマッチング支援があるかないか、とか。別の記事を書いた際、その違いに触れる必要があったので、その時に調べた気がします。

丸田 なるほどねぇ。なぜそれを聞いたかというと、私たちが今回書いた記事って、避難民の人たちがいろんなチャレンジをしながら頑張って暮らしています、という話じゃないですか。イリーナさんのキッチンカーにしても、ユリヤさんの「M-1」出場にしても。
そういう記事も意義はあると思うんですけど「そもそも避難民の生活をサポートする行政の体制はどうなっているのか」という部分をもっと掘り下げて取材すべきだったのかな、と少し反省するところがあるんだよね。もっと話を広げたいと思っていたんですが、今振り返ると、制度面についてはまだまだ不勉強だったなと感じます。
小林 行政支援の問題は大きいよね。私が取材している菊地さんは「滋賀県は避難民の人数も限られているので、支援もオーダーメイドで受けられる」ってよく仰るんですよ。だけど、これが東京や大阪みたいな大都市になると、避難民の人数も多いからそうはいかないだろうと。「都会では一人一人の要望にきっちりと応えてもらえないと思う。そこが気の毒なんだよね」って話していたのがすごく印象的でした。

小島 そこはケースバイケースかもしれないですね。アナスタシアさんたちは大阪在住ですが、僕が取材で「何か困っていることとか不満はないですか?」って聞いた時には「日本の支援はパーフェクト」と言ってたんですよ。住むところがきちんとあって、働かなくても暮らせるよう一定の生活費も支給されているからって。それを聞いて、僕はそれなりに充実した支援が受けられているのかなと感じました。
■ ポーランドと日本、受け入れ国の違い
小林 日本の支援が充実してるっていう受け止め方には、他の国との比較もあると思います。ポーランドとかは、ものすごい数のウクライナ国民が身を寄せているじゃないですか。イリーナさんたちも最初はポーランドに避難したそうなんですが、その頃は避難民でごった返してて、泊まるところもないし、仕事も見つからない状況だったと聞きました。
菊地さんは、当初から「自分たちが取材に応じることで、他のウクライナの人たちにも『日本においでよ』っていうメッセージを伝えたい」って仰っていました。日本に来るまでの道のりは大変だろうし、言葉が通じない不安もあるかもしれない。それでも、とりあえず日本に来たらいいよ、なんとかなるよ、ということを最初の記者会見で呼びかけていましたね。

小島 たしかに、そういう国と比較すると違いが大きいと思います。アナスタシアさんの家族も、侵攻が始まった時は休暇中でポーランドにスキーに行ってたんですよ。ちょうどそのタイミングでロシアの侵攻があったから、ウクライナには戻らなかったそうです。
侵攻後は、避難民がどんどん国境を越えてポーランドに集まってきて、家を借りるのも難しい。だから別の国に行こうと思って、いろんな国に申請をしたら、たまたま日本に受け入れてもらえることになったと。当初は日本に避難することなんて想定していなかったんだけど、それしか選択肢がなかったと言っていました。

■ 伝えるのは「哀」だけで良いのか?
――事態の長期化に伴い、避難民の生活も先行きが見通せなくなってきている部分があるのでしょうか。
小林 避難生活はかなり長引いているから、そういう意味ではいろんな変化が起きていると思います。
私が取材したキッチンカーの取り組みは、避難民の仕事を生み出して、日本人との交流にもつながっている。そういう意味では大成功した事例だと思うんですよね。だけど避難生活が長期化してくると、やっぱり「いつまで続けるのか」という問題が出てきます。
「帰国できる状況になればすぐに帰りたい」という人もいれば、「当面は日本で生活しよう」と考えている人もいる。それぞれのスタンスによって、支援する側の対応も変わってくるんじゃないかなと思います。
小島 アナスタシアさんのお母さんは、日本の支援体制には満足してると言いつつ、「ここにずっといるつもりはない」とも断言していました。お父さんはウクライナに残っていますしね。

一方で、アナスタシアさん自身は、かなり日本での暮らしに適応できちゃっている部分があるんですよ。日本語学校に通って、ひらがなやカタカナも覚えたし、今は日本の小学校に通っているし。同時に、ウクライナの学校のオンライン授業も受けているそうです。さらに彼女は「バンドゥーラ」という伝統楽器を演奏するんですが、そのレッスンもオンラインで続けているそうです。
――すごいですね。
小島 そうなんです。これは彼女を取材してみて、ふと思ったんですが、日本人が避難民の方をみる目って、喜怒哀楽で言えば「哀」ばかりだったんじゃないかなという気がします。記事でも「悲しい」という感情ばかり書いている。僕も取材する時は「遠い国から来てかわいそうだな、大変な思いをしているんだろうな」という前提で話を聞いていたんですけど、暮らしの中には当然、他の感情もあるわけです。
アナスタシアさん自身は、日本でいろんなことにチャレンジしたいと言っていて、ウクライナともうまくつながっている。大変な中でもすごく前向きに暮らしているんですね。人それぞれですが、避難民の生活にはそういう面もあるんだなというのが非常に印象的でした。(続)
座談会の後編はこちら↓
2月24日に開かれた「日本ウクライナ文化交流協会」のコンサートで、アナスタシアさんが民族楽器のバンドゥーラを演奏しました。動画はこちら↓
< 皆さんのご意見、ご感想を是非お聞かせ下さい >