
サム・バーロウ監督作品『Immortality』(イモータリティ)の謎を考察(ネタバレあり)
『Her Story』『Telling Lies』といった革命的な作品を送り出してきたADVゲーム界の鬼才、サム・バーロウ監督の最新作『Immortality』に関する考察を試みてみました。
前二作と同様に物語の全体像を把握しにくいゲーム構造のうえ、今作は「3つの映画作品の未完成フィルム+α」をいろいろな角度から読み解かなくてはならないので、理解のハードルが非常に高いと感じました。
スタッフロールを一度見ただけでは「何が起こっていたのか」を掴むのも困難なゲームですが、テーマやその語り口には前二作を上回る奥深さがあると思います。
当記事はQ&A形式で、『Immortality』作中の謎に対する個人的見解をまとめたものです。
もちろんこれが絶対的な解釈というわけではありませんし、ストーリーラインを簡単に把握する目的のものでもありません。
『Immortality』という優れた作品を解釈する一助になれば幸いです。
※注意(重要!)
当記事は『Immortality』をプレイし、最低でもスタッフロールまで到達したプレイヤーを想定した考察を行っております。
作品の重要な秘密をすべて割ってしまっているので、未プレイの方が読んでしまうとゲームプレイの面白さは完全に損なわれてしまいます。
※※ 絶対に、プレイ前に当記事を読まないでください ※※
※※ 絶対に、プレイ中の方に当記事の内容を伝えないでください ※※
また、可能であれば全フィルムの回収を終え、全ての映像を確認して全実績の解除まで完了されてから当記事をお読みになると、より『Immortality』の世界の奥深さを感じられるのではないかと思います。
Q. マリッサ・マーセルが主演する映画3作品はどうして全てお蔵入りとなってしまったのか?
A. 3作品それぞれに異なる理由がある。
・『アンブロシオ』:撮影終了後、監督アーサー・フィッシャーによって編集中のフィルムが盗難されたため。
・『ミンスキー』:主役級の刑事役であったカール・グリーンウッドが銃の暴発事故によって撮影中に重傷を負い、その後死亡したため。
・『2OE』:主演のマリッサ・マーセルが撮影中に頭から大量出血、その後共演者であったエイミー・アーチャーによって灯油をかけられたうえに火をつけられ、焼死したため。また、表示言語を英語に切り替えてからオープニング画面の「About」(詳細)を確認すると、監督ジョン・デュリックの死亡が直接の原因とされていることがわかる。
(解説)
盗まれた『アンブロシオ』のフィルムを後年になってアーサーが返却しに来たことは、逆再生で見ることのできる不死者「ザ・ワン」のモノローグの中で語られている。

盗難の動機については明示されていないが、
・マリッサとの肉体関係トラブル
・撮影監督ジョン・デュリックとの主導権争い
といったあたりが有力だろう。(詳しくは後述)
『ミンスキー』撮影中の暴発事故でカールは重傷を負ったが、即死ではなかった。
これは後年TVショーに出演したジョン・デュリックの発言からわかる。

『2OE』撮影中のマリッサの死因が共演者エイミーによるものであるとプレイヤー以外の人間に知られているかは不明。
エイミーを操っている不死者「ジ・アザー」(「もうひとり」)が隠蔽していたならば、不審な失踪と見なされた可能性もある。
ジョン・デュリックの死は、彼を操っていた「ザ・ワン」が死亡したため。

Q. フィルムの逆再生によって目撃される「不死者」たちとは何者なのか?
A. 人類の上位種とみなせる存在。基本的には不死。吸血あるいは捕食によって対象の人間に寄生し、自在に操ることができる。人類と異なる次元に生き、記憶や時間を超越する存在だが、「不死者」自身も自分たちがいつから存在しているのかを記憶していない。
(解説)
かつては数多くいたはずの「不死者」だが、現在まで生存しているのは「ザ・ワン」と「ジ・アザー」の二人のみであると、「ザ・ワン」自身は考えている。
「不死者」が恒久的な死を獲得する条件は、宿主の人間が火葬されること。
宿主が死んでも、火葬されていない場合には休眠期間を経て後に目を覚ますことができる。
休眠は、長く活動した後にも必要となる。
寄生する肉体そのものは様々に乗り換えていくことが可能であり、同時に複数人を操ることもできる。
「不死者」は人類と異なる次元に生きているが、宿主の肉体を通じて人類の活動を認識したりコミュニケーションをとることができる。
彼らの姿はフィルムの逆再生によって人間にも認識可能になるが、撮影時期よりも未来の出来事を知っていたり、フィルムに映っていた人物と実際には行われているはずのない会話を交わしているなど、記憶や次元を超越した行動をとっている。

Q. エイミー・アーチャーがマリッサを焼き殺す理由は何か?
A. マリッサに寄生中の衰弱した「ザ・ワン」の意志によるものであり、エイミーに寄生している「ジ・アザー」の手により実行された。火葬を記録したフィルムを残すことで「不死者」はさらなる進化を遂げることができる。
(解説)
火葬により「不死者」は恒久的な死を得ると考えられていたが、カール・グリーンウッドに寄生していた「ジ・アザー」が「ザ・ワン」によって殺害、火葬されたのちに復活したことでその定説が覆された。

火葬後に復活できる条件は「宿主の死をフィルムに記録、逆再生することで『不死者』の死を他の人間に目撃させる」ということ。
フィルムを通じて「不死者」の死を目撃した人間が次の宿主となる。
「ジ・アザー」が復活したのは、エイミー・アーチャーが『ミンスキー』の非公開フィルムを再生し、「ジ・アザー」の死んだ様子を目撃するという偶然の出来事があったため。
エイミーがフィルムを見たのはおそらく『2OE』の撮影期間中、具体的には1999年3月25日から29日の間と思われる。
25日のフィルム(2OE 82)の逆再生においてエイミーはまだ「ジ・アザー」に寄生されていない様子だが、何かを予見したような「ザ・ワン」から視線を向けられている。
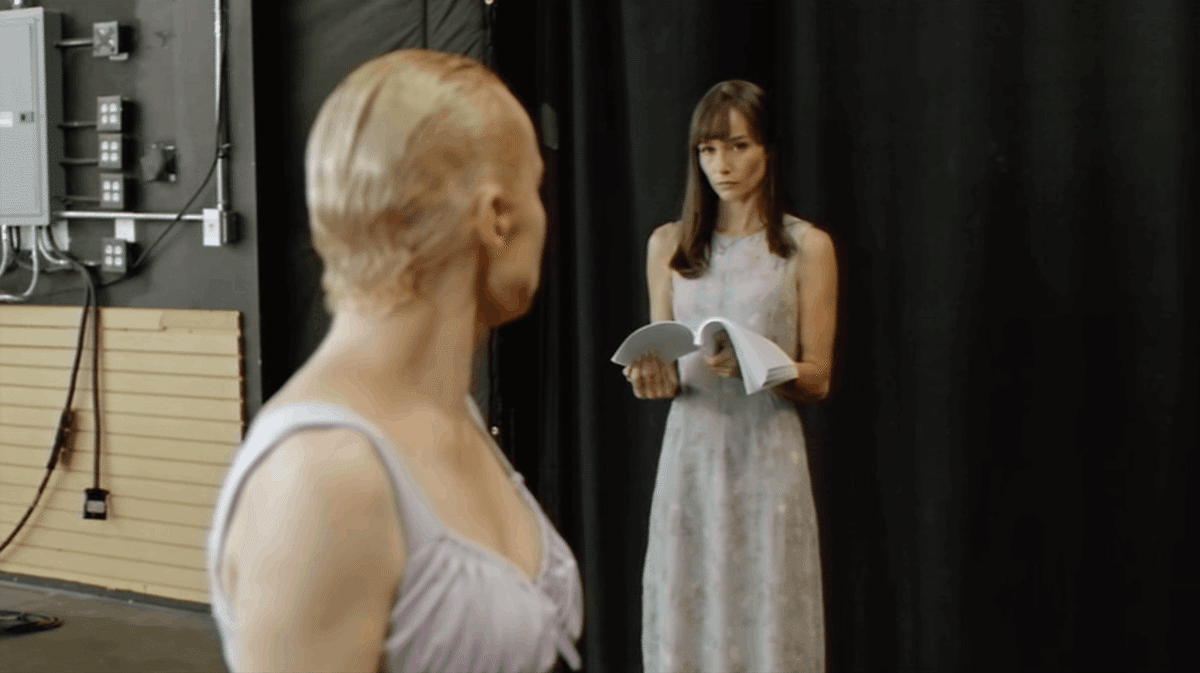
フィルムに記録された「不死者」は精神のみの状態で曖昧な意識を保っており、ある意味で足枷ともいえた人間の肉体を放棄することが可能になった。
また、オリジナルのフィルムからデジタルコピーを作成することが容易な現代では、人間文明が存続するかぎり真の意味での「不死」を獲得することも意味している。
Q. 「ザ・ワン」はマリッサ以外の複数の人物に同時に寄生していたのか?
A. 明確にマリッサと同時期に寄生されていたのはジョン・デュリック。それ以外にも「ザ・ワン」は複数の人物に一時的な寄生を行っていた可能性がある。
(解説)
「ザ・ワン」がジョン・デュリックを宿主とするようになったのは、銃の暴発事故(1970年8月30日)により『ミンスキー』の撮影が中断された直後からと考えられる。
「ザ・ワン」のモノローグによると、彼女がマリッサの口を通じてジョンに自分の正体を告白したのは「ジ・アザー」を殺害した後となっている。
「ジ・アザー」はカール・グリーンウッド以外にも美術係の女性にも寄生を行っていたようだが、『ミンスキー』の撮影中に「ザ・ワン」がカール以外の宿主を殺害したことは考えにくい。
(「ジ・アザー」は銃の暴発事故の際、「今まで死ぬところを見せたことがなかったな」と「ザ・ワン」に告げている)

『2OE』の撮影が始まる以前、1972年2月16日のTVショーに出演したジョンが「ザ・ワン」によって操られている様子からすると、この時点ですでに寄生が完了していることは間違いない。

ジョン以外では、農民風の男性、変わったネックレスを着けた黒衣の女性も、かつての「ザ・ワン」の宿主であったことが暗示されている。
マリッサ以前に彼ら以外にも宿主がいたのは間違いないところだが、この二人は「ザ・ワン」からすれば特に思い入れのある人間であったとも考えられる。
フィルムの逆再生の中にある二人の姿はあくまで「ザ・ワン」のイメージによって再生されている可能性が高く、現実世界での肉体はすでに放棄されているのではないだろうか。
「ザ・ワン」が一時的な寄生を行った対象として、『アンブロシオ』の共演者であったソフィア・モルガナとロバート・ジョーンズも十分な可能性がある。

「不死者」たちは逆再生フィルムの中で、宿主が現実世界で着ている服を基本的にはそのまま身につけている。
『アンブロシオ』のフィルムの逆再生世界で「ザ・ワン」はロバートやソフィアと入れ替わっている場面があり、やはり彼らの服を身につけている。


またモノローグにおいても「ザ・ワン」はしきりに照れながらロバートとソフィアを捕食した意味合いのことをほのめかしてもいる。

しかし二人ともその後のマリッサ関係の映画に現れてくることはなく、どうやらこの入れ替わりは一時的な寄生だった可能性が高い。
ただしソフィアは撮影終了後のパーティに姿が見えず、礼拝堂での撮影シーンで瀕死のマリッサとすり替えられている場面があることから、若々しいソフィアの肉体がマリッサの維持のために消費させられたのではないかという疑いがある。
Q. 1970年8月10日の逆再生で見られる映像では、ジョン・デュリックが「ザ・ワン」によって吸血されているように見える。寄生はこのタイミングからではないか?
A. 8月10日から「ザ・ワン」がジョンへの寄生を開始したとすると、それ以降のマリッサとジョンの会話に不可解な点が残る。時間を超越する「不死者」の能力によって、後から吸血の場面が差し込まれた可能性が高い。
(解説)
1970年8月10日の撮影(ミンスキー 33B)において、ジョン・デュリックが「ザ・ワン」から吸血されているのが逆再生の映像によって確認できる。
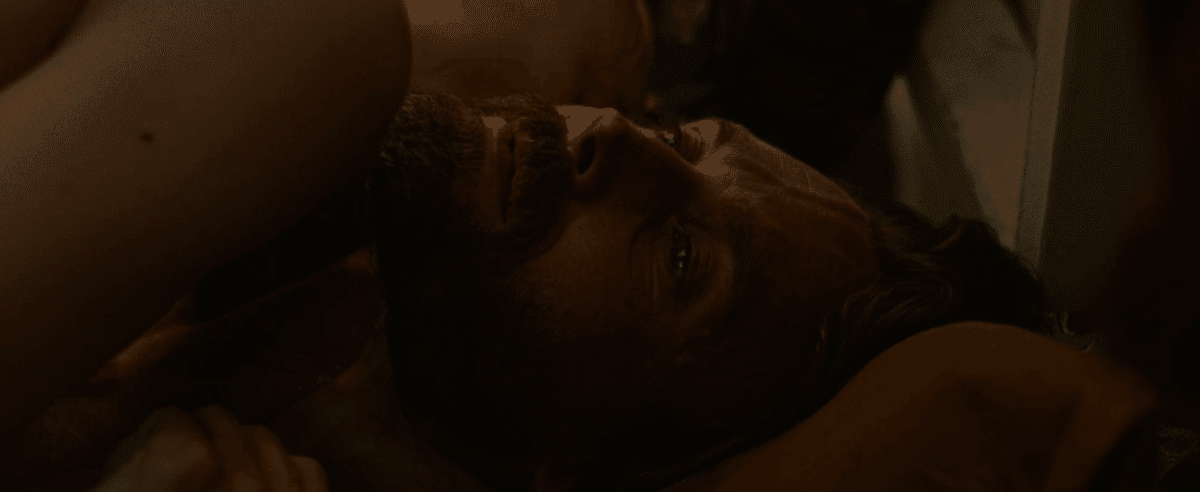
前日9日の撮影において当初のミンスキー役だったダグラス・シモンズが撮影体制への不満から降板しており、監督のジョン自ら代役を務めることになって最初の撮影がこの10日の場面である。
物語上での状況としてはミンスキーとフラニーが事件発生前日、ミンスキー殺害のきっかけとなる口論をしている回想シーンだ。
この8月10日、「ザ・ワン」がジョンへの寄生を開始したと仮定するのは時系列的に見ると矛盾が生じるように思われるかもしれない。
しかし10日以降マリッサとジョンが二人きりで会話しているのが、少なくとも13日と28日の2回、確認できる。
13日はジョンが代役を務めることをマリッサが冷やかす場面、28日はカールに対するマリッサの態度の変化をジョンが訝しげに問う場面となっている。
もしこの時点でマリッサとジョンが「ザ・ワン」の操り人形だとすると、このフィルムに収められた現実世界での会話が「ザ・ワン」の不必要な一人芝居ということになってしまう。
また、13日のフィルムでは後から部屋に入ってきたカールがジョンとキスするのを見てマリッサが驚くが、「ザ・ワン」がジョンを操っているのならこのマリッサの反応は極めて不自然だ。
吸血行為が寄生に関係しているのは明らかだが、10日の逆再生映像は「ザ・ワン」が後から『ミンスキー』のフィルムに仕込んだものである、とするのが最も無理のない説明だろう。
実際に10日以前、7月20日の逆再生映像において「ザ・ワン」が血まみれのジョンとカールを従えているのが確認できる。
この時点でまだジョンは吸血されていないのだから、この映像もまた後から差し込まれたものだ。
(そもそも「ザ・ワン」はカールに寄生していないはずなので、この映像はあくまでも「イメージ」にすぎない)
逆再生世界において、物事は必ずしもその当時に起こったことではない。
このことは1968年10月2日『アンブロシオ』の撮影フィルムの逆再生において、68年当時にはありえなかったスマートフォンと思しき機器について「ザ・ワン」が言及していることからも明らかだ。

また「ザ・ワン」はモノローグにおいて、「不死者」が時間を超越できることも述べており、逆再生世界の時系列はあまり当てにすることができないと考えるべきだろう。
なぜ「ザ・ワン」がジョンへの吸血を10日の撮影場面に仕込んだかについては、それがマリッサ(=「ザ・ワン」)とジョンの共同作業における一つの頂点の瞬間だったからではないだろうか。
該当シーンはミンスキーとフラニーが口論するという脚本の場面を、ふたりの「前戯」として解釈したジョンが現場で変更して撮り始めたものだ。
この提案にマリッサも即座に対応し、ミンスキーとフラニーの愛憎の入り交じった複雑な場面として描かれることになった。
カットの声がかかった後、二人やスタッフたちが次々と声を上げたように、ミンスキー役がダグラス・シモンズのままであったらこの難しいシーンは絶対に撮れなかっただろう。
同じシーンの逆再生世界で「ザ・ワン」はジョンと会話し、二人の間に隔絶と相違があったことを悲しげに告げている。
ほんの一時だけ訪れた頂点と、その後の避けられない離別。
8月10日のフィルムの表と裏に、「ザ・ワン」の悲哀が刻まれている。

Q. 作中で「ジ・アザー」が寄生した対象は誰か?
A. 作中で明示されたのは、『アンブロシオ』の悪魔役の男性、『ミンスキー』の美術(背景)係の女性、カール・グリーンウッド、エイミー・アーチャーの4名。

(解説)
悪魔役と美術係に関しては初登場時からすでに寄生されており、一方のカールとエイミーについては時系列の途中から寄生されたと思われる。
具体的にはカールは1970年8月13日の撮影終了後からジョンとマリッサの部屋を訪ねるまでの間、エイミーは先述のように1999年の3月25日から29日の間に捕食されたというのが有力だろう。
8月13日にジョンとのプライベートなキスをしたあたりから、撮影現場などでもカールの態度が一変していることが観察できる。
その時点まではどこか内向的でありながらそれを覆い隠そうとする強がりが目立ち、また特に性的な話題を避ける傾向にあったのが、ジョンとのキス以降はむしろ堂々とした皮肉屋めいた雰囲気に変わり、自身の中性的な性的指向を明確に打ち出してきている。
アルコールやドラッグの摂取についても積極的になっていることが対比させられている。


こうした変化もマリッサ以外の周囲からは「役作りをこなしてきた」と単純に受け入れられていたことだろう。
そして仲睦まじく見えていたマリッサとの関係もその日を境に急激に悪化し、撮影の合間でも会話らしい会話がほとんど消失してしまっている。
エイミーの変化についてはあまり多く描かれていないが、3月29日の撮影(2OE 84)後からはしばしば休憩を提案したり、過酷な撮影を続けるマリッサを心配そうに見つめている様子が見られるようになる。
これは長期間休眠しなかったために疲弊した「ザ・ワン」の状態を「ジ・アザー」が気遣ってのことだろうが、やはりマリッサとジョンの口を通じて「ザ・ワン」自身から拒絶されている。
Q. カール・グリーンウッドの「中性的な性的指向」とは何か?
A. カールには時系列上に現れた当初から同性愛指向が見られる。そのことをカール本人が意識していたかは不明だが、「ジ・アザー」に寄生されてからはそれをほとんど隠さなくなった。
(解説)
カールの内部にあるものが「男性全般に対する同性愛指向」と断言できるかどうかは少し微妙なところかもしれない。
しかし少なくともカールはジョン・デュリックに対する性愛対象としての興味を早い段階から持っており、マリッサ・マーセルに対してはそこまで積極的な感情を抱いていなかった、というのは間違いない。
1970年6月10日の読み合わせ(ミンスキー 14)は、マリッサ、ジョン、カールの三者によりリラックスした雰囲気で行われた。
カールはソファでジョンと隣り合って座り、ニコニコと非常に上機嫌な様子だ。台詞を読み交わしながら、ときおりジョンを見つめるその視線には敬意以上の何かが込められているように見える。
それが途中で二人の間にマリッサが割って入り、カールにぴったりと密着して座ると途端にカールは表情を曇らせ、どうにもつまらなそうな雰囲気を漂わせ始める。


6月24日の濡れ場のリハーサルにおいても、積極的に体をすり寄せるマリッサに対し、カールは若干引き気味の様子だ。
ジョンから好みのセックスの仕草を確認されるとマリッサは即座に答えるが、カールは引き攣った笑顔で口ごもり「ちょっと考えておくよ」などと言ってごまかす。
意識的にか無意識的にか、カールは自身の同性愛指向をひた隠しにしている。
偏見の強い1970年の時勢を考えれば、売出し中の若手俳優としてそれは当然のことだったのだろう。
カールはいかにも自分が異性愛者であるという顔を崩さず、実際に必要とあらば大して興味のない女性とのセックスをもこなしてみせる。
撮影期間中のパーティの場でカールは「150人から200人ぐらいの女性とセックスした」と言ってのけるが、それは単なる虚勢ばかりとも言いきれない。
カールにとって女性とのセックスは、俳優としてのビジネスを円滑に進めるための必要業務だ。
ベッドの上でも演技をする、そうしたあり方がカールには染みついている。(この点では「不死者」の振る舞いと似ており、「ザ・ワン」とは通じ合うものがあったのかもしれない)
マリッサに寄生している「ザ・ワン」は前作でのアーサー・フィッシャーの教えどおり、俳優を「彫刻」しようとした。
グッドマン刑事という役柄にカールを入り込ませるため、作中のフラニーがしたように実際に誘惑し、肉体関係をもつようになった。
ところがここで「ザ・ワン」の思惑を覆してしまったのがカールに寄生した「ジ・アザー」だ。
「ジ・アザー」は寄生したその瞬間から、カールが必死に抑え込んでいた同性愛指向とジョンへの恋情を共有したはずだ。
「ジ・アザー」にはカールを俳優として長持ちさせようなどという考えは一切ないので、宿主の心の赴くままにジョンへとキスをさせた。
これは、それまで自分が誘惑する側だと思っていた「ザ・ワン」には青天の霹靂だ。
相手を「彫刻」しているつもりだったのが、実際には自分が利用されていたことになる。
奇しくもこの「ザ・ワン」の驚きは、『ミンスキー』作中においてグッドマンの部屋で自分をモデルにした絵を発見したフラニーの驚きと酷似したものとなっている。

Q. アーサー・フィッシャーが『アンブロシオ』のフィルムを盗んだ理由は何か?
A. マリッサの女優デビューを妨害するため。また、撮影監督であるジョンとの主導権争いにもアーサーは敗れており、そちらに対する意趣返しでもある。
(解説)
『アンブロシオ』の撮影開始後マリッサとアーサーが(おそらく半強制的な)肉体関係にあったことは、明示こそされていないものの十分に推察が可能な事柄となっている。

まずモノローグにおいて「ザ・ワン」はアーサーとの出会いに触れながら、「映画は彼にとって色情狂のようなものだった」「彼は私を『彫刻』したかった」「彼は私に『何を食べるべきか』を教えてくれた」と述べている。

特に注目するべきフレーズは「彫刻」であり、これはマリッサの次の出演作となるはずだった『ミンスキー』でも物語上で重要な意味合いを持っている。
『ミンスキー』のストーリー上では、老画家ミンスキーはモデルたちを自分の望む形に「作り変えていた」ことが語られていた。

このモデルとはミンスキーの「ゴーストペインター」でもあるフラニーと、彼女によってミンスキー殺害の犯人に仕立てあげられてしまうオルガのことだが、フラニーはミンスキー亡きあとグッドマン刑事を自分の意のままに「彫刻」し、自身の容疑を晴らすため利用することになる。
このような『ミンスキー』の物語構造は、『アンブロシオ』の撮影時に裏側で起っていた出来事を下敷きにしている。
このことは、ジョン・デュリックが「ザ・ワン」に対して「君を助けたかった。だからこの映画を撮った」と述べているし、「ザ・ワン」もモノローグで同じ内容のことを語っている。
・アーサー・フィッシャー → ミンスキー
・マリッサ・マーセル → フラニー
・ジョン・デュリック → グッドマン刑事
という、現実から虚構への置換が行われていたとするとわかりやすい。
アーサーは世間知らずで上品なモデルであるマリッサを「彫刻」することで、彼女を『アンブロシオ』の修道女マチルダ────敬虔な修道女から淫婦へ変貌するその役柄と同じ境遇に嵌め込むことができると考えた。
アーサーはマリッサを抱き、自分の中にある感情や欲望をそのままカメラの前で曝け出すことを教え込んだ。

『アンブロシオ』のフィルムを時系列順で見ていくと、貞淑で抑制的だったマリッサが淫蕩な自由奔放さを増していくのがよくわかる。
これは「彫刻家」としてのアーサーの腕の確かさを証明している変化といえるだろう。



ところがアーサーの予測を超えた事態が起こる。
撮影監督ジョン・デュリックを中心とした、主要スタッフやキャストたちの「反乱」だ。
アーサーとジョンの間には、主に濡れ場における俳優の目線を巡っての意見の相違が撮影の初期からあり、マリッサを操る「ザ・ワン」は早々にジョンへ目をつけていたのだろう。
撮影中にジョンが自分の意見をアーサーにぶつけると、マリッサはジョンに賛同するようにアドリブを入れる。

撮影後半になるとマリッサ以外の主演俳優たち(前述のように「ザ・ワン」に寄生されていた可能性がある)もアーサーをほとんど尊重せず悪態をつくまでに至り、立場を失ったアーサーは最終的には投げやり気味にジョンが撮影を仕切るのを許すこととなった。


この「反乱」の裏側にいたのは間違いなくマリッサ、そしてそれを操っている「ザ・ワン」だろう。
マリッサはジョンを籠絡して手駒にし、まるで聖者アンブロシオを手玉に取って罠に嵌めた作中のマチルダよろしく、アーサーを騙し討ちにして監督の座から追い落としてしまったのだ。
アーサーがその権威を失墜させているのは、撮影終了パーティの乾杯の構図からも窺い知れる。
乾杯の瞬間、主演俳優たちに囲まれてライトの光を浴びているのは呼ばれてもいないのに勝手に壇上に上がってきたジョンのほうで、監督であったはずのアーサーは薄暗い片隅で孤独に杯を掲げるのみだ。

アーサーは作中の聖者アンブロシオと同じように、自身の「ミューズ」であったはずのマリッサに裏切られて捨てられ、さらには編集中にマリッサとジョンが勝手に撮影した熱い濡れ場のフィルムまで発見して屈辱に震えたことだろう。
最後の復讐の手段として、アーサーは編集中の『アンブロシオ』のフィルムを盗んだ。
映画監督としての名声を取り戻すチャンスを失うことにもなるがマリッサとジョンへの憎しみが勝り、実際に映画が非公開となったためにマリッサは女優デビューを失敗した。
「ザ・ワン」のモノローグによれば、自身の死の直前にアーサーは盗んだフィルムをおそらくジョンへと渡しに訪れ、関係を修復しようとしたということになっている。
これが契機となって「ザ・ワン」は『ミンスキー』での失敗から手放していたマリッサを再び起用し、『2OE』を撮影する意志を固めることになる。
Q. なぜソフィア・モルガナは礼拝堂での説教シーンの撮影中に突然泣き出してしまったのか?
A. 実際に泣いているのはソフィアに寄生している「ザ・ワン」。物語上で少女の凌辱者となる聖者アンブロシオが自身の純潔ぶりと断罪されることのない強さを声高に主張したことで、マリッサのトラウマ、さらには迫害され続けてきた「ザ・ワン」の記憶が刺激されたため。
(解説)
「ザ・ワン」がソフィアに寄生を開始したのは1968年9月17日の撮影(アンブロシオ 46B)の可能性が高く、翌日18日の撮影(アンブロシオ 51A)で初めてソフィアと入れ替わっているのが確認できる。
(前述のように逆再生世界での時系列はあまり信用できないが)


礼拝堂でソフィアが泣き出すのは9月20日の撮影(アンブロシオ 2C)であり、ここでは「ザ・ワン」の隠しきれない心情が表出してしまったとするのが『Immortality』という作品の解釈としては正しいように思われる。

ソフィアは当初は演出に忠実に、説教を行う聖者アンブロシオを憧憬の眼差しで見つめようとしている。
ところが説教が進むにつれ表情が曇りだし、憤りのような怒りのような気配が漂い、最後にはこらえきれずに涙をこぼしてしまう。
アンブロシオの説教の内容は、市井の人々に純潔さが欠けていることを非難するものであり、対比として自らの純潔さと無垢、そしてそれによって神から守られている強さを堂々と誇るものだった。
もちろんこれは物語上で後に堕落して快楽に溺れ、悪魔と魂の取引を行うに至るアンブロシオを描くための伏線になっている。
この説教が、ソフィアの耳を通して「ザ・ワン」の心にどのように響いたのか。
「不死者」はおそらく、宿主のもつ性格やトラウマなどから精神面に大きな影響を受けている。
これはアンブロシオがソフィア演じる少女アントニアを強姦するシーンの撮影(アンブロシオ 54)で、「ザ・ワン」がフランスで凌辱されたマリッサの記憶を呼び起こされて慟哭している場面からも明らかなことだ。

そしてモノローグにおける言葉の端々からすると、過去の「ザ・ワン」自身もこうした凌辱を受け続けてきたのは容易に想像できる。
「ザ・ワン」は幾度も囚われの身となり、拷問を受け、激しい痛みをともなう死を数知れず経験してきている。
「ザ・ワン」が「凌辱者」に対して抱いている憎悪の激しさは苛烈極まりない。
『アンブロシオ』オーディション時の逆再生世界ではアーサー・フィッシャーをナイフで脅しつつ難詰し、『2OE』の撮影時には大富豪ハッセンバーグを演じるテリーを激しく殴打した。
(特に罪のなかったはずの俳優テリーに対して、逆再生世界ではなく現実世界で殴打してしまっている。役柄と役者を混同していることからも「ザ・ワン」の動揺ぶりが窺える)

「ザ・ワン」にとって「凌辱者」は、自らの身体や尊厳を傷つけてくるのみならず、自由を束縛し、人類と「不死者」の統合を目指すための芸術活動をも妨害しようとする明確な「敵」だ。
『アンブロシオ』作中に登場する聖者アンブロシオは「ザ・ワン」が最も憎悪する「敵」の顔をしていたということになる。
Q. なぜ「ザ・ワン」は頑なに映画作りなどの芸術活動を続けようとしているのか。
A. 「不死者」の世界と人間社会の統合を進めるため。人間性の一部として認められることで、「不死者」の生存が保証されることになるから。
(解説)
「ザ・ワン」の映画作りに注ぐ情熱は異常なほどで、「不死者」仲間の「ジ・アザー」も呆れるほどだ。
しかし映画という表現形式に出会ったのは第二次世界大戦中に休眠から覚めたのちのことであり、それまでは有名画家(モノローグでは例としてバルテュスが挙げられている)のモデルをするなどして過ごすことが多かったようだ。
(アーサーに見初められたのもモデルとして石鹸のCMに出演しているのがきっかけだった)
「ザ・ワン」が芸術界隈に身を寄せることが多いのは、そこが「不死者」にとって安全な居場所であるからだ。
『ミンスキー』の取調室シーン(ミンスキー 5B)の逆再生世界において「ザ・ワン」は、人間社会は「法」と「愛」によって構成されると述べている。

簡単に要約してしまえば
「法」=軍隊、管理、破壊
「愛」=芸術、自由、癒し
という二項対立で「ザ・ワン」は人間社会を認識しているということだ。
そして「究極の自由」に生まれついた「不死者」は、何よりもその自由を束縛されることを恐れる、とも述べていた。
「不死者」は「死」という究極の束縛からは逃れられていても、寄生している「肉体」という物理的な足枷から逃れることができていない。
「肉体」が「法」によって拘束されうることこそが、「不死者」の致命的な弱点となっている。
したがって「ザ・ワン」のような「不死者」は「法」の対極にある「愛」の砦、芸術の世界に身を寄せることになった。
そこでは人間離れした奇矯な振る舞いも、いつまでも若々しく不気味なほどの美を保ち続けていることも、すべてが芸術性の名のもとに肯定される。
「不死者」たちにとって居心地のいい空間だ。
そして「ザ・ワン」は芸術を単なる避難場所として利用するだけではなく、積極的に人間社会とコミュニケーションし、人間の視座を自分たちと同じ位置にまで引き上げる手段とすることを考えついた。
すなわちそれが、「不死者」たちの作り上げた「偉大な物語」であり、「ザ・ワン」が執拗に映画作品の中で描こうとしているテーマだ。
映画という媒体を選んだのは、それが「不死者」たちの抱いている感覚────「時間圧縮」を可能にするメディアであるからだ。
映画は、たとえ千年という月日であっても、それを数秒に圧縮することすら可能にしてしまう表現形式といえる。
(さらに言えば編集によって時系列を入れかえることもできる)
「偉大な物語」に替わり、映画を通して人間の世界観を変化させ、最終的には「不死者」を人間性の一部へと統合させること。
これこそが「ザ・ワン」がこだわり続けている大望であり、「ジ・アザー」との不和を決定づけている直接的な原因でもあった。
Q. 「ザ・ワン」と「ジ・アザー」の不和とは何か?
A. 人間社会や芸術活動に対する見解の相違が二人の間にある。
(解説)
芸術活動に血道を上げる「ザ・ワン」とは対照的に、「ジ・アザー」は人間とそれらが作り出す芸術を冷めた眼で眺めている。
「ジ・アザー」はかつて「偉大な物語」を「ザ・ワン」やおそらく他の「不死者」たちと作り上げた過去があり、特にそこでは「林檎と蛇」のアイディアを提供するなど重要な役割を果たしていたことが本人の口から語られている。
「不死者」同士には現実世界でもお互いを引き寄せてしまう性質があるため、「ザ・ワン」が芸術活動をしている場にも「ジ・アザー」は自然に歩み寄ってきてしまう。
『アンブロシオ』においてマチルダと悪魔が会話する場面の逆再生世界で、「ザ・ワン」と「ジ・アザー」はお互いに人類に対する見解の相違があることを示唆し、またその諍いが初めてではないことも明らかにする。
『アンブロシオ』の撮影終了パーティでも二人は裏の世界で何か口論をしていた様子で、それは現実世界でのマリッサと悪魔役の男性の表情にまで反映されている。

『ミンスキー』の撮影現場にも「ジ・アザー」は美術係の女性の姿で早々に入り込むと「アーティスト」たちに対する侮蔑の思いを隠さずに吐き出し、またも「ザ・ワン」から嫌悪されている。

そしてこの美術係の女性の体を放棄したのか維持したままでいたのかは不明だが、「ジ・アザー」は『ミンスキー』の撮影途中でカール・グリーンウッドに寄生する。
目的は、「ザ・ワン」が熱心に行っている「彫刻」には意味がないこと、人間の作る芸術作品に価値などないことを「ザ・ワン」に理解させることだ。
苛立つ「ザ・ワン」に対し「ジ・アザー」は選択を突きつける。
それが「我々か、彼らか」という、1970年8月30日の撮影(ミンスキー 17A)の逆再生世界での問いだ。

「ジ・アザー」には、銃の暴発事故を装ってジョン・デュリックを始末する計画があった。
「ザ・ワン」の芸術活動を終わらせ、「不死者」としての生存を優先させるための少々強引な二者択一だ。
徒労ばかりの芸術活動などより、世界に二人だけ残った「不死者」の絆のほうが「ザ・ワン」にとっては重いはずだと「ジ・アザー」は考えていたのだろう。
ところが予想外に「ザ・ワン」の選んだ答えは選択肢のどちらでもなく、「自分自身」というものだった。
「ザ・ワン」は「ジ・アザー」を火葬することで永遠に葬り、その後ジョンを貪ることで自身の操り人形とした。
「ザ・ワン」は文字通り世界にたった一人だけとなり、エイミー・アーチャーによる当該フィルムの目撃によって「ジ・アザー」が復活するまで、ジョン・デュリックを宿主として孤独な映画作りを続けていた。
Q. 「偉大な物語」とは何か?
A. 「不死者」たちが作り出した旧約聖書と新約聖書にまつわる物語。つまりヨーロッパとアメリカ大陸で最も大きな勢力である宗教。
(解説)
直接的な言葉では一度も明言されていないが、「偉大な物語」が旧約聖書から新約聖書へと連なるキリスト教の物語を指していることは、逆再生世界で語られる言葉をじっくりと追っていけば自然に気がつくことだろう。
傍証を挙げていけばきりがないが、
・「ザ・ワン」は磔刑を経験している
・「林檎と蛇」の発案者が「ジ・アザー」
・「ジ・アザー」が「ザ・ワン」に「彼らは君の死と復活を目撃した」と述べている
・逆再生世界のTVショーの司会者から「あなた方は我々の罪のために死んだと?」と尋ねられ、「ジ・アザー」は「物語だ(A story.)」と答えている
・「ザ・ワン」は聖母マリアの服装を個人的に知っているような口ぶり
・「処女懐胎」にはトリックがあったと「ザ・ワン」が述べる
といったあたりがわかりやすいところか。
「偉大な物語」を「不死者」たちが作り上げた理由は前述したように、「不死者」と人間の統合を進めるためのものだ。
「不死者」のもつ価値観や世界観を人間に共有させることで、「不死者」を「異物」ではなく「人間性の一部」として受け容れさせる下地作りをした。
また、「不死者」たちの弱点は宿主の肉体を火葬されてしまうことであり、これを禁ずるための倫理を構築する必要もあったのだろう。
(キリスト教では火葬を禁忌とする意見が根強い)
しかし「ザ・ワン」がたびたび述べているように、近現代に至って「偉大な物語」は著しく衰退した。
『アンブロシオ』で描かれるようにキリスト教会内部にも堕落は蔓延し、異端狩りのための火刑をも積極的に行った時代すらあった。
ほとんどの人間は「偉大な物語」を心から信じてなどいない。
そうした思いが「ザ・ワン」の焦りや「ジ・アザー」の失望と憤りに繋がっている。
「ジ・アザー」は人間性との統合などはとうに諦めてしまっており、「不死者」はただ生存だけを優先し、可能なかぎり人間社会と関わらない生き方を模索するべきだと考えている。
人間との統合を諦めきれず、芸術活動に活路を見出そうとあがいている「ザ・ワン」とは『アンブロシオ』以前にも幾度も口論となり、喧嘩別れとなっていたようだ。

復活後に「ジ・アザー」が意見を変えるのは、自身が人間の芸術活動によってより高次元の存在になったためであり、ここに至って「不死者」と人類は統合に向けて最初の大きな前進を遂げることになった。
Q. 登場人物の台詞の意味がわかりづらい箇所があるが?
A. 誤訳、あるいは言葉のチョイスの問題で、すんなりとは意味を理解しにくい日本語字幕になっている部分がある。
(解説)
『Immortality』にはおおむね良質な翻訳がされた日本語字幕が付いているが、プレイヤーのストーリー理解を困難にしてしまうような訳も数箇所ほど見受けられる。
細かい誤字脱字はひとまずおくとして、特に重要な誤りを2点挙げておく。
まず、1970年8月25日のフィルム(ミンスキー 24A)の逆再生シーン。
ナイトクラブの個室トイレでのマリッサとカールのセックスシーンの裏側で、「ザ・ワン」と「ジ・アザー」が同じように演じている場面。
「ジ・アザー」が「ザ・ワン」に告げる台詞の字幕が
誰もいない
となっているが、英語での実際の台詞は
No pretense.
で、これは
「ふり」をするな
とでも訳されるのが適当。
おそらく「pretense」(見せかけ、ふり)を「present」(存在している)と間違えたものと思われる。


そして2つ目が、「ザ・ワン」がモノローグで「制約」(chain)について語っている一連の場面。


この「制約」と訳されているもともとの単語は「chain」であり、これはおそらく「連鎖」という意味のほうが強い。
「制約」と似ている「束縛」「足枷」という意味合いもあるかもしれないが、これは芸術家たちの「食物連鎖」を連想させる語りであるため、やはり「連鎖」と訳されるべきだろう。
もちろん、字幕には表示時間と文字数という厳しい制限があるため、非常に難しい翻訳であったことは言うまでもない。
以下に英語での原語、日本語字幕、筆者が字数を気にせず個人的に訳したものを示すので、比較してみてほしい。
There's a chain.
It's very visible if you're sat outside of things.
Arthur Fischer and John Durick were on that chain.
Ideas, traditions, techniques, organic matter gets passed along.
Fischer passed me on to Duric or Duric took me, or I chose to go, it's hard to say.
They both wanted to claim me as theirs.
There's a lifecycle to an artist and it's very important to get the timing right to prune, to use one to fertilize another.
With John, it was the first time I put myself into the chain.
制約がある
離れてみるとよくわかる
フィッシャーとデュリックも 制約に囚われていた
思想 伝統 技法
人を通して受け継がれていく
フィッシャーは 私をデュリックに託した
デュリックが私を奪ったか 私が去ったのかも
2人とも私を手に入れようとした
芸術家は移り変わる
古い者を糧に 他の芸術家を芽吹かせるには
時期の見極めが大切
ジョンの作品で 私は初めて
制約に身を投じた
「連鎖」というものがある。
その外に身を置かれればはっきりと見える。
アーサー・フィッシャーとジョン・デュリックはその「連鎖」の中にいた。
アイディア、流儀、技法……有機物が受け継がれていくように。
フィッシャーが私をデュリックに引き継ぎ……あるいはデュリックが私を持ち去ったのか、私自身がそうすることを選んだのか、よくわからないけど。
彼らは2人とも、私を自分のものだと主張したがっていた。
芸術家にはライフサイクルがあって、どこで切り捨てるか、どこで一方をもう片方の肥やしとするか、そのタイミングが大事。
ジョンと一緒に、私は初めて「連鎖」の中に身を置いたわ。
考察は以上となります。
大変長文になってしまいましたが、お読みいただきありがとうございます。
自分の中である程度明確な答えが出せていないいくつかの疑問も残っていますが、何らかの答えが得られれば記事に追加してみようと思います。
感想や疑問、ご意見などあれば、どのようなものでも大歓迎ですのでぜひお寄せください。

