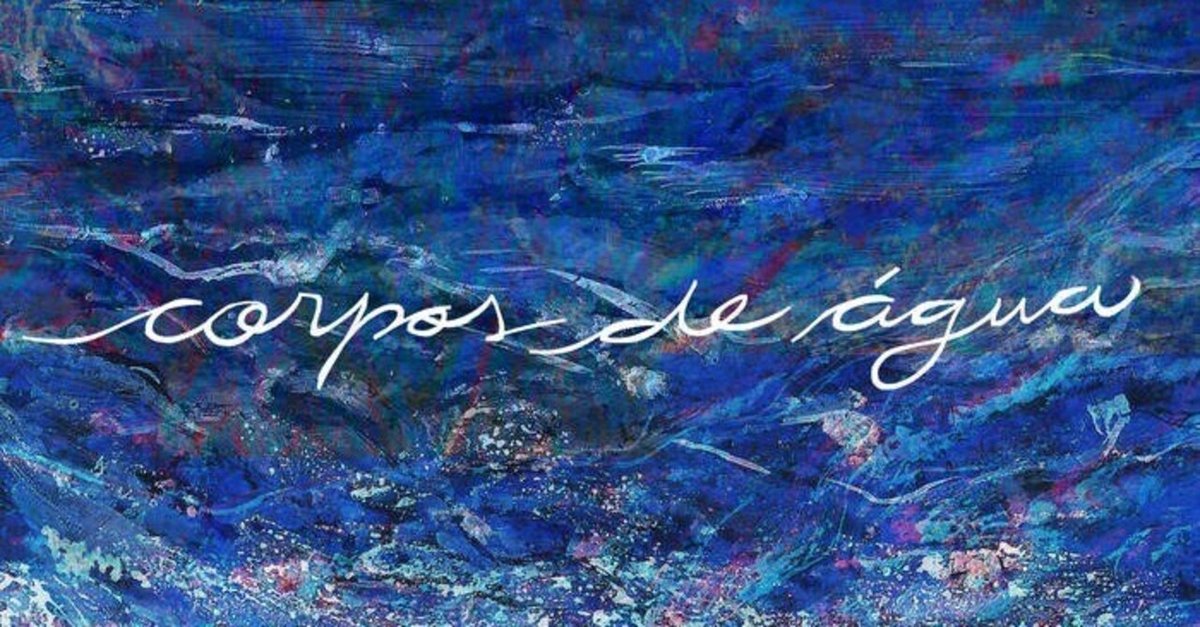
sonhos tomam conta『corpos de água』(2024)
2023年の暮れ、PitchforkとStereogumから2020年代のシューゲイザー・リバイバルを総括する記事が立て続けにリリースされたのを覚えている。両者の論旨には共通点が多く、DusterがTikTokで「#shoegaze」のタグと共にバイラルヒットした現象について言及され、いわゆるZ世代にとってシューゲイザーやドリーム・ポップのサウンドが新鮮に受け止められている事実が、様々なプロジェクトの名前を挙げて解説されていた。
それまでスロウコア/サッドコアの中心バンドとして受容されていたDusterの扱いからも明らかなように、「#shoegaze」の定義はさして厳密ではない。Deftones〜Smashing Pumpkinsのヘヴィな重低音から影響を受けたquannnicの周辺アーティストをはじめ、よりグラマラスにシューゲイザーのサウンドを解釈した(と言われている)Yves Tumorやbar italiaもシーンの周縁を象る存在として捉えられている。RideやSlowdiveの復活(そういえば2025年にはMy Bloody Valentineがダブリンでライブを開催するみたいですね)も重なり、シューゲイザー・リバイバルという現象は多方面から外堀を埋めるように形成されていった。
新しい世代の話に移ろう。2020年代に出現したシューゲイザー関連のプロジェクトの特徴は、発生場所が一元でないことだ。サウスロンドンから、マイアミから、東京から……といったフィジカルな繋がりは重要でない。強いて指摘するならば、デジタル・ネイティブ世代である彼らにとっては、幼少期からのインターネットでの経験が共通していることくらいだろうか。結果的に、このムーブメントは多国籍/無国籍な性質を帯びたものとして成長した(これに関してはヴェイパーウェイブとかハイパーポップとか、インターネット発のムーブメント全般に当てはまる傾向なんだろうけど)。
最も象徴的な例はミシガン州を拠点とする〈Longinus Recordings〉からリリースされたParannoul + Asian Glow + sonhos tomam contaによるコラボアルバム『Downfall of the Neon Youth』(2021)だろう。韓国出身のParannoulとAsian Glowにブラジル出身のsonhos tomam conta。本作は韓国語と英語とポルトガル語の3言語で歌われ、本格的にリバイバルが叫ばれはじめた2021年のシーンを代表する一作となった。
上記の状況を整理することで、ようやくsonhos tomam contaの最新作『corpos de água』に傑作の判を押すことができる。多国籍/無国籍であり、フィジカルの制約を不問にできる現在のシューゲイザー・シーンの中心に位置するプロジェクトの一つとして目されていた、サンパウロ在住のLua Vianaによるsonhos tomam conta。『corpos de água』はその磁場から這い出て、代替不可能な本人性を自覚し、フィジカルなものへと表現を引き寄せる覚悟に満ちているのだ。
アルバム冒頭、「uma súplica」〜「oração do mar」の流れから驚かされる。そのクラシック・ギターのパターンは、明らかにサンバ〜ボサノヴァ由来だ。ボーカルはウィスパーボイス、自然への畏怖と祈りを滔々と重ねる。深いリバーブのかかったエレキ・ギターさえ入っていなければ、少しシリアスなボサノヴァ小品として聞けそうだ。しかし、一度アンビエンスへと潜り、「oração do mar」で先ほどのパターンが再浮上すると、そのままのテンションで激情パートへと移行する。さらに後半ではボサノヴァ特有の拍の頭でリズムを解釈するセオリーに則ったキメさえ挿入される。
ここに一つの発明がある。ボサノヴァとシューゲイザー、成立過程の全く異なる二つのジャンルに「ウィスパーボイス」という共通項を見出すことにより、sonhos tomam contaは難なく両者を架橋したのだ。その後に続く7分の大作「tuas pegadas」も同種の調合だ。さらに激情パートから始まる「de areia e sal」ではよく耳を澄ますとリムショットとスルド〜ロータムが忍び込ませてある。これはサンバでは定番のセクションであり、ディストーション・ギターの洪水に対して屹立する錨のように配置されている。注意深く聞けば聞くほど『corpos de água』がブラジル音楽のセオリーに即したコンセプチュアルな性質を帯びていることがわかるはずだ。
これには主宰のLua Vianaの、自身のパーソナリティに関する深い理解が関係している。本作のリリースにあたって公開されたインタビューで、Luaは自身がブラジル音楽から受けた影響についてこう述べている。
私は、あらゆる芸術作品には固有のメタデータが付随していると考えています。物事は、特定の時間と場所から生まれたからこそ、そのあり方で存在しているのです。私はずっとブラジル音楽を聴いてきましたが、それは常に私の音楽的なボキャブラリーに深い影響を与えてきました。意識的か無意識的かは別として、私は常にサンバ、MPB、ボサノバからインスピレーションを得て、作曲をより味わい深いものにし、より自分らしさを表現しようとしています。結局のところ、私はブラジル人なんです。疎外感と貧困の中で育ち、ほとんど何の資源も持たずに生きてきたのです。
実はsonhos tomam contaの過去作、またはLua Vianaのアンビエント・プロジェクトであるmoondaughterの作品において、ブラジル音楽の要素は長らく顕在化していなかった。前年リリースのEP『the movies aren't enough』収録の「o oceano de solaris (ft. magnólia)」で、初めて象徴的なクラシック・ギターのリズムパターンが登場する。解決することなく進行するコードワークも含め、『corpos de água』の前夜とも呼べる内容だ。『the movies aren't enough』の楽曲で唯一、「o oceano de solaris (ft. magnólia)」のみが『corpos de água』に収録されている。
Luaは自身に備わっているブラジル音楽からの影響を「メタデータ」と秀逸に喩え、それを自覚/実践し、ボサノヴァとシューゲイザーを接続する『corpos de água』のアレンジを発明した。ここでシューゲイザー・リバイバルでは保留できていたはずの本人性が再度立ち上がることとなる。3年前の『Downfall of the Neon Youth』には言語以外のローカルを規定する要素がなかった。しかし、『corpos de água』は揺るがし難い固有性が「メタデータ」として付着している。これを作ったのは、サンパウロに住む、一人の女性なのだ。
ゆえに『corpos de água』の立ち位置は特殊だ。前年に「#shoegaze」で巨大なバズを生み出したWispの「Your Face」が、grayskiesの制作したシューゲイザー風味のタイプビートを購入し、そこにボーカルを吹き込んだものであったこととは、ある意味で対照的だ。優劣の話ではない。むしろ潮流に適っているのは、本人性を保留させながらも自身の声をより多くのリスナーへと届けたWispなのかもしれない。ただ、Luaは本人性を「選択」したのだ。
『corpos de água』が作者の固有性を孕んだサウンドになっていることには必然性がある。これまでのsonhos tomam contaの作品でも、Lua自身の憂鬱や社会への絶望はシリアスなものとして歌われてきた。しかし『corpos de água』ではより具体的な怒りとして歌詞に反映されている。Simon & Garfunkelのカバーである「Scarborough Fair」は反戦歌「Canticle」を挿入したヴァージョンが採用されている。Luaは本作にガザ虐殺の問題を絡め、「時代錯誤」的な行為を強く非難する。そして、この歌は《From the river to the sea, free palestine》というオリジナルの一説で締められている。
プロテスト・ソングは今でも重要だと思いますか?個人的にはデジタル時代には音楽が社会運動に与える影響や意味が弱まっているようにも思えるんです。
プロテスト・ソングがかつてほど重要ではなくなっているという懸念は理解できますし、音楽が社会運動に与える影響力が失われつつあるという意見にも同意します。 全てはマーク・フィッシャーが著書『Capitalist Realism』で説明している新自由主義とその文化的努力による断絶の影響に帰結すると思います。 私見では、帝国主義/自由主義の現状を公然と批判し、実際の変化を提案する芸術が注目されないことこそが問題なのだと思うのです。特にアメリカでは、ブッシュ政権以来、主流派の中で帝国を批判するアーティストが成し遂げたことと言えば、Green Dayのアメリカンドリームを風刺した「American Idiot」くらいでした。
しかし、今こそ、こうしたテーマに取り組む絶好の機会が訪れていると思います。大量虐殺があからさまになるにつれ、反戦運動はベトナム戦争以来、かつてないほど活発になっています。また、南半球の特殊性も、こうした政治的なテーマを議論する上でより良い機会をもたらしていると思います。ですから、私はアーティストとしてできる限りのことをしようとしています。政治的な見解をオープンにし、より多くの抗議アートを制作しようとしています。現代の限界はありますが、私は今でも音楽という芸術形式には人々を鼓舞する大きな可能性があると考えています。
「南半球の特殊性も、こうした政治的なテーマを議論する上でより良い機会をもたらしていると思います」という解釈には、単なるボサノヴァとシューゲイザーの合成以上のローカリティが滲んでいる。ここには先のインタビューで引用した、サンパウロでの決して裕福とは言えなかった生活風景も含まれるだろう。加えて、Luaは自身がトランス女性であることを公言しており、ブラジルという国家においてLGBTQ+が置かれている窮状についても自覚的である。その背景については2022年に本邦でも公開された映画『私はヴァレンティナ』が詳しい。2010年代に同性婚の合法化がラテンアメリカの中でも比較的早いタイミングで認められた一方、トランスジェンダーの殺害数が世界ワースト1位という危機的な状況にあるブラジル。元大統領のジャイル・ボルソナロが極右的な政策方針であったことも、本国のマイノリティには深い失望を与えたという。
現世に存在するありとあらゆる作品に本人性は含まれているし、パーソナリティや固有性を完全に棄却する方がアンタッチャブルな試みだ。しかし『corpos de água』でLuaは本人性をより深い位置で引き受けることを選択し、その試みが未だ誰も辿りついたことのないサウンドを導き、他の誰でもないメッセージへと結びている。ここに込められている「祈り」は、誰の名前で呼ぶこともできないし、誰の名前であっても問題ない。
私の声を聞くことのできない人々に祈る
水の中で生まれ変われる奇跡を
土で汚れたこの体を崩壊させ
そして永遠の源へと私を連れて行く
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
