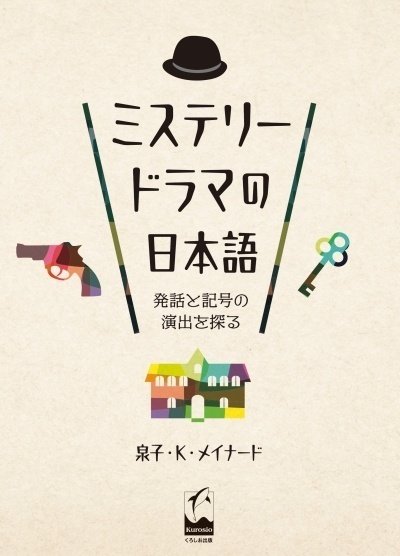16(最終回). 本で冒険する! 『ミステリードラマの日本語 ―発話と記号の演出を探る』 くろしお出版 2023
あくまで個人的な事情
筆者はミステリーが好きである。特に内田康夫による旅情ミステリー、浅見光彦シリーズは、作品を通して日本全国を旅しているような気分にさせてくれる。海外に住む者にとっては、望郷の念と重なることもある。そして、永遠に33歳の独身青年という浅見光彦がトヨタ・ソアラを運転する姿は、以前筆者も運転していたトヨタ・クレスタを思い出させる。(古すぎました!苦笑)
昨今、ポピュラーカルチャーを代表するミステリー作品は、多くテレビドラマ化されている。本を読むのと違って、ドラマには、会話が豊かにドラマチックに演出される。ミステリードラマの日本語は、日常の自然言語とは異なるが、メディアの日本語の一部として消費されるわけで、日本語文化の一部であることは否定できない。ドラマの登場人物は、それぞれのキャラクターを強調することで、作品を盛り上げる。そこで筆者は、最近のミステリードラマを選んで(はい、ご想像通り、浅見光彦も登場します!)、演出される発話と記号を考察することにした。
分析の対象とするのは、探偵ドラマや刑事・警察ドラマなどを中心とする連続・継続ドラマシリーズで、2010年以降、特にここ2、3年にテレビ放送された25作品(253話分)である。実例として考察する会話部分は434例であり、これらをデータとして、制作者の創造的で複雑な発話と記号の演出のプロセスを、言語学、会話・談話分析、記号論の視点から観察・考察する。
発話と記号の演出
本書では、筆者が提唱してきたキャラクター・スピークを分析概念として、キャラクターやキャラが具現化する様子を追う。具体的には、発話行為のルールから逸脱した表現、モノローグや決め台詞、方言や世代差、職業などと関連付けられるバリエーションを分析する。さらにキャラクター・スピークに焦点を当てながら、ジェンダーに関わるアイデンティティ、外国語や非母語としての日本語とステレオタイプ、潜入・偽装捜査官のアイデンティティとその交錯、などを考察する。
以下、ごく限られた例であるが、簡単に演出方法を紹介しておきたい。まず、発話行為(Speech Act)のルール違反、具体的には発話行為の未遂行と、発話行為の誤解の例を観察しよう。(1)では、紐倉が期待される感謝の気持ちを伝える発話行為を遂行していないことを、高家が指摘する。「そうか」で済ませようとする紐倉に対して、「ありがととか言ってごらんよ」とまで言うのである。紐倉の「そうか」は、お礼を言うという感謝の発話行為が期待されるコンテキストであるにもかかわらず、その期待を裏切る。相手を思いやることのない発話態度が確認でき、独りよがり、自己中心的なキャラクターが認められる。従来、発話行為論では、行為として成り立つ条件とその効果について論じられることが多かった。しかし、ドラマの演出には、あえて期待される行為から逸脱することが、それなりの発想・発話態度の表現手段となり、キャラクター・スピークとして機能する。
(1)『インハンド』第4話(TBS 2019)
高家:今メールで送ったぞ。
紐倉:何を?
高家:治験のデータに決まってんだろ。
紐倉:そうか。
高家:そうかって、何かねぎらいの言葉とかないのか。ありがととか言ってごらんよ。
(2)には、発話行為を自分の都合の良いように受け取る誤解が観察できる。褒める発話行為だと誤解する入間の能天気なキャラが発動される。
(2)『イチケイのカラス』第2話(フジテレビ 2021)
坂間:あなたは言うなれば、密室があれば、あえて飛び込む。そう、迷えると書いて、迷探偵!
入間:そんなにほめられたら照れちゃうよ。
坂間:ほめていません!
次に、モノローグとつぶやきが、会話参加のルールに違反する場合を観察しよう。会話は、参加者が互いに相手から期待される発話の順番をとって話者交替することで成り立つ。しかし、モノローグ(語りと告白のためで、発話者はスクリーンに登場しない)と、つぶやき(スクリーンに登場し口を動かすが特定の相手に向けられない発話)が導入されることがある。浅見光彦シリーズには、浅見のモノローグとつぶやきが多く用いられるのだが、それは原作がミステリー小説であることに起因していると思われる。ドラマが小説の手法に割合忠実に制作されているため、モノローグとつぶやきが小説の内面描写の代わりとして用いられるのだろう。(3)は、素人探偵として推理しながら、いろいろと思いを巡らせる浅見のキャラクターを決定的なものとする例である。浅見は関係者(松雪)の案内で道を歩いているのだが、会話には参加せず、彼独特の推理に没頭している。最初はモノローグを繰り返すものの、結局「松雪さん…連れて行って欲しいところが」と話し掛け、会話に参加する状況が観察できる。
(3)浅見光彦シリーズ『神苦楽島』(フジテレビ 2015)
松雪:このあたり、最近のコミック好きの若い女性には人気スポットになるんじゃないかって、うちの山元部長は言ってましたけど、私にはわかりません。
浅見:[歩きながら松雪を無視してモノローグで]〈中田悠理さんと三浦延之さんは、どうして殺されなくてはならなかったのか……〉
松雪:あの、私、こういうこと好きでやってるわけじゃないんで、興味ないなら言ってもらえませんか。
浅見:[歩きながら、松雪を無視して]〈考えられるのは、口封じ……〉 松雪:[怒って踵を返し]帰ります!
浅見:[振リ帰って話し掛ける]松雪さん…連れて行って欲しいところが。 松雪:[溜息混じりに]はぁー。
浅見光彦シリーズには、モノローグやつぶやきといった多様な引用方法が駆使され、その効果として浅見の複雑な声とそれに対応する相手の声が聞こえる。そのキャラクター・ゾーンには、浅見の思考過程や感情、そして発想・発話態度が反映され、それに伴って思慮深く、あくまでマイペースなキャラクターが強調される。
なお、本書の後半では、人称・呼称、笑いのレトリック、文字テロップという異なるタイプの演出方法を記号現象と捉え、それらが登場人物のキャラクター、キャラ、性格などを印象付ける様子を観察する。以下、一人称表現とキャラクター設定の関係について簡単に紹介したい。『メゾン・ド・ポリス』に登場する中年男性たちの一人称の演出が興味深い。ドラマは、警察関係の仕事を引退した男性がシェアハウスで共同生活をするという設定であり、(4)はバレンタインのチョコの味見をしているシーンで、「私」、「僕」、「俺」という一人称が選ばれる。いつも丁寧でフォーマルなリーダータイプの伊達は「私」を、女性に親しげで軽い感じの藤堂は「僕」を、そして、男っぽくざっくばらんでダ体を好む迫田は「俺」を選ぶ。対照的な一人称の選択によって、それぞれのキャラクターが演出される。
(4)『メゾン・ド・ポリス』第6話(TBS 2019)
伊達:私はもう少し、なつかしい味の方が、好きですねえ。
藤堂:僕はもう少し、情熱を感じたいかなあ。
迫田:チョコ、嫌いなんだよ、俺。
同様の演出が:『科捜研の女〈21〉』にも観察される。『科捜研の女〈21〉』の最終話には、長年一緒に仕事をしてきた科捜研のメンバーたちが、法医研究員である榊マリコに次の一人称表現を使ってお礼を言うシーンがある。
(5)『科捜研の女〈21〉』最終回スペシャル(テレビ朝日 2022)
呂太:僕ってさ…なんか、みんなとずれてたり…普通じゃないってよく言われる。
亜美:私も、パソコン命のオタなんで(略)。
蒲原:俺…時々思い出すんです。
日野:正直、僕もいい歳だから、マリコ君の尻ぬぐいなんかやめて(略)。
宇佐美:自分は…自分は、妹を犯罪で、失くしました。(略)マリコさんに教わったから、自分はここにいます。
土門:俺は、最初に会ったとき、こんな女とは、絶対二度と、一緒にやるもんかと思った。
シリーズ最後で交わされるこの会話は、登場人物のキャラクター作りの総仕上げと言える。子供キャラクターの研究員呂太は「僕」、同じく研究員の亜美は「私」、所長の日野は「僕」、蒲原刑事と土門刑事は「俺」、そして実直で控えめの研究員の宇佐美は「自分」を使う。この選択は、マリコと他のメンバーとの関係、つまり、科捜研内の自分の立ち位置と、演じるキャラクターの相関関係によって動機付けられている。人称表現という記号は、キャラクター・スピークとして機能し、その選択は、相手の反応によって支えられながら、それぞれのキャラクターとしての役割を決定的なものとしていく。
ポピュラーカルチャーの学問的冒険
本書で報告するキャラクター・スピークは、キャラクターとアイデンティティの関係を浮き彫りにするのだが、それはポストモダンの日本社会における私達に、その在り方を哲学的に考察するように誘う。ミステリードラマを分析することで得られるキャラクター・スピークの発見は、自分と他者のキャラクターやキャラ発動を楽しむことをも可能にする。
また、最終章では、ポピュラーカルチャーの日本語と日本語教育の関係を理解し、研究結果を日本語教育に応用したり、日本語学習に役立てたりする可能性に触れる。
日本のポピュラーカルチャーは、いわゆるソフトパワーの一部として、商品化され、その演出を凝らした娯楽・芸術作品群は、国内のみならず、アジア圏をはじめとして海外でも広く消費されている。消費する商品としての日本語とは、いったい何者なのか。筆者は、ミステリードラマを分析・考察しその答えを探すことで、変化を続ける日本語の姿の一面を見極めることができたのではないかと思っている。
■この記事の執筆者
泉子・K・メイナード(Senko K. Maynard)
山梨県出身。AFS(アメリカン・フィールド・サービス)で米国に留学。甲府第一高等学校およびアイオワ州コーニング・ハイスクール卒業。東京外国語大学卒業後、再度渡米。1978年イリノイ大学シカゴ校より言語学修士号を、1980年ノースウェスタン大学より理論言語学博士号を取得。その後、ハワイ大学、コネチカット・カレッジ、ハーバード大学、プリンストン大学で教鞭をとる。現在、ニュージャージー州立ラトガース大学栄誉教授(Distinguished Professor of Japanese Language and Linguistics)。会話分析、談話分析、感情と言語理論、語用論、マルチジャンル分析、創造と言語論、ポピュラーカルチャー言語文化論、言語哲学、翻訳論、日本語教育などの分野において、日本語・英語による論文、著書多数。
くろしお出版から刊行の著書
■この記事で取りあげた本
泉子・K・メイナード
『ミステリードラマの日本語 発話と記号の演出を探る』
くろしお出版 2023
出版社の書誌ページ