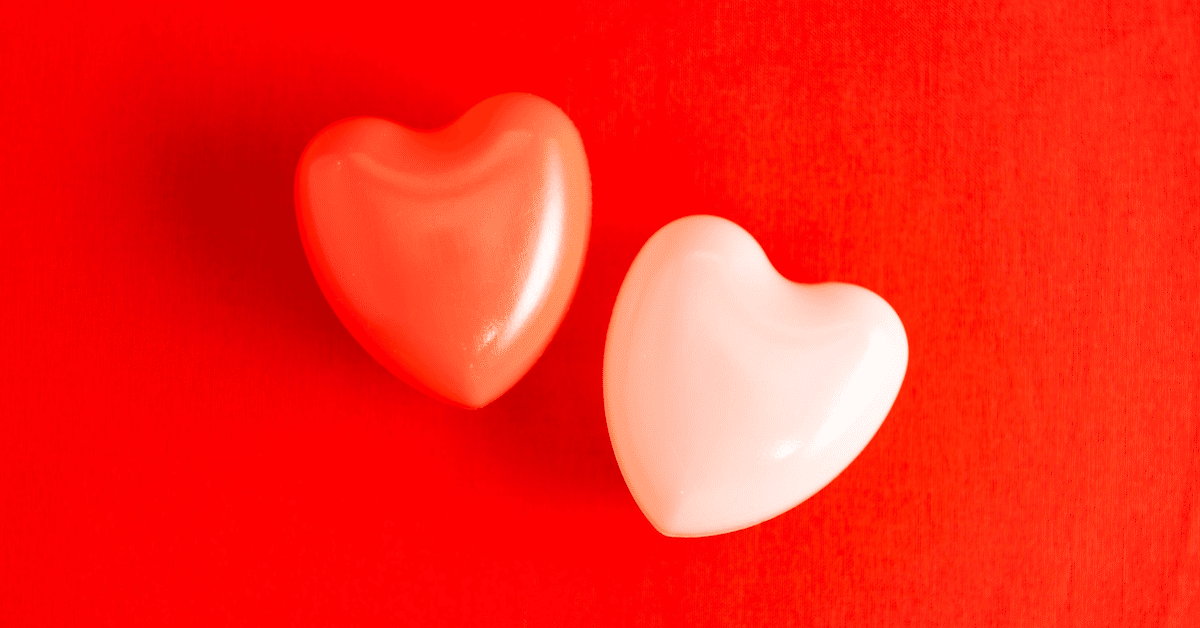
【恋愛小説】噛みたいハート
アフターおねショタ的な話です
初めて静香お姉さんと出会ったとき、僕はお姉さんのことを殺人鬼だと思った。
だってお姉さんは、映画で見た殺人鬼みたいに、口の周りを真っ赤に染めて赤い何かを噛んでいたからだ。
しかし、お姉さんは殺人鬼ではなかった。
僕は二階にある自分の部屋の窓から身を乗り出し、庭の桜をかき分けて、すぐ隣に建つ古い借家に越してきたお姉さんを窓越しに見つめた。
お姉さんは泣いていた。長い黒髪のかかる肩を小刻みに震わせながら、大きな赤いハート型のゼリーのようなものを両手で掬うように持ち、それに唇を寄せていた。
「何食べてるの」
夜風を受けて冷たくなった窓の鉄柵に肘をのせ、体重を預けながら僕はお姉さんに聞いた。お姉さんは赤いハートをちゅるんと食べきると、指で口を拭い、窓を開けた。
「恋心よ」
お姉さんはそう言って微笑んだ。僕は桜の香りに混じって、潰れた果物のような甘い香りが夜風に溶けているのに気がついた。
「私はね、恋心を食べてるの」
そしてその瞬間、僕は恋に落ちたのだ。
*
俺はけたたましいアラームの音で目を覚ます。「隼人、起きなさい」と下の階で母さんが怒鳴る。時刻は午前九時。エアコンはタイマーで明け方に切れていて、開けっ放しの窓からは蒸し暑い夏の空気が葉桜の青臭さをのせてやって来る。夏休み初日の朝の空は、蝉の声が絶えず聞こえる青色だ。
汗だくになったタンクトップをばたばたと仰ぎながら一階に駆け降りた俺を見て、母さんは「あんた、さっさとシャワー浴びちゃいなさい。シーツも洗濯に出して」と叫んだ。
「静香ちゃんが家庭教師に来る時間になっちゃうわよ」
九歳の小学生から十七歳の高校生に成長する中で、「僕」は「俺」になり、静香お姉さんを「静香さん」と呼ぶようになった。静香さんはその間、ずっと変わらず「隣のお姉さん」だった。
「二週間毎日家庭教師にきてくれるなんて、嬉しいねえ、隼人、え? あんた、鼻の下伸びてんじゃないの?」
「うるせえなあ」
手早くシャワーを浴びて着替えると、チャイムが鳴った。玄関扉を開けると白色のワンピースを着た静香さんが立っている。静香さんは長い黒髪をかきあげると、俺の方を見て、「髪、濡れてるよ」と笑った。俺は、多分今俺の耳は赤くなってるんだろうな、と思った。
赤いハートを食べる静香さんを目撃した次の日の放課後、小学生の俺は家の前で静香さんに会った。静香さんはにっこりと微笑むと、俺を家に招いてくれた。
静香さんが通してくれた畳部屋には、昨日嗅いだ甘い香りがかすかに残っていた。俺はたまらず「好きです」と静香さんに言った。
「あら、ありがとう」
静香さんはかがみこむと、小さな俺の頭を優しく撫でた。それから、俺の胸にそっと手を当てた。俺の心臓はとくとくと早く動いていて、その鼓動と合わせるように、黄緑をした手のひらサイズのハートがぽろぽろと三、四個こぼれ落ちたかと思うと、すっと消えた。ハートはすぐに消えちゃうの、きっと元の体に戻るのね、と静香さんは言った。
「君の恋心は、きれいだけど、まだ青い」
静香さんは夢見るように言った。
「熟しきったら、きっとおいしいんでしょうね。きっと、涙が出るほどおいしいの」
それから、俺たち家族は静香さんと親しく交流するようになった。お節介な母さんは、一人暮らしの静香さんによく料理や野菜をおすそ分けしていた。
静香さんは家で占い師のようなカウンセラーのような仕事をしていた。失恋したりつらい恋をしたりといった女性たちが静香さんの元を訪れて相談をするのだ。静香さんは、そんな人たちの恋心を少し食べて減らしてしまう。すっぱり気持ちを手放したいという人の恋心は全て食べ尽くしてしまう。普通の人は恋心が目に見えないから、静香さんに相談すると気持ちがすっきりするのだ、と思って帰路に就く。
「隼人くんが見えるんだもの、びっくりしたわ」
静香さんはしばしば嬉しそうにそう言って、俺の頭を撫でた。
静香さんは恋心を食べるが、天使でも悪魔でもない、人間らしい。いつもは普通にご飯を食べる。恋心を食べなくても生きていけるし、恋心を食べたいとも特に思わない。
「みずみずしい恋心はね、果物や花のいい香りがして、甘いの。人によって味や香りや見た目はいろいろだけどね。だけど、ぼろぼろになった恋心は腐った果物みたいにどろっとして、甘い香りがするのに苦いんだよ」
静香さんと会っていると、俺の恋心は自然とこぼれ出してしまう。
俺は床に転がる果物のようなハートが恥ずかしくなり、目を伏せた。静香さんは俺のハートを手のひらで包むと、「隼人君はきれいな心の持ち主だね」と言ってそっと目を細めた。俺は自分のハートを手に取る。俺の恋心は青りんごと柑橘類の果物と葉っぱの混ざったようなにおいがして、少し舐めると、レモン水のような味がした。
「だめよ」
自分の恋心を味見しようとした俺の頭を静香さんは撫でた。
「自分の恋心は食べちゃだめ」
「ごめんね静香ちゃん、隼人の部屋が汗臭かったらほんと申し訳ないわ」
ジワジワという蝉の声を背にして母さんがそんなことを言ったので、俺は「おい」と声を出した。
「静香さんに変なこと言うなって」
「変なことじゃなくて事実でしょ。あんた高校生になってから図体がすっかりでかくなって、むさくるしいんだから」
「それ去年も言ってただろ」
俺と母親の応酬を前にして静香さんがくすくす笑う。
「お邪魔します」
階段を上がって静香さんを俺の部屋に通した。
「散らかってるけど」
「いえいえ、そんな」
片付いてるわよ、と言いながら静香さんが教材を取り出す。
「じゃあ、夏休み前にやったところをおさらいしましょうか。休憩前に英語をやって、休憩後に国語ね。国語は模試の問題を解いてみましょう」
テキストの文字を追い、高校二年生の一学期の範囲を復習する。出された問題の解答をノートに書き込みながら、視線を上げてテーブルの向かいに座る静香さんの表情を盗み見る。静香さんは真剣な顔をしてテキストをめくり、今日の授業で行う箇所を確認していた。時折シャープペンシルの頭を口元に当てている。
ひと通り解き終わり、採点と解説まで済むと、静香さんが「お疲れ」と微笑んで言った。
「静香さんもお疲れ」
「どうもありがとう」
「氷溶けちゃったから、お茶入れたら水っぽくなっちゃうな」
「大丈夫よ、隼人くんがいいならこのまま頂いちゃいましょう」
「そうだね」
お盆を引き寄せ、結露で濡れた氷入りのグラスに二リットル入りの透明なポットから麦茶を注ぐ。
「はい、どうぞ」
「ありがとう」
グラスを渡すとき、静香さんのほっそりとした手に手が触れてしまい、肩が跳ねた。
静香さんも少し驚いた顔をする。それから、俺の手に視線を落とした。
「隼人くんの手、ずいぶん大きくなったのね。男の人の手って感じ。かっこいいし、学校でモテるんじゃない?」
「別にモテないよ。高校、男子校だし」
「嘘」
静香さんがささやく。吸い込まれそうな目に俺はどぎまぎしながら麦茶を飲む。
「ばれた?」
「バレバレよ。隼人くんの高校、私の母校でもあるもの」
「そうなんだ」
へえ、と俺は言った。
静香さんは出会った頃から過去についてあまり語らない。それに、もしこちらから静香さんのことを聞いたら、黙って姿を消してしまいそうな、儚さ、とは違うけれど、そういう、危うさを感じさせる張り詰めた空気がぴんと張っていた。だから俺は、静香さんの過去をほとんど知らなかった。
「じゃあ、数学の浦野は知ってる? でかい三角定規振り回して、歯の抜けた声で叫んでさ」
「知ってる。数学準備室は浦野先生の声が響いていつも賑やかだったなあ。だけど向かいの国語科準備室はいつも静かで……」
静香さんが窓の方に顔を向けた。その視線の先には葉桜があった。
「ねえ、隼人くんは知ってる? 国語科準備室の窓から見える桜は、とってもきれいなのよ」
静香さんの声はかすかな甘さと切なさを帯びて響いた。俺はどきりとした。
初めて会った日、彼女はなぜ泣いていたんだろう。彼女は誰の恋心を食べていたんだろう。
出会ってから今まで、何度も何度も考えてきた疑問が、今日はひときわ鮮明に浮かび上がってくる。
静香さんは国語科準備室にいた誰かに失恋したのだろうか。そして今もその人を想い続けているのだろうか。
そう思うと胸がしくしく痛んでたまらなくなって、それから、静香さんを愛おしく思う気持ちもどういうわけか膨らんで、気がつくと、「俺は静香さんから見たらまだまだガキかもしれないけど」という言葉が飛び出ていた。
「本気で静香さんが好きなんだ」
本気なんだ……という声を絞り出してすがりつく俺を静香さんは困ったような目で見降ろしていた。目線の位置の高さが、静香さんを静香お姉さんと呼んでいた頃を思い出させる。
「隼人くん、私はおばさんだよ。隼人くんなら、学校の可愛い子と付き合えるじゃない」
「静香さんはおばさんじゃないよ。それに、おばさんでもおばあさんでも関係ない。静香さんが好きなんだ」
胸の鼓動が早くなる。淡い緑と黄色、赤色がグラデーションをつくる、熟れ始めた果実のようなハートがぽろぽろといくつも俺の胸からこぼれ落ちた。艶のあるあんずのような厚みとにおいのそれを、静香さんが一つ拾って覗き込む。
「きれい」
静香さんは魅入られたような目をした。初めて会った夜も、その後俺の青いハートを見たときも――恋心を前にしたとき、静香さんはこういう、どこかぞっとするような美しい目をする。普段は凪いだ風のように微笑んでいる彼女の、淡く澄んだ目には、ひとときだけ赤い火がともる。
「隼人くん、私は隼人くんが思っているようなきれいな人間じゃないよ」
その目を見ていれば分かるよ、と俺は言う。
「隼人くんは私のこと、あんまり知らないでしょう」
静香さんが教えてくれないからね、と俺は言う。
「意地悪」静香さんはつぶやくと、白い喉を反らせて薄くなった麦茶を飲んだ。その姿や仕草は少女みたいに可憐だった。
その日以降の家庭教師の時間はどことなく気まずい、よそよそしい空気が流れた。しかし、黙々と勉強を進めたおかげで、予定よりも早く二週間分のカリキュラムが終了した。
「時間に余裕があるわね。何か質問とか、やっておきたい範囲はある? それとも夏休みの宿題をやる時間にしましょうか」
「そうだなあ……」
ノートを開いたままのテーブルにだらりともたれる。
「ねえ、静香さんって、どうしてここに越してきたの」
「なに、いきなり今になってどうしたのよ」
「別に。俺が静香さんのこと、あんまり知らないでしょってさ、この前静香さんが言ったから」
言いたくないなら無理に言わなくていいけど、と言うと、「ませたこと言って」と頭を軽く叩かれた。
「高校を卒業した後、一年間会社勤めしたんだけどね、ちょっと神経が参っちゃって、会社を辞めたの。会社の寮を出なくちゃいけなくて、だけどまあ身寄りもないし……どうしたものかなあって、なじみのあるこの辺りをふらふらしてたら、隼人くんの家の桜が見えたんだ。桜が見えるところに住んでみたいな、って思ってたら、すぐ隣に借主募集の看板が立ってて」
まあ、今はおかげさまで元気よ、賃料も安いしラッキー、と静香さんが言った。それは良かった、と俺は答える。
「静香さんは桜が好きなんだ」
「そうかもね」
桜自体が好きなの?それとも桜にまつわる思い出が好きなの?という質問が喉まで出かかって止まった。そんなことを言うのはさすがにデリカシーがなさすぎるだろう。
夏休みに入ってから二週間が経った。
静香さんが夏休み、家庭教師に来る期間はあっという間に終了した。
俺は静香さんに対し、押せばいいか引けばいいか考えかねていて、しつこく迫っても迷惑だろうな、と思いつつ、遊びや祭りにも誘いかね、味気ない八月中旬を過ごしていた。
高校の夏休みは八月と九月の二ヶ月だ。俺の高校の友達はまあそんなに張り切って海やプールなどに行くたちでもないし、住むところは離れているし、やや暑さが収まるであろう九月に小旅行に行けば上々だろう、という様子だった。夏期講習帰りに会えるというのもある。そういった夏休み事情を聞いた母さんはスイカの種を噴き出しながら「枯れてんね」と切り捨てた。
一方、母さんはライブだの舞台だのと充実した夏を過ごしていた。父さんは帰宅が遅いから、俺はそういった日の昼間、一人で簡単な食事をしたりゲームをしたりして気ままに過ごしていた。
この日も同様だった。
俺はがらんとしたキッチンでカップラーメンを作りながら雲一つない青空を窓越しに眺めた。そういえば、静香さんをここ数日見ていない気がする。
普段なら窓が開く音や鍵を開閉する音でなんとなく生活している様子が分かるのに、出かけているのかな、と考えた俺は、ふと、そんな風にプライバシーが筒抜けの相手から告白されるのはかなり気が重いことなのではないだろうか、という思考に至った。
さっと血の気が引く。詳しい事情は知らないが、色々と辛い中、静香さんはやっと隣の家に落ち着いたのに、俺はそれをおびやかしたのだ。小学生の頃なら子供の戯れととらえてもらえただろう。だが、今は違う。俺は中肉中背な体型で、筋骨隆々な大男というわけではないが、静香さんの身長をもう越してしまっている。
俺は静香さんにとって恐怖と忌避の対象なのかもしれない。そう思うと申し訳なさでいたたまれなくなった。タイマーが鳴る。背を丸めてカップラーメンをすすっていると、家の外からガタンという大きな音が聞こえてきた。なんだと思い、窓から外を見ると、隣家の玄関で静香さんがうずくまっているのが見えた。
「大丈夫?」
俺は慌てて外に出ると、静香さんに駆け寄った。静香さんは苦しそうに息をしていた。
「ごめんね、大丈夫、夏風邪こじらせちゃって、しばらく寝てたんだけど良くならないし、解熱剤とか食べ物とか買おうと外に出たら転んじゃって……」
「無理しないで、俺……じゃなくても、母さんとかに連絡してくれれば」
「迷惑はかけられないと思って。結局迷惑かけちゃってるけど……ごめん」
謝らないでくださいと言うと静香さんに肩を貸した。
「俺がすぐ買ってくるから静香さんは家で寝てて」
「ありがとう……」
静香さんを助けながら静香さんの家の二階に上がり、布団に寝かせると、俺は急いで近くのドラッグストアへ走り、解熱剤、冷却シート、スポーツドリンク、おかゆ、桃缶、その他レトルト食品や飲料を買って戻った。
「静香さん!」
「大丈夫、ありがとう」
静香さんは少し掠れた声で言うと、ごくごくとスポーツドリンクを飲んだ。
「生き返る……」
「おかゆもあたためて来るから」
「ありがとう、せっかくの夏休みなのにごめんね」
「謝らないでよ」冷却シートを静香さんの額に貼りながら言う。「こちらこそ、ごめん。本当は俺じゃなくて母さんがやった方が良かったよね」
「どういうこと?」
「いや、だから、小学生の頃ならともかく、俺、それなりにでかくなったし、静香さんに好きだって言ってる男だし、怖いかなって……」
そう言った俺に向かって静香さんはぷっと噴き出した後、げらげらと笑い出した。
「隼人くんは優しいのね。だけど、気にしなくていいのよ。私、隼人君をけだものみたいに思ってなんかいないんだから。むしろ私の方こそ未成年なんとか罪に問われちゃうわよ」
「なんとか罪ってなんだよ」
少しだけほっとしなら笑う。
「じゃあ、下の台所借りるから」
「汚いけど引かないでね」
「はいはい、多分引かない」
多分って何よ、と笑う静香さんを愛おしく感じながら、階段を下りた。台所でレトルトの玉子粥を温め、お椀に盛り付けて、皿にあけた桃缶と共にプラスチックのトレイに載せて二階に上がる。
「静香さん、おかゆ……」
襖を開けて部屋に入ったとき、静香さんは布団の中で眠っていた。規則正しい寝息に胸をなでおろしつつトレイを置く。
食器類にかけるラップを取りに戻ろうと立ち上がろうとした時、ふいに手をつかまれたので、俺は驚いて静香さんの方を向いた。
「そばにいて……」
静香さんは泣きそうな細い声でささやいた。俺は静香さんの手を握った。
静香さん、という声が喉の奥から出かけたとき、固いものにつまずいて転んだ。
なんだろうと思い、拾い上げると、それは木の額縁に入った写真だった。左右に並んだ二枚の木の板が蝶番で固定され、本のように閉じられるつくりになっている。写真には、卒業式の幕を背景に立つ、うちの学校の制服を着た静香さんと、優しそうな白髪の男性が映っていた。写真を覆う透明なガラス板の中には、達筆な字で書かれた「沢渡静香さん 卒業おめでとう 国語担当 河嶋」と書かれたメッセージカードが挟み込まれている。
ああ、と僕は思った。写真の中の静香さんは蕩けるような笑みを浮かべている。
静香さんの好きだった相手は、親子以上に年の離れたこの国語の先生なのだ。今、そばにいて、と言った相手も俺じゃなくこの人であるに違いない。
静香さんは、寝汗を浮かべながら、うう、と苦しげにうなった。その途端、静香さんの胸から、小さな薄桃色のハートが、桜吹雪のようにたくさんあふれ始めた。一つ一つのハートは小さいけれど、すごい量だ。薄桃色のハートは、桜や炭酸ジュースのような淡い香りがした。「お姉さん」の恋愛というより、少女の初恋といった様子のそれは、きっと、食べても食べてもなくなりはしないだろう。
俺は畳部屋に座り込み、大量に降り積もる桜の花びらのような静香さんの恋心を両手でかき集め、泣いた。
家に帰ると、ベッドに体を投げ出してぼんやりと天井を見た。薄い鼻水が逆流して鼻の奥がつんとする。俺は、口を開き、わあ、とみっともなく泣いた。あんなすごい想いの前ではどんな横恋慕も適いやしない。
俺は静香さんと彼の関係をあれこれ想像し、邪推した。もしかすると、彼には妻子がいて、道ならぬ恋だったのかもしれない。それで、関係を終わらせるために、静香さんは泣く泣く彼の恋心を食べた――初めて会った晩、食べていた赤いハートは、あの先生のものではないのだろうか。
「ちくしょう」
獣のような声が喉から出てきてびっくりした。体が熱い。頭がちかちかする。怒りや嫉妬の入り混じった感情が湧き上がってくる。無垢な教え子である女子高生に手を出すなんて最低だ。最悪だ。汚い恋心で静香さんの唇を汚して、今もなお静香さんの記憶に居座っている。静香さんも静香さんだ。そんな男を想い続けるなんて、馬鹿だ、大馬鹿だ……。
しかし、何を思っても、自分にはどうすることもできない気がした。
ごろごろと熟れた実のような質感のハートが俺からこぼれ出る。俺は赤く熟した俺の恋心を一つ拾い上げた。
静香さんは、子供の俺の恋心を見て、「君の恋心は、きれいだけど、まだ青い」と言った。
「熟しきったら、きっとおいしいんでしょうね。きっと、涙が出るほどおいしいの」とも。
きっと静香さんは、俺の恋心が熟しきったら、作物を刈り取るように全て食べて、やっかいな想いをすべて断ち切ってしまおうと思ったのだ。
そう考えると苦しくて、俺はハートを片手で握りしめた。ハートからは果実のかぐわしい香りがする。
そういえば、俺はハートを見たことはあるけれど、食べたことはなかった。
「俺も食べられるかな、静香さんみたいに」
一人でつぶやいてみる。俺は手に持ったハートを高く掲げた。
そういえば昔、静香さんは、自分の心は食べちゃいけないと言っていたっけ。いや、構うものか。全部食べてしまえばきっと、このつらい気持ちは消えてくれる。
静香さんへの想いが消えるのは恐ろしかったけれど、それ以上に今の苦しみから逃れたくて、俺は俺のハートに歯を立てた。すもものような、かりんのような、何とも言えないしゃりっとした歯触りと、鋭い甘酸っぱさが生々しく広がるのを俺は感じる。おいしい。おいしい。おいしすぎて泣けてくる。
しゃりっ
しゃりっ
しゃりっ
しゃりっ
隼人、体調悪いの?夕ご飯できたわよ。
隼人、どうしたんだ、何かあったのか。
すみません、隼人くんに風邪をうつしてしまったかもしれません。はい、私は、もうすっかり。
「隼人くん」
静香さんの声で、俺ははっと我に返った。
気がつくと全身にびっしょりと嫌な汗をかきながらベッドの上にいた。電灯はついていないが部屋の中は明るい。どうやら今は昼みたいだった。
「隼人くん、一日近く寝込んでたのよ。ごめんなさい、私が風邪をうつしちゃったのね。水飲んで、ね、ご飯食べれる?」
桐山さん、隼人くん目が覚めましたよ。
静香さんが下の階にいる俺の母さんに声をかけた。
「隼人!」
母さんが駆け上がってくる。
「あんた、ずっと寝ちゃって大丈夫なの? 熱は」
「大丈夫だよ、夏風邪とかじゃないから。クーラーかけずに昼寝しちゃったから熱中症っぽくなっちゃってさ」
「もう、心配させないでよ。お父さんには連絡しておくからね。静香さん、ごめんなさいね、心配かけて」
「いえ、とんでもないです。私がご迷惑をおかけしたのは確かなので」
静香さんに謝りなさいよ、隼人、と言いながら部屋の戸を閉めて階段を下りる母さんを見送ると、俺は涙でひどいことになった顔をティッシュで拭いながら、「ごめん」と言った。それから、静香さんを部屋に置いて下の階に降り、顔を冷水で洗い、歯を磨いた。
再び二階に戻ると、静香さんは正座をして待っていた。怖い顔で俺をにらむ。
「熱中症じゃないんでしょ」静香さんは言った。「隼人くんが倒れたのは、自分の恋心を食べすぎたせいよ。食べても食べても消えないから、どんどん食べて、心そのものすらどんどん目減りして、心の真ん中にがらんと空洞ができる」
「いいんだよ」と俺はどこか虚ろな気持ちで言った。「恋心を持て余して苦しみ続けるよりまだましだ」
静香さんは、しばらくの間何かを考えていたが、やがて俺の腫れぼったい目元に指先を伝わせた。
「自分の恋心は、涙が出るほどおいしいでしょう。私がかつて、この窓の向こうで私の恋心を食べていた時も、たまらなくて涙が出たわ」
「えっ」
俺は小さく叫んだ。赤く熟れた果実の香りで、胸の空洞が少し埋まるような感覚がする。
「あれは国語の先生から取り出した恋心じゃないの。あの、写真に映ってた……」
「先生は私のことをそんな風に思ってなんかなかったわよ。愛妻家だったもの」
静香さんは自嘲気味に笑った。
「私の片想いだったの。告白もしなかった。今にして思えば、身寄りがない寂しさと恋情を混同していたのかもしれないけれど、当時は死ぬほど好きだと思ってた。卒業した後、持病を悪化させて亡くなってしまったときは、この世の終わりだと思ったわ」
「静香さん……」
「先生のいない世界なんて生きてる意味がないと思ってた。だけど、後追いなんかしたらきっと先生は悲しむから、少しずつ、少しずつ、恋心を自分で食べたの」
ごめんなさい、と言った俺に向かって、静香さんは首を横に振った。
「ううん。謝るのは私の方なの」
ねえ隼人くん、君はたぶん覚えてないだろうけど、私たちはあの晩初めて会ったわけじゃないのよ。
先生の死がショックで、職場でもうまくいってなくて、心が疲れた状態で会社を辞めた後、先生のことを思い出しながらこの辺りを歩いてたんだ。
それでうちの桜を見つけたんでしょう、と俺が言うと、それだけじゃないの、と静香さんが苦笑いする。
「私が落とした恋心のかけらを隼人くんが拾ってくれたんだよ。自己完結した想いをきれいだね、って澄んだ目で私を見て言ってくれるんだもの。覚えてないでしょう?」
覚えてない、と俺は答えた。
「うん。そうだよね。あのときの私の身なりはかなりひどかったもの。だけどね、それから、少し気持ちが楽になったの。それから、引っ越ししてすぐ、私は二階の部屋でハートを食べた。賞味期限切れみたいな味がしたべちゃべちゃのハートだった。隼人くんに出会うまで、赤いハートがあふれて止まらなかったのに、隼人くんに会ってから急にハートが出なくなって……それで、君が見たあれが、最後の先生へのハートだったの」
薄情で勝手な女よ、と静香さんはささやいた。
「死ぬまで先生を想い続けると思ってたのに、恋心は徐々に薄くなっていった。その代わり、まだ子供の君の恋心がきれいで、おいしそうで、嬉しくて……君から目が離せなくなった。薄気味悪いでしょう。こんな想い歪んでる。あっていいはずない。だから、ずっと、私はまだ先生のことが好きなんだって自分に言い聞かせてた。だけどね、写真を眺めても、かつての燃えるような気持ちはもう湧き上がって来ないの。恩師に対する懐かしさしかない」
淡々と吐き出す静香さんの目元に何かがちらついた。俺は初め、それを涙だと思った。しかし間違いだった。
ハートだ。
桜の花びらのような淡い小さなハートが静香さんからとめどなくあふれているのだった。
「これ、俺への恋心なの?」
静香さんは泣きそうな顔をして頷いた。
「いっぱい積もらせてくれたんだね」
「今はこんなにあるけど、でも、遠くない未来、全部消えちゃうかもしれない。心変わりしちゃうかもしれない。そもそも、子供にこんな……」
「じゃあ、大人になるよ。大人になったら付き合ってよ」
俺は言った。
「俺が大人になった頃、俺だって静香さんだって、心変わりしてるかもしれない。それは悲しいけど、でも……今、俺は静香さんのことが好きで、静香さんは俺のことが好きで、静香さんのハートはこんなに素敵なんだから、それを否定しなくてもいいじゃないか」
ごめんなさい、ありがとう、と静香さんは言った。
俺は静香さんのハートを一枚舌にのせた。ほんのりと甘くて、花の香りがする。菓子のようにぱちぱちと爆ぜて溶ける。おいしいよ、と俺は静香さんに言った。静香さんは耳を赤くした。
*
「隼人くん、大学卒業おめでとう。お父さんとお母さんにプレゼントする写真、たくさん撮らなきゃね」
シャッターが下りる。俺はまだ子ども扱いだ。「静香さんも一緒に写ってよ」と唇を尖らせると、静香さんがくすぐったそうに笑う。
「新居のガス開栓立ち合いっていつだっけ」
「明日午前だって言ったでしょ」
「静香さんの荷物も荷ほどきしないとね」
「そうね。忙しいなあ、もう」
桜吹雪の中で肩を並べ、スマートフォンを持つ手を目いっぱい遠ざける。何枚か写真を撮ってスマートフォンを下ろすと、ふいに風がやみ、音が消えた。
静香さんがじっと俺を見つめる。俺もまた、静香さんを見つめる。怖いくらいに透き通ったまなざしが飛び込む。
俺たちは物乞いのように手を伸ばしあった。桜の花びらの山のような静香さんのハートを俺が受け止める。果物のようなハートを静香さんが受け止める。
俺は大きく口を開け、たくさんの薬をあおるように花びらを放り込む。静香さんは赤い果実に唇を寄せた後、かじりついた。尖った犬歯が俺のハートに刺さり、ぽたぽたと果汁をこぼす。
「おいしい」
静香さんは目を細めた。息の根が止まりそうだと俺は思った。
